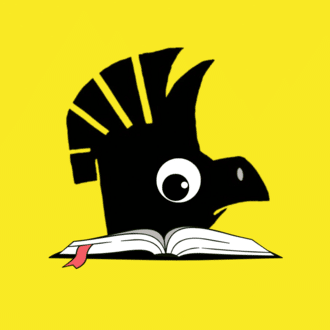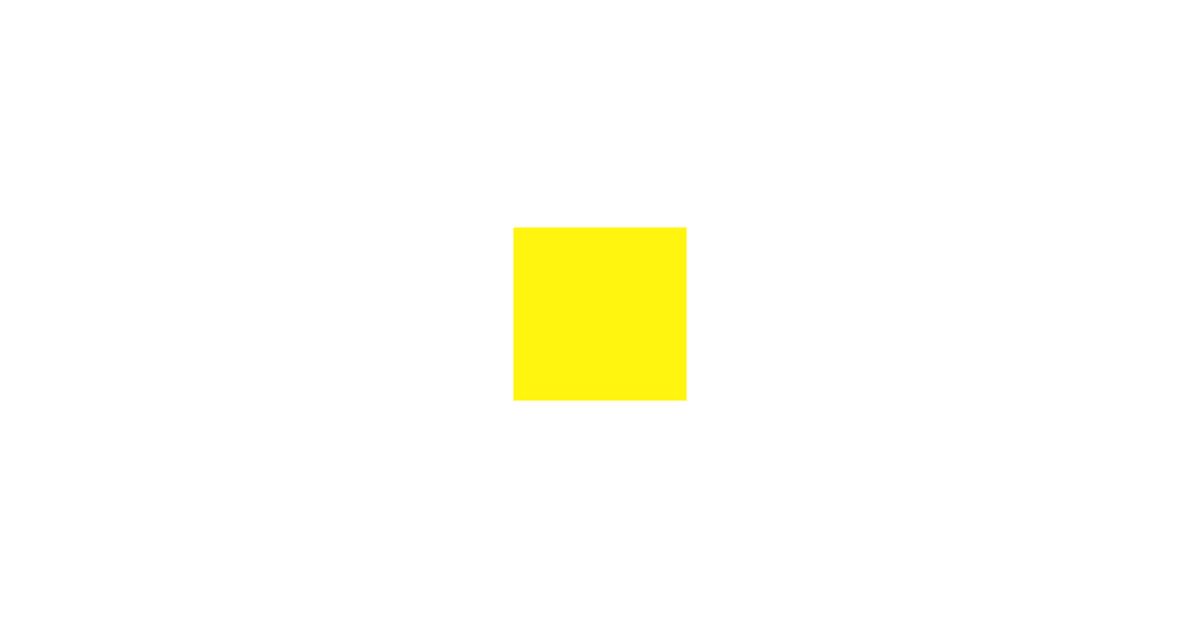
レビュー『インタビュー術』
「インタビューがわかれば、世界がわかる。」という言葉が目に飛び込んできて本書を手に取った。
本書では著者のインタビュー論が語られるのだが、インタビューというものへの見方が随分と変わった。
世界はインタビューでできている
はっとさせられたのが、「聖書も雑誌のアイドル·インタビューも、基本は同じ。」という言葉。
新約聖書はイエス·キリストへのインタビュー集であり、仏典は仏陀へのインタビュー集といえる。
このように、世界のあらゆるところにインタビューが存在しており、歴史はインタビューによって作られたといっても過言ではない。
ゆえに、「世界はインタビューでできている」ともいえる。
いまでも生活のまわりにはインタビューがあふれている。
新聞も雑誌も、ゴーストライターが書いたタレントの本も、インタビューだ。
「人に聞いた話をベース」にしているのがインタビューだとすると、取材、調査、人から聞いたことが元になっている文献の文献調査もインタビューだ。
そして、考えるという行為も「自分で自分の声を聞く」という自分自身へのインタビューだともいえる。
さらに著者は「自分で考えて行動するには、インタビューのことをもっと知らなければならない。」と語る。
インタビューがどのようにおこなわれ、ぼくたちの身のまわりにある情報がどう作られているかを知ることで、メディアへの接し方と、情報の読み方がわかってくる。
インタビューのスタイル
そうしたインタビューにはさまざまなスタイルがあり、それが以下。
・ルポルタージュ風
・Q&Aスタイル
・モノローグ
・対談
・座談会
いままで考えたことがなかったので、その豊富さに驚かされた。
インタビューを行う人は、インタビューをより効果的にみせるために、スタイルを選択するという点でも演出家といえる。
そして、インタビュー記事は、インタビューを行う側のフィルターを通したものとなる。
作り手は、話された言葉を記事にする際、作る側の影響の大きさをきちんと自覚することが必要。
そのうえで、「読者にとっていい記事」を目指さなければいけない。
本書ではその方法論も語られる。
引き出すのか、切り込むのか
黒柳徹子と、田原総一郎のインタビューが比較されている。
黒柳徹子は「引き出す」インタビューで、2〜3時間をかけて、じっくりと相手から物語をひきだしている。
「なんでもあなたは〜なんですって?」と黒柳は話を進める。
すでにみんなが知っている情報を、あえてゲスト自身の言葉で視聴者に披露するべく誘導。
終始にこやかにゲストも楽しく時間を過ごし、視聴者はそれを覗き見るというスタイル。
ゲストは黒柳の反応に、自分の言葉がちゃんと受け止められていると安心。
そして、視聴者は黒柳の反応に共鳴していく。
いっぽうの田原総一郎は「切り込む」インタビューを使い、時間にすると30分と短期決戦型。
「あなたはこういいましたね」「あなたはこうしましたね」「なぜですか」「あなたがやったことに対して、こういっている人がいますよ」と、畳みかけるように質問を投げかけていく。
「ここで反論しないと、あなたは大変なことになりますよ」とプレッシャーをあたえ、白もあり黒でもあるというような曖昧な回答は許さない。
条件付き賛成/条件付き反対という回答は、よりシンプルでわかりやすい替成/反対として田原からゲストへと投げ返される。
誘導尋問のようでもあるが、伝えたいものが人柄ではなく、特定のテーマについての意見であれば、このような強引なスタイルも有効と著者はいう。
本書を読んだ後は、無性にインタビュー本を読みたくなった。
いいなと思ったら応援しよう!