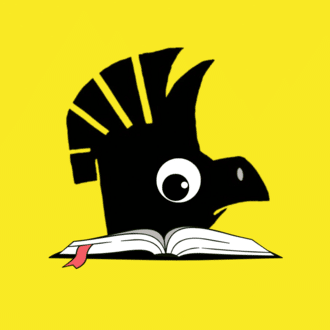アメリカの大ベストセラー『エデュケーション 大学は私の人生を変えた』 - 書評
二日で一気に読んでしまった。
いや、読まされたというべきか。
「世界の終わり」にせっせと備える家族の描写と、そんな家族との関係を問い直す著者の姿に衝撃を受けた。
本書は全米で400万部以上を販売し、ニューヨーク・タイムズ・ベストセラー第1位にも輝いた作品で、ビル・ゲイツやバラク・オバマも大絶賛の傑作ノンフィクション。
本書を読むと「教育のありがたみ」をしみじみと感じることができる。
さまざまな理由で進学できない人や、大学生で何のための勉強しているのか目的を見失った人、勉強のモチベーションを保ちたい社会人など、全ての学びたい人に手にとって欲しい本だ。
書き出し研究
書き出しが魅力的で、一気に本作の内容に引き込まれた。
書き出しの四段落はこう始まる。
私は納屋の横に放置された赤い鉄道車両の上に立っていた。風が舞い、髪が顔に叩きつけられる。開いたシャッの胸元に冷気を感じる。山の近くでは強風が吹き荒れる。まるで頂が息を吐いているかのようだ。下に見える渓谷は、平和で、のどかだ。一方、私たちの農場は躍動している。針葉樹の大木がゆっくりと揺れるかたわらで、ヤマヨモギとアザミが、びゅうびゅうと吹いてくる風におじぎしている。背後では、ゆるやかな丘が空に向かって傾斜を描き、広がり、そのまま山のふもとにつながっていた。視線を上げれば、インディアン・プリンセスの黒い姿がそこにある。
丘には敷きつめられたように野生の小麦が生えていた。針葉樹とヤマヨモギがソリストであったら、小麦畑はコール・ド・バレエだ。小麦の茎がいっせいに動きを合わせる様子は、まるで一○○万人のバレリーナが、ひとり、またひとり、強い風に吹かれて、その黄金色の頭をたれていくように見える。風が作るくぼみは一瞬で消えるけれど、風の形を目撃したような気持ちになる。
丘の中腹に建つ私たちの家に目を移せば、そこには違った動きがある。建物の影が小川まで、気流をかき分けるように伸びている。兄たちが目を覚まし、空模様をうかがっている。母がストーブの近くで小麦のパンケーキを焼いている姿が目に浮かぶ。父がドアの近くで背中を丸め、つま先に鉄板の入ったブーツの紐を結び、たこのできた両手を溶接用手袋にねじ込んでいる姿を思い描く。眼下に延びる高速道路を、スクールバスが停まることなく走りすぎていく。
私はわずか七歳だけど、この事実が、私たち家族を何にも増して、ほかとは区別していることを知っている。私たちは学校に通っていない。
「下に見える渓谷は、平和で、のどかだ。一方、私たちの農場は躍動している。」では静と動の対比が使われており、著者が住んでいた場所を印象づけている。
巧みな比喩も使われており「針葉樹とヤマヨモギがソリストであったら、小麦畑はコール・ド・バレエだ。」と、自然をバレエに例えている。
「風が作るくぼみは一瞬で消えるけれど、風の形を目撃したような気持ちになる。 」と、目に見えない自然の美しさを捉えており、著者の観察眼の確かさがわかる。
「スクールバスが停まることなく走りすぎていく」姿を著者は眺めており、「私たちは学校に通っていない。」というさりげなくハッと驚くべき事実が語られる。
最初は大自然の美しさを描き出し、視点は家族へと映り、最後はスクールバスに焦点が当たる。大自然の美しさと、著者が学校に通っていない事実の対比が印象的だ。
壮絶なライフストーリー
物語の鍵となるモルモン教だが、言葉としては聞いたことがあるものの、どんな宗教なのかを知らなかったので少し調べてみた。
日本語の正式名称は「末日聖徒イエス・キリスト教会」で、1830年に米国人ジョセフ・スミス・ジュニアによって設立され、本部はユタ州ソルトレイクシティにある。
アメリカの人口のうち、モルモン教徒は1.4%と少数派で、かつては一夫多妻制を採用しており、他のキリスト教徒からカルト集団と呼ばれることもあるようだ。
父親は狂信的なモルモン教原理主義者で、他のモルモン教の人たちとも一風変わっており、かなりエキセントリックな考えの持ち主だ。
政府のことを全く信じておらず、アイダホの山奥で暮らし、子供は学校を通わせず、病院に行くのも禁じている。
彼いわく、「病院とは身体を治療する場所ではなく、身体の中に悪魔を埋め込む場所だ」。
病院に行かないので、半身が火傷、頭をぶつけ脳みそが漏れ出るなどの大事故であっても、ハーブとアルコールを身体に塗り、自然治癒に任せている。
家庭内での暴力は見過ごされ、著者は兄から虐待も受けるが、母親は助けてはくれない。
そんな環境下で自らの将来と家族のあり方に疑問を感じた著者は独学で大学に入ろうと決意し、道を切り、家族との関係を問い直していく。
本書はそんな物語だ。
著者の家族のような生活が、21世紀の先進国、しかも経済力世界一の大国であるアメリカで行われている事実には絶句するしかない。
教育が必要な理由
本書の感想は一言では言い尽くせないが、本書を読んでまず感じたことが「教育の必要性」だ。
教育によって得られるものは「さまざまな視点」。
本書を読み、最も恐ろしいと感じた箇所は、何か良くないことが起きると、著者が無意識のうちに「自分が悪いのだ」と自己暗示をかけてしまうことだ。
著者は大学に入ってからも、親から植えつけられた価値観を直せず、自分の家族のあり方に疑問を抱きつつも、故郷の家族のことを思い返しては幾度となく実家に帰っている。
なぜわざわざ狂った家族のところに戻るのか?と毎回もどかしく思うのだが、価値観をなかなか変えることのできないのが洗脳の恐ろしさだ。
著者は両親を愛しているが、家から出ていく著者を両親は許さず「悪魔にとりつかれている」として「改心」を迫るなど、リアルな描写が続き、読み手を戦慄させる。
親という存在の残酷さと、自分を縛る常識から抜け出すことの難しさをひしひしと感じる。
そんな中でも著者の家族への愛と、少しずつ自分の価値観を変えていく努力に心打たれる。
たとえ筆者と同じ環境にいなくても、本書を読み終わったあとは「教育」という言葉の重みが変わると思う。
「勉強の仕方」を考える
本書は勉強の仕方を指南するような、いわゆるハウツー本ではないのだが、著者はケンブリッジ大への留学(返済不要の奨学金付き)を勝ち取るほど優秀で、彼女の勉強方法を抽出してみたくなった。
彼女が世界的な名門大学であるケンブリッジ大への留学に行けた一番の理由は、彼女の論文の出来が良かったからだ。
著者の努力はもちろん相当なものだったのだろうが、それだけでは全く説明がつかない。
なにせ著者は小中高にすらに通ったことのない無学者で、自宅で両親から教育を受けた描写もなく、日中は動物の世話、父親の仕事である廃材処理の手伝い、果物を瓶詰めなどで忙しく過ごしていた。
ここで2つの質問がある。
1つ目は、なぜ優秀な論文を仕上げられるだけの高い言語能力を持っていたのか?
2つ目は、大学在学中にどうやって勉強したのか?
まずは1つ目の質問の答えを探ってみたい。
幼い頃からの聖書の精読
彼女の高い言語能力を説明する要因が一つだけあり、それは幼い頃から習慣となっていた聖書の精読だ。
彼女の父は時間があれば聖書を開き、家族への説得の際にはよく聖書を引用する。
そんな父親の元で育ち、彼女自身も聖書をよく読んでいたという描写があった。
ここからは想像だが、内容をしっかりと理解するまで思考し、読み返し、自分の生活にどう活かせるかを考え抜いていたのではないだろうか。
そうすることで言語能力の向上、ひいては、学習能力の向上を行うことができたのではないかと推測する。
聖書でなくてもいいのだが、何か一つの本を時間をかけて精読し、自分のリアルな生活に照らし合わせてみることが大切だ。
1冊の本を精読することの効用は、作家の平野啓一郎氏の『本の読み方 スロー・リーディングの実践』に詳しく、言語能力の向上は大人であっても決して遅くはない。
日曜日に勉強してはいけない
2つ目の、大学在学中にどうやって勉強したのか?という疑問だが、意外と休み方が大切なのではないだろうか。
著者が日曜日は働けない(学習してはいけない)という教えに忠実に従う描写がある。
著者は宿題をなんとしても土曜日中に終わらせるため、土曜日の夜に、眠りに入るまでは日曜日ではないという自分ルールを作り、日曜日の朝方まで徹夜して勉強する。
徹夜までして大変だなぁと思ったが、日曜日は勉強できないという制約が、1週間の中にメリハリをつけているのではないだろうか。
ここで参考になるのがドイツの社会学者ヨゼフ・ピーパーの『余暇と祝祭』で、この本の中では休むことの重要性を力説している。
ピーパーいわく、日曜日(安息日)は単なる休日ではなく、自分の仕事や学習を振り返り、そこに意味や意義を見出すクリエイティブな時間だという。
もしこの時間がなければ、人間の仕事は単なる労働に陥ってしまうと警告している。
日本人は休むのが苦手とよく言われる。
それは農耕民族だからという説もあるが、最初に制限を作ってしまうことで解決できる。
制限とは、週のうち1日を働いたり学習したりせず、振り返りの日にすると最初から決めてしまうことで、クリエイティビティーや学習効率を高めるのに有効的だ。
まとめ
筆者は1986年、アメリカ北西部でモルモン教サバイバリストの両親の元、7人兄弟の末っ子として生まれる。
父親は「終末論」を狂信しており、文明が滅びた後の世界で生き延びるために、広大な家の庭に大量のガソリンと瓶詰めした手作りした果物を隠している。
政府を疑う父親の指示に従い、子供たちは医者に通うことも学校に行くこともできず、危険な廃材回収の仕事を強いられる。
父親が敷いた家庭内のルールは、いびつな家庭内ヒエラルキーを生み、乱暴な兄からは便器に頭を突っ込まれるなどの虐待を受ける。
そのような環境にいた著者を変えたのは「大学教育」で、現在ハーバード大学公共政策大学院上級研究員で歴史家で、エッセイストとして活躍している。
家庭環境に恵まれず、進学の機会を失った、または失いそうな人に本書をおすすめする。
学習意欲は誰にも奪われない財産であり、自分を変えることで道を切り開いていけることを本書が教えてくれる。
いいなと思ったら応援しよう!