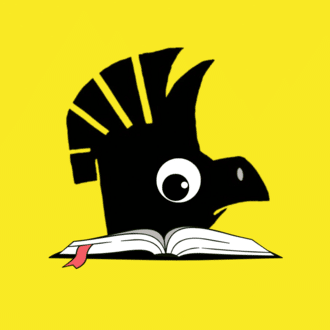noteに毎日投稿している私が、note公式の「文章のコツまとめ」をさらに「まとめ」てみた
みなさん、こんにちは!
あたらしい年がはじまりました。
今年からnoteをはじめてみようと思っている方もおおいはず。
そんな人にぴったりなのが、note公式がだしている「文章のコツまとめ」。
しかし、紹介されている記事がおおく、目をとおすのがおっくうになってしまうかも。
そこで今回は、新年のスタートダッシュをきりたい人のために、上記の「文章のコツまとめ」を、さらに「まとめ」てみました!
おおくの人に読まれる文章の秘訣がもりだくさん。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. そもそもいい記事とは?
文章に自信がなくても、心配はいりません。
記事のおもしろさは、「テーマと内容」が99%を占めています。
「文章力」はわずか1%に過ぎません。
文章力よりも、「書きたい内容」を見つけ、そのテーマについて情熱をそそぐことが大切です。
自分の「おもしろい」、「伝えたい」という思いが重要といえます。
また、良い記事はシンプルに「1人の読者にささる記事」です。
オススメの想定読者は「自分」。
「自分が読みたいと思う記事」を書くことで、おなじ感性や関心をもつ人もきっと喜ぶでしょう。
つまり、自分で「よく書けた!」と感じる記事こそが、本当にいい記事です。
自分の勘を信じ、良し悪しを判断しましょう。
2. 何を書けばいいのか?
表面的な口コミや評論は、もう飽きられています。
具体的なエピソードや、生き生きとした物語をおり交ぜることが求められています。
たとえば「この店おいしかった!」ではなく、「今朝~があって落ち込んでたけど、店員さんが温かい声をかけてくれて、そのあとにでてきたコーヒーに手作りのクッキーがついていて、ほろりときた」のような。
物語でなければ、「新しい情報」かつ「多くのひとが知りたい情報」を選ぶことが重要です。
そして、読者が望むんでいるけれど「手間がかかること」が大切。
具体的には、自分で「調べる」、「まとめる」、「試す」ということが当てはまります。
ほかの人が敬遠する作業を率先することで、「多くのひとが知りたい情報」をうみだし、読者からの信頼をえることができます。
3. タイトルで読者をひきつけるには?
タイトルは記事の顔。
タイトルが魅力的でなければ、中身がどれほどすばらしくても、読者を引きつけることは難しいものです。
良いタイトルとはなにかというと、ずばり「斬新な着眼点」を持っているもの。
「考えてひねり出す」というより、その着眼点に「気づけるかどうか」が大切です。
クリエイターとして優秀と言われる人ほど、世の中や日常を見る「視点の解像度」がたかく、よい着眼点をみつけています。
また、タイトルで個性をだすには「情報っぽさ」を避けることもポイント。
どうすればいいかというと、「生の感じ」を大切にすることです。
たとえば、「まだ使っていないの?TikTokについて徹底解説」よりも、「TikTokに激ハマリした私が、TikTokがなぜ流行っているか考えてみた」といったタイトルが効果的です。
4. どんな構成がいいのか?
構成をつくるのは、じつは簡単です。
自分がもっともおもしろいと思う部分から書き始め、それを中心に構築していけばいいだけ。
それでも困ってしまったら、テンプレートを活用することもオススメ。
たとえば、以下のような科学論文の構成が使えます。
概要: 何について書くのか、どんな事柄を伝えるのかを提示。
結論: 主張や伝えたいこと、分かったことを述べる。
前提: 主張を理解するうえで知っておくべきことを説明。
根拠: 主張の妥当性や理由を解説。
ほかに一般的な型としては、「結論+背景+エピソード+まとめ」があります。
構成は記事の設計図といえます。
設計図が完成するまでは、記事を書きはじめないようにしましょう。
あせって文章を書きはじめると、かえって時間をムダにする可能性があります。
5. 最初と最後の一文で引きこむには?
記事は食事と同じく、「最初の一口目」と「最後のデザートの後味」が重要です。
最初の一口目で読者に、「もっと読み進めたい!」と感じさせれるかどうか。
そして、最後のデザートで「本当に楽しめたな」と思わせることできたかどうか。
最初の一口目では、具体的なエピソードやおもしろい話をつかい、即座に興味を引くのが王道とされています。
最後の一文は、「結論を書かずに終わる投げっぱなし」のものから、「全体で言いたかったことを言いあらわせる一文」などなど。
途中の内容がいかにすばらしくても、最初と最後の一文が魅力的でなければ、全体の印象が損なわれてしまいます。
読者に良い印象をのこし、記事全体の魅力をたかめるために、書き出しと結びに焦点をあてましょう。
6. 記事をシェアしてもらうには?
ブログを成功させるためには、「読後感の設計」が不可欠です
かんたんに言うと「受け手を表現者」にすることが重要です。
どういうことかというと、「読者がみずから記事をシェアしたくなる」きっかけづくりのこと。
そのためには、未知な情報にふれたり、つよく共感したりしたときの「へー!」や「たしかに!」といった驚きが必要です。
そしてすぐれた原稿は、「もっとも重要なメッセージ」を簡潔にまとめられるものです。
文章はその一言をつたえる手段であり、構成や表現はその手段をささえるものです。
「読者が記事を読んだあとに感じるべきこと」を考え、それを明確に伝えることが肝心です。
7. さらに拡散させるには?
noteで埋もれないためには、 じつはX(旧Twitter)との連携が不可欠です。
そして、たんに「記事を書きました」という通知だけではなく、ツイート内で内容が一目瞭然となる工夫が必要です。
というのも、 X(旧Twitter)は情報が簡潔かつ迅速につたわる場なので、自身の記事の情報も、そこで完結するようにしましょう。
ツイートには記事の魅力や要点をたくみに盛りこみ、興味を引く工夫が必要です。
記事へのリンクも添付し、本格的に読みたいとおもう読者を呼びこむことが大切。
記事の良さを的確につたえ、X上での情報発信をつうじて、noteの拡散を促進しましょう。
おわりに
これらのコツをつづけることで、他人からもほめられる経験が増え、執筆の楽しみがひろがるはず。
と、ここまで文章を書くときのコツをまとめてみましたが、もしかするとお腹いっぱいで動けなくなってしまう人もいるかも。
そんなときに覚えておいてほしいのが、ブログに「絶対はない」ということ。
上にあげたコツは、あくまでも「より読まれるようになるためのひとつの提案」であって、絶対ではありません。
大切なのは「自分らしい表現」を見つけることです。
じっさいにぼくも、ほとんどの項目において、どれも満足にできていません。
しかしそれでも、777日以上の投稿をつづけることで、250名以上の方にフォローして頂きました。
まずは「つづけること」を意識し、余裕がでてきたら、上記の項目をひとつずつ「ゆる~く」試してみてはいかがでしょうか。
投稿を「つづけること」に関しては、以下の記事に書きましたので、ご興味があれば。
ぼくも今回まとめたポイントをひとつずつ実践にうつし、さらに良い記事を目指したいと思います。
それでは、良い文章作りを!
いいなと思ったら応援しよう!