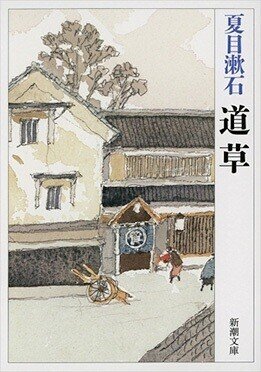「役立たずのすすめ」と「小さな物語」2―「役立たず」という生き方
伊藤徹
(京都工芸繊維大学教授)
本記事は、2021年1月10日に開催された『《時間》のかたち』の刊行記念ミニ講演会「「役立たずのすすめ」と「小さな物語」」の原稿です。
【前回】1 チャップリン《モダンタイムス》から夏目漱石まで
からのつづき
共に生きること
「役立たず」として生きることは、多少正確にいい直せば、仮初の目的を追いながらも、これを仮初のものと意識しつつ、目的の根本的な不在を受け入れて生きることであります。いい換えれば、自分がそれに即して生きている生き方を絶対視せず、したがって、たえず疑いつつ、生きていくことであり、自分が無意味から逃れようと紡ぎ出している生き方の詐術に醒めていることです。目的の妄想の断念でもある、それは、《釣りバカ日誌》の浜ちゃんのようにお気楽な人生を許さないでしょうし、場合によって本書が最後に扱っている漱石『道草』の主人公のように、痛ましい人生しか残されないのかもしれません。けれどもそうした痛ましさを堪えている人間だけが、私たちにとって信頼に足る存在なのではないでしょうか。イメージされるのは、自分の信念を他人に傲慢に押し付けようとする者ではなく、せせこましい目的に齷齪し呻吟しているつまらない他者を見ても、自らと変わらないものとして、これを認め、憐れみと尊敬を以って対するような人です。そうした人との間に生まれる信頼関係、あるいは「友情」だけが、私たちをようやく救ってくれるものなのではないかと、私は考えるのです。
「友情」という言葉を出しましたが、これは「役に立つ」とか有用性とかとは、根本的に異なります。たとえば皆さんの知り合いが、皆さんを自分の役に立ててやろうという思惑で付き合っていたことがわかってしまったとしたら、どうでしょう。そんな人を皆さんは「友人」と呼ぶでしょうか。自分が恋人だと思っていた人物が、自分を役に立つものとしてしか考えていなかったとしたら、「裏切られた」と幻滅し、百年の恋も冷めるのではないでしょうか。「友情」とか「愛情」とかの核にあるのは、有用性とは真逆のもの、むしろ「役立たず」であることです。そう考えてみれば、私たちが有用性とは異なる次元のものをいかに大切にしているのかは、わかるでしょう。
現在蔓延中のコロナ・ウィルスは、人と人との間を割こうとするものですが、それでも私たちはなんとかして人とつながろうとしています。オンラインという手段で友人とおしゃべりするのも、会いづらくなった恋人同士が感染のリスクにもかかわらず会おうとするのも、なにか特定の目的のためではないでしょう。おしゃべりしたいからおしゃべりする。会いたいから会う。ただそれだけです。観光に行かなくても生活できるけれども、少しでも可能性があれば、手を相携えて旅に出る。そんな無理をするのも、人間の生に潜む、有用性を超えたもの、私にいわせれば「役立たず」のゆえです――政府は、それを経済活動という有用性の枠組みに組み込もうとしているわけですが。要するに「役立たず」がいかに大切なことかは、皆さん自身、既によくご存じのことであり、私の「役立たずのすすめ」とは、そういった辺りを言葉にしてみただけなのです。
管理社会への抵抗としての「役立たず」
コロナ蔓延のなか、さまざまな場面でのデジタル化の進行は、おそらく不可避なことでしょう。デジタル化が、私たちの行動を管理し、有意味化していく傾向をもっているのは、明らかです。手段である管理が目的を持たないことなどありえません。けれども、そこに設定された目的の正しさは、いったいどこで保証されるのでしょうか。私の考える「有用性の蝕」に即していえば、いずれの目的も仮初のものでしかないのですから、正当性の保証は原理的に不可能なことといわざるをえません。繰り返しますが、「本来的」な目的などどこにもないのです。にもかかわらず管理を実行するとすれば、それは、特定の目的に向かって私たちの行動を制御し選別し、そこから外れたものを、排除していくことにつながるでしょう。ポーレット・ゴダード演ずる《モダンタイムス》の少女が警察に追いかけられるのは、彼女が「浮浪罪」を犯しているからです。「うろうろすること」自体が犯罪だというのは、いまの日本からすれば基本的に驚きですが、管理が徹底された社会のなかでは、それもまたありうることですし、実際に起こっているホームレスへの襲撃の背後に蠢く感情が、これと結びつかないとはかぎりません。高度な科学技術化が正確に人をフォローしコントロールしていく社会、つまりすべての人が有用性の連関に組み込まれてしまった社会は、なんとも気味の悪いものに思えます。「役立たずのすすめ」は、社会からの単なる逸脱、あるいは現実社会からの逃亡を推奨するものではありません。本書最終章は、そのことを漱石の『草枕』から『道草』への歩みのなかで考えていますが、今後現れてくるかもしれない徹底した管理社会への抵抗の可能性を、私は「役立たず」の次元に根を下ろした「友情」もしくは「連帯」に求めてみたいと考えています。
(3につづく)

伊藤 徹(いとう・とおる)
1957年 静岡市に生まれる。1980年 京都大学文学部卒業。1985年 京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。現在、京都工芸繊維大学教授(哲学・近代日本精神史専攻)。京都大学博士(文学)。著書『柳宗悦 手としての人間』(平凡社、2003年)、『作ることの哲学―科学技術時代のポイエーシス』(世界思想社、2007年)、『芸術家たちの精神史―日本近代化を巡る哲学』(ナカニシヤ出版、2015年)、『作ることの日本近代―1910-40年代の精神史』〔編著〕(世界思想社、2010年)、Wort-Bild-Assimilationen. Japan und die Moderne〔編著〕(Gebr. Mann Verlag、2016年)他。