
『読書会入門』を読む
1冊の本を読んで「どう感じたか」
終わってから誰かと語り合う(話をする)ことを前提とする読書には、一人で読む読書とは、また違った価値が あります。
読んだ直後に他人に わかる言葉で表現しようとする事、同じ本を読んだ誰かから新しい気づきを もらったり。
インプットとアウトプットを同時に行なうことで、自分自身の考え方が立体化されていきます。
「読書会」は、本を読むための 一つの技法です。
【前書きより】

『読書会入門』
人が本で交わる場所
山本多津也 著
幻冬舎新書 (2019.09.25)
「読書会」とは
一般的に「読書会」には、
課題型と紹介型の二通り が あると言われています。
課題型:課題の本と言われる本を決めて、参加者同士が 感想を語り合う。
▶ 課題型の本の決め方
1) 出来るだけ 古典や名著から選ぶ
2) 時代を超えて読み継がれる本には、それなりの理由(普遍性)がある。
3) 敢えて 難しい(難解な)本を選ぶ。
紹介型:参加者が、自分のお薦め本を持ち寄って、本の内容を紹介し合う。
▶ 紹介型について
1) パターンとして、一人一人の持ち時間で 本の紹介をし、全員 廻ったところで終了。ディスカッションと云うよりプレゼン的なイメージになる。
2) 紹介型は、参加者同士で 話が膨らみにくい。
「課題型」を選択するか「紹介型」を選択するかは、主催者の判断に委ねる。
「読書会」の効果
▶ みんなで読む (課題型)
同じ本を読んだ人達と、感想を一つのテーブルに持寄る。
このことに依り、同じ本でも 10人居れば10通りの読み方(感想)が あることに気づく。
▶ 自分の考えを客観的にみることが出来る。
【「本を読む」とは 】
本を読んで、知識(情報)を得ること。
つまり、インプットした知識や情報を、自分なりに咀嚼し、他者に発信(アウトプット)すること。
コミュニティとしての「読書会」
1) 継続学習とコミュニティ。
(P.F.ドラッカー)
2) 読書会を合議制に しない。
3) 参加者同士でヒエラルキー(階層)を作らない。
4) 会則をつくらない。
※ 3) 4) 全員がフラットな関係。
5) 考えの違う人を排除しない。
6) SNSは、連絡網としてのみ使う。議論には、使わない。
「みんなで語る」こと
本を読むことから、何らかの次へのステップへ繋がることが大切。
最終章では、ピエール・バイヤールの『読んでいない本について堂々と語る方法』が紹介されています。

▶ 我々は、たいていの場合「読んでいる」と「読んでいない」の中間領域にいる。
私達は、何を持って本を「読んだ」と言えるのでしょうか。
▶ 1冊の本は、誰かに読まれた、また存在を知られた瞬間から、その人の感受性や思考と融合し、新しいモノへと変化するのです。
▶ 読んでいない本について語る行為も、読んでみたものの読みきったと言い難い本についても、語ることは「創造」する活動なのです。
次の『人を動かす』D.カーネギー
読書会の課題図書として、よく選ばれているようです。
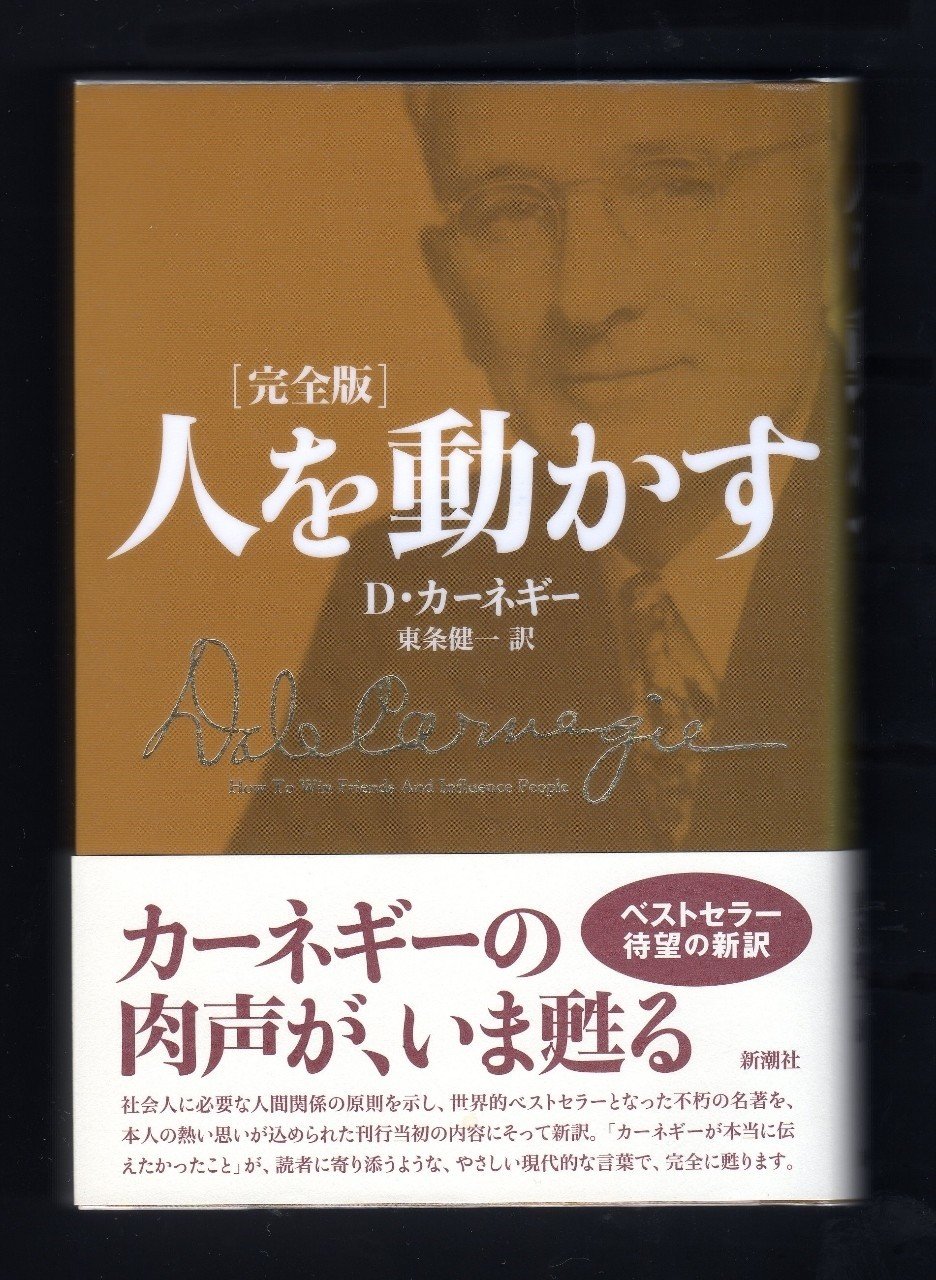
『 人を動かす[完全版]』
D・カーネギー 著
東条健一 訳
新潮社 (2016.11.25)
【Note】2020.03.19
おわりに
マイ・マガジン「読書術」
https://note.com/horippy0724/m/m173580de41e8

2020.03.29
