
【読む前に】『リデザイン•ワーク』
7月の「Online読書会」の課題図書
『リデザイン•ワーク』新しい働き方
リンダ•グラットン 著 池村千秋 訳
東洋経済新報社 (2022.10.27.)
読書会までに読了する その前に
はじめに
(ITやAI などの) 自動化の進展にともない、さまざまな産業の様相と雇用のあり方が変わりはじめている。p.1
の書き出しで、始まっています。
1) 長寿高齢化により、70歳まで働く事が当たり前になる可能性も出てきた。
2) 以前より多様な家族やコミュニティのあり方
3) 勤務先の会社に何を望むか
4) 人々の精神の健康が蝕まれる
5) 気候変動に拍車が掛かる
そこへ、新型コロナウイルス感染症のパンデミック (世界的大流行)
従来の仕事のあり方を「リデザイン(再設計)する」p.2
【ステップ1】 理解する編
【目次】
1) どのように仕事をリデザインするか
仕事をリデザインするための「4段階」のプロセス
① 理解する
② 新たに構想する
③ モデルを作り検証する
④ 行動し創造する
p.35
2) 理解する pp.43〜100.
3) 新たに構想する pp.101〜202.
4) モデルを作り検証する pp.203〜286.
5) 行動し創造する pp.287〜352.
おわりに) 創造力を高める働き方 pp.353〜357.
【東洋経済新報社/ブックレビュー】
【感想】
産業革命や、情報革命など、社会の変化と人々のあり方については、過去も言われて来た。
変革を恐れず。
今回は、コロナ禍における社会変革に、いかに対応していくのか?!
じっくり読んでみたい。
【関連図書】
『思考の整理』

ちくま文庫(1986/昭61/04.24.第一刷)
コンピューター時代を生きぬく
人間らしく生きて行くことは、機械やコンピューターに出来ない、つまり、人間にしか出来ない 優れた創造的、独創的な仕事をどれくらいよく出来るかによる。
pp.214〜215.より
『情報化社会』

講談社現代新書 (1969.05.16.)
情報化社会とは
情報化社会とは「インターネットなどの通信技術の進歩やコンピュータ利用の普及、 情報産業 の発達による情報の大規模な生産・加工・処理・操作・消費によって、従来の工業化社会における社会規範や価値観がかわりつつある社会」と、定義されている。
情報が氾濫する社会に、私たちは どう対応していったらよいのか・・・
現代社会で言われている事が既に50年前に問題提起されている。
『ハイテク社会と労働』
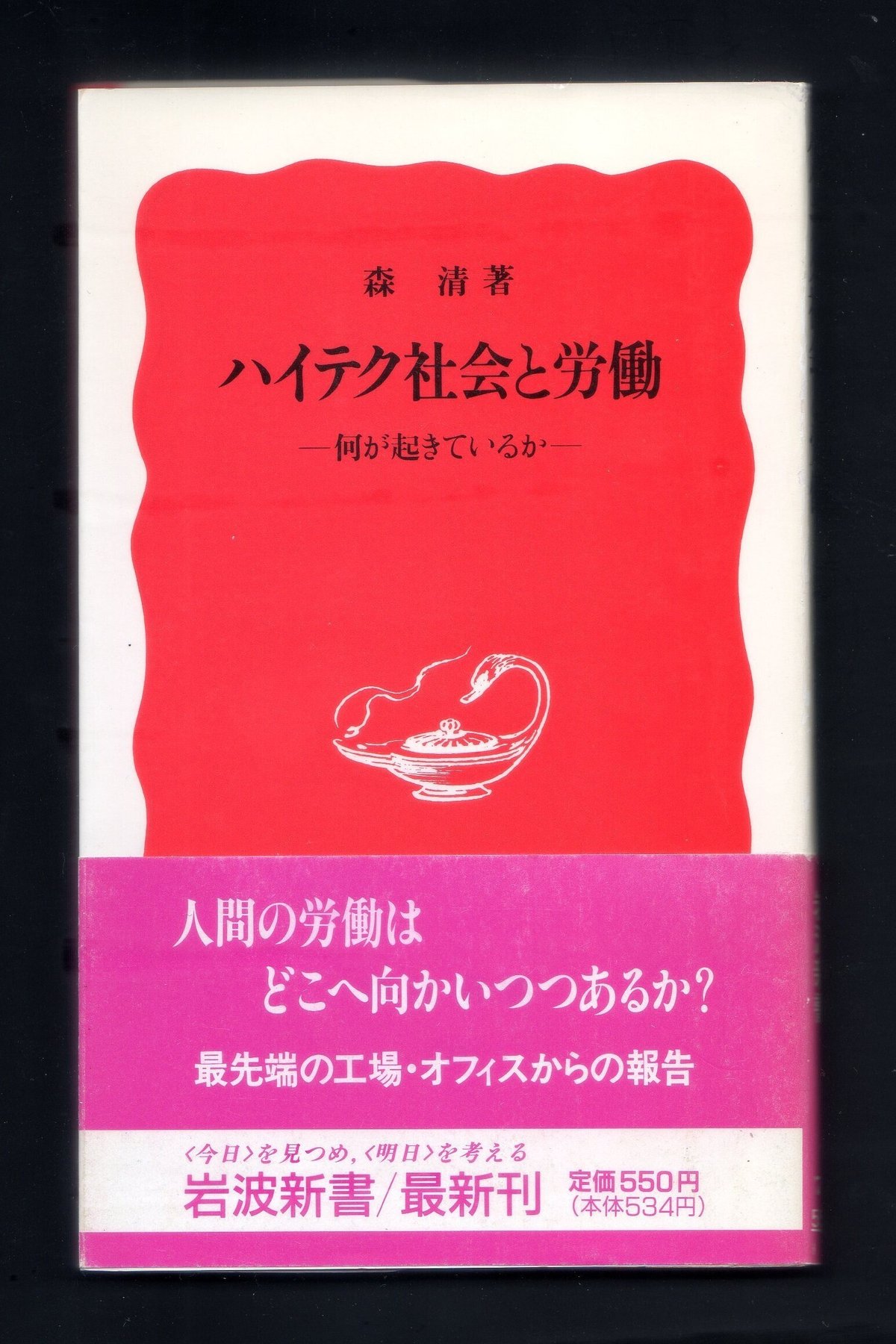
岩波新書 (1989.05.22)
人工知能(AI)社会と労働について、1989年(平成元年)の出版ですが、現在 取り沙汰している問題が提起されています。
[序章] p.1〜
見失われている「労働」
▶ 働くなかで仕事や人に教えられること▶人と力を合わせて働くこと
▶働いた成果で社会と結ばれること
↓
これらによって「労働の喜び」を知る(思う)
1960年代 コンピュータ讃歌 AI(人工知能)の開拓期
コンピュータは、知的労働を機械化する p.10
労働力不足と外国人労働者 p.11
労働の質 p.14
情報化社会の二面性 p.16
[Ⅰ章] ロボット工場と労働 p.19〜
[Ⅱ章] インテリジェントビルでの労働 p.55〜
[Ⅲ章] オフィス(高度情報化工場)の光と影 p.93〜
[Ⅳ章] ソフトウェア労働者たち p.135〜 [Ⅴ章] ロボタイゼーションを越えて p.185〜
あとがきより
ハイテク社会と云うと、いかにもバラ色に見える。しかし、そのような事はない。
pp.231〜233.
【ロボタイゼーション imidas】
【岩波書店/『ハイテク社会と労働』】
2023.05.10.
