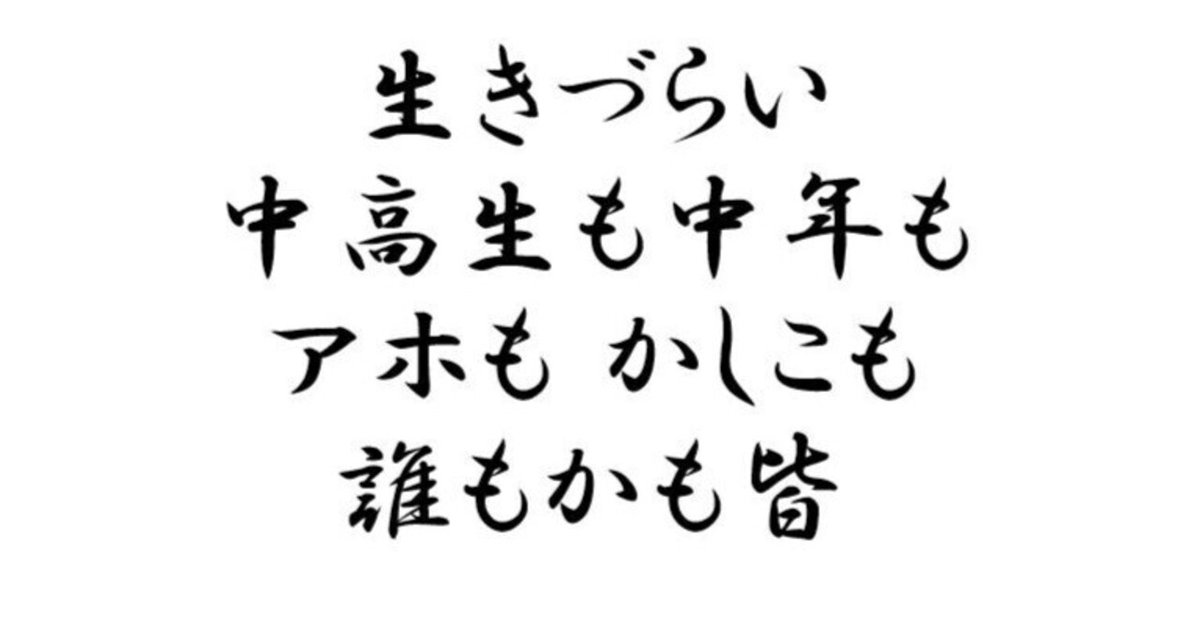
【現代文】青春を 信濃に偲ぶ 独り酒
高校時代の鬼教師による読書感想文の宿題。その10作目の粗筋は、私の記述によると次のようなものだった。
「八才の良平は、毎日村外れへ軽便鉄道の敷設工事を見に行った。トロッコを用いた土の運搬作業を見ているうちに、彼は自分も土工になりたい、そして一緒にトロッコに乗りたいと思うようになる。ある日、願いがかなって、良平は若い二人の土工と一緒に、本線を行くトロッコに思う存分触れることができた。しかし、押しては乗り、乗っては押しているうちに遠くまで来てしまい、日も暮れかかる。『優しい人たちだ』と信じきっていた二人の土工からも『もう帰んな。』と冷たく宣言され、心細さに泣きたい気持ちをおさえながら家へ急いだ。二十六才になり、雑誌の校正係となった今でも、彼はこの苦い経験を思い出すことがある。」・・・「読みはじめ」は「平成4年4月21日」、「読みおわり」は「平成4年4月22日」、「延べ時間」は「1時間」。おや?この所定用紙、10作目では無い。十年以上も前の引越でタンスの奥から発掘した有島武郎『一房の葡萄』の感想文が1作目だと思い込んでいたが、その「読書の記録」欄に残された日付より更に6日早いではないか。即ち、芥川龍之介の『トロッコ』が高校初の課題図書であったのだ。先生は、入学したての4月中にいきなり、短編とはいえ2作も読ませ、その粗筋と感想を提出させていたということになる。まさに鬼の所業。高校生は4月の30日間ずっとトロッコだけに乗りっ放しなわけでは無い。授業は土曜まで続き、他の科目からも胃もたれする量の宿題が出される。まして文学青年でも何でもない普通の高校生だった私にとって、貴重な日曜を読書感想文に費やすのは結構な苦行だった。
だが、それはそれとして、1作目となると、感想文の出来栄えには期待できないな。なんせ、ほぼ同時期に仕上げた2作目『一房の葡萄』のそれには、中学を卒業したばかりの拙さと思考のつまらなさが見事に露呈していたのだから。
粗筋に引き続き、私の感想文は次のようなものだった。
「良平は、例の事件の前にも一度、弟とその友達と三人でトロッコに乗って遊び、背の高い土工に叱られました。それにもかかわらず現場を見に行って、また別の土工に話しかけたところに、いかにも少年らしい好奇心、乗り物へのあこがれの強さを感じました。だからトロッコに乗せてもらったときは無我夢中だったと思います。しかし、海が見えた瞬間、はじめて彼は遠くへ来てしまったことを知り、不安になります。帰りたいけど後にもひけない。八才の少年の頭の中は実際のところ、とても迷いがあったと思います。そして待ち続けた土工が茶店から出てくると、冷たく一言告げられます。楽しくて興味をひくものがあったはずなのに、予想もしなかった展開に、彼は何かに裏切られたような気持ちだったと思います。
そんな八才の良平の、夕暮れの中たった一人で帰途を急がねばならない心細さと、雑誌の校正などという見こみのない仕事につき、妻子を養っていかねばならない二十六才の良平の心細さは、同じものであるからこそ、彼は幼いころの自分を思い出すことがあるのだと思います。大人になれば私も妻子を養っていかねばならないでしょうが、トロッコの思い出は、不安な人生を象徴しているかのように思われました。」・・・これが本作品に対する正しい分析なのか否かについては不明とすべきだろう。執筆者の手を離れた段階で、芥川自身にも妥当解を答えようがない。完成後の芸術は鑑賞する各人のものである。その前提ではあるが、「八才の人生も、二十六才の人生も、歩む道の心細さにおいては同じこと」とする物の見方は、十六才なりに的を射ているように感じる。少なくとも八才、小学校2年時の私は、見知らぬ遠くの町まで冒険し帰宅に惑うような不安を遊びの中で自ずと体験している。では、この感想文の十年後、良平と同じ二十六才となった私はどうだったのか、実際に蓋を開けて実証してみたくなるのが、オトナになってからこの文章に“再会”してしまった人間の必定というものだ。
私は自家製の梅酒を久々に舌の上で転がす。そもそも広口瓶を取り出したくて滅多に開けない戸棚の奥へ手を伸ばした土曜の“申の刻下がり”に、偶然見つけた錻力の箱から「小田原熱海辺りの山々を往復するトロッコ」やら「華岡さん家へ嫁いだ実験台の奥さん」やらが、手品の如く飛び出してきたという次第だ。ロックグラス代わりの湯呑を傾けながら、20年前を脳裏に再現する。二十六というと、入社3年目の営業マン時代。晩酌を始めると、酒の回りと共に、野心的な若手社員として多忙極まりなき任務に全身全霊を尽くしていた過去が思い出される。その熱量や消耗といったものの激しさたるや、もう四十六の今となっては信じ難い程だった。
二十六歳の私は、新幹線に揺られつつ、様々な感情に揺れていた。新幹線というのは、毎週の移動手段である。世の中の殆どの会社が、巨大企業みたいに全都道府県に拠点を設けているわけではない。しかし「巨大」とまでは云えぬ規模でも「大企業」に属する会社というのは、全都道府県に顧客を有している。畢竟、巨大でもない大企業のセールスは、出張で地方各地の得意先を訪ねることとなる。月曜のみを内勤事務に使い、その夜か火曜の朝直行で往路の新幹線に乗り、最寄り駅からレンタカー等で商談・接待・市場調査と走り回り、転々とビジネスホテルに連泊し、金曜の午後か夕刻に復路の新幹線に乗り、事務所に戻って遅くまで残務整理に励み、週末だけを自宅――私だったら当時は東京の自宅、母と二人で暮らすために購入した中古マンション――で過ごす。それが基本的な1週間の流れなのだ。
当時の私は過労により躰の一部が痙攣する程であり、容赦ない激務に泣いていたが、その痙攣すら忍耐の勲章だと歯を食いしばって猛烈に働いていた。カネが欲しかったのである。会社生活初期の数年で輝かなくても途中でパッと昇格する人というのは、真の運と実力を備えた人。運も実力も無さそうな平々凡々たる私は、入社早々のスタートダッシュが肝心だと、自分を戒めていた。業務をマスターし、奇抜な発想でちょっとした功績を立て、まずは社内で目を引く存在にならなければ、いつまでも梲が上がることは無い。そんな二十六才の物思いは、良平のような心細さとは無縁どころか、棘すら秘めたものだった。
・・・役員の派閥や権力闘争だの、本社と支社の組織改編や人事異動だの、全くもって会社員にはそんな話題にばっかり夢中になる奴が多い。夢中になるのは勝手だが、誰かの出世舟に乗っかろうというのか?乗っかったのが泥舟だったらどうするのか?もっと自分の心配をしろと言いたくなる。貧乏な私にとって、この会社での仕事には生活が懸かっている。生活に影響力の無い他人の話題に燃えるようなサラリーマンにはなりたくない。
それとも暇潰しなのだろうか。そのヒマとやらを持て余す中、もし「仕事を与えてもらえるだけで幸せ」と少しでも本気で思うなら、「仕事を与えられ過ぎると不幸せ」だと気付くまで、一度その仕事に心血を注いでみたらどうだ。――自分が日々多忙に苛まれているからだろうか、給料泥棒に憎悪の念が募る。解決策が全く見いだせない故、遣る瀬無いのだが、組織を構成する人員の下位おおよそ二割方の人間は、やる気が無いか、サボり癖があるか、あまりに無能で業務を任せられないか、何らかの事由により自由人なのだ。
料理人だった父が職を探していた頃がふと回顧される。不当に仲間を解雇した社長と大喧嘩した末、啖呵を切って店を辞めてしまったのだ。筋を通した父らしい生き様に、母も私も拍手を送りつつも、一家の生活は火の車。不況の煽りで簡単には次の働き口が決まらず、父の就職活動への意気込みも徐々に失速していく。尊敬とか軽蔑とかいう次元を超越し、活力を削がれた父の姿を見ているのが、ただ辛かった。一方、私はというと、大学の学問というものに意味なんかを問い始め、退屈な講義を聴きにキャンパスへ通うのも億劫だった時期にあり、生意気にも我が道に苦悶していた。すると、小人閑居して不善を為す。「暇な自由人の私が、父の傍から逃げるのは卑怯ではないか」と、誠に身勝手で無駄な真心に駆られる。行き着くところ、放蕩父子二人、真っ昼間からテレビの時代劇の再放送なんかを流しっぱなしに、ウーロンハイを呷っていたという始末だ。
猪口才にも世間の目が煩わしく、私が父に代わって近隣のコンビニへ行き、自分のバイト探しをしている態で、父の求人情報誌と、二人共通銘柄の煙草を買っていた。毎日家に居て、毎日時代劇とウーロンハイといった具合では、さすがに飽きてくる。競輪場で遊ぶような金は無いけれど、偶には憂さを晴らしたいのが人情というもの。「釣り堀へ行く」と言って、母の財布から奪うように小遣いを握りしめた父は、私を連れて実際に釣り堀には出掛けるものの、何をやらせても器用な人で、30分もせぬうちに大物の鯉を次々と釣り上げる。そうなると、すぐに釣りにも飽き、挙句、赤提灯の縄暖簾へと吸い込まれていってしまう。長時間のパート労働でヘトヘトの母だったが、釣り堀へ行った筈の父子が酔って帰宅しようと、文句の一つも口に出さなかった。
あれから6年の時を経た。かつては勉強に身が入らなかった私も、あのふんわりとした自堕落のおかげで自己を見つめ直し、就職氷河期の中、それなりに安定した企業へ入ることが叶った。と同時に父は他界。今は死に物狂いで1円でも多く稼ぎ、収入の全てを母の暮らしを豊かにするためだけに費やしたい。当時、仕事に行けない父も、大学に行かない私も、おそらく世間の下位おおよそ二割方に属していたのだろう。とは申せ、「大きな組織にしがみつき、他人の蜜の御零れを恵んでもらって生きていた訳ではないのだから、会社に蔓延る給料泥棒よりはマシじゃないか」と、団栗の背比べによってプライドを確かめる。・・・
二十六の私の物思いを振り返ってみれば、大体こんなものだった。支社内で相対的に賃金の低い若手層のほうが、新進気鋭で、提案力に富み、機動力にも秀でるため、支社内で相対的に利益構成比の上位を占める有力量販企業向けの営業を担当する。一方、支社内で相対的に賃金の高いベテラン層は何をしているのかと言うと、まず「売ってこい」「何か対策があるだろ」「頭を使え」「ノルマが分かっているのか」と部下の尻を叩くだけの課長が居る。次に、課長補佐はというと、先祖代々蜜月関係の続く卸売店の営業所を決まった日時に伝書鳩。特別なデータや面白い企画書を用意するでもなく、本社の宣伝部が作成したチラシをそのまま持参し、「新商品です。よろしく~。」と配って回り、最後に所長と四方山話でお茶を飲んで帰るだけ。これじゃあ「毎日村外れへ軽便鉄道の敷設工事を見に行っ」ている八才の良平とさほど変わらないではないか。むろん数字の責任者としてエリア全体の実績を取り纏め、最後は人間関係で客に無理を聞いてもらうベテランなりの難しさは理解するけれど、常時シビアな勝負に技巧を凝らしては汗をかいている心身困憊の若手層からしてみると、どうしてもお気楽に見えてしまうのだ。事実、中には本当にお気楽な社員も居座っていたから厄介。しかも、これが陸な就職活動もせずに実力以上の会社に入ったバブル世代だったりもするから余計に厄介。氷河期で苦労した若手は、愚直に頑張っているのが馬鹿らしくなってくる。世代間対立を煽るつもりは無いが、残念ながら当社に限らず20世紀と21世紀の変わり目前後数年間における日本企業って、かなり酷い職場実態だったし、それが今も尾を引いている。社業への貢献度が低いくせに、偉そうで、理不尽で、何か先輩らしいアドバイスをしてくれるわけでもない連中が邪魔で煙たいのは、私も周囲の若手と同感だった。
尤も、まともな社員のみで組織を再構成したところで、その中で再び相対的順位は付けられるのだから、下位おおよそ二割方が再び形成されることは避けられない。が、「新二割方」が「旧二割方」と同類項となるような、絶対的な“落ちこぼれ”の評価に属するかというと、そんな事は無い。よって、蛇足を云えば「なぜ労働組合はあんな奴の雇用まで守らねばならないのか」「なぜ労働組合はダメな管理職を非難しないのか」「景気が悪い時こそ、採用人数を絞るのではなく、逆にどんどん新陳代謝を促すべきだ」とも感じていた。その後の10年余り、給料泥棒を降格やリストラで退場させる具体例も顕著になったので、「この会社の労使って、捨てたもんじゃないなあ」と見直したけれど。
私の毎週の出張先は信州だった。新人から群馬県を2年担当し、西は前橋・伊勢崎・桐生、偶に太田と館林、北は伊香保・沼田、そして偶に北西の草津と、広範囲の回り方のコツみたいなものを漸く掴んだ矢先の異動命令だったが、飽きっぽい私には適切な人事だったのかもしれない。現地までの距離も、営業の範囲も、上州の比では無かったが、会社は3年目の私に期待をかけて抜擢したのだろうし、数字に追われ骨の折れる局面が屡々あろうとも、この国にしかない景色が私を癒してくれたことは間違いない。「日本の屋根」に囲まれ、前任地の群馬県、そこから時計回りに埼玉・山梨・静岡・愛知・岐阜・富山・新潟の計8県と境を接するスケールの内陸国は、日本広しと雖も信濃が唯一。なかんずく私の主戦場は「南信」。新幹線を長野駅で降り、車に乗り換えてからの移動のほうが新幹線の乗車時間よりも長い。門前町の県庁所在地は「北信」、城下町の松本でも「中信」なのである。兎に角、南北に長い。それでも新幹線のスピードと運行本数には感心させられる。都会の青春に終止符を打った女のように新宿発8時ちょうどの特急に乗り、諏訪経由の移動を試したこともあったが、旅情を味わえたというだけで、面倒な割に、飯田までの所要時間が短縮されることは無かった。ドライブの時間が長いのは疲労とリスクを伴う。が、四季折々の山里の眺望を楽しむ余裕を呉れた。例えば春、自分だけのとっておきの場所から、満開の桜色の絨毯の向こうに、真っ白なアルプスの雪化粧と麗らかな青空を独占する。例えば冬、雪一面の綿菓子に神様がつまみ食いの小指を突っ込んだ穴跡のような露天の温泉を満喫する。東京に住みながら別荘を構えているかのような贅沢に浸れるのは、人生長しと雖も孤独な営業マンにしか与えられない刹那のご褒美だった。
母の乳癌が見つかったのは、この頃である。入院日まで「休まず会社へ行け」と強引に私を帰そうとした母だったが、血を分けた家族は息子である私だけ。それが翌日、回診にいらした主治医の先生に「なんだ、身内の方々、結構多いじゃないの」と言われた際は、駆け付けてくれたご近所さんの手助けにこの上ない謝意が込み上げた。手術の前後だけ有給休暇で付き添ったら、皆さんのお言葉に甘えて、暫く“留守”にしていた信州へ発った。私のセールスカーがいつものバックヤード側の駐車場に進入するや否や、懇意にしていただいていたディスカウントストアのバイヤーさんがフォークリフトから飛び降りてきて「大丈夫!手術は成功したんだら。おかぁまも、中日も、これからV字回復だに!」と声を張り上げる。心配してくださっていたのだ。
高校時代の鬼教師による読書感想文の宿題。時系列は前後するが11作目の粗筋は、私の記述によると次のようなものだった。
「名手本陣・妹背家の令嬢・加恵は、貧しい田舎医家・華岡家へ、夫・雲平の京都遊学中に嫁ぐ。ところが、賢く、美しく、また尊敬していた姑・於継の態度が夫の帰りで急変。そこに雲平をめぐる二人の女の戦いは始まった。嫉妬心は彼に注ぐ愛の競争となった。加恵が長女・小弁を出産後、小姑・於勝が乳ガンで亡くなる。やがて青洲と名乗った夫のたゆみない麻酔薬研究が完成を迎えると、強い犠牲の精神を競う嫁姑の願いで人体実験が行なわれる。結果、麻酔薬『通仙散』は完成したものの、気がつけば加恵は実験の薬毒で盲目の人となり、於継は長男・雲平の誕生を見られずに去っていった。最後まで医家を支えつづけた下の小姑・小陸の死後、乳ガン手術にとうとう成功した青洲は、日本を代表する外科医に成長。のち、青洲に奉仕してきた加恵は、黙って息をひきとった。」・・・「読みはじめ」は「H5年1月17日」、「読みおわり」は「H5年1月27日」、「延べ時間」は「10時間」。年が明けて、「平成」を「H」と記すようになった理由は不明。本作品が有吉佐和子の『華岡青洲の妻』であることは言うまでもない。
粗筋に引き続き、私の感想文は次のようなものだった。
「大部分の人が結婚をし、家庭を築いていく。私もそのつもりである。そう思うと、よく耳にする嫁と姑の問題も、自分だけは大丈夫だろうという根拠のない考えによって目をそらすわけにはいかない。骨肉を分けあった親兄弟と、元は他人であった妻とを等しいものとするのが当然であるが、その平等に少しの疑念もないと言うとうそになる。また、夫が間に立って裁くことはないという本作品の一部分も、改めて考えると、自分もその立場に立たされたとき例外ではないだろうと思う。見て見ぬふりはつらい。当時の嫁の苦労に比べたら、今の嫁は気楽だろうとは言え、現代においても、核家族が増加しているなど、根本的に嫁姑の同居は難しいものなのだという問題の影響はあると思う。でも、高校生の私には、これについて具体的な自分なりの答えを出すのは難しい。
次に、単なる嫁と姑との関係からもう一歩踏み込んで、特に考えさせられたのは、理屈ではわからない人間の愛である。於継が青洲のためにすることは、母親が息子に注ぐ愛から来るものであり、それに加恵が対抗心を燃やすのも、夫を愛するからこそである。二人は雲平を共に愛するのに、不思議と協力できない。これが、人間の愛の、そして限りない欲の恐ろしさなのかもしれない。
一方、医学の研究に没頭する青洲の姿には、いかにも男らしい仕事への熱意を感じて良いのだが、於継と加恵の強い愛を受けていながら、仕事に打ち込むばかりで良かったのか。もう少し嫁と姑の関係を良い方向へもっていくことができなかったのだろうか。これは昔も今も変わらない難題だと思う。しかし、これだけは言えるのが、どういった生き方であれ、振り返って本人が満足するものなら、それで素晴らしい人生だということである。」・・・『トロッコ』の感想文には「大人になれば私も妻子を養っていかねばならないでしょうが、」と書き、『華岡青洲の妻』の感想文には「大部分の人が結婚をし、家庭を築いていく。私もそのつもりである。」と書いた、その堂々たる過去が恥ずかしい。蓋を開けてみると、元々モテなかったことに加え、群馬を営業して間もなく学生時代の恋人だった春代にフラれ、折角スナックで知り合った小春ちゃんとはデートする時間も作れない程の過労だった私。そのままズルズルと婚期を逃し、情けなく独身中年へと落第した。
とは申せ、嫁姑問題など、高校生で無くても「具体的な自分なりの答え」なんて出せないのは巷の夫婦が証明している。結婚できなかった分、ややこしい難問にも巻き込まれずに済んだのだと、負け惜しみを承知で承知するのが妥当解といったところだろう。
――二十六の信州から20年。私は長野県の担当も2年で代わり、営業から京都の本社へ異動を命じられ、以降は本社内で部署を転々とするも、ずっと同じビルへ通勤する日々。このまま「古都で過ごす期間」が「首都で過ごした期間」を追い抜くことだろう。痙攣するような多忙からは解放されたが、幸せにしたい人も自分以外には存在しなくなった。つまらぬ46歳の私をつまらぬ和歌に詠むならば、「父母亡くし きょうだいも無く 妻子無く アル中独り 洛中マンション」といったところだろうか。
親戚一同が位牌の肩を寄せ合い暮らす仏壇に線香を捧げ、梅酒をウーロンハイに切り替え、おととい珍しくデパートに売り出されていた小鮒の甘露煮の真空パックを破き、これを肴に本腰で呑み始めると徐に、鼻が洟で詰まり、目が泪で滲み、口に酒を運べなくなってくる。小鮒は「東信」佐久の郷土料理なれど、同じく甘露な「南信」の名物・ざざ虫の佃煮に出会った衝撃が回想され、その回想が、優しかった得意先、厳しかった得意先、特売に成功した日、納品に失敗した日、励まされた先輩、怖かった先輩へと次々に連鎖し、いつの間に歔欷が止め処無くなったのだ。これが歳を取ると涙もろくなるというやつか。否、涙腺が緩いのは昔からだ。「おしん」「北の国から」「男はつらいよ」を見れば、シリーズどの回でも必ずティッシュを手放せなくなる。力士の平幕優勝でも泣く。下積みの長かった演歌歌手の紅白初出場でも泣く。概ね一日一度は何かで泣く。原爆や震災の慰霊の日なども毎年ただ哀しむのではなく嗚咽に及ぶ。他人に冷たいくせして「健気」なる類への感情移入が甚だしいようだ。
仏壇に二本目の線香を捧げ、ウーロンハイを上撰本醸造に切り替え、おととい珍しくデパートに売り出されていた野沢菜のわさび漬けの真空パックを破き、これを肴にますます本腰で呑み続けると徐に、私は「信濃の国」を口ずさんでいた。知る人ぞ知る長野県歌であり、歌詞にも登場する「松本 伊那 佐久 善光寺」、則ち中信・南信・東信・北信、互いに敵視する「四つの平」の民も、この歌1つで肩を寄せ合う。お隣同士は啀み合うのが宿命。これは世界史のエカチェリーナ先生が教えてくれた通りだった。上州を担当していた時も前橋と高崎の抗争ぶりは映画に出来る程だった。因みに、かの旭将軍義仲を生んだ木曽も忘れないでほしい。高速道路の無い代わりに特急列車のレールで名古屋と繋がっている観光名所が点在しているのを、南信担当者としては聊か羨ましく思ったものである。
「♪信濃の国は十州に 境連ぬる国にして~」…此処に生まれ育ったわけでも無く、学校で習ったわけでも無いのに、20年経った今でも諳んじている。十州というのが現在の8県。静岡が駿河と遠江、岐阜が美濃と飛騨に分れていたから十州。繰り返すが、日本広しと雖も、斯様なパノラマを手中に収める内陸国は他に無い。そういえば、内陸なのに鮨屋の軒数がやたらと多い事にも驚かされた。まさに「♪海こそなけれ物さわに」。私は駒ヶ根で食した大トロの握りが今までの鮪で一番だったと断言する。お通しの「おたぐり」の小鉢や、船盛の上で一際光る「馬刺し」の桜色にも只管感嘆するばかりだった。食べ物の美味を操るのは「立地」よりも「場面」と知った。
「いんね、シンマイは読まんに。そうら、中日新聞ら。ここらはもう中京圏の影響が濃いでな。おらほうじゃ、ガキん帽子はみんな青地にDら。」――シンマイとは信濃毎日新聞のことである。「おもしい企画は何でもやるだに。オレは品物を買うんでないら。君の熱意を買ったんだに。」この陽気なバイヤーさん、すっかりご無沙汰となってしまったが、今もご壮健にお過ごしだろうか。この年の夏あたりから、彼の予言通り、確かにドラゴンズはAクラスまで復調し、母は乳癌のみならず肝臓の一部まで切除した大手術から日常に支障なきまでに回復した。私の贔屓球団だけはパリーグのお荷物として相変わらず低迷していたが、当時の監督が元中日の本塁打王だったという奇跡的なご縁で話は弾み、商談のネタは膨らむばかりだった。あの頃の私の“がむしゃら”が懐かしい。
私の営業時代は当社の業績も低迷していた。そりゃそうだ。私が入社する前から巷は大不況だったのだから。今まで売れていたモノが売れなくなり、減収減益の断崖絶壁。されど、あれから20年。まさに“山田副社長”が「午前4時」と表した暗闇から再び陽は昇り、尤も国内需要の喚起というより海外事業の伸張に因るところが大きいが、昼神温泉の業者新年会で「信濃の国」を大合唱していた浴衣姿の小僧には想像だに出来なかった企業グループへと当社は成長しつつある。私の京都への転勤と同時に北海道へ移転したチームもその後、想像だに出来なかったリーグ優勝を幾度か果たしてくれた。Fの帽子の胴上げなんて、人生で未知なる光景だったものだから、どんなふうに祝ったのかも覚えていない。気が付けば、天竜川の如く暴れ出る感涙に、400枚(200組)のボックスティッシュが優に1箱空いていた。
おっと、一人が忘却の彼方だった。過来方は生涯許すまじと心底怨んでいた上司である。が、最早どうでもよくなってしまっていたのだ。これが時薬というやつか。「仕事の基本はイノベーション&コミュニケーション!」が口癖の癖に、商いは船に刻みて剣を求め、振る舞いは虎の威を借る狐そのもの。周囲からも白眼視されるほど、横暴で蒙昧で品格に欠けたリーダーだった。私は「ええっ!『漢文』の授業に登場する滑稽なまでの悪玉って、フィクションじゃなくって、ホントに実在するんだ!」という率直な感想を抱いたものだった・・・つづく
