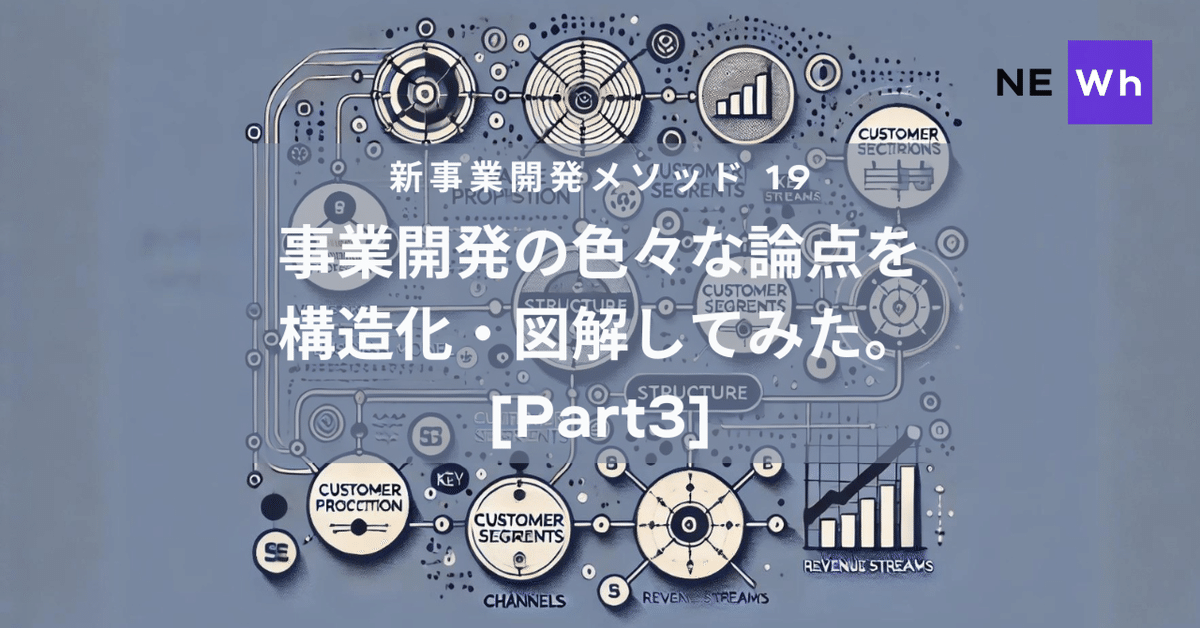
事業開発の色々な論点を構造化・図解してみた。[Part3]
こんにちわ。NEWh堀です。
これまで2度、構造化・図解してみたシリーズをnoteで書いてみてきたのですが、今回はその3回目。まだまだ論点はいっぱいある。
これまでと同様、
事業開発領域における色々な論点の構造を1枚のスライドに落とし、X上で発信している内容から一部を、ピックアップし紹介をしてみました。
part1と、part2記事はこちら。
「問題」と「課題」とは。の図解。

元post
https://x.com/hori_NEWh/status/1805610065191383050
一つ目はこちら。事業開発シーンで最頻出ワードかもしれない課題。でもそもそも課題ってなんだ、問題と何が違うんだ、を可視化してみた図解。「課題とは何か。」というのは結構いろいろなところで語られてるテーマだけど、人によって結構揺れている印象もあったり。いろいろな解釈があっていいだろうし、ケースバイケースだろうし、正解不正解ではないんだけど、私はこう捉えている。というやつ。現在地とありたい姿のGAPが「問題」であり、その配下に潜む様々な要因の中で、自らがピンを止めた要因が「課題」。どこにピンを止めるかは、問題の背景をどう捉えるか、に依存するので、課題の定義には、起案者なりの意思が込められるべきもの。
で、問題と課題がこういう構造だとすると、「いい課題かどうか」だけではダメで、そもそも向き合っているものが「いい問題かどうか」という要素も大事な気がする。
どれだけインパクトのでかい課題を捉えていても、そもそもの問題の重要度が低いとうーむ、だし、その逆もまた然り。
市場を構造化する。のパターンの図解。

元Post
https://x.com/hori_NEWh/status/1669591476345634816
2つ目は市場の構造化。
市場の構造化はSAMTAMSOM的な話もあるけど、ここでの意味合いは、「市場の中には色々なターゲットが混在する中で、どのような分布、構造になっているのか、その上で我々は誰を顧客とすべきか。」的なターゲット論において用いる意味合いでの市場の構造化。
市場の特性やセグメントの上での軸要素次第で、適切な可視化のアプローチって違うよね、という整理。
一番左がBOX図、真ん中がベン図、右がバブルチャート。
どれも使い所はそれぞれあるけど、個人的にはBOX図が好き。
競争環境を可視化する。の図解。

3つ目は、2つ目と同じく市場の構造化パターンの競争環境Ver.
これも色々あるよね、というやつ。
強弱を捉える戦略キャンバス、守備範囲と動きを捉えるドメインマップ、立ち位置を捉えるコレポン(コレスポンデンス分析))。
広告代理店時代はコレポンを使ってたこともあったけど、事業開発シーンだとあまり使わなくなったかも。
他にも可視化のアプローチは色々あるだろうけど、
基本戦略キャンバスとドメインマップがあれば十分な気もしたり。
ステージゲート設計における論点。の図解

元Post
https://x.com/hori_NEWh/status/1781954095395532968
4つ目はちょっとニッチかもしれないけど、企業内事業開発を支える仕組みである「ステージゲート」設計における論点。
ステージゲートと聞くと、"ゲート"の言葉が強く、どう新規事業を評価すべきか、という側面に意識が持ってかれがちだけど、
"ステージ"ゲートという言葉の通り、ゲートとゲートの間に挟まるステージで何を起案者は活動すべきなのか、という活動側の定義の側面も当然ある。
さらに、
ステージと、ゲートだけでは起案者丸投げな側面もあるので、求めるゲート(評価/要件)に向けて、適切なステージ(活動)が展開されるように、インフラとしての起案者を支援する仕組み/機能も当然論点として上がるべき。
どう評価するか、起案者はどのような活動を行うべきか、何を支援するのか。の3点セット。評価者と起案者と支援者(組織)がまさに三位一体となるべきものだよね。というやつ。
投資家が求める観点と起案者/起業家が答えるべき12の問い

最後はこちら。これはほりだけでなく、クオンタムリープベンチャーズ(QXLV)さんと一緒に議論しながら作ってみたもの。
スタートアップシーンにおけるVCが起業家/事業に対してみている観点と、起業家目線で答えるべき問い。
ほりの普段の領域は企業内事業開発で、QXLVさんはスタートアップで、シーンは違うんだけど、企業内事業開発との共通項も多い。
お気に入りは、
自らの描く事業を実現できるのか、という観点であるじっこう性。
・スピード感を持って、やり切れる熱量/パーソナリティがあるか=実行力
・事業実現上の肝となるようなケイパや知識、チャネルを抑えられているのか=実効力。
確かに。
まとめ。
今回も5つほど、X上でのpostからピックアップして紹介してみました。
まだあるので、またそのうち整理して発信する。
ちなみに私のXアカウントはこちら。
https://twitter.com/hori_NEWh
定期的に思いついたタイミングでこういうこと発信してるのでご興味あれば!
