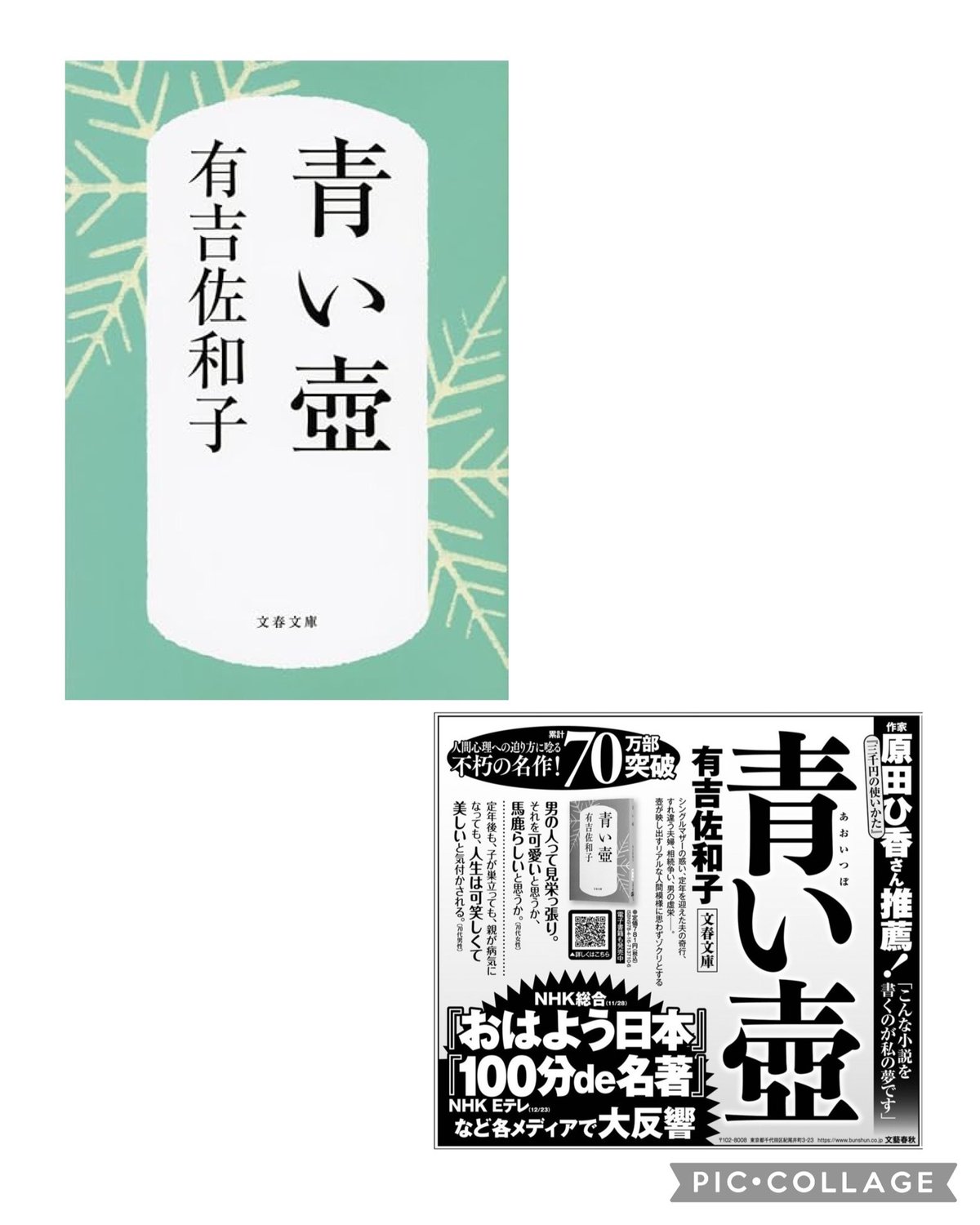ようやく読んだ有吉佐和子〜「青い壺」が見る日常のドラマ
ずっと気になっているが読めていない小説家が何人かいます。有吉佐和子がその一人。私が敬愛する橋本治は若い頃から有吉作品を読んでいて、面白いと書いていたからです。
有吉佐和子と言えば、実家に同居していた祖母の箪笥の上に、「恍惚の人」(1972年)が並んでいたことをよく覚えています。当時、新潮社からは「純文学書き下ろし作品」というシリーズが出ていた、立派な箱入りの本でした。
このシリーズは装丁が素晴らしく、とても魅力的に見えていて、大江健三郎「同時代ゲーム」(1979年)を買って、満足していました。後年ですが、村上春樹「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」(1985年)、小林信彦「ぼくたちの好きな戦争」(1986年)もこのシリーズから発刊され、憧れのシリーズが、自分に近づいてきたと感じていました。
一方で、有吉佐和子という作家は、“おばあちゃん“が読むもの、私のレーダースクリーンには映りませんでした。それが、橋本さんの発言で考えを改めたのです。
にも関わらず。。。。有吉佐和子を読めていませんでした。
背中を押したのは、「青い壺」(文春文庫)の新聞広告。TV番組でも取り上げられ、ベストセラーになっていると宣伝されていました。そして、ようやく読み始めたのです。
これが、滅法面白い。第1話、名匠の父が他界し、省造は<派手に名を売ることは極力避け、地道に制作を続けている>(「青い壺」より)。青磁一筋に、<寺やデパートが配りものにする香炉や壺>を作っているのですが、一点物で焼いた壺が素晴らしい出来栄えです。“青い壺“の誕生です。
こうして世に出た“青い壺“の数奇な運命が、それを所持する人々の生活と共に描かれていくという連作となっています。
ドラマは日常の中に潜んでいる、有吉佐和子はそんなことを言っているようにも思います。そうした、人間のドタバタを、静物である“青い壺“が見つめる。いや、実は“青い壺“がドラマを演出しているのかも。
祖母が生きていた時分に、有吉作品を読んでも、私にはピンとこなかったように思います。この歳になると、「青い壺」の様々なエピソードが、現実味を帯びて響いてきます。可笑しくなったり、ちょっとヒヤッとしたり、自戒したり。
全十三話ですが、第九話は私のお気に入りの一編。女学校時代の同級生が、五十年振りに三泊四日の団体旅行、京都へ行くエピソード。お洒落でもあり、毒もある。好きなセリフ、八十まで生きられるかどうかを話す七十代の元女学生たち。一人がこう言います。
<「八十なんて、世の中に怕い(こわい)ものなんか何もないって気になるんじゃないかしら」>
ちなみに、「青い壺」が上梓されたのは、1977年です。しかし、この小説はまったく古めかしい感じがしません。有吉佐和子が、人間の心に中に潜む普遍的なものを、時代を超えて通用するようなスタイルで描いた、そんな気がします。
ほかにも、待機している本が沢山あるのに、有吉作品にまた手を伸ばしてしまいそうです
*「青い壺」はAmazon Audibleで聴くこともできます