
いい人すぎるよ展×スコット・アラン『GRATITUDE』
教育を本気で語る会、読書大好きのマサです。
最近、SNSで話題になっている「いい人すぎるよ展」について
以前に読んだスコット・アランさんの著書『GRATITUDE』との
共通点について考察しました!
なかなか会場まで足を運ぶ時間がなかったので
SNSやHPで感想やコンテンツなどを見ていた時に
「めっちゃ似てる!」と思ったので
今回はその気付きをまとめてみます!

1 いい人すぎるよ展
「いい人すぎるよ展」は、日常の些細な善意に光を当てる企画展です。
従来のコンテンツに加え、子どもたちのワークショップ
「いいひとすぎるよてん」や、
「かわいい人すぎるよ展」、「心配すぎるよ展」など、
多様な感情に基づく作品が大人気を博しています。
このようにして、「いい人すぎるよ展」は単なるアート展示にとどまらず、観客に感謝や思いやりの重要性を再認識させる場として機能しています。
地域住民との交流を促進することで、
より深い感動体験ができます。
特に「地域住民との協働で制作するご当地コンテンツ」は、
参加者が日常の感謝を改めて見つめ直す機会となっています。
ここが特に印象的だったポイントです!
日常の感謝に意識的に気づくことといえば、
これはまさに『GRATITUDE』の大きなテーマでした!

2 スコット・アラン『GRATITUDE』
この書籍では、感謝の実践が人々の生活をどのように
好転させるかに焦点を当てています。
日常生活における小さな感謝の気持ちが、
心の健康や人間関係を改善する重要な要素です。
この理論は「いい人すぎるよ展」のコンセプトと深く結びついています。日常生活の中で見逃されがちな「いい人」の
行動や思いやりに焦点を当て、
観客に感謝の気持ちを再認識させることを目的としています。
展覧会で展示される作品や体験は、
アランが提唱する感謝の習慣と共鳴し、
観客にポジティブな感情を喚起します。
たとえば、展示内で紹介される「中腰で笑ってくれる人」や
「トイレをきれいに使ってくれる人」といった具体的な例は、
日常生活に潜む小さな善意を象徴しています。
また、アランが強調する「感謝実践による幸福感の向上」は、
展覧会における参加型アートやワークショップとも関連します。
観客が自らの体験を共有し、互いの善意を認め合うことで、
感謝の気持ちが育まれます。
このように、「いい人すぎるよ展」は
アランの理論を実践的に体現してます!
3 日常の善意への注目
スコット・アランの理論と「いい人すぎるよ展」の共通点は、
感謝と共感の重要性にあります。
アランは、感謝の実践が心の健康や人間関係を改善することを強調し、
日常生活における小さな善意や感謝の気持ちが
幸福感を高めると述べています。
展示内で紹介される具体的なエピソードや作品は、
アランが提唱する感謝の習慣と共鳴し、
観客にポジティブな感情を喚起します。
さらに、アランの理論では、感謝が他者とのつながりを強化し、
コミュニティの絆を深める役割を果たすとされています。
同様に、「いい人すぎるよ展」では、
来場者が自分自身や周囲の人々について思い出し、
共感する機会が提供されます。
観客同士が「いい人」としての体験を共有することで、
より豊かな人間関係が築かれることが期待されます。
アランは、感謝の実践が幸福感を高めるだけでなく、
ストレス軽減にも寄与すると述べています。
日常生活から得られる喜びや満足感が増し、
心の健康にも良い影響を与えることが狙われています。
そして、このとき気づいたのが、感謝とストレスの相関性です!
次回は、この感謝の習慣とストレスの緩和がいかに重要か、
青砥瑞人さんの書籍『HAPPY STRESS』と交えながらお話していきます。乞うご期待!
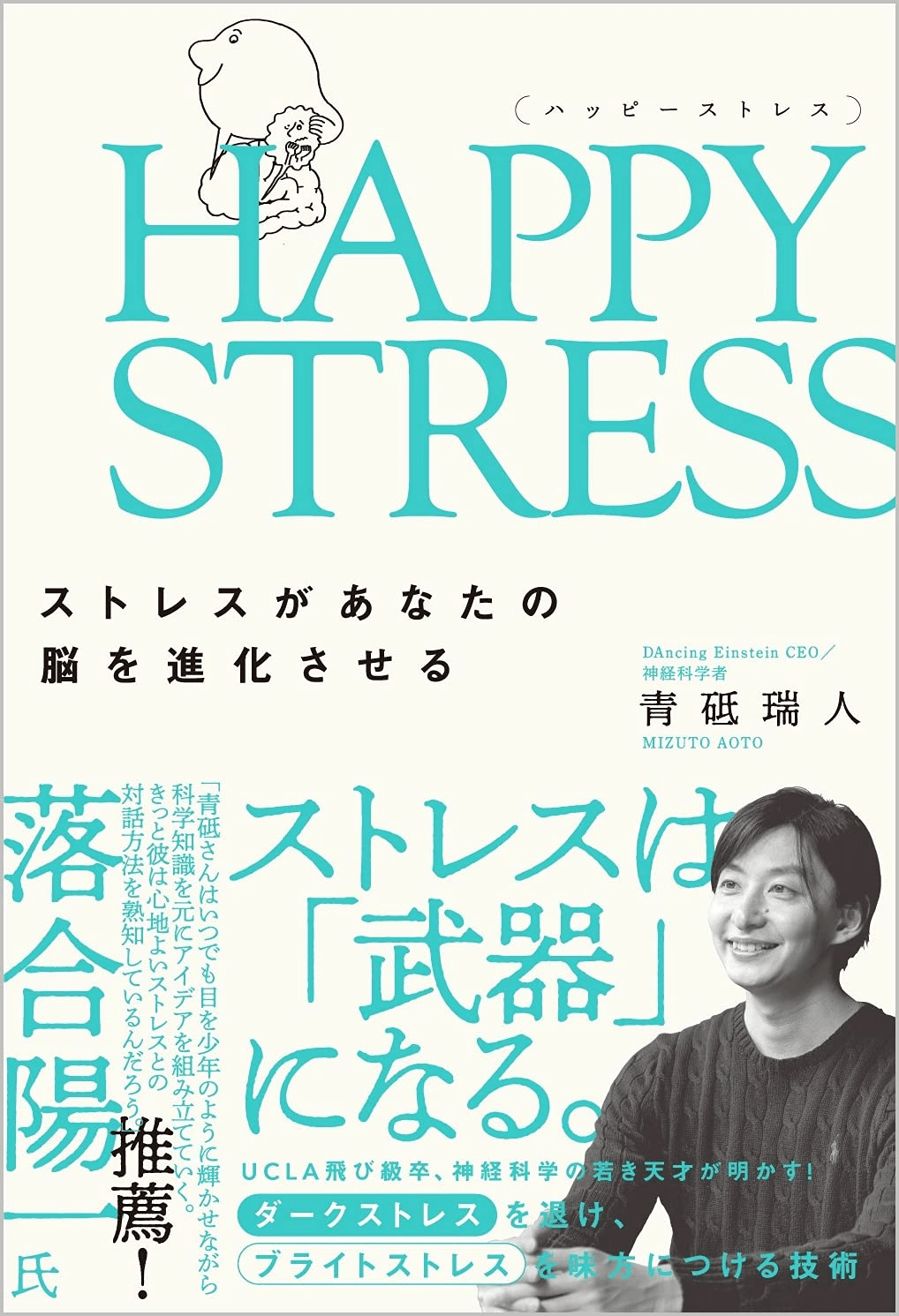
「教育を本気で語る会」ではX(twitter)、 Facebook、 Threads、spotifyでも発信しておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。
