
「ゑとり」と「得たり」(非人)のハロウィンパーティー
「えた」「 ヱタ」「穢多」「ゑとり」「餌取」(えとり)


「恵」(gratia)を持つ者は「恵多」「恵取」とされたらしい。



「恵」とは「禊」によって見い出される「三貴子」を言う。
「古事記」は「乞食」(こつじき)だった。
たくはつ【托鉢】
piṇḍapātika
仏教僧が経文を称えながら鉢を持って人家を回り食べ物を乞うこと。乞食(こつじき)のこと。中国,宋時代からこの語は使われるようになった。
こじき【古事記】
日本現存最古の歴史書,文学書。3巻。序(上表文)によれば,天武天皇の命によって⇨稗田阿礼(ひえだのあれ)が「誦(しょう)習」していた『⇨帝紀』『⇨旧辞』を,元明天皇の命によって⇨太安麻呂(おおのやすまろ)が「撰録」し和銅5(712)年献上したものである。しかし,「誦習」「撰録」の具体的内容については諸家の説が分れ,また序を疑う説,ひいては『古事記』そのものを偽書とする説もあるが,上代特殊仮名づかいの存在により和銅頃の成立であることは確実。天地の始りから推古天皇の時代までの皇室を中心とする歴史を記すが,実質的には神話,伝説,歌謡,系譜が中心で,そのため史料としてはそのまま用いがたい面が多いが,逆に文学書としては興味深い存在といえる。
きゅうじ【旧辞】
『旧事』とも書き,「くじ」とも読む。また『上古諸事』『先代旧事』『本辞』ともいわれる。天皇家の系譜的記事である『⇨帝紀』とともに作成された書物。5~6世紀頃,大和朝廷が国家と民族の過去を顧みようとする歴史的自覚から作られたらしい。現在は伝えられず,『⇨古事記』や『⇨日本書紀』の編纂史料として吸収された記事(因幡の白兎や海幸・山幸の話など)からその内容が推察される。



みそぎ【禊】
身体に罪や⇨穢れのあるとき,または神事の前に,川や海の水につかって,身体を洗い清めること。特に祭りの当事者や神役は,禊によって身体を清浄な状態にすることが必要であった。「記紀」によるとイザナギノミコトが黄泉(よみ)国から帰ったとき,筑紫日向の橘の小戸(おど)の檍原(あはぎはら)の流れで禊をしたのに始るとされる。
三貴子(みはしらのうずのみこ、さんきし)とは『古事記』で黄泉の国から帰ってきた伊邪那岐命(イザナキ)が禊(水浴)で黄泉の汚れを落としたときに最後に生まれ落ちた三柱の神々のことである[1]。イザナキ自身が自らの生んだ諸神の中で最も貴いとしたところからこの名が生まれた。三貴神(さんきしん)とも呼ばれる[1]。
天照大御神 - イザナキの左目から生まれたとされる女神(本来は男神だったとする説もある[2])。太陽神。
月読命 - イザナキの右目から生まれたとされる神(性別は記載していないが、男神とされることが多い)。夜を統べる月神。
須佐之男命 - イザナキの鼻から生まれたとされる男神。海原の神。
『日本書紀』本文は伊弉諾尊と伊弉冉尊が共に「いかにぞ天下の主者を生まざらむ」と言って最後に生んだ四柱の神々のうち三柱で、月神の後、素戔嗚尊の前に蛭児(ヒルコ)も生んだとする。
えたがしら【穢多頭】
江戸幕府が関八州(相模,武蔵,安房,上総,下総,常陸,上野,下野),甲斐,伊豆,陸奥,駿河の 12ヵ国の⇨穢多を統率するために任命した役人。浅草の⇨弾左衛門がそれで,長州征伐後,その配下とともに解放された。また,一部の諸藩でも設けられた。
えた ヱタ
(「下学集」など中世以降、侮蔑の意をこめて「穢多」の2字を当てた)中世・近世の賤民身分の一つ。牛馬の死体処理などに従事し、罪人の逮捕・処刑にも使役された。江戸幕藩体制下では、非人とともに士農工商より下位の身分に固定、一般に居住地や職業を制限され、皮革業に関与する者が多かった。1871年(明治4)太政官布告により平民の籍に編入された後も社会的差別が存続し、現在なお根絶されていない。塵袋「ゑとりをはやくいひて、いひゆがめて—と云へり、たととは通音也」→部落解放運動
塵袋「ゑとりをはやくいひて、いひゆがめて—と云へり、たととは通音也」
えた【穢多】
封建時代の主要な賤民身分。語源はたかの餌取(えとり)という説があるが,つまびらかでない。南北朝時代頃から卑賤の意味をもつ穢多の字があてられるようになった。鎌倉,室町時代には寺社に隷属する手工業者,雑芸人らを,穢多,⇨非人,河原者,⇨散所(さんじょ)などと呼んだが,まだ明確な社会的身分としての規定はなく,戦国時代に一部は解放された。江戸時代に入り封建的身分制度の確立とともに,没落した一部の住民をも加えて,⇨士農工商の身分からもはずされた最低身分の一つとして法制的にも固定され,皮革業,治安警備,清掃,雑役などに職業を制限された。皮多,長吏,その他の地方的名称があったが,非人よりは上位におかれた。職業,住居,交際などにおいて一般庶民と差別され,宗門人別帳(→宗門改帳)も別に作成された。明治4(1871)年8月 28日太政官布告でその身分制は廃止され,形式的には解放されることになった。幕末には 28万人を数えた。(→賤, ⇨部落解放運動)
おんけい【恩恵】
charis; gratia; grace
恩寵,聖寵,恵みとも訳される。人間に⇨救済をもたらす神の恵みのたまものをいうキリスト教神学の基礎概念。その解釈については各教会,各学派で異なる。中世神学によれば,人間は有限の目的のため創造され,これに必要な能力がそなえられた(これを自然という)が,さらに神の無償の好意によって,無限な神自身を知と愛の目的とするよう高められ,その達成に必要な性質や能力を新たに与えられた。この性質,能力を恩恵,新しい次元全体を超自然または⇨義の状態という。人類は全体として神にそむき(→原罪),この超自然の状態を失ったが,イエス・キリストの受肉と死と復活によってこの状態を回復した。それゆえ,恩恵はさらに罪のゆるしをもたらし,「キリストの恩恵」とも呼ばれる。恩恵が衣服のように人間本性に異質であれば,それによる救済は単に外面的なもの,強いられたものにすぎなくなる。逆に本性に内在的であれば,当然のものとなり,神からの絶対的無償性がそこなわれる。後者の線を強調したのが⇨ペラギウス派で,それによれば創造がそのまま恩恵であり,救いは結局人間の自力によるものとなり,⇨律法主義,パリサイ主義(→パリサイ派)につながる。前者を推し進めればマニケイスム(→マニ教)で,人間本性は根源的に堕落,悪化,破壊されたままにとどまり,救いは「人間の」救いではなく神の一方的意志行為にすぎなくなる。この緊張関係は,すでに新約の時代から,信仰による義を強調した⇨パウロ,善業の必要を説いたヤコブ書に象徴されるように,教会の全歴史を通じて存在し,恩恵は自然を破壊せず,むしろそれを前提とし,完成するとの公理にもかかわらず,問題は完全に解決されることなく,恩恵と自由意志の問題として今日まで論争されている(→恩恵論争)。宗教改革においてはカトリック側はペラギウス的傾向にひかれ,プロテスタント側はマニケイスム的傾向に傾いて信仰のみによる義を強調し,恩恵は堕落し破壊された人性を内在的に回復高揚することなく,単にそれによって神が人間を義とみなすという⇨義認説をとった。
こうかてきおんけい【効果的恩恵】
gratia efficax
カトリック神学の概念で,神の⇨恩恵を人間における結果の面からみたもの。充足的恩恵 gratia sufficiensに対するもの。後者が所定の効果(救い)を生じるに十分でありながら,人間の側からの協力のないため効果を生じないのに対し,前者は必ず人間の協力をもたらし効果を生じる恩恵である。しかも意志の自由は奪わないとされる。アウグスチヌスに基づき,恩恵と自由を調和させようとする思想(→恩恵論争)。
じゅうそくてきおんけい【充足的恩恵】
gratia sufficiens
⇨恩恵に関するカトリック神学上の概念。恩恵と人間の意志の自由の関係について L.⇨モリナが提出し⇨恩恵論争を巻起した。魂の救いに必要な効果を生じるに十分な恩恵であるが,人間の側からの自由な協力がないため効果を生じないもの。非効果的恩恵とも呼ばれる。(→効果的恩恵)


ゑ
①五十音図ワ行の第4音。平安中期までは「う」に近い半母音〔w〕と母音〔e〕との結合した音節で〔we〕と発音し、ア行・ヤ行の「え」と区別があったが、以後混同し、現代の発音は「え」〔e〕と同じ。
②平仮名「ゑ」は「恵」の草体。片仮名「ヱ」は「恵」の草体の終りの部分。
「ルンペンプロレタリアート」は「非人階級」だった。
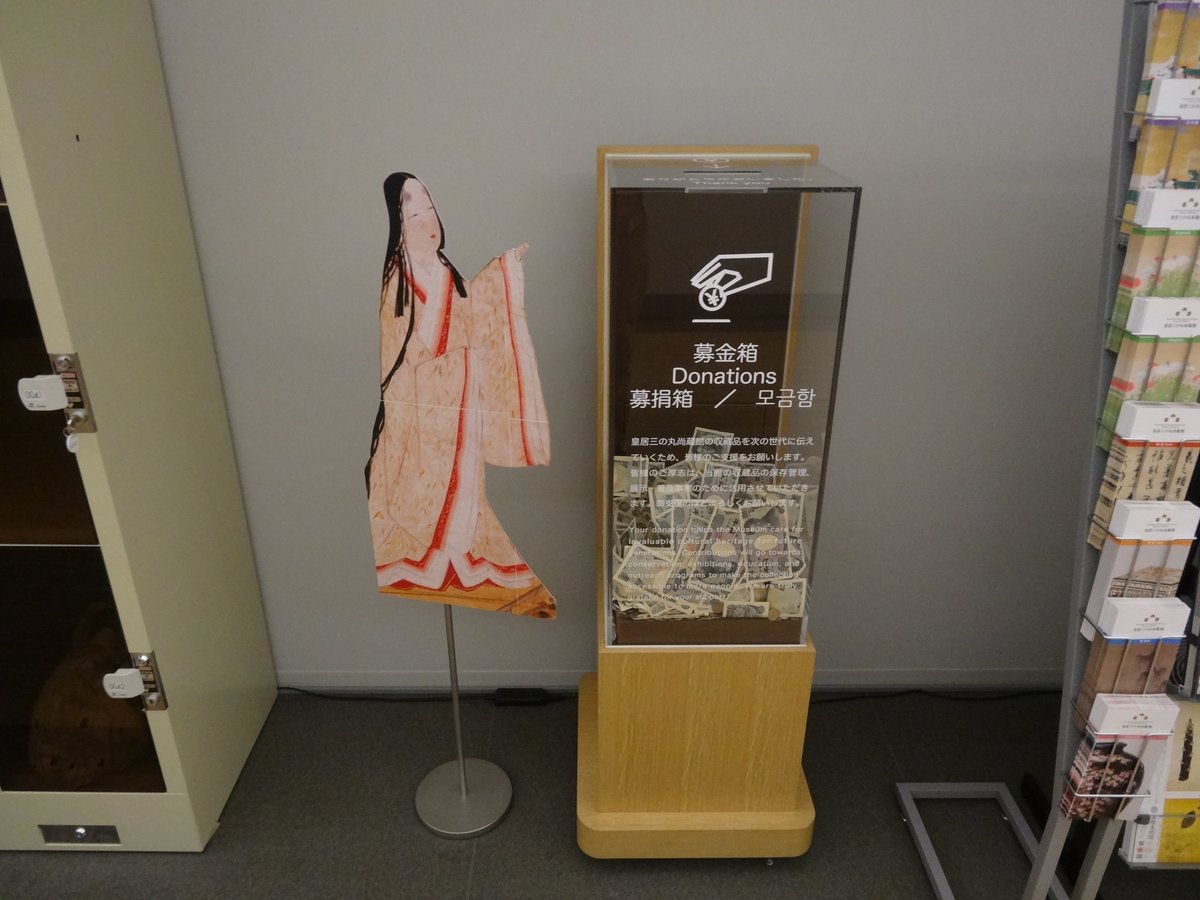
「得たり」は「非人」を示している。
それはルンペンを意味する。
lum・pen [lʌmpən]〓
―adj. 社会的地位を失った人(たち)の,ルンペンの,浮浪者の,根無し草の.
―n. ルンペン,浮浪者.
[1948.LUMPENPROLETARIAT から抽出]
lum・pen・pro・le・tar・i・at [lʌmpənpròulitέəriət]
―n. ⦅時に L―⦆ (特にマルクス理論で)ルンペンプロレタリアート:未熟練労働者,浮浪者,犯罪者を含む最下層のプロレタリアート;階級意識や連帯性に欠ける.
[1924.<ドイツ語(1850年の K.Marx の用語)=Lumpen ぼろ服をまとった人,または Lumpen―(Lump「ぼろ服を着た汚い人」の連結形)+Proletariat 無産階級(PROLETARIAT)]
え‐たり【得たり】
〔連語〕
《動詞「う(得)」の連用形+完了の助動詞「たり」。感動詞的に用いる》事がうまく運んだときや、事をうまくしとげたときに発する語。しめた。うまくいった。「統一もなき無趣味の三十一文字(みそひともじ)となし自ら―とする事初心の弊なり」〈子規・墨汁一滴〉
え‐たり【得たり】
(動詞ウ(得)の連用形に助動詞タリが付いた形。感動詞的に用いる)うまくいった。しめた。古今著聞集(12)「—や—やと大声を出(いだ)す時」
ひ‐にん【非人】
①〔仏〕人間でないもの、すなわち天竜八部衆などの類。開目抄「人(にん)—等の一切の衆の前に於て」
②出家遁世の沙門。世捨て人。正法眼蔵随聞記(2)「我は—也、遁世籠居の身なれば」
③いやしい身分の人。極貧の人や乞食(こじき)を指す。仮名草子、伊曾保物語「汝、乞食—をいやしむる事なかれ」
④江戸幕藩体制下、えたとともに四民の下におかれた最下層の身分。卑俗な遊芸、罪人の送致、刑屍の埋葬などに従事した。
⇀ひにん‐あずけ【非人預】
ひにん【非人】
江戸時代の最下層身分,またはその身分の者。中世では賤民身分の呼称の一つであったが,江戸時代には⇨穢多(えた)と非人は区別され,それぞれ一つの身分をなしていた。親子代々その身分を世襲する非人と,軽犯罪,貧困などで庶民から転落したものとがあり,職業を制限され,物乞,遊芸,行刑などにあたった。江戸では穢多頭支配下の非人頭(車善七ら)に属し,身分上,穢多より下位にあったが,農工商身分に復帰する道もあった。明治4(1871)年その身分制が廃止された頃は全国に2万 3480人を数えた。(→賤, ⇨番太)
非人
(ヒジン)
①死人のようになった人。
②身体に障害のある人。
③自然のままで、人為によらないこと。
④ならず者。
⑤(ヒニン)㋐〓人間でないもの。夜叉(ヤシャ)・悪鬼など。㋑貧窮者。㋒罪人。㋓世捨て人。法師。
ひにんよせば【非人寄場】
⇨人足寄場
「非人寄場」の記述はない。
「人足寄場」は「職業訓練」だった。
にんそくよせば【人足寄場】
正式名称は加役方人足寄場。江戸幕府が設けた無宿人収容所。松平定信は⇨寛政の改革に際し,寛政2(1790)年江戸⇨石川島に収容所を設け,無宿人,刑期を終えた浮浪人などに大工,建具,塗物などの技術を修得させ,その更生をはかった。以後,幕末まで存続。
ひにん‐てか【非人手下】
江戸時代、庶民に科した付加刑で、非人身分に落とすもの。非人頭に引き渡し、その部下に編入した。
ひにんてか【非人手下】
江戸時代,庶人に科せられた刑罰の一つ。『公事方御定書』には,以前よりの例として,「弾左衛門立会いのうえ,非人頭へ渡す」とある。つまり,その籍に入れ,非人としてしまうことをいう。また,特に罪科の重い場合は,遠国に送遣して遠国非人手下とされた。心中(相対死)して双方とも死にそこなった場合には,男女とも3日さらしのうえ弾左衛門引渡しに,また姉妹,伯母,姪と密通した場合には遠国非人手下にそれぞれ処せられる定めであった。
ひにん‐ごや【非人小屋】
非人が起居する小屋。幕府・諸藩で、非人・乞食などを収容し、職業補導等を行なった施設。非人寄場(よせば)。
ひにんごや【非人小屋】
江戸時代,幕府や諸藩で設けた⇨非人,乞食,貧民などの収容,授産施設。幕府の非人寄場,加賀藩の非人小屋などが知られる。江戸では浅草,品川などに非人小屋が建てられ,非人頭がその支配にあたった。小屋は掘建て小屋で,天井を張ることは禁じられていた。
④江戸幕藩体制下、えたとともに四民の下におかれた最下層の身分。卑俗な遊芸、罪人の送致、刑屍の埋葬などに従事した。
ひにん‐あずけ【非人預】 ‥アヅケ
〓「ためあずけ(溜預)」に同じ。
ため‐あずけ【溜預】 ‥アヅケ
江戸幕府が重病および15歳以下の犯罪人にとった囚禁の措置。品川・浅草両所にあった非人小屋の溜(ため)に預け、平癒・成長を待って刑を執行した。非人預。
ため‐あずけ【溜預】 ‥アヅケ
江戸幕府が重病および15歳以下の犯罪人にとった囚禁の措置。品川・浅草両所にあった非人小屋の溜(ため)に預け、平癒・成長を待って刑を執行した。非人預。

