
紙ものあれこれ2:「紙箱を作りたい」から生まれた絵本のようなZINEのはなし
こんばんは。今日は「紙ものあれこれ」その2。紙箱とじゃばらの絵本のようなZINEのお話をしてみたいと思います。
初めて作ったZINEについての記事をたくさんの方にご覧いただけて嬉しかったので、今回はその第二弾。相変わらず長めですが、お付き合いいただけましたら幸いです。
よかったら第一弾も読んでみてくださいね。
「紙博」がやってくる
さて、そもそものきっかけは、2023年の3月に手紙社さんの主催する「紙博」といイベントの「ZINE・出版」コーナーにお声かけいただいたのがきっかけでした。
紙博は、イラストレーターや写真家さんなど個人で活動されている作家さんや、魅力的な紙ものを扱う個人のお店、メーカーさんなど、紙にまつわる作り手が一堂に集う、紙もの好きにはたまらないイベントです。
2017年に誕生以来毎回とても賑わい、私も初回からスタッフとして参加していたのですが、まさか出ることになるとは……!! ところが当時くらしの学校でご用できるものといったら小さなZINE1冊(在庫僅少)、ブックカバー、ポストカードの3種類と、私個人で作ったポストカードが数種類、久米さんの額が数点のみ……。

そして会場となる浅草の台東館さんの机は、普通の会議机の倍の奥行きがあり、1台でもかなり大きいのです。このままではスカスカのブースが誕生してしまう……。なんとかしてお客さんに楽しんでいただけるように新作を用意せねばなりません。
ということで、「くらしの学校 紙もの増産計画」が始まりました。
紙箱が作りたい&ZINEが必要
ひとまず今あるもの、作りたいものをひたすら紙に書き出して、作戦を練ることにしました。開催まで2ヶ月ない状況だったので、納期が長いものはNG。書き出した中で、久米さんとふたりで「これは絶対作りたい!」となったのが「スタンプ」「ラッピング袋」「紙箱」の3つでした。
今日は紙箱のお話なので、スタンプとラッピング袋については写真を少しだけ

イベントでは「いそう〜!」「こっちはいなさそう〜(笑)」と楽しそうに見てもらえて、嬉しいです

インドの絨毯の模様をイメージして描きました。
紙箱の浪漫
突然ですが、紙箱って浪漫があると思いませんか。
前々からずっと、ずーっと作りたかったんですが、
コストが高い・小ロットで作りにくい・保管が嵩張るの三苦で、なかなか手が出せずにいました。実はお勤めしてた頃も、紙箱を作りたい!と提案してはいたのですが(会社で他の作家さんと一緒に作るグッズのお話です)やっぱり「紙箱は難しいんじゃない?」ということで、夢叶わず。
ですが、紙の目利きが集まる、素材としての紙や印刷加工を愛する人たちが集まる紙博なら、きっと同じようにときめいてくれる人もいるはず。ということで、紙箱作りが決定しました。
そうして出来上がったのがこちらの2種類。

小さい茶色の方が、名刺サイズ。グレーの方は、横幅は同じでロングサイズです。どちらもマッチ箱のようなスライド式。シルバーと黒の箔押しでイラストを印刷してもらいました。とっても綺麗に仕上げていただいて、ふたりともほくほくでした。

私は小さい方を名刺入れにして使っています

さて、多分お店でこの箱を見ても、まさかZINEが入っているとは思わない人がほとんどだと思います。紙雑貨を入れるにしても、ミニカードとか、ラベルとか、そういうものの方が馴染みがありますよね。
ではなんでこんな形になったのでしょう。
まず最初に考えたのは、紙箱を開けるときのワクワク感が欲しいな、ということでした。はじめ、カードを入れる想定をして試算した際に、ある程度のボリュームを出せる量入れようと思うと、なかなかの販売価格になってしまうことがわかりました。印刷業を生業とするメーカーさんみたいな価格では、なかなかどうして作れません……。でもやっぱり、開けた時にスカスカしているのはがっかりしてしまいますよね。
そして私たちは「ZINE・出版」のコーナーにお声かけいただいていて、当時くらしの学校のZINEは「UNE PETITE MAISON」の1種類だったので、せめてもう1、2種類は欲しいね、と話していました。
そこで「紙箱いっぱいのボリュームのある中身」と「ZINEを作りたい」が合わさって「紙箱の中にZINEを詰めたら楽しいのでは?」となったわけです。

今回のZINEも蛇腹折りは手作業です。なんとなく「ハリセンの要領で簡単に折れそう!」と思ってスタートしたのですが、きちんと規定の幅で折ろうと思うとこれがなかなか難しい……。リソグラフで両面印刷するので、透けない厚みの用紙を折ることを考えるとスジ入れするのですが、定規で測った位置にスジを入れていっても、紙の厚みの計算がなかなか難しく、びっくりするぐらいずれてしまうのです。

最終的には久米さんが、厚紙の台紙に、折り目位置に合わせた幅1mmの溝を切り抜くという見事な技を披露してくれて、そこに合わせてスジを入れることで無事に蛇腹折り本が完成したのでした。建築模型づくりで鍛えられたカッター捌きに感謝です。

一軒の家と、その住人たちの物語
先に製本のお話を書いてしまいましたが、一番難産だったのは中身でした。くらしの学校として作るので、家や建築にまつわるものが良いけれど、雑貨としてもちゃんと魅力があるものに仕上げたい。箱と中身の関連性も欲しい。そんなところから生まれたのが、
一軒の家を描いたパッケージ と そこに住む住人たちのZINE でした。
図書館でカバンがはち切れそうなくらいのヨーロッパの家の写真資料を集めてきて、
捲り、時にgoogle mapで調べ、あれこれスケッチをしながら、イメージとする街並みを決めました。

「Sunny day & Rainy day」と名付けたこちらは、イギリスの海辺の町にある家をイメージ。六角形を半分に割ったような形の、サンルームとその上に広々としたバルコニーがあるお家です。「晴れの日」と「雨の日」をテーマにした、小さなZINEが入っています。

「Morning & Night」と名付けたこちらは、デンマークの漁村のイメージ。茅葺き屋根に惹かれて、鶏小屋のある長閑な村の中にある一軒家にしました。こちらの中身は「朝」と「夜」をテーマにしたZINE。
すごく小さいですが、実はどちらもパッケージの中に住人の姿があります。手に取った方は、ぜひ目を凝らしてみてくださいね。
実は初めは海外のアルファベットの絵本やかるたのようなイメージで、例えばMorningであれば「朝にまつわるアイテムのイラストと、その名前を英語で綴ったページ」が淡々と続く本を考えていました。物語というよりは、雑貨っぽいイメージですね。
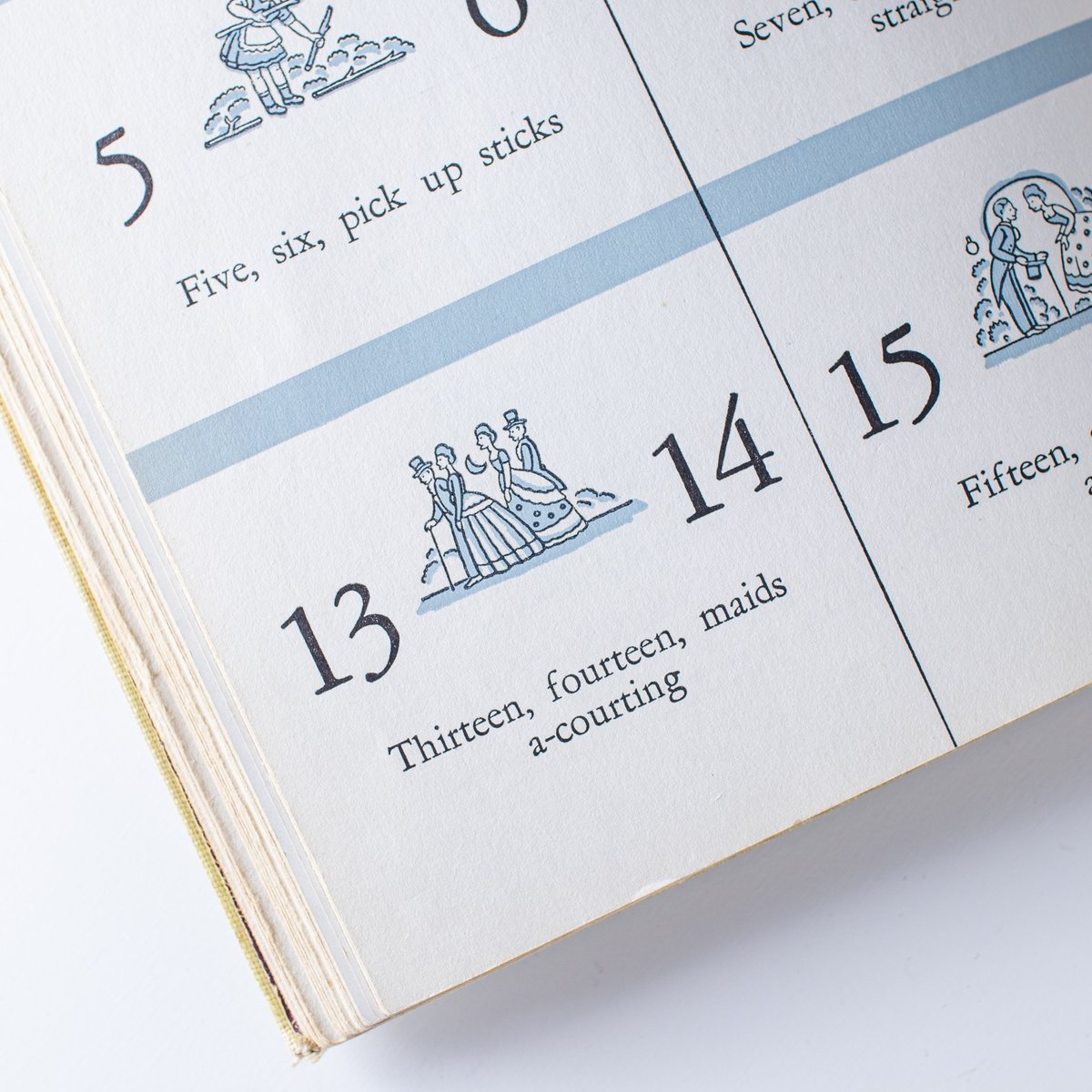
けれど考えているうちに「主人公がいた方が楽しいかな」「少し物語があった方が面白いかも」とずんずん深みにはまり、気がついたら絵本のような形に。

「Sunny day」と「Rainy day」の住人は、どちらもお気に入りの椅子は同じのよう。
元々絵本が大好きで、特に海外の古い洋書絵本を前にするとすっかり財布の紐が緩くなってしまう私ですが、物語を考えるのは苦手。絵本は描いてみたいけれど、物語は書けないな、と諦めているところがありました。
このnoteで、何度も「絵本のようなZINE」と描いているのは、正直なところ絵本と呼んで良いのか、ちょっと自信がないから、という理由もあります。絵を描いてからも、何度も何度も文章を直して、また絵も直して……本当に直前の直前まで悩み続けて、出来上がったのがこの4冊でした。
刻々と迫る締め切りに(本当にイベント直前に出来上がったのです……)苦しくなりながらも、とても楽しかったのは、やっぱり絵を描くところ。1ページずつ捲っていく本としての体裁がベースではありますが、2ページの見開きや、時には5ページ分に連なる絵など、ページの大きさを自由に使える蛇腹ならではの構成を考えるのは、本当にワクワクする時間でした。

苦手、と言いつつ、やっぱり文字を読むのはずっと好きなので、言葉も大切にしたくて、本当に何度も何度も直して、読んでもらって、また直して。

幸い何とか時間に完成を決められることなく、自分で「完成!」と言って仕上げることができました。おかげでイベントはものすごい睡眠不足でしたが、アドレナリンが出ていたので開催中はすっかり疲れも忘れ、とても楽しい時間でした。
お話自体は、なんてこともない日常を描いたものです。でも、それと同時に、大切にしたいなと思ったことを描いてもいます。あとはやっぱり「くらしの学校」から発行する本なので、窓の金具や、玄関のタイル、街並みに潜む植木の形、窓格子やドアの装飾、昔から受け継がれてきた、愛らしい家具。建築を見て楽しむ、気軽に楽しむことを身近に感じてもらえたらなと思って、絵のモチーフを選びました。

実は後書きに書こうと思って、一度書いて、消した文章が4冊分ありました。どんなことを思って、それぞれの本を書いたかについてです。消したのは、読んだ人に自由に見てもらいたかったから。けれど、私自身が読者になる時、作者の言葉を読むことも好きなので、その中からひとつだけ、ここにひっそり残しておきたいと思います。

世界の国々には、ため息が落ちるような魅力的な家がたくさんあります。
眺めているとついつい夢中になって羨ましくなってしまいますが、
自分の家の中や、近くの場所に、
お気に入りの場所を見つけることも忘れないでいたいなと思います。


今回お話したZINEには、蛇腹本だけを封筒に詰めた、通常版もあります。今、この文章を描いていて「お手紙版」にしたら可愛かったかなあ、なんて思っていますが、封筒に宛名を貼るように、1枚ずつシールを貼って作りました。
大切にしたいもの、心惹かれるものを、今できる精一杯の形に留めた本です。
もし、お目にかかる機会があったなら、少しだけ覗いてみてもらえたら、そうして一部でも、共感してもらえたり、いいなあと思ってもらえる部分があったなら、とても嬉しいです。

こちらのシリーズは、期間限定で、5/31(水)まで、オンラインストアでも販売しています。
もしよかったら、少し覗いてみていただけると嬉しいです。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
