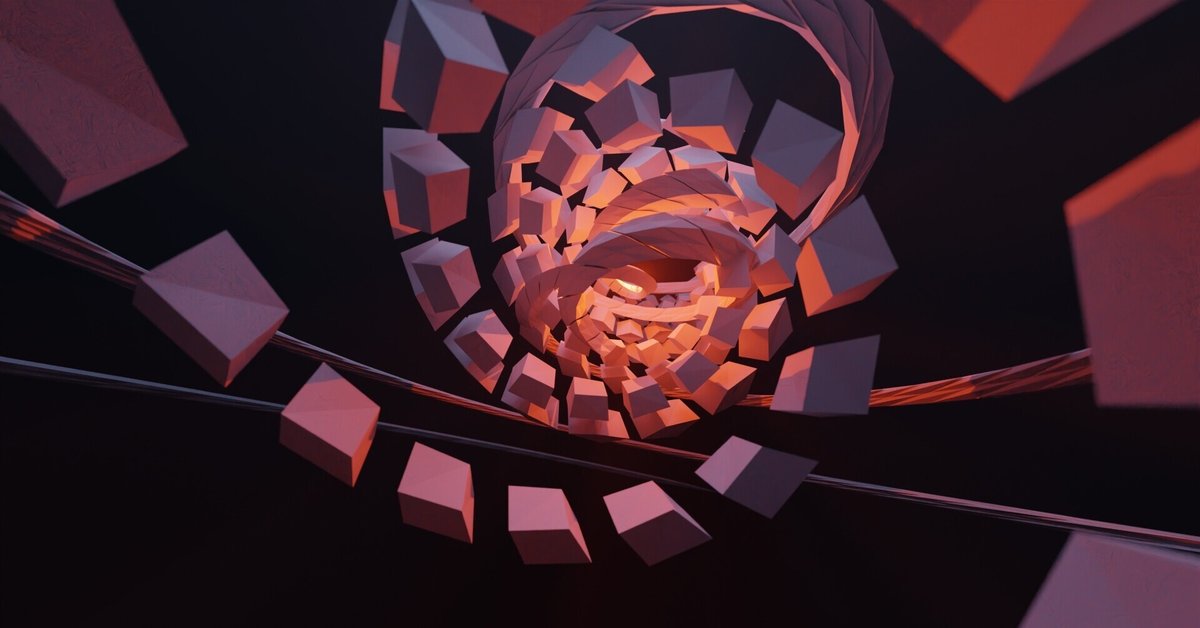
ひょっとしたら新しい生き方になるかもしれない
昨日の夜からの腹痛が朝まで残っている。
経験からしてもうじき治まるだろう。
しかし大学生あたりから胃や腸が弱くなった。
原因不明の腹痛や胃痛は本当にテンションが下がるのでやめてほしい。
色んな病院に行ったが、これといった良い解決法は見つかっていない。
以前に胃カメラをした際に「ばくじょう胃ですね」と医者に言われた。
胃はだいたい円形をしているが、ばくじょう胃というのは「ひょうたん」のような感じで中央部分がギュッと絞られたような形をしている。
特に問題はないが普通の人よりは消化が悪いらしい。
サラリーマンのときは嫌々いっていた健康診断は、今ではありがたい制度だと分かる。
「体は資本」とは上手いことを言ったものだ。
色んな遊びや買い物、付き合いをしてきたが「結局は健康が一番だな」と最近は思う。
昔はお金やキャリアなど欲していたが、今はガラッと変わってしまった。
自然と現状維持を求めているのかもしれない。
現状維持と聞くとネガティブに聞こえるかもしれないが、
「現状に満足する」という風に僕は捉えている。
例えば給料が上がったとして、生活コストを据え置きで生きれる人はどれくらいいるだろうか?
僕も含め多くの人は、「給料が上がった分だけ生活コストも上げる」のが通常である。
それはライフステージが上がったと言い換えられるが、今の僕からするとヒヤヒヤするものを感じる。
商売で言うところの「薄利多売」になる可能性があるからだ。
売上が右肩上がりになっている中、コストも一緒に右肩上がりになったとしたら「利益率」はいつまで経っても変わらない。
小売、飲食を中心に「薄利多売」にならざるを得ないビジネスモデルは
「利益率は変えられないから利益額が増えていくことを狙う」という感じ。
そのままスケールアップすれば利益率10%でも利益額が10億になればOKという具合。
スケールアップを狙いやすい反面、キャッシュフローが不利になりやすい。
今回のコロナなど突然の売上不振によって、上がり切ったコストの支払いがままならず事実上の倒産、いわゆる「黒字倒産」になった会社は多かった。
話は逸れたが、こういったことは個人にも起きる。
また困ったことに「一度上げた生活コストはなかなか下げられない」ことがほとんど。
家賃20万のタワマンに住んでいて収入が下がったとしても、家賃6万のアパートに引っ越すことは簡単ではない。
借金をしてでもタワマンに住み続ける人をたくさん見てきた。
まあでもそんなことを言っていたら、日本の景気はいつまで経っても戻らないか。
お金をたくさん使う人がいるからこそ企業が儲かって景気が良くなっていくわけだし。
一方でお金に余裕がない人が、少ない収入のなかで出来るだけ生活を楽にすることはできないものだろうか?
どこまでいってもお金持ちと貧乏人の2極化を無くすことはできなくて、貧乏人については「頑張って稼げ」と精神論をかけることしかないのも寂しい。
どんなに頑張っても金持ちになれない運命だったとしても、明日に絶望することなく生きていく方法があれば、と思う。
パッと思いつく方法だと「共同購入」が分かりやすい。
シェアハウス、カーシェアなど「シェアリングエコノミー」と呼ばれるものだ。
まず大原則として少ない収入で生活を楽にするには「所有しない」ことが大事である。
「人はドリルが欲しいのではない、穴を開けたいのだ」というフレーズがあるように、本にしろ、家電にしろ「本体が欲しいのではなく、それを持って実現できること」が欲しいわけだ。
さらに一度買ったものを生涯持ち続けることは稀で、
・故障
・流行の変化
・本人の生活の変化
などで買い替えることになる。
どうせいつかは捨てるのであれば所有するのではなく、レンタルで時期を見て商品を変えていけば良いのだ。
僕の実家ではコープ生協の宅配を使っていた。
僕の地元は田舎のためスーパーや百貨店が近所になく、宅配を利用するしか方法がなかったからである。
共同購入の仕組み
コープ生協の宅配のようなサービスは大なり小なり「共同購入」という仕組みを取り入れている。
流通業や小売業は「たくさん買ってくれたら安くするよ」という商売になっていることが多い。
例えば運賃とっても1回の走行で100個運ぶのと、1,000個運ぶのではガソリン代は同じだ。
そうすると100個運ぶより1,000個運んだ方が、
「1個当たりの運賃が安くなる」
100個だろうと1,000個だろうと同じトラック1台に変わりないため、「積載効率」という言葉でも表現されるようになった。
ヤマトや日本郵便が「コンパクト」というサイズを新しく導入し始めたのも積載効率から来ている。
話を戻して「たくさん買うと安くなる」とはいえ、個人が大量に買うのには限界がある。
食品だと賞味期限の問題も絡んでくる。
そうした場合に、1つのカタログを同じ地区で回して使うことで、
「みんなで買えば数が増えるから、結果的に安くなる」
という考えが生まれた。
「卸売り価格だから安いです!」というキャッチフレーズがあるように、
「店頭でなく在庫センターから買う」という点も盛り込まれた。
最近では原油価格の高騰で、共同購入だろうと個人購入だろうと大きな価格差はなくなってしまったが、当時の田舎ならではの仕組みだった。
現代版の共同購入
僕は共同購入を現代に持ち込める部分はがあるのではないかと思った。
例えばネットフリックスを「家族で1アカウント契約して、みんなで見る」
なんてことをやっている人は多いのではないだろうか。
いわゆる「なりすまし」と呼ばれるもので法律には違反していないが、サービスのなかで利用規約として「なりすまし防止」を進めている企業もある。
そんな感じで特定の誰かが代表者として購入して、あらかじめ決められたメンバーだけに共有していくスタイル。
お金は会費という形で定期的にメンバーが代表者に均等割りした金額を支払うことで成立する。
シェアハウスやカーシェアもほとんど同じ仕組みのはずだ。
税法上の問題は「事業として見なされるか」の1点で、
町内会のお祭りのように「集めたお金で不特定多数に販売する」ことさえ
やっていなければ基本的には「社会人サークル」のような位置づけで見なされる。
「身内の中だけでお金が回っていること」
「特定のメンバーに上がり(利益)が出ていない事」
「源泉徴収が発生しないこと(会費を使って講師、コンパニオンを呼んだり、アルバイトを雇っていない事)」
であれば消費税だけで、ほかの納税義務は発生しない。
規模があまりにも大きくなりすぎると「一般社団法人」と見なされる場合もあるが、先ほどのネットフリックスのような家族間、友人間であれば、そこまで神経質にならなくて良いケースがほとんど。
デメリットを挙げるとすれば「会費の延滞」などトラブルがあると人間関係がギクシャクすることだが、まあ普通に生きていれば誰しも経験するレベルの軽いトラブルだろう。
知らない人とやるのは好ましくないのかもしれない。
共同購入を実験してみた
僕は今年に入ったぐらいのときに今回の話を思いついて、仲の良い友人を誘って実験している最中だ。
まだ1年も経っていないため検証結果というほどのレベルではないが、現時点での状況をまとめてみる。
現時点で僕らが共同購入として利用するサービスは以下のようなもの。
・動画サイト
・ビデオ通話アプリ
・チャットアプリ
・クラウドストレージ
・レンタルサーバー
・本、消耗品
・飲み会など
月5,000円を出し合って上記のモノ、サービスを割安で利用している。
本などの「モノ」については最終的に誰が持っているかを管理する必要はあるが、今のところ紛失したりはしていない。
デジタル系については少し神経を使う。
先ほどのネットフリックスのようにログイン情報を複数人で共有しないといけないからだ。
最近では2段階認証のサービスがあり、この手のサービスはリアルタイムで代表者が認証作業をする必要がある。
リアルタイムというのが少し手間だが、「1分くらいでパスワードが失効する」ということは、メールやチャットで共有しても悪用される可能性が限りなく低いという捉え方もできる。
2段階認証のないものは、メンバーでしか分からない方法でログイン情報を共有している。
現状でも丁寧に取り扱っているが、将来的には「NFTを限定配布する」という方法も取り入れても良いかもしれない。
イーサリアムを作ったヴィタリックが本人が運営するブログで、
「配布先を限定したNFT」について説いている。
NFTは通貨のように転売や両替など「お金」としての使い方がメインだが、
ヴィタリック曰はく「特定の人しか使えないNFT」を作ることで、
学校の卒業証書のように「そのグループに所属する資格がある」という使い道ができるそうだ。
これによってログイン情報を閲覧する人をさらに厳格化できるはずだ。
そして肝心の支払いと会費についてだが、支払いの方は特に問題なさそうだ。
代表者がクレカ、現金などで責任をもって支払えば問題ない。
ちなみにデジタル系で「クレカの保存」はしないようにしている。
基本的に信頼関係のある人とでやっているが、それでも誤って決済ボタンをクリックしてしまう可能性があるからだ。
会費の徴収にはStripeという決済サービスを使っている。
ECサイトやオンラインサロンでも多く取り入れられていて、
「リンクを送るだけで、決済を実行してもらえる」という手軽さが特徴だ。
リンクをもらった人はリンクをクリックするとStripeの決済画面が立ち上がるので、好きな方法で指定された金額を振り込むだけだ。
さらに定期購入というサービスもあり、今回のように「同じ金額を定期的に振り込んでもらう」という場合には、初回のみリンクを送るだけで2回目以降は自動で振込が実行される。
毎回メンバーにリンクを送るのも大変なのでありがたい。
あとは代表者が集めたお金を分かるように管理するくらいだ。
個人のお金なのか、みんなのお金なのかグチャグチャになると後で面倒なことになるから気を付けたい。
またこの仕組みは代表者を変えてもOKなはずなので、「代表」といっても大きな責任を負うことはない。
銀行の共同口座を作ってメンバー同士で監視し合うとようにしても良い。
アナログなブロックチェーンとでも言えば良い。
以上が現時点での経過観察といったところ。
また何かしら工夫ができる点が出てくるかもしれないだろうから、気が向いたら共有したいと思う。
最後にメンタル的な話をして終わりたい。
共同購入をするようになって、少しばかり「分別」がついた気がする。
部活やサークルでも特定の個人がワガママに欲しいものを会費で買ったりしたらブーイングが起こるように、
「それは本当に必要な買い物か?」
と考える癖がついた。
所有かシェアか以前の話で、自分にとって本当に必要なものは見極める必要があるのだろう。
前段に話した「収入が増えて生活コストも増える」ことを、
気持ちばかり抑えられるようになる人が増えるかもしれない。
