
人間の忠実さ、脆さ、そして神の憐れみ。
何かを握りしめ守ることは良いこと?
「○○説/○○主義を握りしめている人は、そうすることで自分自身を守っているのだと思います。」と、ある方が言っておられました。
自分自身を守っている・・・う~ん、私はどうなんだろう。自己防衛の手段として○○説/○○主義を握りしめているという側面があるのかな?そしてもしそれがあるのだとしたら、その原因は何だろう・・そんなことに想いを巡らせていました。
何かを握りしめ守るということは良いことなのでしょうか。私の理解する限り、「守る, ギ:téreó」という行為は、その対象如何によっては、まことに善であり、大いに奨励されるべきこととして聖書の中で描写されていると思います。
マタイ28:20「わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように(διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα,,)」
ヨハネ8:51「だれでもわたしのことばを守るならば、その人は決して死を見ることがありません(ἐμὸν λόγον τηρήσῃ θάνατον οὐ,,)」
1テモテ6:14「私たちの主イエス・キリストの現われの時まであなたは命令を守り(τηρῆσαί σε τὴν,,)」
2テモテ4:7「信仰を守り通しました(τὴν πίστιν τετήρηκα,,)」
黙示録1:3「この預言のことば、、を聞いて、そこに書かれていることを守る人々は幸いである(προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν,,)」
黙2:26「また最後までわたしのわざを守る者には、、(καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους,,)」
黙22:9「この書のことばを堅く守る人々、、(καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους,,)」
また、守るという受身的な表現だけでなく、聖書はまた、ひとたび伝えられた信仰のために戦いなさいと強い表現も用い(ユダ3)、黙示録の記者はスミルナの教会に向け「あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない・・・死に至るまで忠実でありなさい」(黙2:10)と命じています。
実際、私たちの生きる多元主義・相対主義社会において、「死に至るまで忠実」である覚悟で何かを堅く信じ、それをぎゅっと握りしめ、それを守ろうとしている人は、「ファナティカルな原理主義者」と冷ややかな目で見られ、軽蔑され、危険視されがちです。
河上肇と秀夫人の例
少し話は脱線しますが、みなさんは河上肇という人物をご存知でしょうか。彼は若き日にキリスト者内村鑑三の影響を受けますが、その後、マルクス主義者となり、京大教授の職を辞し、共産主義の実践活動に入ります。

その後、日本共産党の党員となったため検挙され、長い投獄生活を送ることになります。刑期が三分の一を過ぎた頃、「もしも転向声明を出すなら仮釈放してやる」という旨のことを刑務所長がにおわせました。
彼は迷いました。外で彼の出獄を待ち続けてくれている忠実な奥さん(秀夫人)のことを想いました。しかし、その河上肇の迷いをふっきらせたのは、面会に来た奥さんの励ましのことばだったそうです。
(秀夫人)「お仕合わせなことに、あなたは恩赦にもおかかりになったんですもの、まるまるお勤めになっても、あともう三年足らずの御辛抱です。そりゃお辛いことは重々お察し致しますが、それかって無理をしてお出になると、折角早く出ていらしても、あとできっと後悔なさるに決ってます。そうだと結句そのほうがお辛い事になろうと、私、それを一番心配いたしますの。
無事に勤め上げてお出になりましたのなら、今度こそそりゃもう、一生の重荷を卸したというお気持ちで、気楽に余生を楽しんでいただきたい。私はそればかりを楽みにこうして居ますが、せっかく早くお出になりましても、あなたの事ですから、何かご自身に気の済まんことがあると、いつまでも世間が狭いような思いをなすって、お落付きにならんに極(き)まってます。私はそれをお側(そば)で見るのが、とても辛い。それが今眼に見えるようです。せっかくお気の済むように思う存分のことをなすってここまでおいでになったんですもの、、、」
面会時間が終わり、自分の独房に戻った頃には、河上肇はもう覚悟を決めていたそうです。
彼は、自らの信ずるマルクス主義を「握りしめ」、初志貫徹すべく、人生のすべてをなげうち、この道に人生を投じました。
評論家の加藤周一は「〔河上肇の思想は〕手作りの思想だ。だから、その歩みはのろいが、時代がどう変わろうと揺れない。」と彼を評しています。
もちろん、マルクス主義は、キリスト教世界観とは相入れない唯物論的な立場ですが、それでも一般恩寵により、「何かを堅く信じ、それに徹した生き方の力強さ」というものを河上肇・秀夫人の人生は私たちに物語っているように思います。
イエスさまだけを見つめ、主だけを『握りしめ』ましょう?
また最近では、「私たちキリスト者にとって大切なのは、○○説とか○○主義とか、そういうドグマを握りしめることではありません。それらはどれ一つとして完璧な体系ではありません。ですから私たちはイエスさまだけを見つめ、主だけを『握りしめ』ましょう。」というような寛容な声も多方面から聞こえてきます。
しかしそういう方々の言う「イエスさま」の内実は往々にして、聖書の啓示するイエス・キリスト像とは微妙に異なっています。その事に関し、A・W・トーザーは次のように述べています。
最近もてはやされているのは、『いつも笑顔で、愛想のよい、無性の宗教マスコット』としての神の御子のイメージである。そしてこのマスコットはやわらかい手で誰彼となく握手を交わし、どんな問題に関してもいつも『そうですよ、そうですよ。』と相槌を打ってくれるのだ。しかしこのようなイメージは、真理としての御言葉の中には見いだされない。
一つの落とし穴
しかしながら、そういった虚像のイエスを拒絶し、聖書の教理に妥協なく忠実であろうとする過程で、もう一つ気を付けなければならない点があることに気づきました。
それは自分でも気づかない内に、
「(真理だと自分の信じている)○○説/○○主義/〇〇教を堅く握り、守る」
という本来のスタンスから、
「○○説/○○主義/〇〇教を信じている自分を守る」
という自己保身へと
中身が変わっていく場合があるということです。
〔自己保身の中身の一例〕
● これまでずっと○○説/○○主義/〇〇教を信じ、それを公にしてきた。(だから今さら引っ込みがつかないと感じる。)
● ○○説/○○主義/〇〇教を基盤におく自分の所属団体・グループとの大切な人間関係がある。
(違ったことを言い始めて、荒波を立てるようなことはしたくない。)
(ここが私の安全ゾーン。)
(だから、今のままでいい。うん、今のままがいい。)
信じている「対象内容」を遵守する覚悟が本当にできている人は、いざとなったらどんな犠牲を払ってでも、そしていかなる恥辱・孤独の谷を通ってでもそれを固守する(あるいはそれが誤っていると確信した暁には潔く転向する)心のへりくだりと勇気をもっているのではないかと思います。
ジョン・ヘンリー・ニューマンの例
ジョン・ヘンリー・ニューマン(1801-1890)という人がいます。彼は、19世紀にオックスフォード大学を中心に起こったイギリス国教会内の霊的刷新運動の指導者です。(オックスフォード運動)。
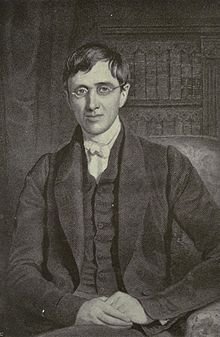
しかしその後、彼はローマ・カトリックに劇的改宗をします。年齢にして40代半ばで起こった出来事です。なぜ?どうして?ニューマンは20年近く、国教会の牧師として献身的に奉仕し、しかも彼には運動の同志であったピュージーやキーブルというかけがえのない朋友たちがいました。
しかしいろいろなプロセスがあった末、1843年、彼は「友たちよ、さらば」という説教をし、国教会の講壇を、そして彼が築き上げた交友関係すべてに別れを告げ、一人、ローマ・カトリシズムへと向かうのです。
いったい何が彼をして聖公会からローマ・カトリックに改宗せしめたのでしょうか?ニューマンのような堅固な人物が転向を決意したというのは余程の理由があったからこそなのでしょう。
ここでの私の焦点は聖公会・カトリック主義それぞれの正誤にあるのではなく、一人のキリスト者の「転向」の決断およびその動機にあります。
なぜなら往々にして、そういった人々の転向の動機を掘り下げてみることで、普段、自分や自分の属するグループが見過ごしてしまいがちな、真理のある一側面にはっと気づかされることがあると思うからです。
トーマス・シュライナー教授の例
また、こういった転向は、宗派間だけにとどまりません。南部バプテスト神学校新約解釈学のトーマス・シュライナー教授は、2009年に自分の終末論が「無千年王国説」から「歴史的前千年王国説」に変わったとする転向声明を発表し、話題を呼びました。

しかしそれから7年後の2016年、彼はGospel Coalitionの鼎談で、次のような告白をしています。
僕は、ディスペンセーション主義前千年王国説を信じる教会で生育し、成人後、歴史的前千年王国説に立場が変わりました。でも、黙示録の講解説教の準備にとりかかる中で、もしや無千年王国説が最も整合性のある解釈なのではないかと考えるようになり、説教途中に自分自身の立場が変わったのです。
ところが、黙示録20章のサタンの箇所や第一の復活のことがやはりどうしてもひっかかり、2009年、再び、歴史的前千年王国説に転向。
それが・・実は、2016年にさしかかり、また無千年王国説の方に回帰しつつあるのです。こういう風に自分は、アミレと歴史的プレミレの間を行ったり来たりしていて、正直、ここの解釈について決定的な確信はないんです。
「神学校教授が、こんなにコロコロ意見を変えて、情けない。」そう思う人はいるでしょうか。いや、むしろ、彼のこの告白によってどれだけ多くの牧会者や信徒が励ましを受けたか分からないと思います。
彼の転向は、彼の情けなさや不能の表れではなく、むしろ聖書の真理を前にした一人の人間の謙遜さと探求の精神の表れだと私は受け取っています。
彼は自分の面子を守ることを放棄することにより、彼の信じる対象である神の偉大さをこの世に証していると思います。
人間の持つ心的〈荷物〉や諸前提の存在は如何ともしがたい現実だと思います。
しかしこういった信仰者たちの真実なる姿を通し、私は、人間存在の諸制限や脆さを憐れみ、忍耐と愛と赦しの内に、今日もご自身を啓示しようとしておられる神の愛を感じ、そこに慰めと励ましを見出しています。
