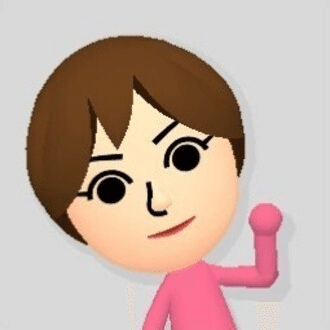図やイラストを積極的に活用。深い理解を促す〜#noteとTwitter イベントレポ〜
9/15(木)に開催された「#noteとTwitter」のイベントレポです。
配信を見返す時間がない方、考えを深めたい方におすすめです。
当日メモしたTwitterの投稿
「美味しいところをちぎって投稿」
— ひとみ hitomi|つながる旅ログ (@ichito0123) September 15, 2022
→映画の予告編と似ている気が。
見所がいくつかパターンあると、なんとなく気になってきちゃう。
そう、切り抜きも同じですね!#noteとTwitter
メモでこちらにRT
— ひとみ hitomi|つながる旅ログ (@ichito0123) September 15, 2022
後日noteにまとめます。#noteとTwitter https://t.co/qYDkvw3OUi
時間帯というよりも、
— ひとみ hitomi|つながる旅ログ (@ichito0123) September 15, 2022
同じ記事の切り口を変えて「接触面積を増やす」。
同じショートケーキでも、
・いちごだけをを見せる場合
・クリームをメインに見せる場合
・スポンジの生地を見せる場合
で反応する層が違いそう。#noteとTwitter
学んだところ:「接触面積を増やす」
前のTwitterの投稿にも関連するのですが…
どういうことか、アーカイブのYouTube動画を拝借します。
「アプリマーケティング研究所」さんの場合は、同じnoteの投稿を朝・昼・夜に分けて見せるところを変えてツイートしているそうです。


それぞれの時間帯で反応する層が異なりますし、ずっと応援してくれるフォロワーさんでも、見どころが色々出ていれば新鮮な情報として受け止めてもらえる可能性があります。
ゲストの「アプリマーケティング研究所」の鶴谷さんは、「切り抜きをTwitterでしているようなもの」と仰っており、皆様にも想像がしやすいのではないでしょうか。
ツイートするとき・noteに書いてある画像にも"こだわり"がありそう。
ゲストの鶴谷さん、徳力さんは特にイベントの中で深掘りされていませんでしたが私はこの話を聞いて、noteやTwitterに投稿されている画像にもこだわりというか、工夫があるように感じました。
イベントの中では、鶴谷さんがイラストレーターさんに依頼されている話題もありましたが、そのイラストもどこをPICK UPしてイラスト化するのかに工夫があるように思います。
例えば、このnoteを見てみましょう。
とあるアプリについて、開発した会社の社長さんにインタビューされているnoteです。
インタビューでは対話形式で書かれているのですが、Twitterでは要約を投稿されています。ただ、画像は同じ。発信するメディアによって、アピールするポイントを簡潔に書かれているのは、とても勉強になります。
※noteの記事の中に、下記の画像がどこにあるのかぜひ探してみてくださいね!
YouTubeマーケで「タイトルと動画」の期待値を揃えたほうが効果良かった
— アプリマーケティング研究所 (@appmarkelabo) June 22, 2022
釣りっぽいタイトルで再生数を伸ばそうとするよりも「PR感」を出したほうが、データ上の効果も高かった
タイトルと乖離すると「期待値のズレ」が生まれガッカリするため。紹介動画とわかるほうが良いhttps://t.co/WXkrEFiTIs pic.twitter.com/ID7mEmg4EN
私はWeb上の記事だと斜め読みするタイプなので、こうした図解があるとわかりやすいですね。
プレゼンのときのスライドとはまた別ですが、スライドを作るような感じで画像を作成してみると、別の人に届く可能性がありますね。
さらに、「アプリマーケティング研究所」Twitterアカウントでは、同じnoteの記事を2,3個分けて投稿されていますね。
N1分析からはじめるYouTubeマーケ。コアユーザーの「好きなチャンネル」にPRを依頼すると成果がでやすい
— アプリマーケティング研究所 (@appmarkelabo) June 22, 2022
なぜならコアユーザーの支持するコンテンツには「似ている人」が集まっている可能性が高いため
自社を支持するユーザーが支持するコンテンツは何か?を分析すると良いhttps://t.co/WXkrEFiTIs pic.twitter.com/TAwLdYhfqP
YouTubeマーケは「初期のコメント」のテーマ熱量を見ると効果を予測しやすい
— アプリマーケティング研究所 (@appmarkelabo) June 22, 2022
コアなファンがする「初期コメント」に視聴者の熱量があらわれやすいため
効果の高い動画は「語学」などテーマにコメントが向いていて、低めのものは無関係なコメが多かった。HiNativeの事例https://t.co/WXkrEFiTIs pic.twitter.com/QG5kCeKenH
Yahooさんでも、同じ取り組みがある
先日、この記事がTwitterタイムラインで流れてきました。
図で「分かりやすく」とは…
1つの解決法:
「まずイラストを大きめに出して何を伝えているのかを直感的に伝え、そこにテキストを添える方がよい」
まさに、アプリマーケティング研究所さん同様、記事の要約を画像で補っているのです。
合わせて読みたい
SNSの情報は「点」であるから、「線」で情報発信するのが求められる時代になるのでは?という考え。「接触面積を増やす」と鶴谷さんが仰っているのと、少し被る点がありそうです。
現在、こうしたイベントレポはじめ事例を研究して貯めている有料マガジン「UXを考える」を発信しています。ぜひご覧ください。

いいなと思ったら応援しよう!