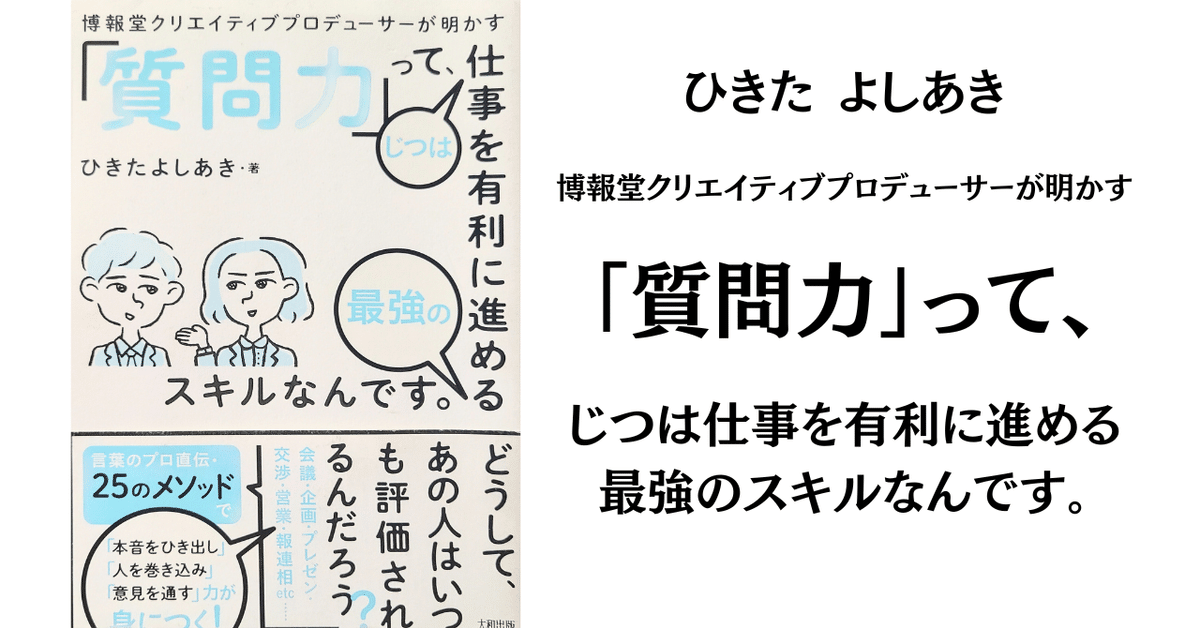
【読書録】「質問力」って、じつは仕事を有利に進める最強のスキルなんです。
久しぶりに更新していきたいと思います。
今日紹介する本は、ひきたよしあき氏の「質問力」です。
最近、時間がある時は、様々な方のお話を聞きたくて、お時間を頂いてお話を伺うことがあります。
毎回、質問の仕方によって全然違う。
さらに深く聞きたいことがあるのに、そのためにどのように質問すればよいか毎回考えていました。そのような中、素晴らしい本に出会いました。
この本、3人のキャラクターが中心となるストーリーで展開され、文字も大きめで読みやすく会話形式で進行するため、内容に飽きることなく理解できます。
ストーリーは5日間で進んでいきますので、各パートで重要な内容を記載していきます。
【自分に対する質問力を磨く】
このストーリーで一番伝えたいことは、自問自答で「脳」を質問体質に変えようという事です。普段の生活の中で質問をする習慣がなければ、質問力を向上させることは難しいと述べられています。
例えば、「今、なぜ私は疲れているのか?」と自分に質問することで、
脳が活性化され、疲れの原因を見つけ出すことができます。
日常生活の中で、なぜそのような感情を抱いているのか、なぜその行動を取ったのかといったさまざまな機会に対して自問自答する訓練を行うことで、質問する習慣を身につけることができます。特に勉強になったところを書いていきます。
クエスチョンメモ
これは書くという動作を組み入れることです。
つまり自分の頭に浮かんだ「質問」を書き出さす等いことです。
日常生活やこうして本を読んでいる時も?をつけて書き出すことです。
こうすることで、夜寝る前に今日は1日どんな風に脳が動いたかを目に見る
ことができる。こうすることで自分の質問レベルが上がっていきます。
解決策のない質問はダメ
自問自答で一つ気を付けることがあります。
例えば財布を忘れた時のこんな質問を思い浮かべると思います。
「どうして忘れたのか?」
答えはこんな感じになります。
「今日は少し寝坊してた」「ばたばたしていた」など。
これは質問の答えになっていますが解決策には結びつかないです。
「質問」はその先に解決策や展望があることが大事。
なので「why(どうして)」から「HOW(どうすれば)」にすることです。
どうしたらと解決策を出てくる質問を通じて質問力が磨いてきます。
【聞く姿勢を磨き上げる】
まず質問を受ける側になったとして、質問者があなたの発言に対して無反応だったどんな印象を受けるでしょうか?
相槌も打たないそうするとこちらの印象は最悪になってしまいます。
なので、聞くときは「あなたの話を真剣に聞いています」という信号を出すべきです。
「名司会者に学ぶ」
ココは確かにと思ったところです。相槌は確かに必要ですが、「ふんふん」「はあはあ」と言っているだけでは、真剣に聞いていない印象を受けるかもしれません。
テレビの司会者がどんな相槌を打っているかというと
実は相槌を口にしない。
その代わりに「驚きました」「それはひどいですね」と話の内容に即した
自分の感情を、顔や動きに態度を示しています。
さらに彼らは「倒置法」を使ってその感情を強調させています。
例えば「聞かせてください!その話」など文法をわざと崩して聞きたこと
言葉を先にもって来るそうです。
ものまねで相手の「心の声」を聞く
お付き合いしている2人が同じような仕草や表情、同じようなタイミングで笑い、同じような格好で人の話を聞く。心理学ではこれを「ペーシング」といいます。
聞く姿勢ではこのページングを活用します。
まずは服装です。質問で相手の意見を引き出す場ではなるべく相手に揃えます。相手がTシャツなのにこちらがスーツでは息苦しくなります。
そして相手の感情、相手の話の速さに自分を合わせることです。
相手が落ち込んでいるのに、あなたが朗らかにしていれば「人の気持ちをわからないやつ」と思われます。相手のものまねんをしていると相手の体調や喜怒哀楽の状態がわかるようになります。「聞き上手はものまね上手」だという事。
相手があまりしゃべらない方の場合、オウム返しを使ってみましょう。
これはとにかく相手の言った言葉を繰り返す方法です。例えば「働き方改革が大事なんだ」と言ったら「働き方改革が大事なんですね」と繰り返す。
オウム返しも相槌とお同じようにあなたの話を良く聞いているという印象を与えることができます。
【5つの質問の型で的確な答えを導く】
質問することが苦手な人でもこの型をマスターすればどんな人でも自由自在に相手から良質な情報や答えを引き出すことができます。
今回は「5WIH」「起承転結」について書いていこうと思います。
「5W1H」を会話文に取り入れる

例えば、あなたのパートナーが「最近、どこにも一緒に旅行に行ってない。いきたい」と言ったとします。その場合、
「いつ頃行きたいですか(When)」
「どこに行きたいですか(Where)」
「行ったら何をしようと思っていますか(What)」
と答えると、質問の内容を深く考えずに質問力を発揮できます。
質問の順番は、適切なものを選択して使用します。
同じ質問を繰り返しても構いません。それによって正確な情報を得ることができます。ただし、同じテーマについて深く掘り下げすぎると、尋問のような印象を与えてしまうことに注意してください。
そのため、3回程度にとどめておくことが良いでしょう。
「起承転結」に当てはめて尋ねよう
この手法は講義や会議の場で、的確かつ短時間で質問内容を相手に伝える方法となります。例えば:
起(伝えるべきポイントを述べる): 「海外ボランティア経験について質問します。」
承(具体的な質問内容を示す): 「海外ボランティア経験を、就活の際に好意的に考える企業が多いというのは本当でしょうか?」
転(自身の見解や疑問を述べる): 「学生の間では都市伝説のように有利だと言われていて、実際に就活目当てでボランティアに参加する学生がたくさんいます。」
結(相手に答えてほしいポイントを強調する): 「ボランティアの内容にもよると思いますが、先生に企業の方の本音をお聞きしたいです。」

このように、質問の構造に「起承転結」を当てはめることで、質問の目的やポイントが明確に伝わりやすくなります。
また、ストーリー感を出すことで相手の関心を引きやすくなります。
そして、無駄な情報を排除することで、効果的なコミュニケーションが可能となります。
「裏質問で相手の本音を引き出す」
相手の質問はただ質問するだけでは聞けません。もう少ししゃべりたいという気持ちにさせることです。一般論を聞くとヒーローインタビューの手法について書いていこうと思います。
「一般的には○○」と尋ねよう
「投影法」とは、相手の意見ではなく一般的な考え方や傾向を知りたいときに使われる質問方法です。
例えば、ある会議でA案とB案のポスターについて意見を求められたとします。
しかし、若い人たちは上司や周囲の目を気にして率直な意見を述べることができないかもしれません。
そんな場合、一般的な若者の意見を知りたいと尋ねることで、より率直な回答を引き出すことができます。
ただし、相手からの回答が必ずしも一般論であるとは限りません。
彼らの意見には個人の考えが反映される場合もあります。
このような場合、相手が本音を出しにくい場合には、一般的な意見を聞くことで、自己投影を促してみることが重要です。
以上を踏まえて、相手の関心を引きつけ、本音を引き出すために、
「一般的には○○」という形で質問し、必要に応じて投影法を利用してみてください。
「ヒーロインタビュー」で相手の自己肯定感を満たす
相手の物語や成功に至るまでの心境や努力を引き出すためには、以下のようなアプローチが効果的です:
今の心境を聞く: 相手が現在どんな状況にいるのか、どのように感じているのかを尋ねることで、心を開かせることができます。
過去の苦労話を聞く: 相手がどんな苦労や困難を経験してきたのかを聞くことで、彼らの自己承認を満たし、信念や執着、こだわりを理解することができます。
未来の展望を聞く: 相手が将来どのような展望を持っているのかを聞くことで、彼らの方向性や目標について知ることができます。
これらの中で、特に重要なのは「過去の苦労話」です。相手が乗り越えてきた困難や苦労について尋ねることで、彼らの成功への道のりや信念、執着がより明確になります。
このようなアプローチを通じて、相手を心地よく感じさせ、本音を引き出すことができます。
巻き込むテクニックで自分の意見を通す
この章では、会議や交渉の場やプライベートの場において質問で相手を誘導しあなた味方へと巻き込んでいく方法が書かれています。
以下の2ついて書いていこうと思います。
【話の流れに「方向指示器」をつける】
この本法は簡単でいつもの会話よりも「接続詞」を意識的に使うだけです。
「それからどうなったの」「そこでどう思ったの」「するとこういうことが言えるわけ?」と接続詞の「順接+質問」を意識することです。
逆に話の流れを止めるには「しかし、それは一概には言えないのでは」と「逆説+質問」に置き換えることです。他には、
順説《だから、それで、そのため、したがって、すると》
逆説《しかし、だけど、けれども、ところが、それなのに》
選択《または、それとも、あるいは、もしくは》
対比《一方、反対に、逆に、他方、反面》覚えておくといいです。
【質問におけるキラーワード】
質問力が最も力を発揮するキラーワードがあります。それは!
『具体的』
『例えば』
『この他に』
ただこの3つのフレーズを使用するときは順番が大切です。
いきないり「他にある」と聞いてしまうと発言を全否定することになる。
最後に具体的に言ってください。だとここまで離開できなかったのかと疑われてしまいます。
例えばマイドリームという商品を聞きたい時に
「マイドリームについて具体的に教えてもらえませんか?」
「2018年に日本の文具メーカから発売されたノートシリーズになります。」
「マイドリームは例えばどのようなシーンで使われるのですか」
「10代の女子たちが授業中に使うノートして使われています。
「他にはどのような使われ方をしますか」
みたいな感じで行う。相手が理想を語る→具体的にはと質問→相手にわかりやすく説明してもらう→例えばと質問する→相手に具体的な商品や企画を説明してもらう。「このほかにと質問する」→相手に他の事例や代案を説明してもらう流れにする。
まとめ
いつも成果を出す人が質問で自然とやっている事
起承転結にまとまっている質問は答えやすい
一般論を使えば口下手な人の本心を引き出せる
具体的に、例えば、この他には、企画を強くするキラーワード
あえて完璧にしないことで想像以上の結果が生まれる
最後まで読んで頂きありがとうございます。もっと詳しく知りたい方はぜひ本書をお読みください。
