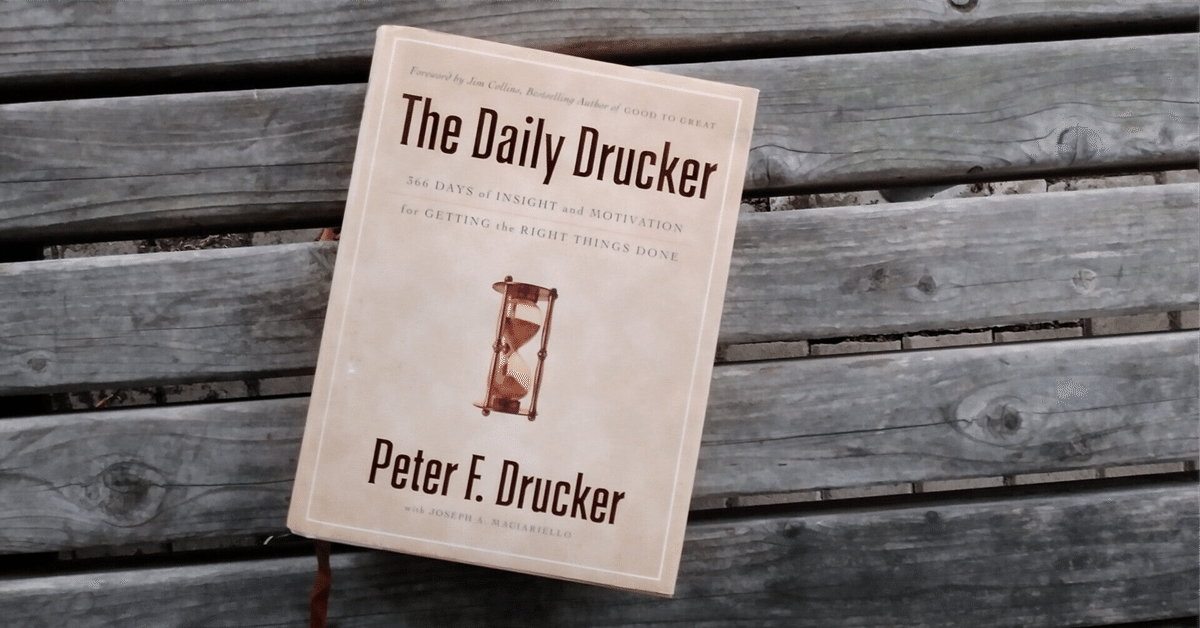
14. 目標管理制度の歴史⑦ ドラッカーのMBOの具体的な運用
前回の記事ではMBOの誤解について書きました
今回は、MBOのより具体的なことについて、ドラッカーはどのように言ったのかをみてみましょう
パワポ1枚サマリー

筆者作成
目標は、
事業の全貌の把握
個々の活動のチェック
とるべき行動の明示
意思決定の評価
現場の活動の評価と成果の向上
これらを可能とするものです。
MBOは目標達成度の評価という人事制度のツールではなく、目標設定により個人の自律と責任を最大化し大きな組織目標を達成するため経営管理、上司が部下をマネジメントする仕組みである
いや、奥が深い
キーワードだらけ
受験生なら全部にマーカー引くぐらい
〇〇くん、今期は目標未達だから1点(10点満点)ね。悪いねぇ、会社のルールだからボーナスはなし。来期は頑張ってねー。家のローンもあるんでしょ?その代わりじゃないけどさ、今晩、飲みにでも行く?
この日本中でありそうな?会話と、全く違う
今までの記事は、もしかすると精神論とか、理想論だとか言われるかもしれません。具体的なMBOの運用について書かなかったので
ドラッカーの本には、かなり具体的なことが、実際の企業の事例をもとに、事細かに書かれています
だからこそ、実務界隈でこんなに広がったんだと思います
でも、単なるテクニックやツールでないからこそ、世界中で共感され、受け入れられたように思います
特に、ドラッカーのデビュー作、1939年の「経済人の終わり」で経済至上主義からの脱却を説いており、彼の思想のベースになっています
一見、MBOは、企業の利潤の最大化(≒お金儲け≒経済至上主義)を目的に、そのツールとして機能しているようにも思えますが、経済至上主義からの脱却を説いた人がMBOを提案してることを、よく考えて、しっかり受け止める必要があるんじゃないかなと、僕は思います
何が一番大事?
話が長くて、よくわからんよ。迫田さん、要は何が一番大事なの?
とよく言われます。ごめんなさい
全部大事 と言いたいところのですが、ぐっと抑えて
あえて言うならば、図の真ん中にも書いた、
上司と部下のコミュニケーションが目標達成の鍵
この部分が大事だなと思いました。コミュニケーションといっても、下記の3つの要素が特に大事、成功の鍵のように思っており、自分でも実践を頑張ってます(なかなか上手くできませんが)
双方向性:部下一人ではない、上司からの押しつけでもない双方向なコミュニケーション(目標設定、進捗確認、継続的なフィードバック)
ゴール:あくまでも目標達成がゴール。仲良しクラブではない
自立性:双方向のコミュニケーションも自律的な管理のため
結局、こまかいMBO制度の運用について何もふれずに、今回も精神論ばかりで、コンサル失格・マネージャー失格と言われそうですが・・・笑
最後まで長文お読みいただきありがとうございました
