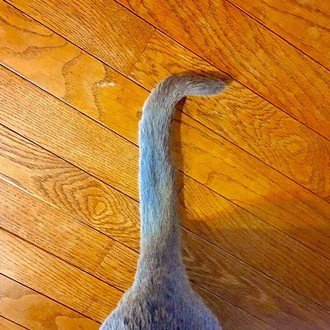Photo by
423shibusan
【宅建エッセイ】どんどん増える科目と日々変わるやる気の波
ようやく全ての科目に手をつけるところまで進み、試験内容の全体が見えてきた。と言っても、ここから知識として定着させてどんな角度で問われても「この場合はこう!」と答えられるようにならなければいけないのだが。
果てしない...。
宅建の試験範囲は、①宅建業法、②法令上の制限、③権利関係、④税・その他と大きく分けて4つの科目があり、私はこの順番で各科目に手をつけ始めた。
出題される順番とは違うのだが「宅建業法」は4つの中で一番出題数が多く、得点源になるので最初にとりかかることに。そして次に出題数が多いのは「権利関係」なのだが、こいつが厄介なのだ。
まず、勉強する範囲がかなり広い。民法を始め複数の法律に関する問題が集まった科目で、民法だけでも1,000以上の条文がある上に長文の判例問題などもあり、宅建試験を難しくさせている「鬼門」とも言われている。らしい。
そんな噂に怖気付いた私は、優先順位を3番目にして、確実に点を取れそうな科目から重点的に勉強を進めていくことにした。
ここから先は
1,891字
この記事のみ
¥
100
期間限定!Amazon Payで支払うと抽選で
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
サポート、嬉しいです。小躍りして喜びます^^ いただいたサポートで銭湯と周辺にある居酒屋さんに行って、素敵なお店を紹介する記事を書きます。♨🍺♨