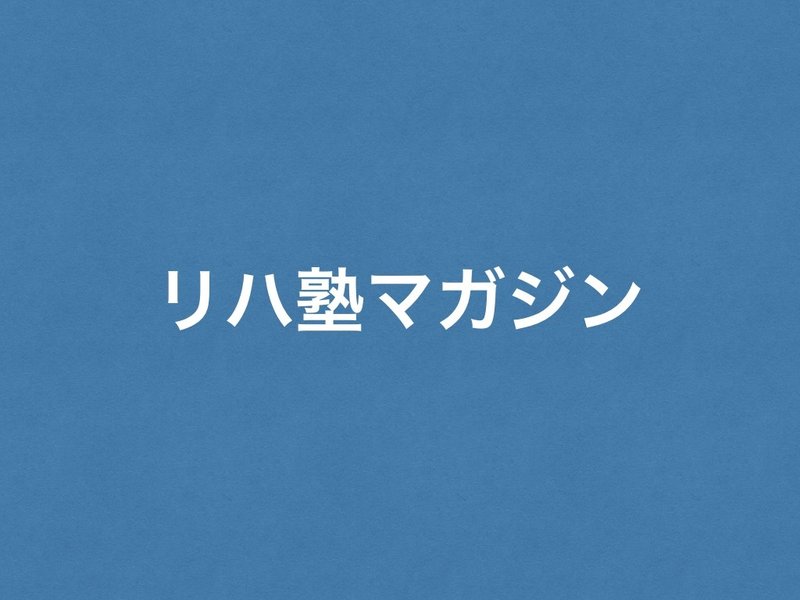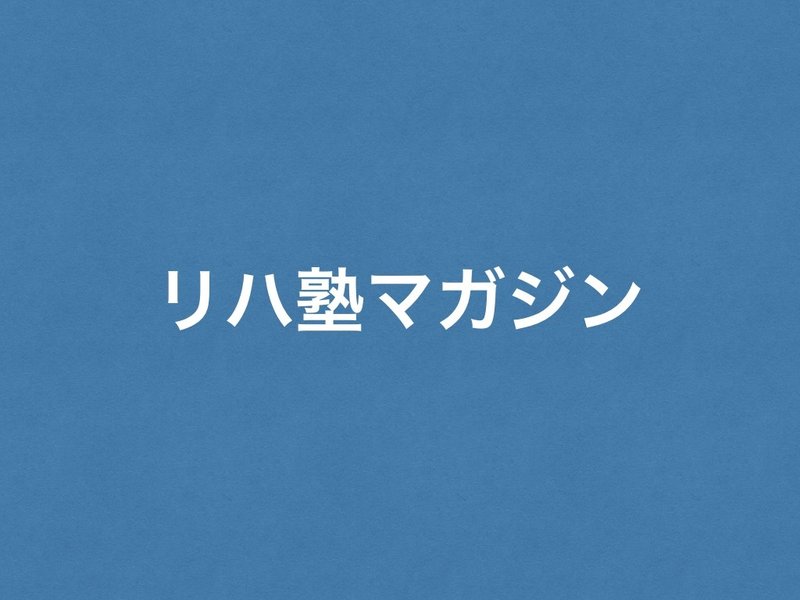深殿筋症候群に対する評価とアプローチ
リハ塾の松井です!
臨床で腰下肢痛の訴えを聞いたら、どのように対応しますか?
など、腰下肢痛を起こす病態はいくつか考えられますが、今回は「深殿筋症候群」について解説します。
梨状筋症候群と言う方が聞き覚えがあるかもしれませんが、最近は梨状筋以外の筋骨格構造も坐骨神経痛を引き起こすことが言われているため、深殿筋症候群と言われるようになっています。
深殿筋とは、後方の大殿筋、前方の大腿骨頸部、外側の大腿骨粗線と大腿筋膜張筋に到達する殿部腱膜層、内側の仙結節靭帯から構成され