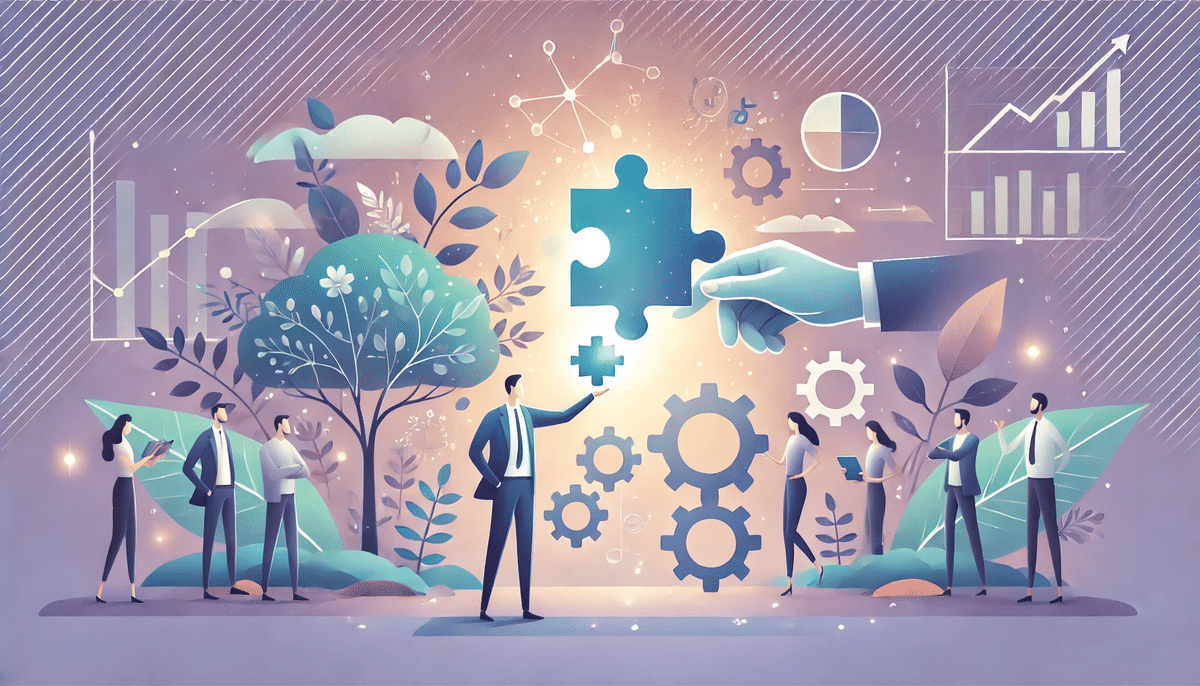【書籍】「任せる力」が組織を変える:楠木建氏が語るマネジャーの本質ーTHE21
The21 2025年1月号の中で、「この仕事は任せられない」はたいてい上司の思い込み(楠木 建氏)p16を取り上げます。
ここでは、楠木氏が「マネジャーとしての役割と部下育成の重要性」について解説しています。楠木氏は特に、マネジャーに求められるのは部下に仕事を任せる能力であり、それがマネジメントの本質だと強調しています。
このテーマは、 長く語られてはいますが、一方で永遠のテーマともいえるものです。企業にとっても重要な観点でありますので、考察を深めてみたいと思います。
部下に仕事を任せることの重要性
楠木氏によれば、マネジメントとは「自分が手を動かすのではなく、人を通じて物事を成し遂げること」に他なりません。これは、単に指示を出すだけでなく、部下が自律的に仕事を進められる環境を整えることを意味します。
しかし、多くのマネジャーは「この仕事は任せられない」という思い込みに縛られてしまい、結果的に自分自身でプレイヤーとしての業務に追われてしまいます。これは、マネジャーとしての本来の役割から外れる行為であり、組織全体のパフォーマンスを低下させる要因になると指摘されています。
「人的資本」としての部下育成
部下に仕事を任せることは、近年注目される「人的資本経営」の視点からも非常に重要です。楠木氏は、「人的資本」とは資源や資産と異なり、将来の価値を生み出す力があると述べています。そのため、部下への投資は単なる短期的な労働力の補充ではなく、長期的な成長を見据えたものにすべきだとしています。部下に責任ある仕事を任せ、見守りながら成長を支えることが、結果的に企業全体の利益を大きく引き上げると述べています。
部下に仕事を任せる際のポイント
部下に仕事を任せる際には、単にタスクを割り振るだけではなく、部下の適性や意欲を見極めることが重要です。楠木氏はこれを「ベクトルの向きと大きさ」と表現しています。具体的には、その人が得意なこと、やりたいことを見極め、それに合致した仕事を任せることが重要です。ベクトルが合っていない仕事を無理に任せても、部下は成長しないばかりか、仕事に対するモチベーションを失う可能性があります。
マイクロマネジメントと原因究明の違い
部下の進捗を細かく管理し、遅れが生じた際にたしなめるだけの「マイクロマネジメント」は、むしろ無能なマネジメントであると楠木氏は批判します。それよりも、進捗が遅れている原因を一緒に探り、その根本的な問題を解決することがマネジャーの役割であると述べています。原因が部下の能力にある場合だけでなく、人手不足や外部の要因など、さまざまな要因が絡む可能性を考慮し、部下と向き合う姿勢が求められます。
組織文化と思い込みの打破
マネジャーの思い込みが、部下に仕事を任せられない理由になっている場合が多々あります。例えば、「重要なクライアントの仕事だから任せられない」「定時退社する部下には責任ある仕事を任せられない」といった先入観です。これらは往々にして正確ではなく、実際には部下に任せることで新たな可能性を引き出す機会を失っている場合が多いと楠木氏は指摘します。思い込みを取り除くことで、組織全体の成長にもつながると述べています。
マネジャーとしての理想的な働き方
楠木氏は、マネジャーがプレイヤーとしての業務を完全にやめ、部下と向き合う時間を最大化することを提案しています。具体的には、勤務時間の8割を部下とのコミュニケーションや指導に充てることが理想的だと述べています。これにより、部下の信頼を得るだけでなく、長期的に見てチーム全体の成果を向上させることができると強調しています。
この内容は、現代のマネジャーに対する示唆に富んでおり、特に部下育成やチームのパフォーマンス向上を目指す人々にとって非常に有益なものです。具体例や理論に基づいた説明は、マネジメントの本質を理解する助けとなるものでしょう。
人事の視点から考えること
ここで楠木氏が語っている「マネジャーとしての役割」と「部下に仕事を任せることの重要性」は、現代の人事業務において非常に参考になる内容です。組織全体に与える影響や具体的な施策を深掘りしつつ、どのように応用できるかを考えて考察してみます。
部下に仕事を任せる文化の重要性
楠木氏が指摘するように、マネジャーが自分で仕事を抱え込み、プレイヤーとして動き続けることは、組織全体のパフォーマンスを低下させるだけでなく、部下の成長機会を奪う結果となります。人事部門としては、こうした現状を改善するために、マネジャーが「部下に仕事を任せること」の価値を理解し、それを実践できる文化を醸成することが求められます。これには、まずマネジャーが自身の役割を正確に認識し、適切なリーダーシップを発揮するための教育が欠かせません。
例えば、マネジャー研修では、「自分が直接動くこと」と「他者を通じて成果を上げること」の違いを学ぶセッションを設け、部下に仕事を任せる際の具体的な方法論を教えることが重要です。さらに、部下に仕事を任せるプロセスを体系化し、それが部下の成長と組織の成功につながるという考え方を浸透させる必要があります。
また、部下に仕事を任せることで得られるメリットについても明確に伝えるべきです。例えば、マネジャー自身が業務の中で余裕を持ち、戦略的な思考を働かせられるようになる点や、部下の自主性が高まり、組織全体の生産性が向上する点などです。これらのメリットを具体的な数値や事例で示すことで、マネジャーが部下への仕事の委譲を前向きに捉えられるよう支援します。
マネジャーの能力開発における人事の役割
マネジャーが部下に仕事を任せるための能力を育むプログラムを開発し、提供することが重要です。楠木氏の言葉を借りれば、マネジャーには「部下のベクトルを見極める」能力が求められます。これには、部下の適性ややる気を見抜く力、つまり観察力や洞察力が必要です。この能力を高めるために、人事部門が提供できる具体的な施策として以下が挙げられます。
適性判断ワークショップ
部下の強みや興味を引き出す質問方法、観察ポイントを実践的に学べる研修を実施します。例えば、部下との1対1の面談で「キャリア目標」や「やりたい仕事」について掘り下げるスキルを身につけるプログラムを提供することが考えられます。
フィードバックスキルの強化
マネジャーが部下に適切なフィードバックを行えるよう、具体的かつ建設的なフィードバックの仕方を学ぶセミナーを企画します。部下がどのような行動を変えるべきか、またそれが組織の成果にどうつながるのかを明確に伝える力を育成することが目的です。
問題解決力の養成
楠木氏が述べる「原因究明」に焦点を当て、問題の根本原因を特定し、それを解決するための方法論を習得する研修を導入します。この際、人事が具体的なケーススタディを用意し、実際の職場で直面する課題に即したトレーニングを提供することが効果的です。
多様な働き方を尊重する評価システムの構築
現代の職場では、育児中の社員や時短勤務者、フレックスタイム制度を利用する社員など、多様な働き方をしている人々が増えています。その中で「定時退社する社員には重要な仕事を任せられない」というような先入観は、特定の社員に不利な評価を与える原因となりかねません。人事部門としては、こうした偏見を取り除き、多様な働き方を尊重しながらも公平な評価を行う仕組みを構築する必要があります。
例えば、勤務時間ではなく、成果やプロセスを重視した評価基準を導入することが考えられます。また、時短勤務者やリモートワーク社員にも責任ある仕事を与え、その成果を適切に評価する仕組みを整備することが重要です。このような取り組みによって、社員のモチベーションを高め、組織全体の生産性向上を図ることができます。
人的資本経営の推進と組織文化の変革
「人的資本経営」は、人事の視点から見ても非常に重要なテーマです。人的資本への投資は、単なる短期的な補充ではなく、長期的な成長を見据えた戦略的な取り組みであるべきです。人事部門は、この考えを経営陣や管理職に浸透させ、組織全体で共有するための役割を果たさなければなりません。
具体的には、タレントマネジメントシステムを活用し、社員一人ひとりのスキルや適性、キャリア志向を把握し、それに基づいた仕事の割り振りを実現することが求められます。また、組織全体で「部下の成長を喜ぶ文化」を育むために、成功事例の共有やリーダーシップ研修を通じて、部下育成の重要性を強調する取り組みを進めるべきでしょう。
まとめ
楠木氏の提言は、人事部門が果たすべき役割を改めて考えさせられる内容でした。特に、「部下に仕事を任せる」という行為が、単に個人の成長だけでなく、組織全体の競争力を高める鍵であることを認識し、人事戦略に組み込むことが重要です。これにより、マネジャーがより効果的に部下を育成し、組織全体の生産性とエンゲージメントが向上するでしょう。
このように、部下に仕事を任せることの意義は実は多岐にわたり、組織全体の成功を支える重要な要素であることが改めて理解できたところです。