
理系文系論争!論理的思考力が高いのはどっちだ!?
こんにちは。
本日2本目の記事になりますが、「理系」と「文系」の間で昔から繰り広げられている論争を私なりの観点からみていきたいと思います。
ちなみに私はコテコテの「理系」大学出身です。
正直学生時代は「文系」というものに魅力を見いだせず、「理系」こそ将来の役に立つと考えるような偏った考えだったと思います。
理系の方が就職しやすいとも言われ、文系はなんとなくちゃらちゃらしているようなイメージと学問に遊んでいる印象でした。
しかし今は全く考えは違います。
文系と理系は助け合う事でお互いの良さを引き出すことが出来ると思っています。
そのあたりを書いていきます。
世間の「文系」と「理系」の見方
世間一般に文系はこういう人、理系はこういう人というイメージ像がありますよね。
例えば文系。
①感情表現豊か
②直観で行動する
③コミュニケーション力が高い
理系は、
①思考力が高い
②冷静に分析するのが得意
③口下手
世間の印象は上記のようなものが強いようです。
確かに私が学生の頃から「文系」は明るい、「理系」は暗いみたいな偏見もありましたし、なぜか理系の方が頭がいいみたいな見方も多かったように思います。
果たしてこのイメージは合っているのでしょうか。
私の今の考えは全く違います。
論理的思考力
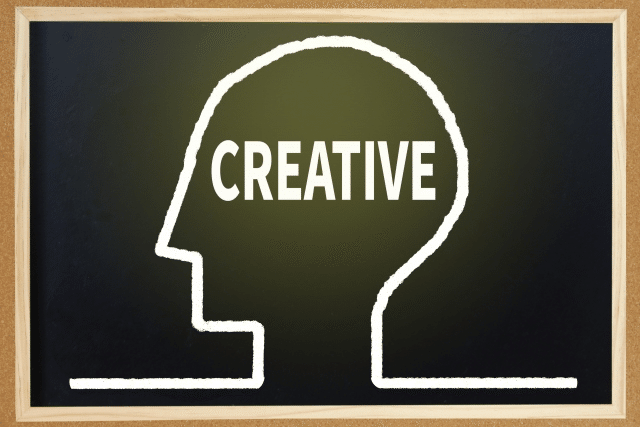
まず理系が得意と言われている論理的思考力ですが、果たして本当にそうなのでしょうか。
論理という言葉を辞書で引くと「物事の筋道」であったり、「法則的なもの」とあります。
確かに理系科目の「数学」や「物理」のように現代における絶対的な公式が存在し、その公式に当てはめることで答えを導きだす行為は論理的思考だと思います。また合理的ともいえるかもしれません。
理系の子の考え方は世の中には法則が存在し、必ず答えが存在する事や今は未知の物の答えが今後導き出せる事に惹かれるのかもしれません。
こういう論理を「形式論理」と言ったりします。形式論理とは、法則などの不変のものに対する論理です。
一方で、文系の科目には論理的な考えはないのかと言えばそれは誤解です。
「現代文」や「小説」などの作者の気持ちを考えたり、人間社会における法則・法律では判断できかねる事象に対して、実質的な論理を展開するのが実質論理です。
例えば、裁判などで法律に接触している被告人を有罪とするのが形式論理で、しかし情状酌量の余地があると減刑することが実質論理であるというとわかりるかもしれません。
実質論理は形式論理と比較すると、必ずしも答えが一つではないと定義できるかもしれません。
しかし論理=答えを得る過程と捉えるならば、形式論理も実質論理も論理ですね。
つまり文系の論理と理系の論理は性質の違う部分はあれど、論理的思考力が文系は劣るという考えは少し違うのかもしれません。
論理的思考力の「理系」と「文系」のそれぞれの強み
形式論理と実質論理の話をしましたが、ではそれぞれの論理的思考力の強みは何なのかを考えます。
理系の方が得意とする形式理論の考えでは、研究職がやはり向いています。世の中に存在する物質や原理原則を理解して、方程式や法則を当てはめることで新しい技術を創出することが出来ます。
このように形式理論の積み重ねが現代の技術に継承されております。
つまり形式理論を得意とする理系の方が世の中の基盤を作ってきたというのは真実かもしれません。
あくまで私の予想ですが、理系の方が文系に比べてビジネス面で重宝されるのは、イノベーションを起こす可能性が高い事が評価されているのかもしれません。
しかし人間は社会性がある生き物ですので、すべて公式や法則に当てはめた答えが正しいとなると由々しき事態が起きると想像できます。もちろん理系の人に社会性が無いという話ではないです。
一例ですが、殺人=死刑などかなり極論な自体が起きやすくなると思います。
そこで社会性が強い文系の登場なのです。
むしろビジネス上で必要な能力は実質理論的な考えだと思っています。
経済は社会性が大事です。人類が連携することで大きな経済力が出来ます。
裁判官や弁護士などが必要であったり、必ずしもルールで縛ることが出来ないのが人間社会です。
そういった意味で文系の方はスムーズな経済活動を行っていく上で重要なポジションであると言えます。
「理系」と「文系」が連携することで爆発力が生まれる

私は理系と文系の関係がなんとなくパソコンのシステムの関係性に似ているような気がしました。
それは、理系の計算力や問題解決力はCPUに例えられ、理系が解決した答えを民衆や社会に浸透させるのが文系でありOSに例えられるのではないでしょうか。
経済学者のピータードラッカーの言葉を借りると、「専門家だけでは世の中に価値を提供できない。価値を翻訳するものが必要である」とおっしゃっています。(言葉は違うかもしれませんが著書「マネジメント」でこんなことを言っています(笑))
ここでいう専門家が「理系」であり、翻訳者が「文系」です。
簡単に言うと理系の方が出した正解はみんなに理解するのが難しい場合が多いので、文系の方がみんなにわかる表現や言葉にすることで価値が生まれると理解できるのではないでしょうか。
つまり両者は切っても切れない関係があり、どちらが優れているか優れていないかを議論することはナンセンスだと思います。
どちらも学ぶべき学問であり、その人がどちらに興味を持つかだけなのです。
個人的には「実質理論」が面白い
私は理系大学出身で考え方も理系よりなのですが、今は文系的な考え方が面白いと思っています。
ビジネスにおいて答えのある問題を解く機会はあまりありません。
自分で顧客の問題を提起し、その問題を解決することで初めてビジネス的な価値が生まれます。
この顧客の問題は時代、見方、宗教、人種などの違いで多岐にわたります。
答えがさまざまある中で、その時の「最適解」を見つける思考力がビジネスで成功する要素であると考えています。
定まらない答えを見つけることの面白さに魅了されました。
まとめ
結論は「理系文系論争」自体がナンセンスであると思いました。
論理的思考力に差はないと思います。
就職に有利だからとか、大学生活が楽だからとかそんな理由で選ぶものではそもそもなくて、ましてや優劣をつけるものでもないです。
学問は必要だから先人から受け継がれてきたのです。
学問に不要な要素はありません。
有難うございました!
