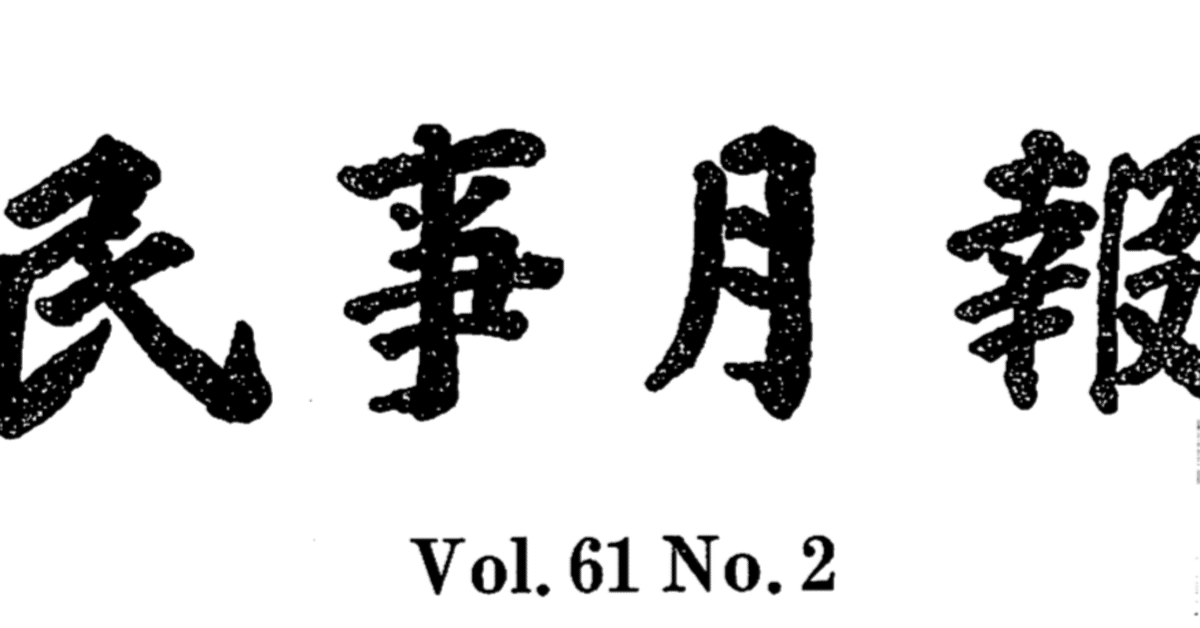
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(平成18年1月18日法登1第93号東京法務局民事行政部長照会、平成18年1月20日民商第135号民事局商事課長回答、同日民商第136号法務局民事行政部長(除く東京)、地方法務局長あて民事局商事課長通知)
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて
(平成18年1月18日法登1第93号東京法務局民事行政部長照会、平成18年1月20日民商第135号民事局商事課長回答、同日民商第136号法務局民事行政部長(除く東京)、地方法務局長あて民事局商事課長通知)
(通知)
標記の件について、別紙1のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙2のとおり回答しましたので、この旨管下登記官に周知方取り計らい願います。
別紙1
(照会)
商業・法人登記の申請書に、司法書士が作成代理人として記名押印又は署名をしている定款(公証人の認証が必要な場合にあっては、その認証を受けた定款)が添付されている場合において、他に却下事由がないときは、当該申請を受理して差し支えないと考えますが、この点につき、いささか疑義がありますので、照会します。
別紙2
(回答)
本月18日付け2法登1第93号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおりと考えます。
おって、本件については大臣官房司法法制部と協議済みですので申し添えます。
【解説】
1 司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて
本件は、司法士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請を受理することができることについて疑義があるとして照会があった事案につき、当該登記の申請は、他に却下事由がないときは,受理して差し支えない旨の回答がされたものである。 司法士の業務範囲と司法書士による定款作成に関しては、昭和29年1月13日付け法務省民事甲第2553号法務事務次官回答(以下「昭和29年回答」という。)があり、本件についても、後記2で述べるとおり、弁護士法第72条との関係が問題となる。この昭和29年回答によれば、司法書士 が行った定款作成代理行為につき、その具体的な行為によっては、弁護 士法第72条の違反の問題を生ずる場合があり得ることになる(昭和29年回答と弁護士法等との関係の詳細については、後記2を参照されたい。)が、この場合に、仮に当該定款の効力に影響があるとすれば、登記申請の却 下事由である商業登記法第24条第10号の「登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。」に該当する可能性がある。
しかし、登記申請の審査に当たって、形式的審査権限のみを有する登 記官は、添付された定款が代理人である司法書士によって作成されるに際し、後記2に示したような「一般の法律事件に関して代理その他の法律事務を取り扱うこと」に該当すると判断されるような事情が存在したか否かを審査・判断することはできない。そのようなことから、司法書士が作成代理人となった定款について、弁護士法第72条に違反する場合 の当該定款の効力につき論ずるまでもなく、当該定款が添付された登記申請については他の却下事由がなければ受理して差し支えないものとして、本件の回答が行われたものと考えられる。
なお、司法書士が登記申請の添付情報となる定款の作成代理を行うことは、司法書士法に違反するものではなく、そのことも、本件回答の前提となっているものと考えられる。
以上のとおり、本件の回答は、昭和29年回答の考え方を前提として、司法書士が作成代理人となっている定款が添付された登記申請の取扱いについて、商業登記手続の仕組上、当然の帰結を示したものと考えられる。
2 司法士の業務範囲及び司法書士による定款作成代理について(昭和29年回答との関係)
司法書士が登記申請の添付情報となる定款の作成代理を行うことについては、弁護士又は弁護士法人でない者が報酬を得る目的で一般の法律事件に関して代理その他の法律事務を取り扱うことを禁止している弁護士法第72条との関係が問題となり得る。
司法書士の業務範囲と弁護士法との関係については、昭和28年10月26日付けで日本弁護士連合会会長から法務大臣あて照会された「司法書士の業務範囲と弁護士法の関係について司法書士の業務範囲に関する照会の件」において、「特に会社定款の起案作成その他会社設立に必要な類 を作成することは同条に違反しないか。」との照会があり、これに対し、「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申書。登記申委任状)の作成は、司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証)の作成は、含まれない。なお、後者の場合において、書類の作成で法律判断を必要としないものについては、弁護士法第72条の違反の問題を生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」旨の昭和29年回答がされている。
仮に、定款作成代理が司法書士法の定める司法書士の業務範囲に含まれるのであれば、弁護士法第72条ただしの「この法律又は他の法律に 別段の定めがある場合」に該当し、類型的に弁護士法第72条違反の問題は生じないということになるが、昭和29年回答は、定款の作成が司法書士法に規定される司法書士の業務範囲に含まれるものではないとして、 弁護士法第72条ただし書の適用場面ではないことを明らかにしている。
司法書士の業務範囲に関する昭和29年回答の考え方に照らせば、司法書士が定款作成代理をする場合においては、その具体的な行為が、弁護士法第72条本文にいう「一般の法律事件に関して代理その他の法律事務を取り扱うこと」に該当するか否かという点が問題となると考えられる。その際、具体的な行為が、それに該当する場合であれば、弁護士法第72条違反ということになるが、そうでなければ、弁護士法に違反するものではなく,適法な行為であると考えられる。昭和29年回答が、弁護士法 第72条の違反の問題を生じない場合と生ずる場合とがあるとしているのも、このような考え方に立つものと考えられる。
本件の回答は、このような昭和29年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。
なお、本件の回答には、弁護士法を所管する大臣官房司法法制部と協議済みである旨のおって書きが付されている。
(数原・横山)
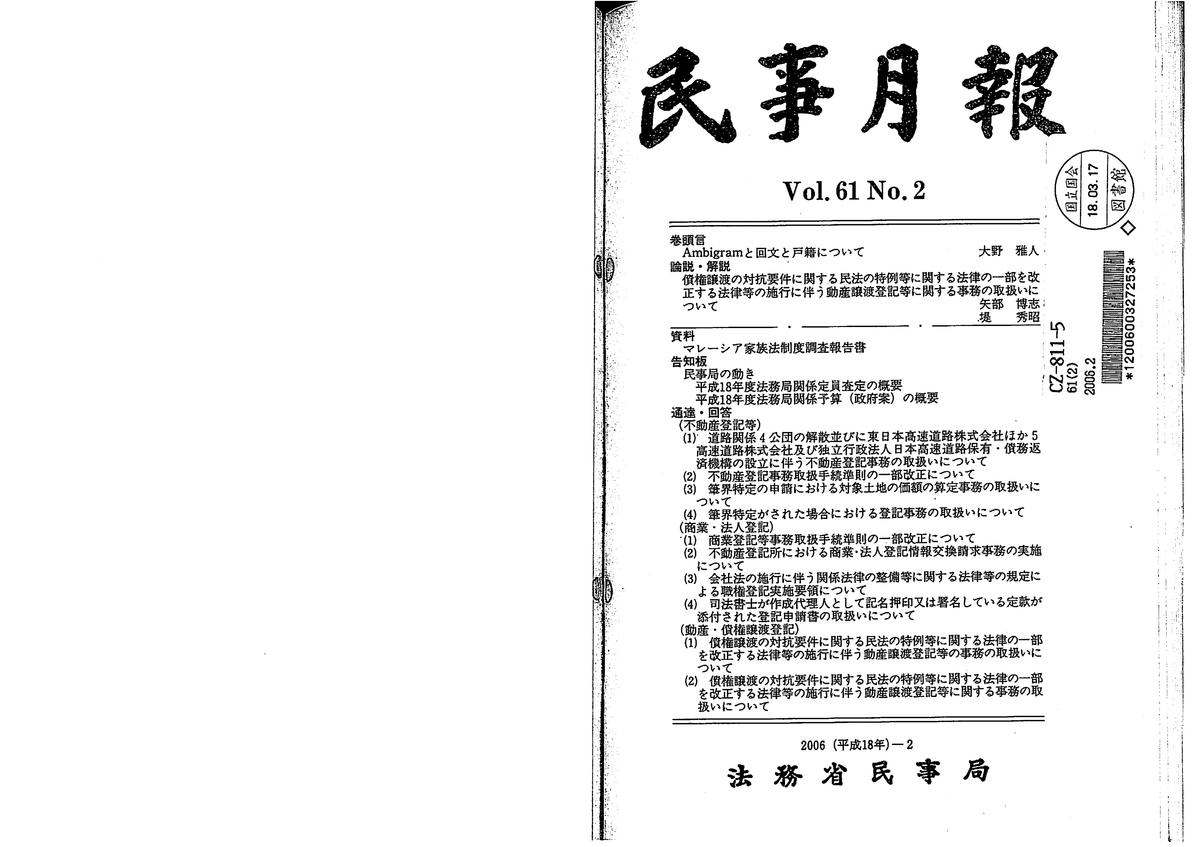
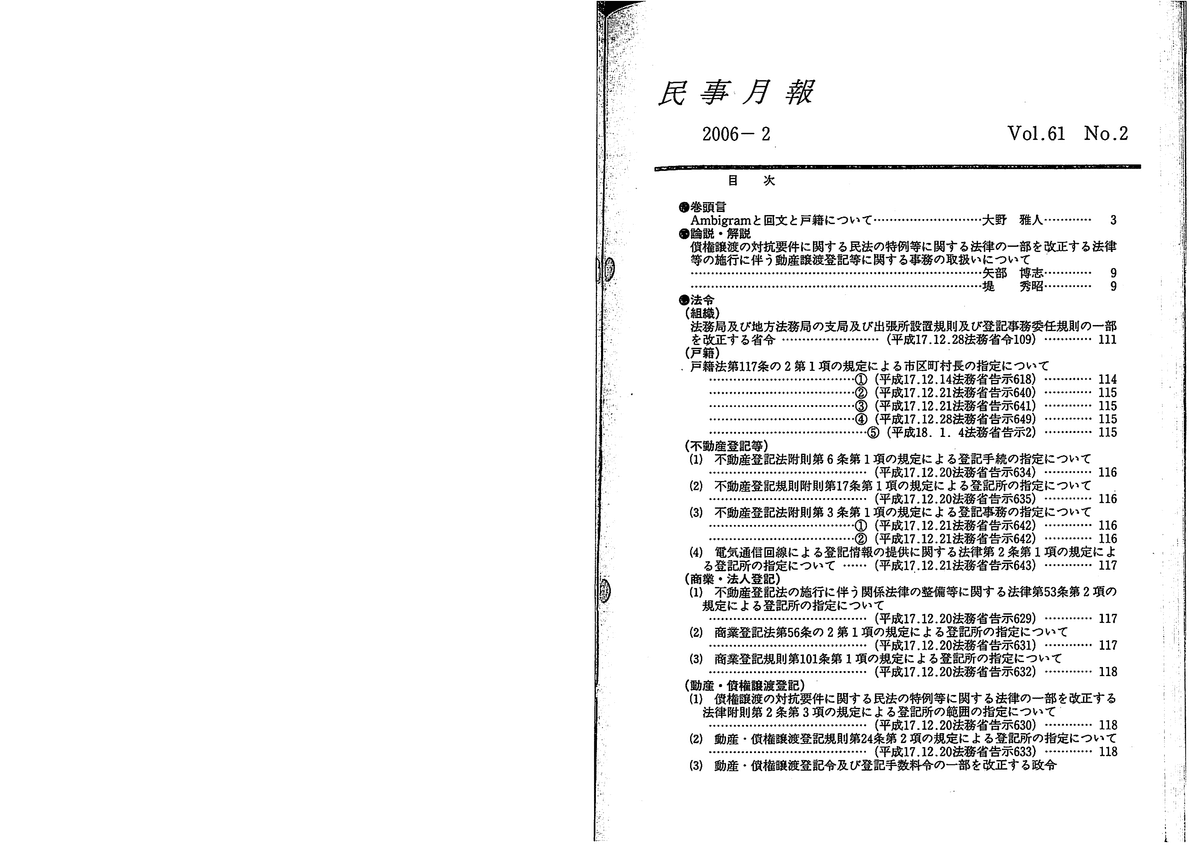
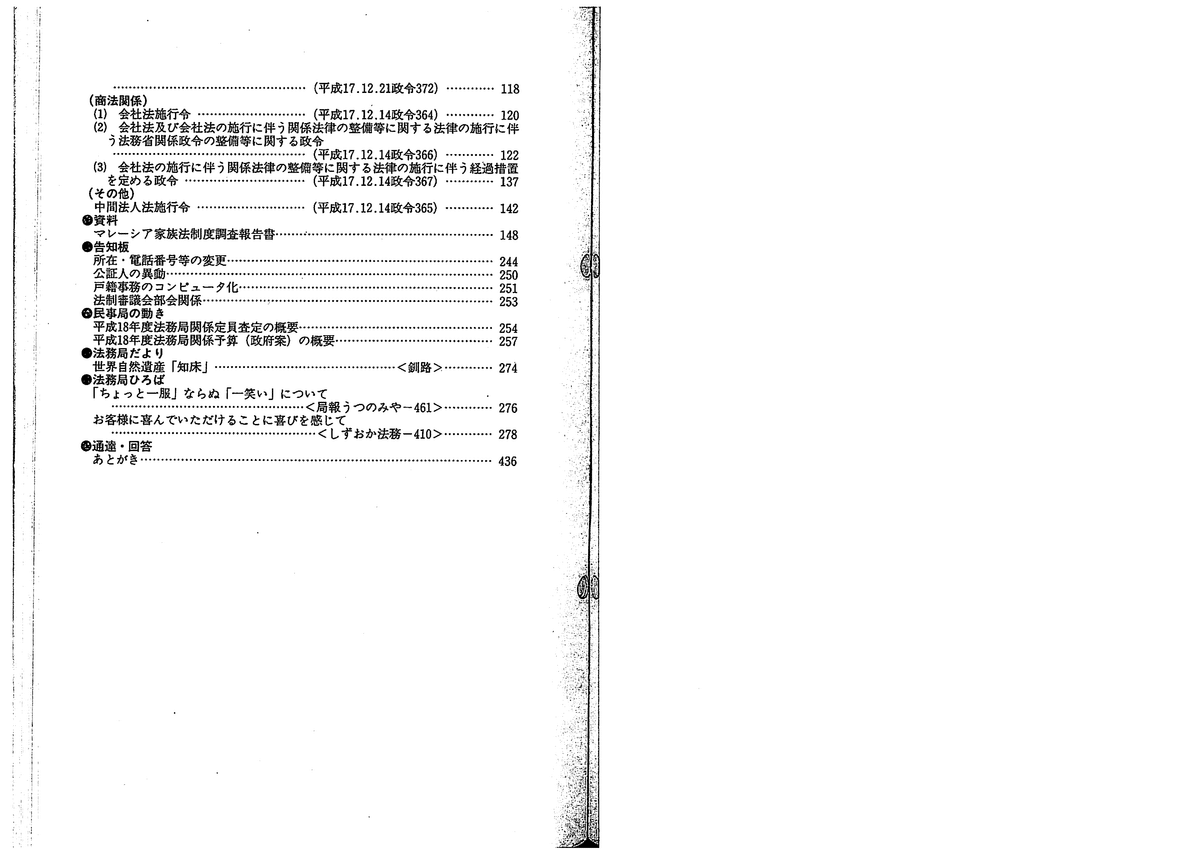
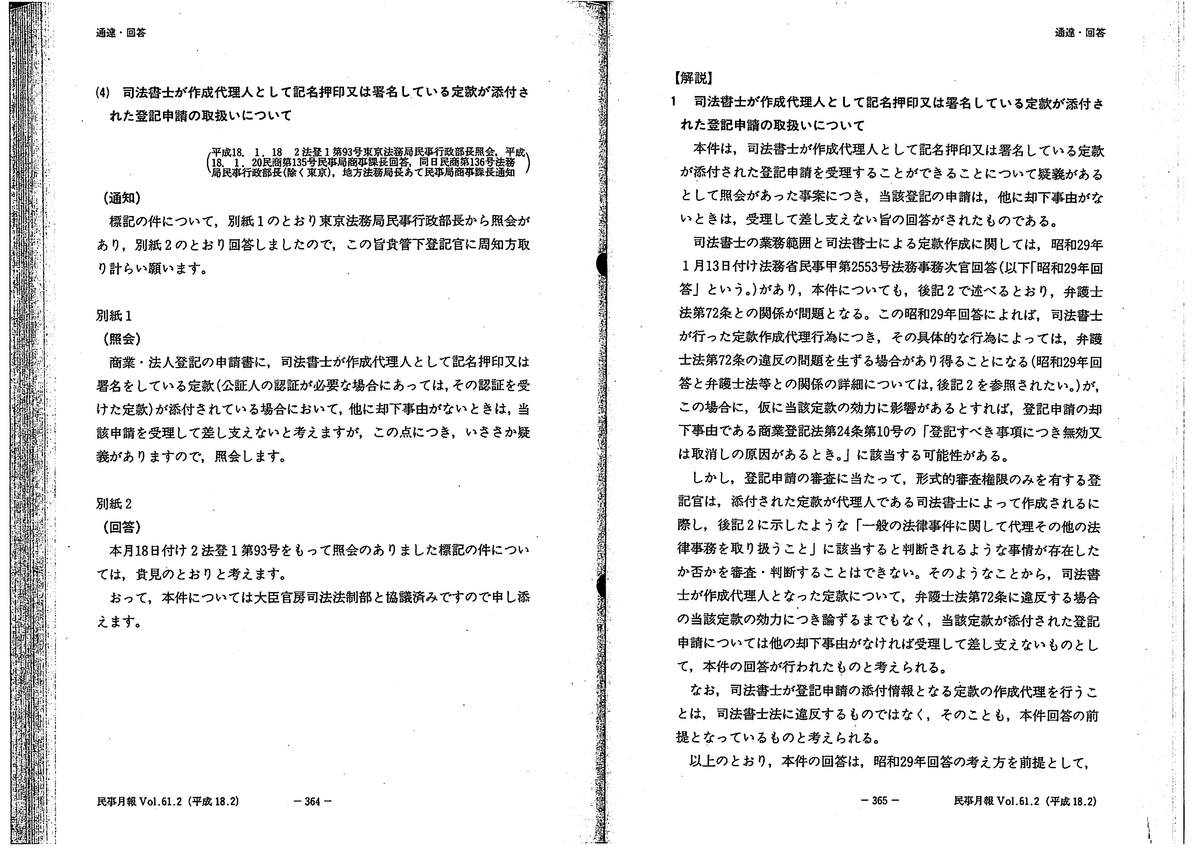
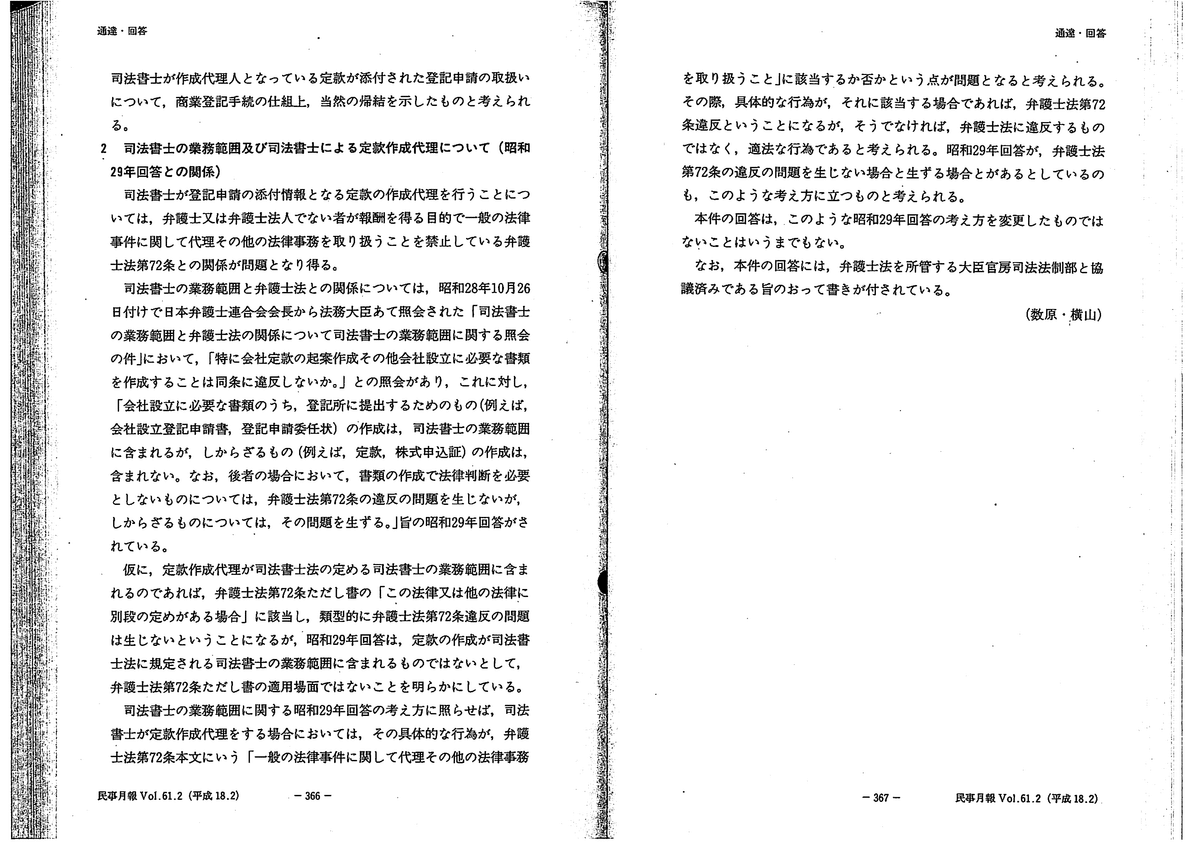
発行者に照会したところ、本文書は、「国…が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」「前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国…が作成するもの」(著作権法13条)として、解説部分も含めて著作権法の対象外と理解して構わないようですが、出所は明記してほしいというご指示がありました。
出所は、法務省民事局発行の民事月報第61巻2号(平成18年2月)であることをここに明記しておきます。
