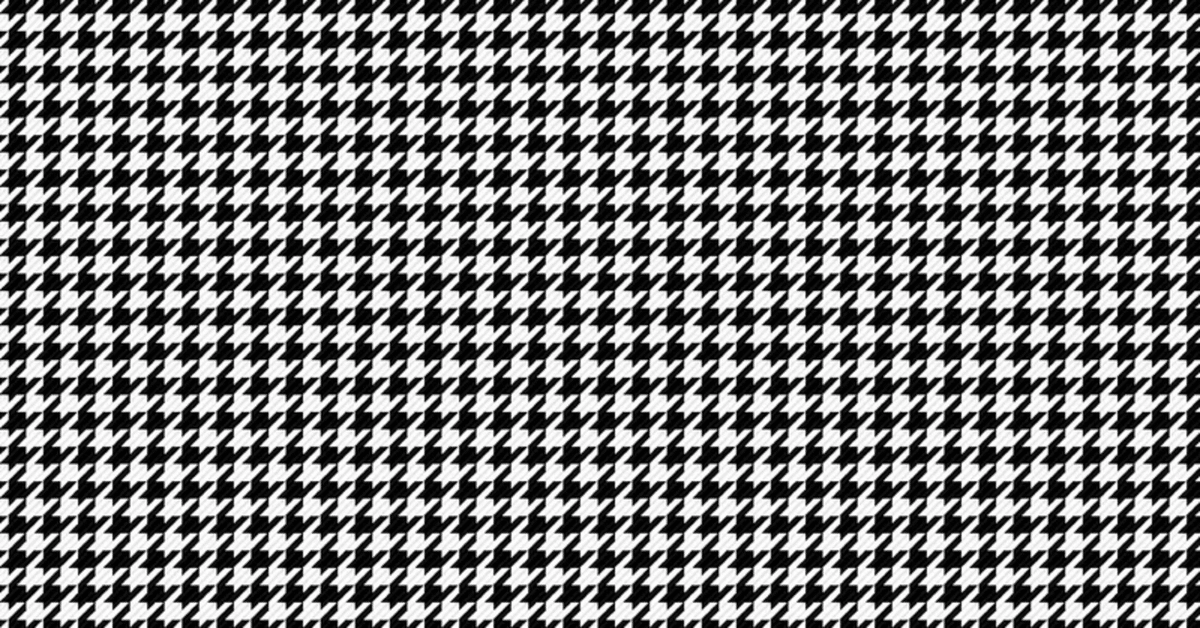
【万華鏡】書くこと
はじめましての人も、
前から知ってる方も、
ごきげんよう。
偏光です。
改めて思い返すと書いてない。
(文字数:約1500文字)
かつて私は書く行為そのものが大好きだった。
……と、言いたいところだが、
ここはあえて正式名称で言うと、
ワードプロセッサなる物の存在を知らず、
知った後も自分個人のために購入・所有できるなどとは、
考えも付かなかった頃には、
書くとはすなわち、
形状に、色味や質感は様々だとしても、
まっさらな紙に向かって、
自らの手指で操る筆記用具で、
一文字ずつの、
インクや墨汁や炭素の粉を染み付かせる、
という行為であり、
それ以外には存在しなかっただけだ。
今やボード上に並んだキー配列を、
わざわざ脳内でローマ字変換しながら打ち込み、
画面上に日本語変換表示されてくれる文字列を、
目視確認しながら、
誤変換などがあれば時折修正する行為になっている。
今時フリック入力だよ、
と笑われてしまうかもしれないが、
それもローマ字入力の一変形なんだ。
日本語使用者は本来、
何行の何列目あるいは方向などを、
脳内でほんのかすかにすら意識しないまま、
「こ」を
「ち」を
「ふ」を書き記せたばかりか、
「東風」と書いて「こち」と読ませる、
離れ業までやってのけていたはずだ。
それはともかく今や私が大好きな行為は、
(キーボードを)打ち込む事に変わってしまった。
書いていない。
つまり「何らかの文章を生成する行為」
という最終目的が共通であるために、
実際の手指を使っての行動そのものは、
もはやほとんど問われなくなった。
AIで、あるいはAIが、書く、
という表現にも、
それほど違和感がなくなってくるわけだ。
ここで気になって、
「書」という字の字源を調べてみた。
「日」の部分が大きく変化したようだが、
無理やりに結び付けて表すとしたら、
「手に持った道具によって、
日々の様々な事柄をまとめ上げる」
行為を意味する。
元来は「手に持った道具」であった。
まさしく書く行為が大好きだった頃の私は、
時折辞書を引きながら、
一文字ずつを書き記していくその行為に、
自らの手指とその動きにより、
呪力、とも呼べそうな念を込めていた気がするが、
打ち込む、にそこまでの呪力が宿るかどうか。
言葉に語句の一つ一つも、
書く、ほどには重要なものに、
思われなくなっていくのではないか。
……と、適当にまとめて切り上げたいところだが、
料紙に、良質な墨や筆を、
いつでもふんだんに使えていた身分の者であれば、
自らの頭の内に、
わざわざ文語体で組み上げた文章を記述する際の、
筆運びのスムーズさは、
キーボードを打ち込む速さに変換スピードと、
それほど遜色が無かったのではないか。
もしかすると古典籍時代の感覚に、
かえって立ち戻っているのではないか。
そうだったら面白い。
過去に比べて優れているとも劣っているとも、
言い切れない点が小気味良い。
単に私はそう思った、
だけの話だ。
余談だが「万華鏡」という一語こそ、
筆記用具で書いてみたい語句の筆頭に挙げ切れそうだ。
「万」の左右かつ上下バランス調整に、
「華」の最後の縦線の勢い。
「鏡」の最後の弧を描いた後の跳ね上げ。
どれをとっても手に指先が、
一種独特の達成感を得て法悦に浸りそうだ。
今の時点で明言しておきますが、
私は語句文章を対象にした、
わりと珍しいタイプの変態です。
以上です。
ここまでを読んで下さり有難うございます。
いいなと思ったら応援しよう!

