
なぜコーチングがビジネスマンからアーティスト、お母さんまで必須科目なのか
この記事を書いた人
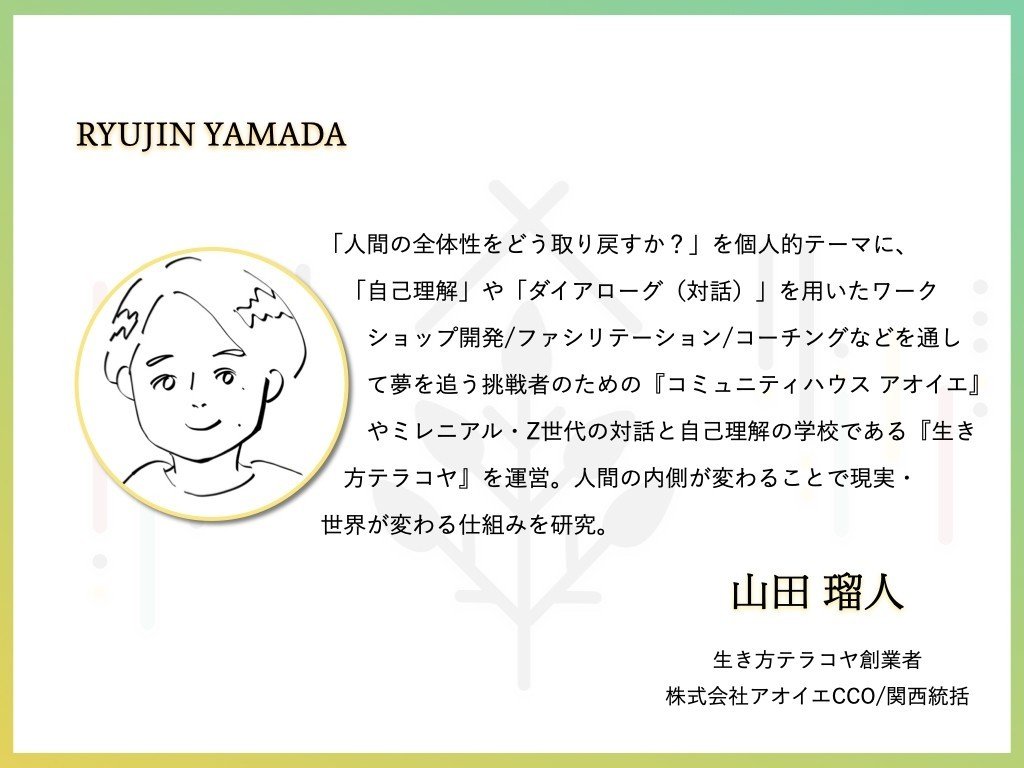
0.はじめに
私は仕事として、様々な職業・背景・価値観の主に20代に対して、自己理解を通して自分自身を自分の居場所にしていき、固定的なセルフイメージを破壊しながら本来望んでいた人生を生きるサポートをしております。具体的には、ワークショップ開発/ファシリテーションやコミュニティ運営、コミュニティハウスの提供を方法としていますが、その中の1つに「コーチング」という手法があります。
ここ10年ほどで日本でも頻繁に見かけるようになったコーチングとは、一体なんなのでしょうか?最大手のコーチ・エィさんでは以下のように定義されています。
コーチ・エィでは、コーチングを「目標達成に必要な知識、スキル、ツールが何であるかを棚卸しし、それをテーラーメイド(個別対応)で備えさせるプロセスである」と定義しています。つまり、コーチングとは自発的行動を促進するコミュニケーションのことをいいます。現在では組織のマネジメントにおける人材開発手法として、多くの企業・組織が、人材開発、リーダー育成、組織開発のためにコーチングを導入しています。
私自身、自己理解の常識化において「対話的な文化の浸透」が急務だと考えており、その具体的な手法の1つとしてコーチングは大いに注目しています。コーチ・エィさんの定義にあるように「自発的行動を促進するコミュニケーション」と広くコーチングを捉えると、その射程はビジネスに限らないことは想像に難くないと思います。
これまでの個人的なストーリーを辿ると教育という畑でしばらくキャリアの土壌を耕していました。そこで出会うのは、未就学児から小学生、中学生、高校生、大学生、専門学生、会社員、起業家、フリーランス、アーティスト、お父さんお母さんなど縦幅が高く、あえてカテゴライズするのであれば、富裕層から貧困家庭、リーダー、発達障害、行動的なイノベーター、中流の人々、自信のない人など横幅も広く多岐に渡るものでした。しかし、これらの支援/共創の過程で感じざるを得なかったことがあります。それは「結局は対話による合意から全てが始まる」という一つの事実です。
社会構成主義、と後に説明しようと思う「対話から始まる」スタンスを取ることで、より「コーチング」という手法、もしくはその根底に潜む思想、信念をより解像度高く説明することが重要だと考えるようになったのです。また、社会構成主義以外にも、コーチングへの理解を深める知見・領域があるとも考えています。今回は、それらの紹介を通して、コーチングの魅力や価値、射程の広さを感じていただきたく、拙い知識・表現ではありますが筆を取ることに致しました。それでは、前置きはこれくらいにして、実際に本題に入っていきます!
1.コーチングとは何か?
それでは、コーチングとは何かという問題をもう少し深く見ていきたいと思います。先の定義では、「目標達成に必要な知識、スキル、ツールが何であるかを棚卸しし、それをテーラーメイド(個別対応)で備えさせるプロセスである」よろしく「自発的行動を促進するコミュニケーション」としました。本記事で特に参考にする『コーチングのすべて その成り立ち・流派・理論から実践の指針まで』では7つもの具体的な定義を書籍や論文から引用し、その共通項を「変化」「不安」「関係」「学習」とまとめています。
変化:方向性と成長を意味し、より良いものを目指して進んでいきます。クライアントの外的変化に最善の形で対処するために「思考」「感情」「行動」へのアプローチをします。
不安:クライアントは現在自分が望んでいる地点にはいないことで、不安を抱えています。不安定な生活、問題、課題、目標に対する不安などが、概して漠然としているところからはじまります。
関係:コーチングでは、パートナーシップという協力な関係を築きます。信頼に基づき、クライアントとコーチはお互いに唯一無二の存在として関係し、その質がコーチングの成功を大きく左右します。
学習:クライアントの問題解決や目標達成という学習に終わらず、自律的に学習し成長に向かっていく学習能力を育てます。クライアントが学習者になることで、自走していくためです。
以上の4つを踏まえると、多様な定義のあるコーチングですが、そのエッセンスは「クライアントが心から向かいたい変化に対して、付随する不安に最善の対処をしながら理想への学習をしていくための、良質で唯一無二の関係性を結ぶこと」 と言えるかもしれません。
2.コーチングの「思想」
以上のような定義があるコーチングですが、その思想は一体どういったものなのでしょうか?どんな価値観や信念を元に、上述のまどろっこしい手法を取るのでしょうか?(だって、うだうだ問いかけずに教えたり、勝手に上司や親がやったほうが早そうでしょう?楽そうでしょう?)
ここからは、コーチングの元になっている思想や学問、領域について挙げていこうと思います。例えば、以下のものがあると思います。
a.人間性心理学
b.東洋哲学
c.社会構成主義
もちろん、これ以外にも多くの思想、学問に基づいていると思いますが、概論的に3つを紹介します。これらの要点を押さえることで、よりコーチングに対する深い理解が図れると思います!
3.人間性心理学
「自分自身の力で平和な気持ちになろうとするなら、音楽家は曲を創り、画家は絵を書き、詩人は詩を書かねばならない。人は自分がなり得るものにならなければならない。この心理的欲求こそが我々の言う自己実現なのだ。(中略)人間性心理学が取り上げるのは、人間が達成感を求める気持ち、つまり人間が実際に自分のなれるものになろう、自分がなれるものすべてになろうとする性質なのだ」
欲求階層説(昨今では眉唾ものだが)で有名なアブラハム・マズローは、人間性心理学の第一人者とも言え、上のセリフには人間性心理学の考え方が詰まっています。それまで心理学の主流だった、外側に見える行動など客観的な観察を重視する行動主義や、人間の内側深くに眠る気づきにくい動機まで射程に入れる精神分析が主流だった時代において、第3勢力として現れたのが人間性心理学でした。客観的なものや、病理的なものは人間の1つの側面にすぎず、別の面にある希望や健康、愛情、自己実現に目をつけたのでした。
コーチングにおいては、理想や目標達成に近づくための支援をするのですが、大切なことは目標を達成することのみではありません。その過程において、クライアントがいくつかの選択肢を持ち、それぞれに対する思考や感情に気づき、自発的に選択肢を決定し自分だけの道を生み出していく「芸術家」として唯一無二に関わることです。そういった姿勢は、人間性心理学が持つ「自己実現的」な考え方にかなり符合します。また、人間性心理学では以下のような原則があります。
①人が自分自身を体験する方法は、心理学的に根拠のある観点である。
②人間の本質に関する楽観的な見解-人間は自己実現を望んでいる。
③1人1人の人間は、完全で、唯一無二の存在である。
④人は皆、かけがえのない尊い存在である
⑤選択肢はないよりも、あった方が良い。人は皆、選択肢を持っており、その選択肢から選んでみたいと思っている。
このように、かなりポジティブで楽観的、健康的な考え方が特徴ですね。目の前の人を、全体的なものとして扱い、唯一無二として関わる。これは、ビジネスマンからお母さんまで必要な考え方であると思います。
4.東洋哲学/思想
2つ目は、日本の歴史からのギフトでもある東洋哲学です。東洋哲学とは何かというのは、最も難しい問いの1つです。なぜなら、東洋哲学とは言語的な説明が難しく、体験的であるからです。「悟り」をイメージしてもらえばわかりやすいですが、頭では理解できても体感的にイメージできないものがほとんどです。
さらに、東洋哲学には「無為自然」「上善如水」のような、「ありのまま」と現代では言われるような考え方が多いと考えられがちで、理想に対する変化を伴うコーチングとの整合性が見えにくいのもあるかと思います。
それでは、一体どの部分において影響を与えているのか。その1つは、「自己認識」や「自己理解」に対する考え方です。自己認識や自己理解は、コーチングで手に入れられるものの1つです。先に挙げた「唯一無二のかけがえのない自分」として、他でもない自分自身について深い気付きを得ることができるのは、学習者への一歩とも言えます。
東洋哲学では、西洋が「世界とは何であるか」を求め神を作り出していった一方で「自分とは何であるか」という内側に問いを向けてきた特徴があります。紀元前のころからです。座禅、只管打坐などが有名な禅仏教を思い出してみても、「座るだけ」とか「言葉通りにいかない問いかけ」など自分自身との戦いであり、内側に何かしらの結論や帰る場所を求めています。
このように「体験的、内観的に自己を理解し信頼していく」というやり方は、コーチングに通ずる部分が多いのです。コーチングは、「自発的行動を促進するコミュニケーション」とも言いましたから、あくまでクライアント側が自分自身の気づき、納得の範囲で考え、感じ、行動します。コーチが可能なのは、教えることや押し付けることではなく、問いかけることです。考えるのも、感じるのも、動くのも唯一無二のクライアントのみだからです。このように、体験や自己決定、それを通した内側の気づきを重視する点で、コーチングは東洋哲学の影響を強く影響を受けています。
余談ですが、コーチングやカウンセリングなど対話的なコミュニケーションの多くでは、ただ相手の話に心と耳を傾ける「傾聴」や、ただ相手の言ったことをもう一度話すだけの「オウム返し」という手法・思想が用いられます。これは、クライアントが自分自身の発言を通して内側に向き合うための、方法の1つなんですね。
5.社会構成主義
3つ目に紹介するのは、社会構成主義についてです。社会構成主義とは、ジャック・デリダやケネス・J・ガーゲンなどが有名な社会学の1つの主義です。簡単に要点をテキストにすると、以下のような知見があります。
人々はお互いの言葉の対話の中で合意に基づいて「意味」を作っていくのであり、「意味」とは話し手と聞き手の相互作用の結果である。
このように、「人は認知を通して現実に気づくのだから、客観的な事実など存在しない」というような立場を取り、対話での合意が社会を構成しているという考え方です。例えば、フランスには蛾が蝶と区別されておらず、どちらも”papillon(パピヨン)”と言う。そのコミュニティで「あれは蝶だ」「これは蛾だ」という同意に基づいて言葉が生まれ、意味を形成していることをわかりやすい事例です。他にも、日本語には雨に関する美しい表現が多いですが、湿度が高く、四季がめぐる日本ならではの社会的な構成なのですね。"Words create World"と言われるのも納得します。
これがどのようにコーチングに影響を与えているのか?コーチングや自己理解に関わっていて強く感じることですが、多くの人の悩みや問題意識の入り口は「いかに私が社会の被害者か」という口調のものが散見されます。それは社会構成主義的に考えると、「自分と社会は分離していて、社会は私を攻撃してきて、それは私にはどうしようもないことだ」という観念とも言えます。そのため、セッション初期には「普通は〜〜」「常識的には〜〜」など外的な規範を主語に話すことに終始したり、「上司が〜〜」「親が〜〜」「パートナーが〜〜」など他責気味に話すことがあります。(相談に来るタイミングまで、それはその人にとって最善だったのだと個人的には考えております)
しかし、コーチングでは自己決定を助けるのですから、主語を取り返していきます。いかに「私はどう感じているか」「私はどう考えているか」「私はどう行動したいのか、どう行動したのか」などと自分自身が人生に対するコントロール権をある程度までは持っていたということを思い出すサポートをしていきます。「社会がダメ、世界が悪い、あいつのせいだ」という潜在的な考え方が「私も含めて構成される私と世界にどう影響を与えていくか」という視点へとリプレイスされていきます。このような新しい世界観の合意をクライエントと取っていく点で、コーチングは非常に社会構成主義的だと考えています。
他にも「先生と生徒」「上司と部下」「マネージャーとプレイヤー」「黒人と白人」など、言葉が分節によって世界を切り取っていく以上、別の側面としては人と人に分断を起こしうることが見えてきます。使用している言葉、セリフが一体どのような合意に基づいているのかを知ることは、前提が異なる他者と想像力を働かせて共に生きていく上で非常に重要だと考えています。(このテキストは、「人は他者と共同して自分らしさを発揮することが幸福の1つである」という個人的な合意で書かれていますね)
6.本線へ。どうしてコーチングが必須科目なのか?
ここまで、5000字を越える遠回りをしてしまいました、、、笑 要旨をまとめるとすると、以下のようにまとめられるでしょうか。
①コーチングとは、自発的行動を促進するコミュニケーションで、要素としては「変化」「不安」「関係」「学習」がある。
②自己実現や健康、夢、希望を前提とする人間性心理学に基づき、他者を全体的で唯一無二の存在と考え接する必要がある。
③理屈や正解以上に、その人の体感的な納得感や腹落ちとそれに基づく行動の変化を支援する。
④コミュニケーションや言葉が双方の合意に基づいていることに気づき、合意形成を重視したり、無意識な言動の背後にある固定的な合意を想像する。
そして、今回伝えたかったのは「これって全人類に大切なスタンス・スキルじゃないですか??????」ということです。
COVID-19(新型コロナウィルス)が私たち人類の積み上げてきた社会システムがいかに限定的で脆弱であるかを露見させた、とあちらこちらで言われて久しくなりました。VUCAモデルと言われるように、社会環境は刻一刻とVolutilityでUncertainly、Complexity、Ambiguityになり続けてきました。コロナウィルスによって変わったのではなく、毎秒社会は変わり続けており、それが露見したに過ぎないと考えています。
冷静な観察、丹念な情報収集を重ねれば見るより明らかである社会の変化を、beforeコロナまで放置させたのは、他でもない「対話不足」だと考えています。あらゆることは常に変化をしていきます。諸行無常です。常なるものなどないのであれば、文章を書いている私も読んでいるあなたも、帰りを待つ愛する妻や夫、大切な子どももビジネスパートナーも顧客も、今この瞬間で変わり続けているのです。
なぜあらゆる人にコーチングが必須科目か?それは、あらゆる人に対話が必須科目であるからです。変わりゆく自分と他者、世界を大切しにながら、居心地よく自分らしく、それでいて最大限の可能性を自他ともに引き出せるコミュニケーションの思想でありながら、具体的な手法でもありうるのがコーチングです。そのような対話的な文化が広がった先の世界を見たくて、私は今のような仕事をしております。
思考と感情、行動にアプローチするのがコーチングでした。思考と感情は、現在読んでいただきましたあなたの頭や心に浮かぶもの全てです。行動としてはどうでしょう?書籍を買う、借りる。コーチングに明るい知人に聴いてみる。セミナーや講座に参加してみる。ちょっとだけ気をつけて、隣の人と話してみる。なんでも大丈夫です!小さなことから始まっていき、それがいずれドミノのように大きな変化を及ぼすことが非常に楽しみです。
追伸:もし、生き方テラコヤでコーチングを学ぶことをお考えになられるのであれば、お手伝いさせてください!コーチングを受けることもできますし、単発のワークショップから全12回の連続プログラムまで用意しています!
https://ikiteracoaching1.peatix.com/view
追伸の追伸:今更ながら「コーチングが必須科目」という言葉は、強い表現なように思えてきました。「対話」が必須科目であり、その手法の1つとして「コーチング」はオススメですよ、そして記事の入り口や取っ掛かりとしてそのオススメのコーチングを使わせてくださいね、ということでした。気を悪くされる方がいらっしゃったら、本当にすみません。
![helpwell [公式]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/90311891/profile_0a3539d490025645c45ddba56f7ee1fd.png?width=60)