
マルクス『資本論』試論⑥
第一部 資本の生産過程(承前)
労働生産力の様々な複合的諸要因
(1)ドイツ語初版

そのため,ある商品の価値の大きさは,その生産に要する労働時間が一定であれば,一定である.しかし,後者〔労働時間〕は,労働生産力に変動があれば,そのつど変動する.労働生産力は多種多様な事情によって規定されており,なかでも特に労働者の技能の平均度,科学とその技術的応用可能性との発展段階,生産過程の社会的結合,生産手段の規模と作用能力,そして自然環境によって,規定されている.同量の労働でも,例えば,豊作のときには八ブッシェルの小麦に表現され,凶作のときには四ブッシェルの小麦にしか表現されない.同量の労働でも,豊かな鉱山では貧しい鉱山でよりも多くの金属を産出する,等々.
(2)ドイツ語第二版


そのため,ある商品の価値の大きさは,その生産に要する労働時間が一定であれば,一定である.しかし,後者〔労働時間〕は,労働生産力に変動があれば,そのつど変動する.労働生産力は多種多様な事情によって規定されており,なかでも特に労働者の技能の平均度,科学とその技術的応用可能性との発展段階,生産過程の社会的結合,生産手段の規模と作用能力,そして自然環境によって,規定されている.同量の労働でも,例えば,豊作のときには八ブッシェルの小麦に表現され,凶作のときには四ブッシェルの小麦にしか表現されない.同量の労働でも,豊かな鉱山では貧しい鉱山でよりも多くの金属を産出する,等々.
(3)フランス語版

ある商品の価値量は,その生産に要する時間が一定であれば,当然ながら一定である.だがこの労働時間は,労働生産力に変動があれば,そのつど変動する.労働生産力は多種多様な事情によって規定されており,なかでも特に労働者の技能の平均度,科学の発展とその技術的応用の度合い,生産の社会的結合,生産手段の範囲と効率,そして純粋に自然条件によって,規定されている.同量の労働でも,例えば,豊作のときには八ブッシェルの小麦に表現され,凶作のときには四ブッシェルの小麦にしか表現されない.同量の労働でも,豊かな鉱山では貧しい鉱山でよりも多くの金属を供給する,等々.
(4)ドイツ語第三版

そのため,ある商品の価値の大きさは,その生産に要する労働時間が一定であれば,一定である.しかし,後者〔労働時間〕は,労働生産力に変動があれば,そのつど変動する.労働生産力は多種多様な事情によって規定されており,なかでも特に労働者の技能の平均度,科学とその技術的応用可能性との発展段階,生産過程の社会的結合,生産手段の規模と作用能力,そして自然環境によって,規定されている.同量の労働でも,例えば,豊作のときには八ブッシェルの小麦に表現され,凶作のときには四ブッシェルの小麦にしか表現されない.同量の労働でも,豊かな鉱山では貧しい鉱山でよりも多くの金属を産出する,等々.
ここでマルクスは「労働時間」という量に影響を与える〈労働生産力〉という質の諸要因について言及している.「ある商品の生産に要する労働時間」は,例えば8時間や9時間のような一定の量として計測される.だが,同じ8時間や9時間の労働であっても,労働の質によって生産性は変化する.この労働の質のことを〈労働生産力 Produktivkraft der Arbeit〉とマルクスは呼ぶ.〈労働生産力〉は「労働者の技能の平均度,科学とその技術的応用可能性との発展段階,生産過程の社会的結合,生産手段の規模と作用能力,そして自然環境」といった様々な複合的な諸要因によって変動する.〈労働生産力〉の良し悪しは,その内的要因としてはその国のいわば文明化の度合いに依存しているが,同時に,その外的要因としては.小麦や鉱山の例に見られるように気候や土壌などの〈自然環境 Naturverhältnisses〉に影響を受ける.
労働時間の不完全な表現としてのダイヤモンドと金
(1)ドイツ語初版

ダイヤモンドは地表に出ていることがまれだから,その発見には平均的に多くの労働時間が費やされる.したがって,ダイヤモンドはわずかな量で多くの労働を表わす.ジェーコブ(Jacob)は,金にその全価値が支払われたことがあるかどうかを疑っている.このことは,ダイヤモンドにはもっとよくあてはまる.エッシュヴェーゲ(Eschwege)によれば,1823年には,ブラジルのダイヤモンド鉱山の過去80年間の総産額は,ブラジルの砂糖またはコーヒーの農場の一年半分の平均生産物の価格にも達していなかったというが,じつはそれよりもずっと多くの労働を,したがってずっと多くの価値を表わしていたにもかかわらず,そうだったのである.もしも鉱山がもっと豊かだったならば,それだけ同じ労働量がより多くのダイヤモンドに表わされたであろうし,それだけダイヤモンドの価値は下がったであろう.もしほんのわずかの労働で石炭をダイヤモンドに変えることに成功するならば,ダイヤモンドの価値が瓦礫の価値よりも低く下がることもありうる.
(2)ドイツ語第二版

ダイヤモンドは地表に出ていることがまれだから,その発見には平均的に多くの労働時間が費やされる.したがって,ダイヤモンドはわずかな量で多くの労働を表わす.ジェーコブは,金にその全価値が支払われたことがあるかどうかを疑っている.このことは,ダイヤモンドにはもっとよくあてはまる.エッシュヴェーゲによれば,1823年には,ブラジルのダイヤモンド鉱山の過去80年間の総産額は,ブラジルの砂糖またはコーヒーの農場の一年半分の平均生産物の価格にも達していなかったというが,じつはそれよりもずっと多くの労働を,したがってずっと多くの価値を表わしていたにもかかわらず,そうだったのである.もしも鉱山がもっと豊かだったならば,それだけ同じ労働量がより多くのダイヤモンドに表わされたであろうし,それだけダイヤモンドの価値は下がったであろう.もしほんのわずかの労働で石炭をダイヤモンドに変えることに成功するならば,ダイヤモンドの価値が瓦礫の価値よりも低く下がることもありうる.
(3)フランス語版

(4)ドイツ語第三版

ダイヤモンドは地表に出ていることがまれだから,その発見には平均的に多くの労働時間が費やされる.したがって,ダイヤモンドはわずかな量で多くの労働を表わす.ジェーコブは,金にその全価値が支払われたことがあるかどうかを疑っている.このことは,ダイヤモンドにはもっとよくあてはまる.エッシュヴェーゲによれば,1823年には,ブラジルのダイヤモンド鉱山の過去80年間の総産額は,ブラジルの砂糖またはコーヒーの農場の一年半分の平均生産物の価格にも達していなかったというが,じつはそれよりもずっと多くの労働を,したがってずっと多くの価値を表わしていたにもかかわらず,そうだったのである.もしも鉱山がもっと豊かだったならば,それだけ同じ労働量がより多くのダイヤモンドに表わされたであろうし,それだけダイヤモンドの価値は下がったであろう.もしほんのわずかの労働で石炭をダイヤモンドに変えることに成功するならば,ダイヤモンドの価値が瓦礫の価値よりも低く下がることもありうる.
ここでマルクスは「エッシュヴェーゲによれば」と述べているものの,『資本論』ではその参照元を明示していない.実はこれがハーマン・メリヴェール(Herman Merivale, 1806-1874)の『植民地化と植民地に関する講義』(Lectures on Colonization and Colonies, 1841)からの抜粋であることが,いわゆる『要綱』(Grundrisse)のノートⅦ"Vermischtes"(MEW, Bd.42, S.724)から確認できる.

*エッシュヴェーゲ氏によれば,1823年にはまだおよそ2万人の黒人がそれに従事していた.彼が見積もるところでは,80年におよぶダイヤモンド採掘の全体量がブラジルの砂糖やコーヒーの18カ月分の産出量を超えることはほとんどないというのである!
砂糖やコーヒー農場と比較すると,ダイヤモンドと金とは,鉱山から採掘されるその量がごく僅かであり,それらの採掘に投じられてきた平均的労働時間が長期にわたり,さらにそれらの価格にはその労働時間が十分に反映されていないという点で共通している.とりわけダイヤモンドは,金と比較すると,採掘に投じられてきた労働時間がその価格により十分に反映されていないという.
以上のようにマルクスはダイヤモンドを例に挙げているが,その筆致は理論以上のものを示している.「金 Gold にその全価値が支払われたことがあるかどうか」という疑いが金以上に「ダイヤモンドにはもっとよくあてはまる」とマルクスが述べるとき,ここでマルクスが言わんとしていることは,ダイヤモンドには金以上にその価値がより不完全にしか表現されておらず,そこにはより大きなギャップが生じているということである.このギャップはいかにして生じたのだろうか?
一商品価値の大きさが,労働生産力と労働量に対してもつ相関関係
(1)ドイツ語初版

一般的に言えば,労働の生産力が大きければ大きいほど,一物品の生産に必要な労働時間はそれだけ小さく,その物品に結晶している労働量(Arbeitsmasse)はそれだけ小さく,その物品の価値はそれだけ小さい.逆に,労働の生産力が小さければ小さいほど,一物品の生産に必要な労働時間はそれだけ大きく,その物品の価値はそれだけ大きい.つまり,一商品の価値の大きさ(Werthgrösse)は,その商品に実現される労働の量(Quantum)に正比例し,その労働の生産力に反比例して変動するのである.
(2)ドイツ語第二版

一般的に言えば,労働の生産力が大きければ大きいほど,一物品の生産に必要な労働時間はそれだけ小さく,その物品に結晶している労働量はそれだけ小さく,その物品の価値はそれだけ小さい.逆に,労働の生産力が小さければ小さいほど,一物品の生産に必要な労働時間はそれだけ大きく,その物品の価値はそれだけ大きい.つまり,一商品の価値の大きさは,その商品に実現される労働の量に正比例し,その労働の生産力に反比例して変動するのである.
(3)フランス語版

一般的に,労働の生産力が大きければ大きいほど,一物品の生産に必要な〔労働〕時間はそれだけ短く,その物品に結晶している労働の量(masse)はそれだけ小さく,その物品の価値はそれだけ小さい.逆に,労働の生産力が小さければ小さいほど,一物品の生産に必要な労働時間はそれだけ大きく,その物品の価値はそれだけ大きい.つまり,一商品の価値の数量(quantité)は,その商品に実現される労働の量(quantum)に正比例し,その労働の生産力に反比例して変動するのである.
(4)ドイツ語第三版

一般的に言えば,労働の生産力が大きければ大きいほど,一物品の生産に必要な労働時間はそれだけ小さく,その物品に結晶している労働量はそれだけ小さく,その物品の価値はそれだけ小さい.逆に,労働の生産力が小さければ小さいほど,一物品の生産に必要な労働時間はそれだけ大きく,その物品の価値はそれだけ大きい.つまり,一商品の価値の大きさは,その商品に実現される労働の量に正比例し,その労働の生産力に反比例して変動するのである.
ここでは一商品価値の大きさに対する労働生産力と労働量の相関関係が「一般的な Allgemein」ものとして経済学の公式のように示されている.すなわち,労働生産力の増大(↑)は,平均的労働時間を縮小(↓)し,労働量を減少(↓)させる.このことは商品に結晶化する価値の減少(↓)として示される. これに対して,労働生産力の減少(↓)は,平均的労働時間を増大(↑)させ,労働量を増大(↑)させる.このことは商品に結晶化する価値の増大(↑)として示される.このことをマルクスは「一商品の価値の大きさは,その商品に実現される労働の量に正比例し,その労働の生産力に反比例して変動するのである」とまとめている.一商品価値の大きさは,労働量とは正の相関関係にあり,労働量生産力とは負の相関関係にある.
マルクスと労働価値説
以下のパラグラフは,前回のパラグラフの内容の要約と今後のパラグラフの方向性を示す中継地点のような役割を持っている.
(1)ドイツ語初版

我々は今や価値の実体を知っている.それは労働である.我々はその〔価値の〕大きさの尺度を知っている.それは労働時間である.その〔価値の〕形式,このことは価値に交換‐価値という印を押すのであるが,この形式を分析するのはまだこれからのことである.しかし,まずその前に,すでに見いだされた諸規定をもう少し詳しく展開しなければならない.
(2)フランス語版

我々は今や価値の実体を知っている.それは労働である.我々はその〔労働の〕量の尺度を知っている.それは労働の持続時間である.
(*ドイツ語第二版・第三版には該当のパラグラフが存在しない.)
ここでマルクスが「我々は今や価値の実体を知っている.それは労働である」と述べるとき,このことはマルクスが労働価値説の立場を取っていることを端的に示している.
「ある物」の分析
(1)ドイツ語初版


ある物は,交換価値でなくとも,使用価値でありうる.それは,人間にとってのその物の存在(Dasein)が,労働をつうじて媒介されていない場合である.たとえば空気や処女地や自然の草原や野生の樹木などがそれである.ある物は,商品ではなくても,有用であり人間労働の生産物であることがありうる.自分の生産物によって自分自身の欲望を満足させる人は,使用価値はつくるが,商品はつくらない.商品を生産するためには,彼は使用価値を生産するだけではなく,他人のための使用価値,〔すなわち〕社会的使用価値を生産しなければならない.最後に,どんな物も,使用対象であることなしには,価値ではありえない.物が無用であれば,それに含まれている労働もまた無用であり,労働のなかにはいらず,したがって価値をも形成しないのである.
(2)ドイツ語第二版

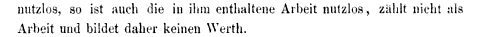
ある物は,価値ではなくても,使用価値であることがありうる.それは,人間にとってのその物の効用が労働によって媒介されていない場合である.たとえば空気や処女地や自然の草原や野生の樹木などがそれである.ある物は,商品ではなくても,有用であり人間労働の生産物であることがありうる.自分の生産物によって自分自身の欲望を満足させる人は,使用価値はつくるが,商品はつくらない.商品を生産するためには,彼は使用価値を生産するだけではなく,他人のための使用価値,社会的使用価値を生産しなければならない.最後に,どんな物も,使用対象であることなしには,価値ではありえない.物が無用であれば,それに含まれている労働も無用であり,労働のなかにはいらず,したがって価値をも形成しないのである.
(3)フランス語版


ある物は,価値ではなくても,使用価値であることがありうる.それには,その物が人間の労働によって生まれることなしに人間にとって有用であることだけで十分である.たとえば空気や自然の草原や処女地などがそうである.ある物は,商品ではなくても,有用であり人間労働の生産物であることがありうる.自分の生産物によって自分自身の欲望を満足させる人は,個人的な使用価値を造るだけである.商品を生産するためには,彼は使用価値を生産するだけではなく,他人のための使用価値,社会的使用価値を生産しなければならない.最後に,どんな物も,それが有用なものでない限り,価値ではありえない.物が無用であれば,それに含まれている労働も無駄に費やされ,したがって価値を造らない.
(4)ドイツ語第三版


ある物は,価値ではなくても,使用価値であることがありうる.それは,人間にとってのその物の効用が労働によって媒介されていない場合である.たとえば空気や処女地や自然の草原や野生の樹木などがそれである.ある物は,商品ではなくても,有用であり人間労働の生産物であることがありうる.自分の生産物によって自分自身の欲望を満足させる人は,使用価値はつくるが,商品はつくらない.商品を生産するためには,彼は使用価値を生産するだけではなく,他人のための使用価値,社会的使用価値を生産しなければならない.最後に,どんな物も,使用対象であることなしには,価値ではありえない.物が無用であれば,それに含まれている労働も無用であり,労働のなかにはいらず,したがって価値をも形成しないのである.
ここでマルクスは,「ある物」の「存在 Dasein」を主に三つの側面から考察している.
〈交換価値〉或いは「労働による媒介」の欠如:《ある物は,(交換)価値ではなくとも,使用価値であることがありうる》.なぜなら,その物が持つ「人間にとっての効用 Nutzen für den Menschen」がその物を「使用価値」たらしめるのであるが,ある物が「交換価値」を持つのはその物が「労働によって媒介されて durch Arbeit vermittelt」いる場合に限定されるからである.したがって,ある物にまだ労働が投下されておらず,なおかつ,その物が自然のあり方のままで使用価値を持っている場合には,《ある物は(交換)価値であることなしに使用価値であることが可能である》.この例としてマルクスは「空気や処女地や自然の草原や野生の樹木など」を挙げている.
〈商品〉の欠如:《ある物は,商品ではなくとも,有用であり人間労働の生産物であることがありうる》.人間的労働には,大きく分けて二種類ある.一つは〈自分自身の欲望を満足させる〉という意味で「有用な」人間的労働であり,もう一つは〈他者の欲望を満足させる〉という意味で「有用な」人間的労働である.その物が〈商品〉として存在するためには,その物が「他人のための使用価値,すなわち社会的使用価値」を備えている必要がある,とマルクスはいう.つまり,この「他人のための使用価値,すなわち社会的使用価値」を形成するのは,確かに「労働」ではあるが,もっというとそれは「社会的分業」としての人間的労働に他ならない.
〈使用価値〉の欠如:《どんな物も,使用対象であることなしには,価値ではありえない》.労働によって生まれた産物が「無用 nutzlose」である場合がそうである.われわれが「価値のないガラクタ」と呼ぶものが凡そこれに当てはまるであろう.
以上三点でもってマルクスは「交換価値」と「商品」と「使用価値」とがそれぞれ厳密には異なる概念であることを示している。それを「商品」として考察するならば,一つには「使用価値」から見た「商品」と,もう一つには「交換価値」から見た「商品」という二面性を持っている.だが,それを「ある物」として考察してみれば,それは「交換価値」と「商品」と「使用価値」という三つの側面から分析できることがわかる.『資本論』第一章第一節を通じて示されたのは,まさにこの点である.
文献
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
