
ヴィーコ『新しい学』試論③
新しい批判術

さらに,ここで触れておくなら,この著作では,これまで欠如していたあるひとつの新しい批判術を用いて同じ異教諸国民の創建者たちにかんする真理の探究に入ることによって(これまで批判がかかわってきた著作家たちがそれらの諸国民の内部に登場するまでには〔それらの諸国民が創建されてから〕優に千年以上が経過していたにちがいないのである),ここに哲学は文献学*12,すなわち,諸民族の言語,習俗,平時および戦時における事蹟についての歴史のすべてなど,人間の選択意志に依存することがらすべてにかんする学問の検査に乗りだす(なにしろ,それの提供する原因は残念ながら曖昧ではっきりとしておらず,また結果も無限に多様であるため,これまでそれについて推理することには,わたしたちはほとんど恐怖を抱いてきたのだった).
ヴィーコは『学問の方法』でクリティカとトピカという二つの方法について言及している.キケロの『トピカ』以来,クリティカは真偽についての判断の術(ars iudicandi)とされ,トピカは論拠についての発見の術(ars inveniendi)とされてきた*13.時代的には若者はポール=ロワイヤル論理学を優先的に学んでいたが,このような論理学やデカルトの方法をヴィーコは当時のクリティカとして位置付けている.こうしたクリティカ中心の時代にあって,ヴィーコはキケロに倣い,トピカがクリティカよりも先行することを説いているのである.
以上を踏まえて先ほどのパラグラフでは,『新しい学』の中で「新しい批判術」を用いることが宣言されている.この批判術は,一体何が,どのような点で「新しい」のであろうか.これがただの「批判」ではなく,〈術 ars 〉としての「批判」であるからには,そこにはいかにしてキケロ以来の伝統が受け継がれ,そして発展させられているのであろうか.
この批判術の〈新しさ〉は,ポール=ロワイヤル論理学やデカルト主義のようないわば〈推論の精確さ〉だけにこだわったものではないという含意があるのではないだろうか.この「新しい批判術」は,「人間の選択意志に依存することがらすべてにかんする学説を検討すること」だと述べられている.「人間の選択意志」とは一体何であろうか.この点,ヴィーコは次のように述べている.

Ⅺ 人間の選択意志は,その自然本性においてはきわめて不確実なものであるが,人間として生きていくにあたって必要または有益なことがらについての,人々の共通感覚によって確実なものにされ,限定をあたえられる.そして,この人間として生きていくにあたって必要または有益なことがらこそは,万民の自然法の二つの源泉なのである.
「人間の選択意志」(あるいは「恣意」)は,いわゆる人間の自由意志に関わるものであり,エピクロスの〈逸れ〉の概念のように決定論的な発想から抜け出るものである.したがってそれはきわめて曖昧であり,ここで「不確実」と呼ばれる所以である.しかし,ヴィーコはこの「人間の選択意志」は「共通感覚」(あるいは常識,コモンセンス)によって確固として規定されているという.というのも,人間は生物として生きていくのに必要なもの,有用なものを,一定程度の共通認識として持っているからである.そして言語・習俗・歴史といったものが「人間の選択意志」に依存しているということは,これら言語・習俗・歴史などの学説は、「人間の選択意志」を規定しているところの「共通感覚」(常識、コモンセンス)を基盤としており,この「共通感覚」(常識,コモンセンス)によって(「人間の選択意志」を介して)間接的に規定されているということになる.そこでこれらの学説の基盤となっている「共通感覚」(常識,コモンセンス)こそが問題となる.

Ⅻ 共通感覚とは,ある階級全体,ある都市民全体,ある国民全体,あるいは人類全体によって共通に感覚されている,なんらの反省をもともなっていない判断 giudizio のことである.
この公理は,つぎの定義とともに,諸国民の創建者にかんする新しい批判術を提供するだろう.それらの諸国民のなかにこれまで批判が携わってきた著作家たちが出現するまでには,優に千年以上の歳月が経過していたにちがいないのである.
「共通感覚」 (常識,コモンセンス)における〈共通〉性とは「ある階級全体,ある都市民全体,ある国民全体,あるいは人類全体」における〈共通〉性であり,またその〈感覚〉性は,それが感覚であるがゆえに理性を介しない直截的で「無反省的な」ものである.
しかもこの「共通感覚」が件の「新しい批判術」を提供すると述べられている点に関しては,わたしたちはキケロが彼の『トピカ』においてトピカとクリティカをそれぞれ〈発見の術〉と〈判断の術〉として区別していたことを想起する必要がある.これこそまさに「新しい批判術」を提供する「共通感覚」が「判断」であるとされている所以である.
ヴィーコとマルクス
こうした「批判」の方法は様々なトピックの書物を分野横断的に読解し,「批判 Kritik」として統合していくマルクスの方法に受け継がれていると言えるのではなだろうか.かつて柄谷行人は『トランスクリティーク』(柄谷2010)でマルクスからカントへ遡って読み込む必要性を感じたと述べていたように記憶しているが,マルクスの「批判」はカント以前のヴィーコの「新しい批判術」にまで遡る必要があるのではないか.
こうした読み方は,当時「死せる犬」と扱われていたヘーゲルの弟子だと自ら述べた序文を読んだとしてもそうはならないはずである.しかし,ヘーゲルをいくら読みといたとしてもマルクスの「批判」の立脚点は,ヘーゲルには見出すことができない.ヘーゲルとは別の思想家を経由する必要がある.もちろん若きマルクスがフォイエルバッハの人間主義に影響を受けており,そのフォイエルバッハがヘーゲル哲学「批判」をマルクスのヘーゲル法哲学「批判」よりも先に著していることは重々承知している.しかしマルクスのエスプリに富んだ「批判」の仕方*14は,同時代のいわゆるヘーゲル左派(Hegelsche Linke)の「批判」の仕方とは明らかに違っている.むしろここで注目したいのは,思想史における「批判」のもっと大きな流れのことである.
例えば,フォイエルバッハのヘーゲル哲学「批判」の方法は,逆さまにされていた主語と述語を転倒させるというものであった.しかしこれはその内容とは裏腹に形式論理的な批判に過ぎず,素材を抜きにした単なるクリティカに過ぎなかった.これに対してマルクスはフォイエルバッハのようなクリティカだけでは空疎な批判に陥ることに気付き,『独仏年誌』(Deutsch-Französische Jahrbücher, 1844)以降,古典派経済学や人間社会に関する事柄を分野横断的にその生涯にわたって学び,現実的な問題の場所を発見すること,すなわちトピカを重視した(マルクスがエンゲルスの『状態』を評価するのもこの観点からであろう).こうした点が,マルクスと他のヘーゲル左派との大きな分岐点になったのではないかと思われる.
マルクスがヴィーコに言及しているのは,『資本論』(Das Kapital, 1863)の一箇所とラサール宛手紙(1862. 4. 28)だけであるという(木前2008:8).しかし,もしマルクスの「批判」の源流がこのようにヴィーコに見いだされるとしたら,なんとも面白くはないだろうか.
「質料」と「形式」

そしてそこに諸国民すべての歴史が時間の中を経過するさいの根底に存在している永遠の理念的な歴史の素描を発見することによって,それを知識の形式にまで連れ戻す.
ここで「知識」と訳されている原語は"Scienza"であり,これは本書のタイトル『新しい学の諸原理』における「学」のことである.
なお「形式 forma」は,アリストテレス的な用法で、「質料」と関わりを持つ.『新しい学』第1巻「原理の確立」第2部「要素について」の冒頭では次のように述べられている.

したがって,これまで年表の上に配列してきた質料〔materie〕に形式〔forma〕をあたえるために,わたしたちはいまここに,つぎのような哲学上ならびに文献学上の公理と,若干の合理的で適当とおもわれる要請とを,いくつかの明確になった定義とともに提示しておく.これらは,あたかも生物の体内を血液がめぐるように,この学の内部を流れめぐり,この学が諸国民の共通の自然本性について推理することがらの全体にわたって,この学に生命をあたえてくれるはずのものなのである.
ここで「形式 forma」と「質料 materie」が強調されているように,これらは形而上学の用語として使用されていることがわかる.『新しい学』第1巻第2部以降で「学の形式」を与えられるところの「質料」については,第1巻第1部「年表への注記——ここにおいて質料〔素材〕の配列がなされる——」で叙述されるという構造になっている.
ここでヴィーコは「公理」のことを"Assiomi, o Degnità"というように言い換えているが,Verneによれば,この箇所は『新しい学』で"assioma"を"degnita"と等置した唯一の箇所だそうである*15.Verneは,ユークリッドの『原論』,ニュートンの『プリンキピア』,そしてアリストテレスの『分析論後書』に言及した後,次のように述べている.
ヴィーコはみずからの公理を哲学的かつ文献学的なものの両方として描いているが,しかしヴィーコが,『新しい学』は幾何学的な思考法に基づいていると主張しているにもかかわらず,その公理は決して自明なものでもなければ,演繹されたものでもないのである.ヴィーコの公理は,その原理としては最も必要で適合的なものとして考えられ,そして諸国民の共通の自然本性を把握するのに最も偉大な価値を有している.ヴィーコの公理は「トピカ」(τόποι)すなわちコモンプレイスという地位を有しており,そこから『新しい学』の諸々の特殊性を整序する原理が引き出されるのである.
「幾何学」と〈製作者〉の思想
たしかに「公理」や「定義」といった用語を見ると,ユークリッド幾何学のような原理原則が想起されよう.実際,ヴィーコは『新しい学』第1巻第4部「方法について」で「永遠の理念的な歴史」とともに「幾何学」について次のように言及している.

それゆえ,この学は同時に,諸国民すべての歴史がかれらの勃興,前進,停止,衰退,終焉にわたって時間の中を経過していくさいの根底に存在しているひとつの永遠の理念的な歴史を描きだすことになる.それどころか,わたしたちはさらに一歩を進めて断言したいのだが,この学を省察する者がこの永遠の理念的な歴史を自分自身に語るのは,この諸国民の世界はたしかに人間たちによって作られてきたのであり(これはここでさきに立てられた疑いえない第一原理である.それゆえ,それの〔生成の〕様式はわたしたちの人間の知性自体の諸様態の内部に見いだされるべきであるので,その〈なければならなかったのであり,ならないのであり,ならないであろう〉という証明のなかで,彼自身がそれを自分の前に作りだしてみせるかぎりにおいてなのだ.なぜなら,事物を作る者自身がそれらについて語るとき,そのときほど話が確実なことはありえないからである.こうして,幾何学がそれの諸要素にもとづいて大きさの世界を構成したり観照したりするとき,それはその世界をみずから自分の前に作りだしているわけであるが,この学もまさしく幾何学と同様の行き方をすることになる.ただし,人間たちの事蹟にかんするもろもろの秩序には点,線,面,図形以上に実在性があるだけに,そこには,それだけいっそう多くの実在性がともなっている.そして,このこと自体が,そのような証明は一種神的なものであって,読者よ,あなたに神的な喜悦をもたらすにちがいないということの論拠になる.それというのも,神においては認識することと製作することとは同一のことがらであるからである.
ヴィーコが「永遠の理念的な歴史」を我々人間が語りうると考えるのは,それを作ってきたのが我々人間だからである.ここで人間はその歴史に関しては造物主たる神と同じ地位へと引き上げられている.ヴィーコは製作者の技法を「幾何学」*16になぞらえているが,〈製作者〉だけが真の意味で(いわば「神的に」)認識しているというのはヴィーコの思想としてよく知られているものであり,これを仮に〈製作者〉の思想とでも呼んでおこう.ヴィーコのこのような〈製作者〉の思想は,マルクスやサイードといった偉大な思想家に大きな影響を与えた.〈製作者〉の思想とは,それを造りし者だけがそれを最もよく理解している,というものである.ただし,ヴィーコは幾何学と人間に関する事柄との違いについても述べており,その違いは「実在性(リアリティ)」の多様性にあると述べている.
〈新しい学〉における〈権威の哲学〉の側面
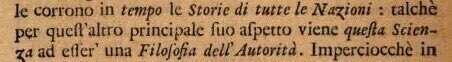
そうであるから,このいまひとつの主要な面からすれば,この学は権威の哲学であることになる.
「この学」つまりヴィーコの〈新しい学〉は,いくつかの主要な側面から考察されており,それらの諸側面の一つが「権威の哲学」である.ヴィーコの〈新しい学〉の主要な諸側面については,第2巻「詩的知恵」第1部「詩的形而上学」第2章「この学の主要な諸側面についての系」で次のように整理されている.
1. 神の摂理についての悟性的に推理された国家神学
2. 権威の哲学
3. 人間的観念の歴史
4. 哲学的批判
5. 永遠の理念的な歴史
6. 万民の自然法の体系
7. 世界史の始まり
先の引用箇所で最も関わりが深いと思われるのは,「詩的形而上学」の次のパラグラフである.

この権威の哲学が神の摂理についての悟性的に推理された国家神学のあとに続いてやってくるのは,神の摂理についての悟性的に推理された国家神学の提供する神学的証拠を受けて,権威の哲学はみずからの提供する哲学的証拠によって文献学的証拠を明晰判明なものにし(この三種類の証拠はすべてすでに「方法」において枚挙しておいたところである),諸国民の不明瞭きわまりない古代のことどもについて,「公理」において述べておいたように,その自然本性からしてきわめて不確実なものである人間の選択意志を確実なものへと引き戻すからである.これは文献学を知識の形式に引き戻すというに等しい.
ここで〈新しい学〉の主要な諸側面の特徴の一つは,不確実なものを確実なものへと「還元する reduce」点にある.古代のことどもが不確実で曖昧であるのは,あくまで近代諸国民のわれわれにとってのことであり,古代人の常識からすればそれは確実なものであったはずである.したがって,〈新しい学〉とは,今となっては不確実になってしまったものを,かつての確実なものへと「引き戻す reduce」というのである.
物語と論理学

それというのも,ここで見いだし直される詩のいまひとつ別の新たな諸原理に続いてやってくる,同じくここで発見される神話学のいまひとつ別の新たな諸原理によって,物語〔神話伝説〕というのはギリシアの最も古い諸氏族の習俗の真実にして厳格な歴史であったこと,そして,第一には,神々の物語はなおも最も粗野な状態にあった異教世界の人間たちが人類にとって必要または有用なことどものすべてを神であると信じていた時代の歴史であったことが論証されるからである.なお,そのような詩の創作者は最初の諸民族自身であったのであって,最初の諸民族はすべて神学詩人たちからなっていたことが見いだされるのである.疑いもなく神々の物語によって異教諸国民を創建した当の者たちであると伝承がわたしたちに語っている,例の神学詩人たちからである.
この箇所を読解するにあたって,「物語」という語に注目してみよう.ヴィーコは本書第2巻「詩的知恵」第2部「詩的論理学」第1章「詩的論理学について」の箇所で,「物語」という言葉の語源的解明を以下のように試みている.

論理学〔Logica〕という言い方はギリシア語のロゴス〔λόγος〕という語からやってきたものである.これは最初,そして本来は物語を意味していた.それがイタリア語に移し換えられてファヴェッラ〔言葉〕となったのだった.また,物語はギリシア語ではミュートス〔μῦθος〕とも言われた。そして、このミュートスからラテン語のムートゥス〔無言の/沈黙した〕という語は出てきている.言葉は,人々がまだ無言であった時代に,まずはストラボンが黄金のくだりで音声語ないしは分節語以前に存在したと述べているメンタルな言語として生まれたのだった.したがって、ロゴス〔λόγος〕は観念と話し言葉の双方を指しているのである.
「ロゴス λόγος」と「ミュートス μῦθος」とは「物語」を意味するものとして対比的に用いられていた.ヴィーコが「ロゴス λόγος は観念と話し言葉の双方を指している」と述べたとき,ヴィーコは「ロゴス」の相異なる二重の意味を強く認識していたといえる.
ヘシオドス『神統記』

また,ここでは,この新しい批判術の諸原理を用いて,人間的な必要または利益の,異教世界の最初の人間たちによって気づかれたどのような特定の時点および特殊な機会に,かれらは,かれら自身がみずから作り出して信じこむにいたった恐るべき宗教をもって,まずはどの神々を,ついではどの神々を想像していったのかが,省察される.そのような自然神統記,すなわち,最初の人間たちの頭の中で自然的に作られていった神々の系譜は,神々の詩的歴史についての悟性的に推理された年代学をあたえてくれるのである.
単語
p.6. l.33.【接続詞】E「…と、そして」
p.6. l.33.【副詞】quivi「そこで」
p.6. l.33.【前置詞】co'「〜と共に」: 前置詞conの短縮形
p.6. l.34.【名詞】Principj「原理原則」: 男性名詞principioの複数形
p.6. l.34.【限定詞】questa「その」: 限定詞questoの女性単数
p.6. l.34.【形容詞】Nuov'「新しい」: 形容詞nuovoの女性形nuovaの短縮形
p.6. l.34.【名詞】Arte「芸術」: 女性名詞arte
p.6. l.34.【形容詞】Critica「批判」: 形容詞criticoの女性形
ここで触れられている内容は,訳者(上村忠男)が示しているように,ちょうど本書第一部「年表への注記」の以下の箇所と対応している.

この時代についておもしろいことをひとつ,神話伝説はわたしたちに語っている.神々は地上で人間たちと交わっていたというのだ.わたしたちもまた,年代学に確実性をあたえるために,この著作において,あるひとつの自然神統記,すなわち,人間的な必要または利益にかかわる一定の機会がおとずれたとき,それらを自分たちに恵みあたえられた援助ないし恩恵であると感じとって,ギリシア人の想像力のなかで自然に作られていった神々の誕生の系譜を省察するであろう(当時は,世界がいまだ幼児期にあって,もろもろの恐るべき宗教に威圧されていた.こうして,人間たちが見たり,想像したりしたもの,あるいはまたかれら自身が作り出したものまでも含めて,これらのいっさいをかれらは神々であると受けとっていたのだった).そして,いわゆる〈大〉氏族の有名な十二の神々,あるいは家族の時代に人間たちによって祭られていた神々について,詩的歴史についての悟性的に推理された年代学を用いて十二の小時期を設けることによって,神々の時代が九百年間続いたことが確定される.こうして世俗の世界史に起源があたえられることになるのである.
ヴィーコがここで「自然神統記 Teogonia Naturale」と呼んでいるものは,これが「ギリシア人の想像力のなかで自然に作られていった神々の誕生の系譜 Generazione degli Dei, fatta naturalmente nelle fantasie de'Greci」である点を考慮すると,おそらく紀元前700年頃の古代ギリシアの詩人ヘシオドス(Ἡσίοδος)の作品とされている叙事詩『神統記』(θεογονία)のことを指していると思われる.「テオゴニアー」という言葉は本来「神々の誕生の系譜」の意である.したがってまたヴィーコが「十二の神々 dodici Dei」と呼んでいるのも,ギリシア神話のいわゆるオリュンポス十二神(Δωδεκάθεον)のことであろうと思われる.
ホメロスの詩とその文体

こうしてまた,第二には,英雄物語 Favole Eroiche も,すべての諸国民においてそれらの国民が野蛮状態にあった時代に花開いていたのが見られる英雄たち Eroi とかれらの英雄的習俗の真実の歴史 Storie vere なのであった.だから,ホメロスの二つの詩はなおも野蛮状態にあったギリシアの諸氏族の自然法の二大宝庫であることが見いだされるのである.なお,その時代はギリシア史の父 Padre della Greca Storia と称されるヘロドトス Erodoto の時代までギリシア人のあいだで続いていたことが,この著作 Opera において確定される.じっさいにも,ヘロドトスの著作はいずれも大部分が物語で埋まっており,文体 Stile もホメロス的な Omerico ところを多分にとどめている.そして,かれのあとに続いてやってきて,詩的な語法と通俗的な語法との中間を行くような語法を使っている歴史家 Storici たちもすべて,なおもこの勢力圏内にとどまっていたのであった.
「ホメロスの二つの詩」というのは『イリアス』と『オデュッセイア』のことであろう.なぜこれらが「ギリシア諸氏族の自然法の二大宝庫」なのか.その理由は,まさにホメロスの詩が伝承された最も古い文学作品であったからではないだろうか.
今回注目したいのは,ヴィーコが「文体 Stile」に言及している点である.まず「文体」が「ホメロス的」だというのは,どういうことを意味するだろうか.ホメロスの詩が文字として書き起こされたのは紀元前6世紀頃であり,その作品の成立した紀元前8世紀頃よりもずっと後になってからである.それまでの間,ホメロスの詩は朗読されて伝承されてきたのであるから,そこには音楽的な抑揚があったと考えられる.その点を考慮すると,ヴィーコが「詩的な」フレーズと「通俗的な」フレーズという区別をしたことの意味も理解できるだろう.つまりヴィーコは,ホメロスの詩にみられるような音楽的な抑揚のある文体のことを「詩的な」フレーズと呼び,後にそうした音楽的な抑揚の失われた散文のような文体のことを「通俗的な」フレーズと呼んで区別したのではないだろうか.年代的には「詩的な」フレーズが「通俗的な」フレーズに先行していたのであり,「詩的な」フレーズが失われてしまうまでは,ホメロスの「勢力圏内にとどまっていた」のである.
単語
p.7. l.7.【名詞】favole: 女性名詞favola「寓話、物語」の複数形
p.7. l.7.【形容詞】eroiche: 形容詞eroico「英雄の」の女性複数形
p.7. l.7.【動詞】furono: 動詞essere「〜である」の直接法遠過去/三人称複数
p.7. l.8.【名詞】storie: 女性名詞storia「歴史、物語」の複数形
p.7. l.8.【形容詞】vere: 形容詞vero「真実の」の女性複数形
p.7. l.8.【縮約】degli: 前置詞diと冠詞gliの縮約(contraction)
p.7. l.8.【名詞】 eroi: 男性名詞eroe「英雄たち」の複数形
p.7. l.8.【限定詞】lor: 所有限定詞loro「彼らの」の語尾音消失(apocope)形
p.7. l.8.【形容詞】eroici: 形容詞eroico「英雄的」の男性複数形
p.7. l.8.【名詞】costumi: 男性名詞costume「習慣、慣習」の複数形
(つづく)
註
*12: 「哲学 Filosofia」と「文献学 Filologia」については次の箇所も参照のこと.「哲学は道理〔理性〕を観照し,そこから真実なるものについての知識が生まれる.文献学は人間の選択意志の所産である権威を観察し,そこから確実なるものについての意識が生まれる./この公理は,後半部分にかんして,文献学者とは諸言語および内にあっての習俗や法律と外にあっての戦争,講和,同盟,旅行,通商などの双方を含めた諸国民の事蹟の認識に携わっている文法家,歴史家,批評家の全体のことである,と定義する.」(Vico1744: 75–76,上村訳(上)165頁).
*13: キケロは『トピカ』で次のように述べている.「およそ議論のための厳密な方法は二つの部門,つまり一は発見(invenire)の部門,他は判断(iudicare)の部門からなり,私が思うに,アリストテレスがこの両部門の創始者であった.ところがストア派は後者の部門だけに関心を寄せてきたにすぎない.実際,ストア派は,彼らが弁証術(dialektike)と呼ぶ学において,判断の方法だけに専心してきたのである.しかし,トピカ(topica)と呼ばれる発見の術の方が,実用に役立つだけでなく,自然の秩序において先行するにもかかわらず,彼らはこれをまったく無視してきたのである.」(キケロ2010:21).
*14: フォイエルバッハに多大な影響を受けた若きマルクスの「批判」とその「方法」については荒川2013をみよ.
*15: "Vico uses assioma only once in the New Science, and he equates it with degnità."(Venere2015: 254).
*16: ヴィーコは『自伝』の中で幾何学学習の効用について語っている(ヴィーコ2012).
文献
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
