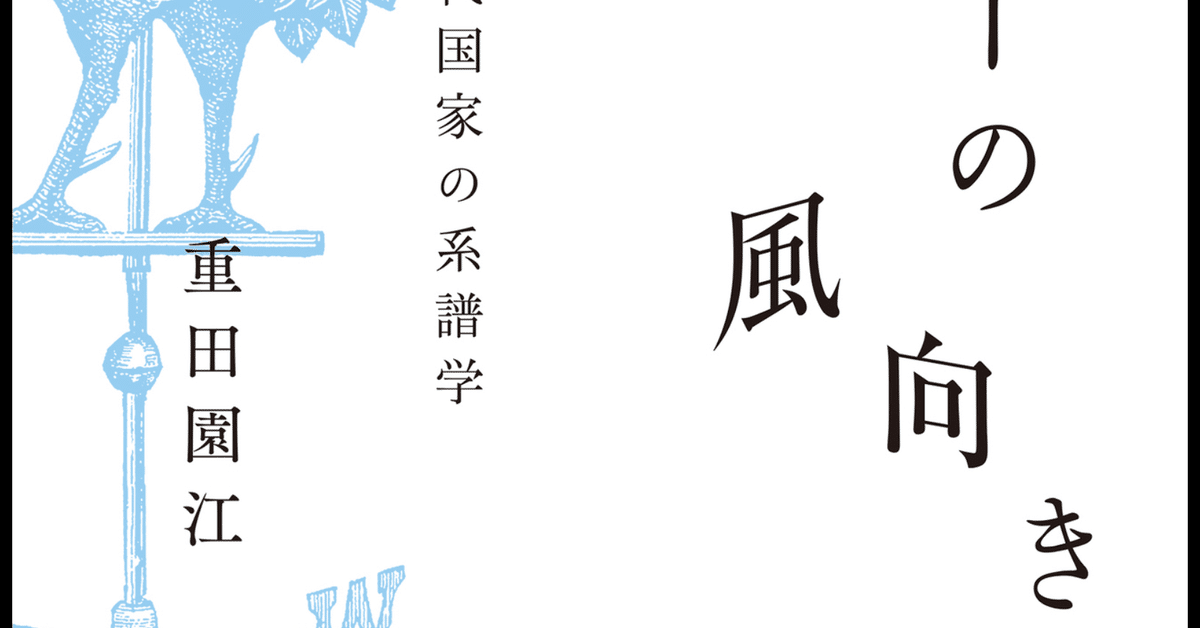
早稲田大学 教育学部 2022年度 国語入試問題を解く——重田園江先生の問題提起を受けて
はじめに
フーコーをはじめとする人文社会科学研究で知られている重田園江(1968-)先生が、自身の著作『フーコーの風向き』(青土社、2020年)を取り上げた早稲田大学教育学部の入試問題に疑問を呈している。せっかくなので私も問題を解いてみよう。
問一はどういう設問なのか
まずは問一を読んでみる。
問一 傍線部1「個と全体の近代特有の結合」とあるが、どういうことを指しているか。(略)
イ 国家と個人の利害の結びつきを前提とすること。
ロ 国家が個人も幸福になるように理論を構築すること。
ハ 国家の力を増大させるために個人の幸福を実現すること。
ニ イデオロギーよりも具体的な政策として国家が個人を管理すること。
ホ 国家の力と個人の幸福とが同時に増大または減少するようにすること。
(「早稲田大学 教育学部 2022年度 入試問題」読売新聞社)
真面目に考えると、いずれの選択肢も誤答として退けるのが難しいように思われる。官房学やポリツァイの問題を多少でも齧ったことのある生徒にとっては、なおさら難しいのではないか。重田先生は、この問一に対する早稲田大学の解答に、次のような疑問を投げかけている。
三予備校は当初すべて「ホ」を正解とした。大学の解答は「イ」である。イは「国家と個人の利害を結びつけること」(「前提」ということばがない場合)であれば、正解の一つである。しかし、いったいなぜ「ホ」が正解でないかは不明である。
傍線部直前の段落に、「全体と個の利害を結びつけ、国家の力と個人の幸福とが相関して増大したり減少したりするようなしかたで両者を同時に生み出す」と書かれている。国家と個人の利害を結びつけることの言い換えが、この文章の後半部分、つまり選択肢「ホ」である。国語の選択問題に独特の流儀に倣って、正答の適切さに度合いがあるとするなら、正答は「ホ」となる。そして、「イ」にある「前提」という単語は課題文には書かれていない。著者の意図としても「、」で結ばれる前半と後半(「全体と個の利害を結びつけ」と「国家の力と個人の幸福とが相関して増大したり減少したりするようなしかたで両者を同時に生み出す」)は、前提と結果ではなく並列あるいは言い換えによる説明である。
(重田園江「入試国語選択問題の「正解」について――早稲田大学教育学部の説明責任(OPINION)」SYNODOS、2022.03.14)
私がこの問一を解いたところ、さしあたり「ホ」が正解ではないかと考えた。時間制限の中で問題を解くとすれば、傍線部1からそれほど離れていない、しかも本文中の文言とほとんど変わらぬ「ホ」を選ぶのが無難である。しかも全体の時間配分を考慮すると、他の選択肢を吟味する時間が勿体ない。だが、早稲田大学側の解答では、「イ」が正解である。どうしてだろうか。
問一の文章をもう一度確認してみよう。
問一 傍線部1「個と全体の近代特有の結合」とあるが、〔これは〕どういうことを指しているか。
問一の問題文を正確に言い直すならば、傍線部1「個と全体の近代特有の結合」とは「どういうことを指しているか」と問うことになろう。つまり、その文言が指している事柄(Sache)が問題であり、設問としては、指示される事柄がテクストの中に存在していなければならない。そしてこの正解は、早稲田大学によれば、「国家と個人の利害の結びつきを前提とすること」(イ)であって、「国家の力と個人の幸福とが同時に増大または減少するようにすること」(ホ)ではないとされる。おそらく「ホ」が誤答なのは、選択肢から「相関して」という文言が消えていることによって、「国家の力と個人の幸福とが【両者のあいだに相関はないけれども、それぞれが独立した変数として】同時に増大または減少するようにすること」として選択肢の一文を理解せねばならないからではないか。だとすれば、なんという引っかけ問題であろうか。
選択肢イの「前提」とは何か
「イ」について言うと、重田先生の指摘するように、たしかに本文中には「前提」という語は書かれていない。問一が設問として成立するためには、この「前提」と換言可能な語が本文中にあるはずである。では、その語とは一体何であろうか。
私見では、その「前提」、より正確には「国家と個人の利害の結びつきを前提とすること」(イ)に該当する——と出題者が頭の中で考えている——と考えられるのが、「全体と個の利害を結びつけ、……両者〔すなわち国家の力と個人の幸福と〕を同時に生み出す、知と権力の枠組み」あるいは「〔国家と個人というそれぞれの事柄の〕問題設定とを不可分に結びつけ、全体と個を同時に対象として構成する知のあり方」であり、これは具体的には「国家理性論」であるとされる。しかし、こうした「知のあり方」を「前提とすること」と言い換えるのは、どう考えても乱暴すぎる整理である。
……むしろここでフーコーが問題としているのは、全体と個の利害を結びつけ、国家の力と個人の幸福とが相関して増大したり減少したりするようなしかたで両者を同時に生み出す、知と権力の枠組みである。
……こうした個と全体の近代特有の結合を最初に構想した政治理論として、国家理性論が位置づけられるのである。ここで国家理性論は、国家とは何か、その繁栄と秩序維持のために必要な事柄とは何かという問題設定と、個人とは何か、その幸福と安定した生のために必要な事柄とは何かという問題設定とを不可分に結びつけ、その意味で全体と個を同時に対象として構成する知のあり方と見なされている。
(重田園江『フーコーの風向き』青土社、2020年、強調引用者)
選択肢ニは誤答なのか
ここで傍線部1のパラグラフ全体を再度確認したい。
たとえば、健康で衛生的な生活を送ることは、個人にとって幸福であると同時に、公衆衛生や都市の秩序形成に役立ち、また国家の経済的生産性を高めることにも寄与する。そしてこれが単にイデオロギーとして唱えられるのではなく、公衆衛生のための医療の展開や都市計画の徹底など、さまざまな装置を用いた身体への働きかけを伴うことで、個人と国家の健康管理を実現してゆく。こうした個と全体の近代特有の結合を最初に構想した政治理論として、国家理性論が位置づけられるのである。ここで国家理性論は、国家とは何か、その繁栄と秩序維持のために必要な事柄とは何かという問題設定と、個人とは何か、その幸福と安定した生のために必要な事柄とは何かという問題設定とを不可分に結びつけ、その意味で全体と個を同時に対象として構成する知のあり方と見なされている。
(重田園江『フーコーの風向き』青土社、2020年)
傍線部1が属する一文には「こうした個と全体の近代特有の結合を最初に構想した政治理論として、国家理性論が位置づけられるのである」と書かれている。「こうした」とあるから、テクスト上で直前に指示されているものがあるのは確かであり、しかもそれを「最初に構想した」のは「国家理性論」であるとされる。したがってそれは、「国家理性論」に特徴的なものであって、後続する政治理論においては二番煎じになるようなものである。
ここで「こうした個と全体の近代特有の結合」の一例として挙げられているのが、「個人と国家の健康管理」であり、いわゆるポリツァイの一環である。これがいわゆるポリツァイのあり方を指しているのだということに思い至るならば、選択肢ニ「イデオロギーよりも具体的な政策として国家が個人を管理すること」は、全くの誤答とは言い切れないのではないか。実際、ポリツァイは単なる「イデオロギー」ではなく「具体的な政策」であり、「国家が個人を管理する」(テクストでは「さまざまな装置を用いた身体への働きかけを伴う」と述べられている箇所が、国家から個人への管理に該当するであろう)というのも一見すると間違いとは思われない。なおかつその内容が「こうした個と全体の近代特有の結合」と同一のパラグラフの中で述べられているのであるから、距離も近い。だが、選択肢ニは三予備校や重田先生自身も言及すらされず、検討に値しないという具合である。私の頭が悪いだけだろうか。
問二に正答はあるか
せっかくなので問二も読んでみよう。
問二 傍線部2「社会に固有の「自然性」によって構成される人口という対象の発見あるいは発明が、生政治を可能にしている」とあるが、それはなぜか。
イ 生政治は出生率や死亡率などの人口構成に関わる数値と不可分の関係にあるが、それは遺伝学や優生学の影響を受けるので、容易に個人のレベルの問題に還元され得ることによって可能となっているから。
ロ 生政治の目的は国家の力の元になる公衆衛生の向上にあったので、人々の生活に即した実態としての人口が重要で、それを数字で表すことができる人口統計学の発明で人々の生活に即した国家権力を行使できるから。
ハ 生政治とは人間が生きることそれ自体に関する政治なので、単なる個人の集合としての全体の数字ではなく、人間が生きることに関わる様々な側面に即した数値に分けることによって人々をきめ細かく統治できるから。
ニ 生政治は国民を統治するには全体的かつ個別的に人々に働きかけることが求められるとする国家理性論を元にしているが、それには全体と個別を同時に計測できる人口統計学がなければならず、それは十七世紀以降に可能になったから。
ホ 近代以前は統計学が未発達だったので、地域ごとの特質を反映させた数字を人口と捉えることができず、人々にとって特に重要な公衆衛生を国家の問題として発見できなかったが、その後の人口統計学の発展によって生政治が行えるようになったから。
(「早稲田大学 教育学部 2022年度 入試問題」読売新聞社)
正解は「ハ」らしいのだが、「人間が生きることに関わる様々な側面」というのが謎である。「人間が生きること」というのはソクラテスの頃から哲学者の頭を悩ませてきた事柄であり、そのようにパラフレーズされる内容が本文中にあったかどうかさらに悩ましい。
ここで問われている理由そのものは、傍線部2が含まれている文全体を読むとよくわかる。
こうした人口という対象、国家を構成する個人の単なる総和には還元しえず、また人工的構成物である「主権国家」とも異なる、風土、住環境の生物学的条件、人々の相互交通など、社会に固有の「自然性」によって構成される人口という対象の発見あるいは発明が、生政治を可能にしている。
(重田園江『フーコーの風向き』青土社、2020年、強調引用者)
ここで「風土、住環境の生物学的条件、人々の相互交通など」という箇所が決定的だと思うが、要するに「社会に固有の「自然性」」は、モンテスキューが考察したように国土ごとにそれぞれ個別具体性を持っており、それゆえホッブズ・ロック・ルソーらのように「主権国家」を人工的構造物とみなした社会契約論者のごとくに抽象的な理論へと還元されうる類のものではない、ということである。生政治が己の対象とする「人口 population 」は、このような地理的な差異に基づいている。
フーコーにとって「人口」とは何か
問三も見てみよう。
問三 傍線部3「フーコーがいう「人口」に当たるもの」とあるが、それは何か。(略)
イ 政治組織としての国家。
ロ 国家の一部としての地域。
ハ 人々を人口として見た全体。
ニ 特定の集合体としての社会。
ホ 人口学によって見いだされた個人。
(「早稲田大学 教育学部 2022年度 入試問題」読売新聞社)
「人口」は国家にとっての管理の対象ではあるから、「政治組織としての国家」(イ)でもなければ、「国家の一部としての地域」(ロ)でもない。また「人口」は「群」として扱われるから、「人口学によって見いだされた個人」というのも誤り。残る選択肢は「人々を人口としてみた全体」(ハ)か「特定の集合体としての社会」(ニ)である。「ハ」は限りなく正答に近いと思われるのだが、フーコーの「人口」の内容を問うているのに「人々を人口としてみた全体」ではまるで禅問答というかトートロジカルであるから、誤りであろうか。そう考えると、消去法で「ニ」にたどり着く。しかし、重田先生は問三に関して次のように述べている。
大学が提示した解答例では「ニ」が正答である。駿台のコメントにあるとおり、選択肢のうち「ハ」と「ニ」の違いが不明である。人口と社会は課題文内ではほぼ入替可能な語として並列して使われている。そして、問2のところで見たように、これは「新しい「全体」」を指しているので、「ハ」の方が正解に見える。さらに「ニ」の「特定の集合体としての社会」は、「特定」の内容が何なのか、どのように「特定」なのかが説明されておらず、本文内にも前後に「特定」の語がないので、消去法で「ハ」となる。
(重田園江「入試国語選択問題の「正解」について――早稲田大学教育学部の説明責任(OPINION)」SYNODOS、2022.03.14)
重田先生は「前後に「特定」の語がないので、消去法で「ハ」となる」と述べているが、実は探すと「特定」の語が出てくる。おそらく出題者は、「フーコーがいう「人口」に当たるもの」として、以下の箇所(二つ前のパラグラフの内容)を念頭に置いているのではないかと思われる。
生政治とは、すでに引用した部分で述べられているとおり、人口を対象とする政治である。ではここで「人口」とは何か。「それは単に多くの人間からなる集団ではない。生物学的な過程と法則によって貫かれ、制御され、支配された生ける者である。人口は特定の出生率、死亡率、年齢構成曲線、年齢分布図、健康状態を有し、また危機に瀕したり発展したりする」。したがってpopulationは、ある特定地域に居住する人口(住民)を意味するとともに、年齢や階層別に分類される人の就業であり、また統計上の母集団、一定地域に生息する生物個体群をも意味する。
(重田園江『フーコーの風向き』青土社、2020年、強調引用者)
「特定の集合体としての社会」(ニ)とは、「特定地域に居住する人口」と言い換えることもできる。つまり、選択肢ニでは、その地域に固有のあり方のことを「特定の」と形容しているわけである。
一人一人の個人の単純な総和が「人口」なのではない。それは、「全体」として捉えられた場合に、固有のあり方を持っている。こうした考え方を有機体論と呼ぶ。例えば、あらゆる物質は水素や炭素などの化学元素に還元され得るが、一人の人間が化学実験室から諸々の元素の寄せ集めによって生まれるのではないのと同様、一人一人の個人から総体としての「人口」が生まれるのではない。「人口」を説明するために、個体の単純な総和と解される可能性がある「集合体」という語を持ち出すことは、不適切であり得る。「人口」は、実はそれ自体を「個」として捉えられるような一つの「全体」である。そのように考えると、正答肢とされている「特定の集合体としての社会」(ニ)は、どうやら怪しく思えてくる。むしろ「集合体」をとり除いて、「特定の社会」とでもした方がまだマシかもしれない。「人口」においては「集合体」よりは一つの「全体」として扱う方が重要になってくるからだ。そう考えると、重田先生の言うように、「人々を人口として見た全体」(ハ)が内容的には正解と考えられる。
選択肢ホの日本語がおかしい
問四に進もう。
問四 傍線部4「生政治の展開の中で、ある人口の出生率と死亡率、生殖能力や罹病率などの全体が、「経済や政治の多くの問題と結びつけられ」(フーコー)重視されるようになった」とあるが、それはなぜか。(略)
イ 人口を一定に保つためには、出生率と死亡率、生殖能力や罹病率などを規範に合わせなければならないと考えられていたから。
ロ 出生率、死亡率、自殺率、犯罪率こそが社会秩序を不安定にするので、正常性を基準とすることでそれらを一定に保てると考えられていたから。
ハ 国家にとっては人口構成が一定であるのが望ましいので、出生率と死亡率、生殖能力や罹病率が変動しないようにすべきだと考えられていたから。
ニ 国家にとって人口構成は最重要項目なので、その変動要因となる数値をコントロールすることで人口を望ましいレベルに管理できると考えられていたから。
ホ 生政治では、たとえば人口構成を出生率と死亡率、生殖能力や罹病率などの様々な数値を一定の値に保つことで国民を統治しやすくなると考えられていたから。
(「早稲田大学 教育学部 2022年度 入試問題」読売新聞社)
傍線部4の前のパラグラフでは、ジョルジュ・カンギレム(Georges Canguilhem, 1904-1995)の『正常と病理』(Le normal et le pathologique, 1943=66)が言及されつつも、統計学がもたらした「正常と異常」というテーマが取り上げられる。要するに、経済や政治においては、統計学によって人口の動態をエビデンスとして利用することができるようになったことが設問の背景として挙げられる。
「人口を一定に保つためには、出生率と死亡率、生殖能力や罹病率などを規範に合わせなければならない」(イ)というのは、むしろ「出生率と死亡率、生殖能力や罹病率など」が規範になり得ることを取り違えているから誤りであろう。
「出生率、死亡率、自殺率、犯罪率」(ロ)は統計学的に示された数値であって、これが原因で「社会秩序を不安定にする」のは誤りであろう。
「国家にとっては人口構成が一定であるのが望ましいので、出生率と死亡率、生殖能力や罹病率が変動しないようにすべきだ」(ハ)というのは、本文中では以下の箇所に関係がある。
ここで、正常性は人口レベルでの統治の基準、尺度となる。というのは、社会の大量現象における「率」の一定性(出生率、死亡率、自殺率、犯罪率などの一定性)は、社会に秩序が保たれていることの証左であり、率の激しい変動は、上昇にせよ下降にせよ介入のための指標となるからである。たとえば、出生率が死亡率に比して極端に高い上昇曲線を示している場合には、その上昇を抑える施策が必要かどうかが、政治的・経済的目標との関連で検討される。
(重田園江『フーコーの風向き』青土社、2020年、強調引用者)
重田によれば、「社会の大量現象における「率」の一定性(出生率、死亡率、自殺率、犯罪率などの一定性)は、社会に秩序が保たれていることの証左であ」るとされる。したがって、「一定であるのが望ましい」(ハ)と考えられるのは、「人口構成」ではなくて、その人口構成を今後左右するであろう指標となり得る「出生率、死亡率、自殺率、犯罪率など」の「率」である。また「生殖能力や罹病率が変動しないようにすべきだ」(ハ)というのは、おそらく国家が健康促進する限りで、インポテンツや不妊は改善されるべきであろうと考えられるし、罹病率は常に低減が要求されるべき指標であるから、「ハ」は誤りであると考えられる。
「国家にとって人口構成は最重要項目なので、その変動要因となる数値をコントロールすることで人口を望ましいレベルに管理できると考えられていたから」(ニ)というのは概ね問題なさそうであるが、重田先生も述べているように、「国家にとって人口構成は最重要項目」なのかは必ずしも明示的ではない。むしろ国家にとって何かヨリ最重要項目が他にあるからこそ、「人口構成」が俎上に載せられるのではないか。重田先生は問四に関して次のように述べている。
ここでは選択肢「ニ」と「ホ」が正答候補となる。私は当初の駿台とともに「ニ」を選んだが、大学の「解答例」は、河合塾・代ゼミとともに「ホ」を正答とする。ニの前半「国家にとって人口構成は最重要項目なので」が間違いなのだろうか。しかし、課題文を読むと、ずっと国家にとっての人口の重要性が書かれているので、この部分を理由に弾く根拠はどこにあるのだろう。少なくとも「最重要項目でない」とは書かれておらず、「最重要項目となったことが近代国家の特徴だ」と書かれているように読める。さらに、後半部分は少なくとも「ホ」と同じ程度には正答に見える。
(重田園江「入試国語選択問題の「正解」について――早稲田大学教育学部の説明責任(OPINION)」SYNODOS、2022.03.14)
重田先生は「ニ」を正答と選ぶが、早稲田大学側は「ホ」を正答としている。「ホ」を丁寧に読んでみよう。
ホ 生政治では、たとえば人口構成を出生率と死亡率、生殖能力や罹病率などの様々な数値を一定の値に保つことで国民を統治しやすくなると考えられていたから。
もう一度よく読んでほしいのだが、「生政治では、たとえば【人口構成を】出生率と死亡率〔の数値を一定の値に保つことで〕、〔また〕生殖能力や罹病率などの様々な数値を一定の値に保つことで〔、〕【国民を】統治しやすくなると考えられていたから」と補っても、「人口構成」を目的語とする動詞がここで何であるかは不明であり、他動詞が一つ抜けている(「国民を統治しやすくなる」がワンセットであり、「人口構成」を「統治しやすくなる」とは考えられない)。このように「ホ」は日本語として成り立っていないので、誤りと考える。また「国民」(ネイション)という語も、重田先生は問題文中で用いていないのであるから、このような政治学的に重要な概念を不用意にパラフレーズして持ち出すことも、本来であれば避けたいところである。したがって、消去法で「ニ」が正解となる。
おわりに
一通り問題を解いてみて、重田先生の意見(要するに、早稲田大学側の正答が間違っているのではないかという問題提起と、早稲田大学側がその選択肢を正答とする理由の開示請求)には概ね同意できる。『フーコーの風向き』は、表題の通りフーコーのあの難解な思想を取り上げているのだから、それに基づく設問の選択肢を正しく選ぶことも一筋縄ではいかない。これは単なる国語力、読解力の問題ではない。つまり、問題文で引用されているテクストの箇所を正確に把握するためには、同時にその著作全体を読まねばならず、理解度において両者のあいだに相関があるとされる。これは「解釈学的循環」と呼ばれている。これこそまさにテクスト解釈における「全体的かつ個別的」な問題とでも言えようか(近代に特有なのかは知らん)。
