
中年の心に突き刺さる名言で振り返る2024年8月の読書
2024年8月の読書10冊は、(私の思う)著者の名言も引用しながら振り返りたい。内訳は・・・
野球×2、発達障害×2、老後戦略×2、美容・転職・小説・昆虫が各1
①電車の窓に映った自分が死んだ父に見えた日、スキンケアはじめました(伊藤聡)

50代のおじさんが自分の容姿が亡き父に見えた(アイシーデッドピープル?)ことをきっかけに、美容という未知の冒険に旅立った日々が軽妙なタッチで語られる。
男性が美容に感じる「恥ずかしさ」への考察も興味深く、美容に関する“偏見”“アンコンシャスバイアス”への気づきも促される。
“おじさん・イン・スキンケアランド”の世界へ、さあご一緒に!
(読売新聞書評より引用)
私はなぜスキンケアをするのか。
しだいにその理由は「昨日の自分より少しよくなれるから」なのではないか、という気がしてきた。(伊藤聡)
そう、美容は自分をよりよくするための手段なのだ。
②転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書き方(谷所健一郎)

採用担当として多くの応募書類を読み、56歳になって自ら履歴書・職務経歴書を選考に落ちて書き直し、落ちなくても書き直した地べたの経験が今の自分の仕事(相談員)にも生きている。
もともとは、現在の仕事で我流で指導している内容に不安を持って勉強しなおす意図で読んだのだが、自分の理解とのギャップはあまりなく安心した。
むしろ、自分自身のために“自分の市場価値”の集大成をどれだけ書けるか、企業の選考のためでなくとも、いつでも準備しておきたい。
職務経歴書から活躍する姿がイメージできれば、採用担当者は間違いなく、「会ってみたい」と思います(谷所健一郎)
③リスペクト R・E・S・P・E・C・T(ブレイディみかこ)

2014年ロンドンで起きた事件がモデルの小説。
ソーシャルクレンジングにより塗りつぶされようとするシングルマザーたち
人として当たり前に持ちうるはずのもの、それは・・・
・尊厳=リスペクト
・尊厳を持って生きるとはどういうことか
パンのために薔薇を手放してはいけない、だからこそ母ちゃんたちは立ち上がったのだ。
対岸の火事と思ってはいけない。
登場人物の一人、幸太の言葉が重く響く。
何か心当たりがあって後ろめたい(苦笑)
人間って、実は支配されたほうが楽だと思う部分があって、そうすればもう自分で何も考えなくて済むし、安心だからと思って自分の生を誰かに丸投げしてしまうんだ。(幸太)
④アロハで酒場へ なぎら式70歳から始める「年不相応」生活のススメ(なぎら健壱)

「飲めば死ぬ、飲まなくても死ぬ」と都合のいいことをうそぶき、古希になっても泥酔を繰り返すのはいかがなものかと思う笑。
が、現役フォークシンガーの傍ら、カメラに自転車、絵画と多芸多趣味で人生を楽しみ尽くしている点は「イケてる爺ちゃん」。
筆者の語る通り「すぐに忘れてしまうような実のない話」だが笑、ゆるさの中に垣間見える「プロ意識」は迫力がある。
自由人だからこその著者の以下の言葉は特に自分に響いた。
定年はね、社会が決めたことであって自分自身が決めたことじゃないんですよ。本来、引き際は自分が決めるものなんです。(なぎら健壱)
そう、幕引きは自分で決める。
⑤60歳からの新・投資術(頼藤太希)

自分に投資した成果で誰かの役に立つ、そんなDIE WITH ZEROを目指す。
役に立てなくなったら推し活一本に絞る笑。
やみくもに資産形成しても意味はないでしょう。
なぜなら、お金は使うために存在するのであって、お金は使ってこそ価値があるからです。1000万円の資産があれば、1000万円分の経験・思い出を得ることができます。
死んだときに多くの資産が残っているということは、そのお金を使って得られたはずの経験・思い出を得られなかったと考えることができるわけです。(頼藤太希)
⑥日本百名虫 フォトジェニックな虫たち(坂爪真吾)

自分の子どもたちが小さい頃、自宅でカブトムシを育て、アゲハチョウを羽化させたり、今も庭でカマキリを飼い?昆虫には縁が深い。
この本で一層「虫LOVE」の世界へ誘われる。
美しい写真と著者の昆虫愛に満ちたワードセンス溢れる文章、多様で面白い見た目の虫を育む日本の国土の豊かさを再認識。
控えめに言って小さな名著だ。
▼大人になって忘れてしまった“ロマン”を感じさせてくれる言葉▼
年齢も学歴も社会的地位も関係なく、とにかく「良い虫」「デカい虫」を採ったやつが偉い。ミヤマクワガタは、そんな昆虫の世界の素晴らしさを教えてくれる名虫である。 *本表紙はヒメオオクワガタ
⑦自閉症スペクトラム症「発達障害」最新の理解と治療革命(岡田尊司)

数ある発達障害関連著書の中で、本書が際立つのは七分の三の紙数を割いた治療や改善のアプローチに使っている点。
発達障害への理解が「回復」の道を作る第一歩。
障害など関係なく、誰もが「変われる」という普遍的な真実を信じて前にすすもう。
優れたカウンセラーは、ごく自然に相手の関心に寄り添い、のめり込み、本気で感動します。まるで入門して弟子になったように教えを乞い、自らファンになります。(岡田尊司)
自分もそのように仕事をしていこうと思う。
⑧あらゆることは今起こる(柴崎友香)
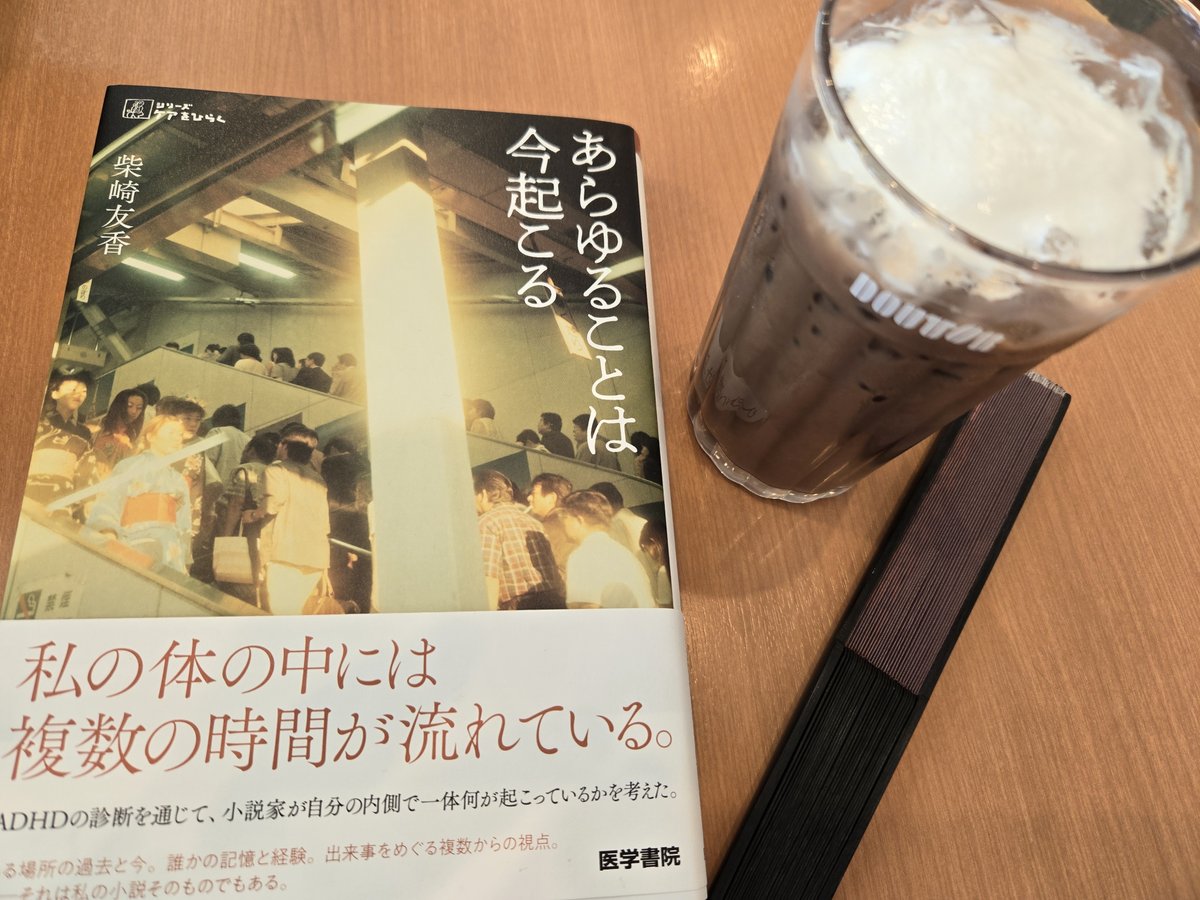
芥川賞受賞歴もある著者がADHDと診断された経験をもとに刊行、書名は著者自らの時間の感じ方を表現している。
発達障害と言ってもそれぞれ特性は異なる。理解するために特性を「ステレオタイプ」に見ようとしていた自分に気づき反省。
筆者の生きづらさを読んで、自分が世界とどう向き合っているかを振り返ることができる。
そもそも「できない」から悪い「人と違う」からいけないという社会の風潮を変えるのが先決、以下の言葉に集約される。
数が少ない、多数派よりも少ないというだけでなぜ「足りない」「できない」側になってしまうのか、なぜ多いほうが少数のほうに「配慮や理解をしてあげる」感じになってしまうのか、ここはすごく重要なことだと思う。
(柴崎友香)
⑨甲子園は通過点です 勝利至上主義と決別した男たち(氏原英明)

そもそも「高校の部活動」がなぜこんなに大人のエンタメになってしまったのか。暑さ対策をしながらも足をつる選手は続出、勝利のために相変わらず投球数を投げさせる指導者、健康よりもドラマ性を重視してしてタイブレーク性や7回制に異を唱える識者たち。
抜本的な議論をして、日本のスポーツ文化全体が良い方向に向かうといい。
▼著者のレポートより▼
▼以下、要旨▼
🔹新潟県高野連の球数制限導入決断
・2018新潟単独の革命ー日本高野連を動かす
・登板過多ー済美高校エース232球完投
米メディア「クレイジーだ」
・野球界の危機ー甲子園で勝つことだけ目指す
野球をする子ども増えない→先を見据える
・勝利至上主義<子どもの身体(球数制限)
・T字型体制(横と縦のつながり)
🔹甲子園に取りつかれた鬼軍曹の改心
・金沢成泰(明秀日立/光星学院)
甲子園絶対主義(勝利至上主義)への疑問
・伊丹一のワル“坂本勇人”→野球で人生変わる
・指導者が本来目指すものー選手の伸び
レギュラー補欠垣根取り払う(全員出場させる)
・勝利のためにやっていたこと
長時間上位下達の練習/サイン盗み(2塁走者)
・中谷仁(智辯和歌山)
ー2019木製バットで国体→球数減
・同世代のエースが登板過多で投手断念
全投手を戦力に⇔投手一人(壊れたら終わり)
・智辯を出てたら間違いないと言われる人材に
🔹公立校から始まる球数制限とリーグ戦
・ドミニカ共和国(メジャー輩出2位)の高校野球
日本の高校球児よりはるかに劣るプレー
→16-18歳でなく先を見る(日本短期ビジョン)
・球数制限を導入ー市ヶ尾高校
→投手全体の意識向上、誰もが登板可能性 ✖公立不利
・大阪で始まったリーグ戦取り組み/LIGA
負けられないトーナメントー特定の投手頼り
🔹サッカー界の育成のカリスマの試み
・国内重視の野球、世界立ち位置見るサッカー
サッカー界全体のため活動する指導者/経営者
・育成のカリスマー幸野健一(サッカーコンサル)
スポーツを文化に⇔オリンピック一過性(日本)
日本スポーツは運動=体育(忍耐努力我慢礼儀)
・PFI活用ー市川GUNNERS
テクノロジー活用/合理的育成メソッド
全員を試合に出しながら強いチームづくり
・忍耐・努力の高校野球(部活)
ー100人の補欠がアルプススタンド(異様)
・世界との差ーインテンシティ/環境(競争原理)
・トーナメントー天国か地獄(見る側のドラマ)
→リーグ戦ー幸せのヒエラルキー
選手全員が試合に出れてこそ伸びる
・名将もてはやす甲子園→主役になるのは選手
⑩もう一度、投げたかった 炎のストッパー 津田恒美・最後の闘い(山登義明/大古滋久)

西本、槇原、内藤、ブライアント、西村、松永、清原…懐かしい
今夏の高校野球選手権第3試合に登場の山口県南陽工業のエースだった津田恒実さんが亡くなってはや31年。
壮絶な闘病生活、献身的な晃代夫人のサポートが心をうつ。
苦痛と絶望の中でも再びマウンドに立つ夢を諦めなかった…夢を抱いたまま旅立つも、だからこそ意味のある闘病の2年間だと響いた。
弱気は最大の敵。
最後まで自分との戦いを貫いたのだ。
私の読書記事に最後までつきあっていただきありがとうございます。気になる著書はあったでしょうか?
これからも多様な著者・著書に巡り合い、自分を高めていきたいと思います。スキンケア含めて笑。
