
編集後記の思い出
今日は仕事前に『アフリカ』の編集後記を書いた。『アフリカ』を読む人には、編集後記からまず読む、という方が多いみたいだ。後ろのページから開きたい天邪鬼が多いのか…(悪口じゃないです、私は天邪鬼です)、いや、まずは表紙をひらくが、ぺらぺらとめくってみて、読むのは最後のページから、ということかもしれない。
編集後記を書くのには、そんなには時間をかけない。推敲を含めても、ほとんどの場合、1日で仕上げてしまう。1ページの、短い原稿だ。

はじめて「編集後記」を書いたのは、卒業した大学の、学科の非常勤スタッフをしていた頃に出した『寄港』という同人雑誌の創刊号で、こんな書き出しだ。
「寄港」というのは、小川国夫の処女作品集『アポロンの島』の中の一篇で、地中海沿岸のある港に立ち寄った青年が体験する世界の、音のスケッチのようなものだ。そこで青年は、体の奥に息づいている何かしらの不安を、どうすべくもなくもてあましている。
いったい自分は何を書きたいのか、と問う時に、漠然としたことを言えば、まずあるのは、そのどうしようもない不安のようなものなのだろう。ここに集まった原稿からも、それを感じている。
いったい何を言いたいのか… わかるような、わからないような、だけれど、20代前半で、何やらとても意気込んでいるのは伝わってくる(かな?)
『寄港』は、4冊つくって、"休刊"になった。その後のことは、ぼくはよく知らないが。そのあと、もうそういう雑誌をやるのは懲り懲り、やりたくない、と思っていた中、ある出会いをきっかけに、魔が差してつくってしまったのが『アフリカ』2006年8月号だった。
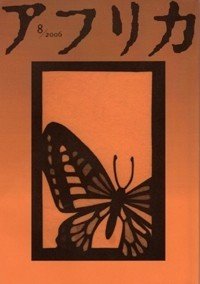
その編集後記は、こう始まる。
どうしても中央にいられない性分というのだろうか。同人雑誌は辺境の国にある。けっして中央の、大きな存在になることはない。いつまでも隅っこで、ちまちまと生きているものである。その気持ちは忘れない方がいいだろう。マイナーであることの誇りもないことはないが、それよりも中央に出て行かれると困る状況がある。それは生存上、仕方のないことである。
同人雑誌というものは、どこの国のどの時代にも存在するというようなものではない。農村において生まれやすいという説があって、そうすると、日本における同人雑誌の歴史は、日本人の農民気質が生み出したものかもしれない、と思うがどうだろう。
いまの編集後記と比べると、随分と違う。だいたい『アフリカ』を、同人雑誌だと思っているところからして違う。まだ『アフリカ』は生まれたばかりの赤ん坊で、『アフリカ』がどんなものだか、どんなふうに育っていくのか、成長して、何者になるのかなんてサッパリ、わかりようがないわけだ。
これについては、ある人と、面白い指摘だけれど、「中央」という言い方はどうかなぁ? という話をした記憶がある。ソウデスネ。
そのあと、こんなことも書いている。
同人雑誌は、自然と出来るものだ。また、人が集まったところにしか出来ない。そうでなければ、つくる必要がないから。同人雑誌をやらなければならない、どうしてもやりたい、という気持ちはない。文学をやる同志がいて、ではやろうか、というだけである。
この、最初の「2006年8月号」は、「ほんとうに一冊だけというつもり」でつくったと以前にも書いている(「突然、出てきたものだった──『アフリカ』前史」、『アフリカ』2016年8月号)が、この編集後記でも、やろうと思ってやったわけじゃないよ、たまたま出来たものです、と言っていたわけだ。
随分、挑戦的な感じもする。いや、実際に、挑戦的だった。そしてぼくは、その気持ちを忘れたくないと思っている。
(つづく)
「道草の家・ことのは山房」のトップ・ページに置いてある"日めくりカレンダー"、1日めくって、6月28日。今日は、久しぶりに「ひなた工房」のことを。
※"日めくりカレンダー"は、毎日だいたい朝に更新しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
