
【特集】『アフリカ』vol.34(2023年3月号)のライナー・ノーツ
わたしはこまって、どぎまぎして──未来のことはわかりませんよ、と答えた。概括するということがわたしには苦手なのである。(長谷川四郎)
さて、遅くなってしまいましたが、『アフリカ』最新号(vol.34/2023年3月号)をご紹介しましょう。
楽屋話は例によって「水牛のように」4月号の「『アフリカ』を続けて(22)」で書いています。それを読んだ方には、くり返しになる部分もあるかもしれませんけど、ここでは誌面を写真で見ていただきつつ、少し内容に入り込んだ話をしましょうか。

その前に、『アフリカ』って何? という話はこれまでもたびたび書いていますが、あらためて…
簡潔に言うと、私(下窪俊哉)が読みたいと思うものを折々に集めて、つくっている雑誌です。
書いてほしいと思うひとに声をかけて、つくっている、と言った方がよいかもしれません。何を読みたいかは、自分でも初めからわかっているわけではないからです。
個人的な雑誌、プライベート・プレスなどと呼んでいます。 表紙にはいつも「アフリカ」という誌名と、発行年月のみが記されていて、切り絵(を画像化して印刷したもの)が置かれています。
何の、どんな雑誌なのか、表紙を見ただけではサッパリわからない。
「vol.34」というのも奥付に書いてあるだけで、他には書かれていないので、何号なのかもすぐにはわからない。最初の頃は奥付にも書かなかったので、「号数のない雑誌」なんて呼ぶ人もいました。

切り絵は、最初の号からずっと"切って"くれている向谷陽子さん。今回は、どうして羊と灯台になったのか…?
たぶん羊は、現在のところアフリカキカクの最新刊である『モグとユウヒの冒険』に、出てきそうで出てこない(?)動物だったからでしょう。
灯台になった理由は、もしかしたら私が最近、ヴァージニア・ウルフを読んでいたので、その連想で、あるいはそうではなくて、向谷さんが何かきっかけをつかんで灯台を"切ろう"と思ったのかもしれません。
じっくりと見ると、羊は時間をかけてじっくり、細かく制作されているのがわかります。対照的に灯台の方はシンプルです。
今回は迷いなく、表紙には羊にいてもらうことにしました。なぜ迷わなかったのかは、うまく説明できませんけど。

装幀の守安涼くんも、創刊時から変わらず。最近はもう阿吽の呼吸というのか、私からは必要最低限のことだけ伝えて、あとはデザインの別候補など一切なし、ワン・テイクで一発OKという見事な仕事ぶりです。1日かからず。

表紙を開くと、いきなり本文!(よくやります、エッセイが多いですが、たまに詩が始まる場合もあります)「道草の家のWSマガジン」にも載っていたなつめさんの「ペンネームが決まる」ですが、「WSマガジン」から推敲と校正を経て少し変わっています。
離婚して息子とふたり実家に戻ったなつめさんは、そこでも居心地の悪さを感じていて、東京の下町から山間部の小さな村に移住します。何もかもが新しい暮らしを始めるにあたって、「別の名前」を自分で自分につけようと考えますが、なかなか決められません。
私の中にもう一人、別の場所で生きる名前である。それは私がこの先、私の仕事を一から作り、活動するときに呼ばれる名前となってほしい。この名前は自分で決めていい。そう考えるとワクワクしてくる。
その名前は、ある時にふと、やってきてくれます。

続いて、いつもの目次。裏表紙に使った切り絵の灯台と、(そこから連想された)2008年7月号の目次にあった切り絵が(浮かび上がるように)再登場しています。隣のページには、『アフリカ』ファンには好評のクレジットページも当然あります。細かいところまで見てほしい。じつに真面目です(どこが?)

続いて「vehicle」、神田由布子さんによる詩ですが、これも「道草の家のWSマガジン」に載っていた作品です。推敲や校正を経て、ですが、この詩は一言一句変わってません。でも、この詩はぜひ縦書きで読みたい! ということになりました。
ある午後、雲を見ていたら
目の前にそれがやってきた
「乗ってゆきませんか」
何語かわからないが
運転手はたしかにそう言った。
そうやって始まります。旅立ちが朝ではなく「午後」であることに、少し注目しましょう。「それ」はふとそこにやってきます。「何語かわからない」つまり何と言ったのかわからないが(ここでふと、神田さんが翻訳の仕事をされていることを思い出します)、旅に誘われていることを知ります。新しい何かを始める時、それは人生のいつであってもいい。そしてこの詩は、(詩を)書くということについて、いつまでも応答を続けるでしょう。

すっかりお馴染みになったUNIさん、新作の短篇小説は「日々の球体」です。これまで『アフリカ』に載った中では一番長い、400字の原稿用紙にしたら約30枚、短篇小説としては、いい感じの長さです。
「日々の球体」は、交わったり、すれ違ったりしている男女三人の人間模様を描いています。
実衣(みい)は5人組の(なんて言ってみたくなる感じなんですが)派遣グループのひとりとして事務仕事をしている。
社会のなかで何の役に立っているのかちっともわからないこの仕事にも、華やかさの濃淡がある。データをシステムに流し込むまでのホコリ取りのような作業や電話対応は、時間だけ取られてうまみが少ないと唐戸は思っているのだろう。上手に逃げる。
といったような人間観察が、出てくる人たちに対して繰り広げられる。その表現はときに皮肉たっぷりでありながらも、ピリッとした親しみも感じられます。小説はやがて、実衣の幼馴染である七菜香(ななか)、いちょう並木の坂の上にある大学の裏に住む譲(じょう)の話に流れてゆき、彼らの日々は「球体」を描いてゆく… ということでしょうか。彼らがどこへゆくのか、おそらく作者も気にしながら、その書きっぷりは軽やかに揺れているようです。

続いて、犬飼愛生さんの詩「寿司喰う牛、ハイに煙、あのbarの窓から四句」、かつてないくらい長いタイトルがいかしてますね? これは冒頭の数行をひきましょうか。
私は何十年と寿司を喰ってきたが、いまだわからないことがある
なんでこんなに好きなのかを
私が嫌いな煙のことを心底好きな人もいるしとろけるような顔で好きだ好きだ
なんならお前よりも好きと言われた気もするいやお前なんて呼ばれたことなかったわ
犬飼さんの作品は詩とエッセイで「同じ人が書いたの?」と言われるくらい落差がある(と言われる)、けれど、この詩にはエッセイの中にあった要素も流れ込んできているようで、ついには短歌が挿入されたりもして見開き2ページの中でごった煮になっている新境地です。
「エッセイの中にあった要素」というのは、私は何となくそう感じているんですが、どこに、どう出ているでしょうか? これはバーにおける独り言が発展したものなのかもしれない、と想像しながら読んでみます。

下窪俊哉さん(私ですね)の新作「四章の季節/道草指南」は短編小説で、「日々の球体」と同じくらいの長さですが、読後に感じる長さはそれぞれ違うかもしれません。
小説の中に、ある街が浮かび上がっています。「きみ」はそこへ迷い込むように入っていく。目的の場所へ「きみ」はいつもスンナリとはたどり着けないけれど、やがて行き着く。そこには「道草氏」と呼ばれる人物がいて、「きみ」は彼に道草を習いたいなどと言う。「道草氏」は道草を教えるとは言わないが、やがて、彼の道草論というような話を始めます。
──ある日、突然、ですかねえ。
遠い目をして言っている。
──天の声が聞こえたとかですか。
──ああ、そんなのはない。
──ないですか。
きみはあってほしかったような声を出してしまう。
──まるでない、そんな劇的なことは。
この小説は、かわす、それる、ズレる、(ひっくり返す?)、といったことをめぐる対話で成り立っていると言えそうです。私という作者は、その人たちと「きみ」が出会う場所、空間を、一日という時間の流れ、一年という季節の流れを背景に舞台的に描こうとした。どれだけ書けたか、と自分では不安というか不満もありますが、書けるだけ書きました。

続いて、髙城青さんの「それだけで世界がまわるなら - 2年めとコーヒーのはなし」。エッセイ漫画「それだけで世界がまわるなら」としては2020年秋(vol.31)以来の続編で、お父さんを亡くして2年がたった家族の現在を、そのお父さんが大好きだったコーヒーを介して描いて(書いて)あります。週に3、4日ほど、実家の母に珈琲を淹れて届けるというのが習慣化していると言います。
でもたぶん
父に対してのさまざまなことには
まだ、まっすぐ向き合えてはいないことは自分でわかっている
「ひとに対する思い出もそれぞれだな」と青さんは言います。死者はまだ身近な存在で、いまの暮らしと記憶の風景とが一緒くたにもなっている。それでも日々は過ぎてゆき、微かなところに変化もあり、そんなことをしっかり書き(描き)留めようとしています。

竹内敏喜さんは20年前、私が初めて雑誌をつくった時に(『寄港』という名前の雑誌でしたが)書いてくれて以来の付き合いです。でも、『アフリカ』に原稿を寄せてもらうのは初めて。「蛇足から」は今回、1〜3を掲載していますが、続きがあるのかもしれません(というよりあらゆる原稿は"とりあえず終わらせている"のであって、本当の終わりというのはないはずです)。
ここでは、いま書くことの怖れを感じつつ、「善」と「正義」への考察が繰り広げられる。いや、考察ではないのかもしれない。ことばを探っている。それは「詩をひらく鍵」だと言います。
もはや残り少ない美しいもの、その調和が壊されるのを
繰りかえし見るしかない、夢のなかでも何度も見させられながら
どんな手がおこなうのか
それは単なる組織上の上司の手ではないのか
一歩、ふみ出すごとに
おのれの音がちいさくなる
固くふみ締めてみても
ひびきは霞みゆく
そんなふうな危うい感じで、詩は何とか持ちこたえています。それを読む私も、決して安全な場所に立ってはいない、いまにも消えてしまいそうな存在としてあるのだと感じます。

富田克也さんと私が初めて会ったのは2010年の夏、『デルタ 小川国夫原作オムニバス』という映画の公開前に、それにかかわった人たちとその関連作品を特集上映していた、ある夜でした。その後、富田さんと高野貴子さん、相澤虎之助さん、そして井川拓さんら空族との不思議な付き合いが生まれましたが、いろいろあって、井川さんは翌2011年4月に急逝してしまいます。
その井川さんが晩年、児童文学作品を書いていたことは、本人からも聞いていました。没後、友人や家族から遺稿を読ませてもらい、いつか本にできたら… と思っていたのが『モグとユウヒの冒険』でした。
「自然を感知した人〜井川拓と空族の黎明期」は、富田さんが若き日の井川さんについて語った貴重な記録(約8千字)。聞き手は私です。
いま、「身に沁みて考えるようになった」ことがあって、それは「自然っていうこと」なんだという話から始まります。井川さんは若くしてそれを感知して──見方によっては感知しすぎていて、苦しみ、また表現して伝えようとしていたと言います。
自分たちが普段、この人間社会で生きてしまっているとベールに覆われてしまっているそれを全部引っ剥がした時にズドーンって見える、まさにこれを真実と言わずして何と言う? っていう自然が、目の前にひろがっている。
おそらくゴッホは、自分の中にある狂気の先に見えてしまうそれをね、目の前に見て、それを描かずにはおれないっていう状態で描いたと思うんです。
と、「美術館でゴッホの絵を観て、卒倒して救急車で運ばれた」らしいエピソードを交えて語っている場面もあります。
また、井川拓の話をするということは富田さん自身の若い頃、映画をつくり始めた頃の話をすることになるんですね。話は徐々に、映像制作集団「空族」の誕生秘話にもなってゆく。『雲の上』の前に撮影され、未完に終わった『エリコへ下る道』がどんな映画だったのかも、ようやく聞くことができました。
空族の知られざる黎明期のエピソードが、詰まっています。
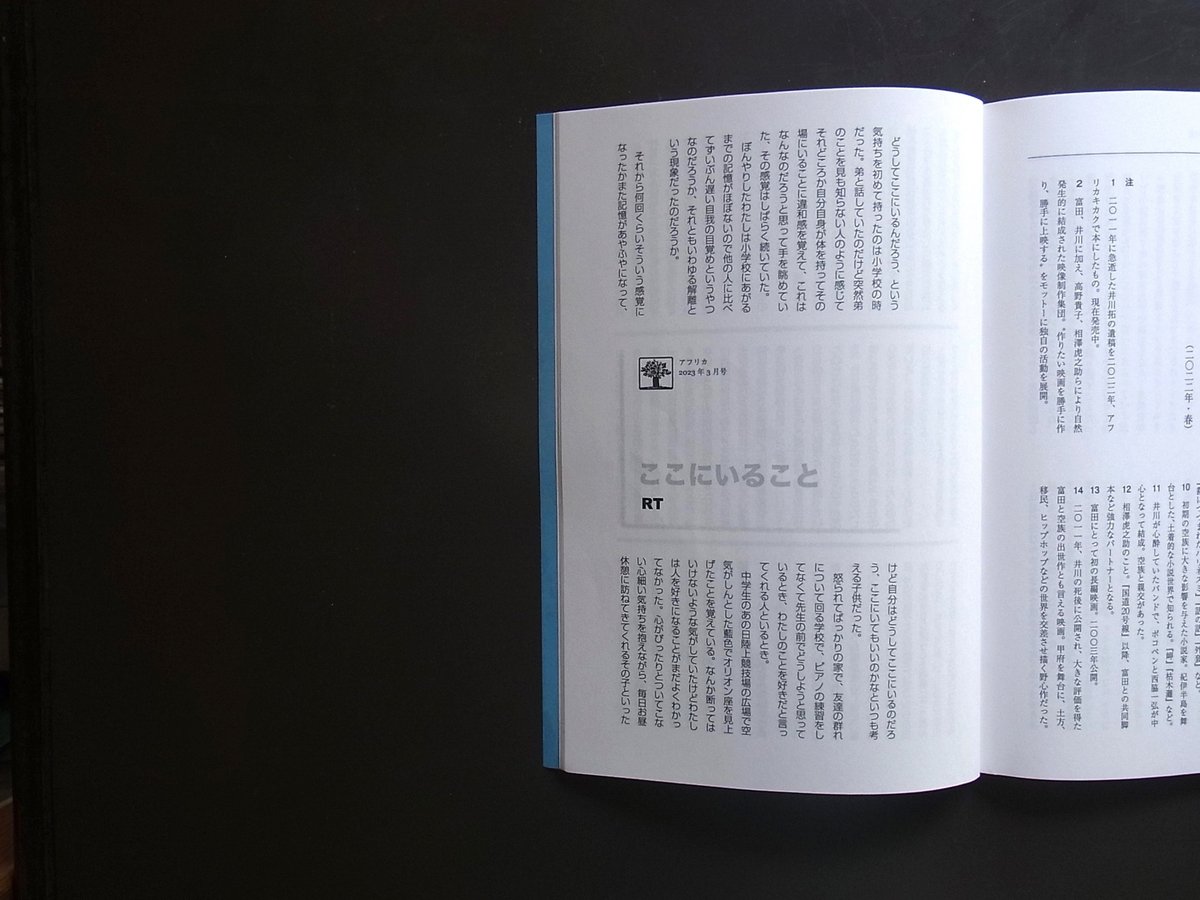
続いて、RTさんの「ここにいること」。「心がぴったりとついてこない」と感じるこどもが大人になり、さまざまな時間を経て「人の為に何かしたい」と思うまでになる経緯を書いたエッセイです。
経済活動から少し離れたところで営まれている活動に、救われる人の話でもある。「鬱」ということへの言及と、空を眺めているところなど、「自然を感知した人」に通じる要素が幾つもあり、並べて載せることにしました。
一日が終わるとくたくたで、ちょっとさみしくて、ちょっと悲しくて、そんな時いつもは黙っている空が話しかけてくるみたいに思えるのはどうしてだろう。
しかしRTさんはそのまま空の方へ行ってしまうわけではなく、空を感じつつも人間社会に踏みとどまって「いろいろと挑戦してみよう」と思うようになってゆきます。その中のひとつとして「文章を書きたい」ということもあり、『アフリカ』とその周辺にある場所、人との出会いについても書かれていますが、それも「いろいろ」ある中のひとつであり、できるだけバランスよく歩んでゆこうとしている姿が、私のくり返し読む中には浮かんできました。
でも、そのバランスっていうのは、いつもきれいにとれるものではないかもしれない。どんなふうにうまくバランスを崩しながらやってゆけるのか、ということをいま私はRTさんの文章を読みながら(自分のこととして)考え始めています。

そして今回の『アフリカ』ラストは、犬飼愛生さんの「相当なアソートassort②「通帳持って」」です。前回と同じく、見開き2ページの短いコントのようなものですが──コントと言ってしまって失礼しました、たいへんシリアスな話でもあります。
舞台は銀行の窓口、そしてATM。
息子が暗唱番号を間違えたせいで、息子の預金が入っている口座がロックされた。私はすぐさま、息子の通帳と保険証をひっつかんで銀行の窓口へ走った。ああまずい、お金を下ろさなければ。だって、私は息子のお金を立て替えている。息子の預金から返してもらうんだから。
そうやって窓口に行けば、ロックはすぐに解除されるはず、と思うでしょうけど、犬飼さんのエッセイでそんなふうに物事がスンナリ運ぶはずがない(そうなったら書いてないでしょうから)。事態は一転、二転、三転… しかし、この人はどうしてそんなに焦っているのでしょうか?

ラストの作品はそんな犬飼さんによる芸達者な短文ですが、いつものようにその後のページもあります。またしても虚実入り乱れた「執筆者など紹介」(「など」がポイントだったりして?)と「五里霧中ノート」は、まあ相変わらずです。
『アフリカ』だけ読んでウェブ情報は見ていないという方も中にはいらっしゃるので、お知らせも幾つか載せています。ウェブ情報を頻繁に見ているので知っているという方も、たとえば10年後などにこのページを見たら、ああそんなこともあったねえ? となるでしょう(100年後のことは考えられていませんが、10年後のことくらいは考えられます)。

そして、本当のラストは、いつも通りの編集後記です(それで前のラストが嘘だったということにはならないはずですが!)
『アフリカ』を毎号、読んでいる人たちには、この編集後記から読むという方が多いのかもしれません。編集後記という名のエッセイと言ってもよさそうです。近況を伝えつつ、何かを感じ、考え、ということが入ってきます。
今回は、始めたばかりの『道草の家のWSマガジン』のことを中心に書き、その流れで『水牛』のことにも少し触れました。
多少のゆるさや軽さが人の営みには必要だろう。きちんとしたものでなくていい、まずはどんどん生み出してゆこう。──その精神がリレーされてゆく未来に、私は本当の自由を夢見ている。
さて、その『アフリカ』は、アフリカキカクのウェブショップで販売中。
いつもの珈琲焙煎舎(府中市)では店頭で発売中。どうして珈琲焙煎舎だけなの? という質問には、もう説明するのが面倒くさくなってきていますが、精神的な故郷といいますか、そういう関係性のある場所です。ノンビリしていて良いところなので、疲れた頃にちょっと足を伸ばして、行ってみてください。珈琲が大好きな方はとくに。
羊に見られる表紙の『アフリカ』最新号、#アフリカキカク のホームグラウンド(?)珈琲焙煎舎 @coffeebaisensya にはいつものように到着、発売中、焙煎舎の珈琲は相変わらずの美味しさです。京王線とJR南武線・分倍河原駅から徒歩10分弱の、のんびりした通りで営業中。 pic.twitter.com/hpnDcEWaz5
— 道草の家 a.k.a. アフリカキカク (@michikusanoie) March 31, 2023
書店営業などは殆どしていないのですが、そういうことをする余裕がないからです。でも逆に「売りたい」と連絡をくださる店、人には良い条件で(と思います)卸しているので、本当に売りたいと思う方のみ、引き続きどうぞ。ここだけの話、たくさん来られるとそれはそれで対応が難しくなるので、そっとご連絡ください。この段落はひそひそ話でした。
もちろん読みたい方へは、ご注文いただければ、すぐにお届けします。いつでもどうぞ!
(CM)今日も一日頑張った方、ゆっくり休んだ方、ダラダラしてしまった方、しんどかった方、楽しかった方、悲しいことがあった方、よく覚えてない方、私は何だろう、いろんな人の日々の暮らしの中にそっと置いて。話しかけてみて。#アフリカキカク の本です。 https://t.co/T4I6GyAfVS pic.twitter.com/hZ6Gf14yNS
— 道草の家 a.k.a. アフリカキカク (@michikusanoie) May 24, 2023
日本列島の津々浦々どこへでも送ります。国外への発送にかんしても、もしご希望があればご連絡ください。たまにあるのですが、できる限りの対応をしています。

さて、その『アフリカ』、次は秋頃を予定しています。始めた頃の、年2回のペースに戻してゆきたい、と考えているからですが、さて、どうなりますやら?
(つづく)
気づいたら今月も「道草の家のWSマガジン」の〆切である9日が近づいてきている。参加方法は? 何か書いて、私に送るだけです(私への送り先がわからない方はDMでも何でもご連絡ください)。
