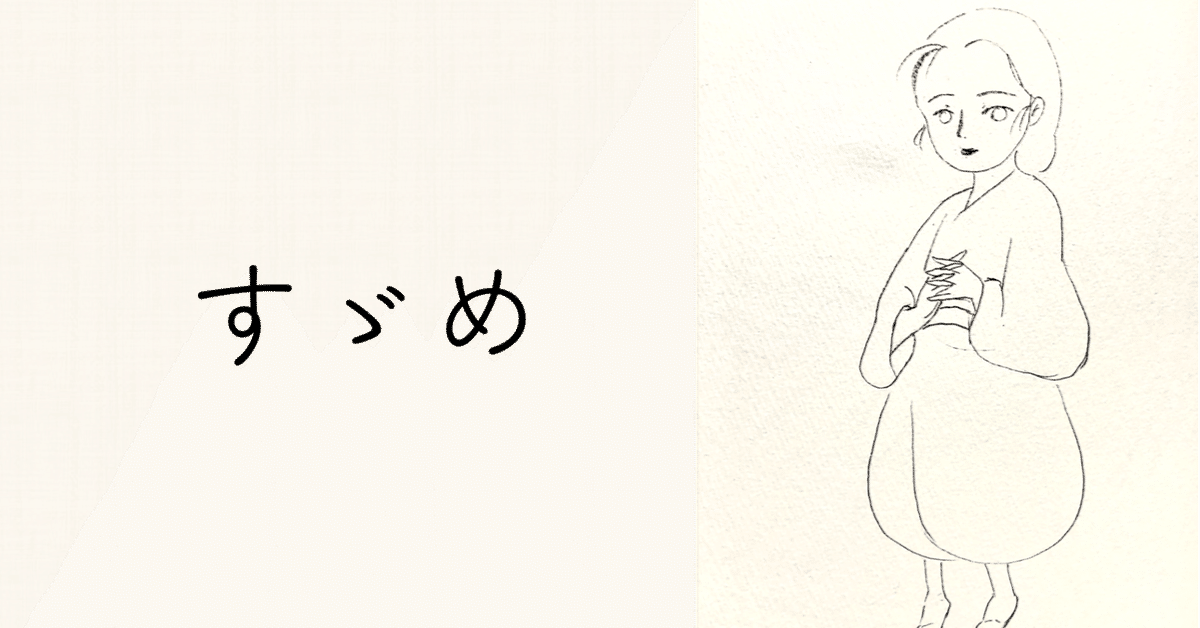
すゞめ-3
夏が過ぎ、新学期が始まって少しした頃のことです。
放課後。村へのバスは本数が少なく、わたくしはよく、図書室や教室に残って、時間を待っておりました。
電気が消され、窓からの明かりだけになった放課後の教室は、お掃除のせいか、風が通ったようにとても居心地がいいのです。借りていた本を読み終わり、バスまでまだ時間があることを確認したわたくしが、図書室に本を返そうと廊下に出た時です。廊下の真ん中に一人、コギノさんが立っておられました。
わたくしは教室の戸口で動けなくなりました。コギノさんの目の前には、廊下に張り出されたわたくしの綴り方が、入選の花をつけられていたのです。
わたくしはあの綴り方を返却した日から、コギノさんに謝ることができないでおりました。悪いことをしたという訳ではないのです。ただ、わたくしはあの時、コギノさんのことを、裏切ってしまったような気がしていたのです。
コギノさんはいつも正々堂々としております。学校で一人でも、決して不安な様子を見せず、学年で一番でも、今まで威張ったところを見せたことがありません。その彼女に、わたくしは何かしら期待して彼女の顔を見たのです。ですから、振り返った彼女の凛々しく澄んだお顔に、わたくしは顔を向けられなくなりました。自分の卑しい心を、コギノさんに見抜かれた気分になったのです。けれど、そこでさらに顔を背けたわたくしは、正々堂々とした彼女に比べ、どれほど卑怯なのでしょう。
――わたくしは結局、本を鞄にもどしました。
学校前でバスに乗るのは、大人も子供も大勢いますが、わたくしたちの村に着く頃には、バスにはわたくしとコギノさんだけになります。コギノさんは運転席の後ろで、わたくしはバスの後ろの席に座っていました。わたくしは前の席で揺れるおかっぱの髪をみては、気配を潜めておりました。
道路の縁には彼岸花が咲いており、バスの窓を美しい紅くれなひが線になって流れて行きました。
村に着き、コギノさんは先に降りました。運転手はわたくしたちの顔を覚えてくださっていますから、わたくしはわざと、支度に手間取っているようにして、遅れてバスを降りました。降りてくるわたくしを、コギノさんはバス停で待っていました。
わたくしはどきりとし、そうして驚いてしまった自分を恥ずかしく思いました。謝らなければならない。そう思って言葉を探しましたが、いい言葉が見つかりません。困った時のくせで、わたくしが足元に顔を伏せておりますと、コギノさんが、
「メルさんの綴り方読みました。とても良かった。」
あの通る声で、それだけ言うと、コギノさんの上等な靴がくるりと回りました。わたくしが顔を上げた時には、堂々とした小さな後ろ姿が、村に歩いて行かれるところでした。
コギノさんのその姿と大人びた声に、わたくしはなんだか、すっかり褒められ、許された気になりました。そして、コギノさんのことが一遍に好きになってしまいました。
その日から、わたくしはエダさんと時間を合わせて帰るようになりました。エダさんはとても賢い方で、難しいことをたくさん考えておられました。
「都会では女性も男性も、区別なく働くことが常識なんですよ。」
ある日エダさんはそんなことを言いました。
大正は四十七年で終わり、昭咊になって随分経ちました。その間にも、様々な法令が指定され、女性の活躍する世が訪れていました。
「女の人でも、男の人と同じだけお給料をいただけますし、同じように役職にもつけます。きちんと大学を出れば、高級技能職でも働けるんです。」
それはわたくしには驚くような話でした。村ではどの家も、水田と小さな畑をやっています。大人になれば、男は家の田畑を継ぎ、女はお嫁に出てその家の田畑を耕すのが、村の常識でした。家を継げない男たちは波止場で働き、女もお嫁に行くまでは港町に出て、お裁縫などで働くのが普通でした。この頃はお仕事が多様になりましたから、和裁をお店に頼むことも普通になっており、港には洋裁のお店なども多くありました。
港にやって来る船は、都市からのものも多かったですが、普通の村娘だったわたくしは、港からさらに都市に行くなどと、これまで考えたこともありませんでした。町で生まれ育ったネリムさんなどは、都会に憧れているようでしたが、大学を、何より高級技能職などを考えているお友達は、他におりませんでした。そういった仕事をされるのは、お国の中でも特別な人だと思っていたのです。
「エダさんは、村を出て行かれるのですか?」
「ええ。いつかは。」
エダさんはきっぱりとそう言われました。
いいなと思ったら応援しよう!

