
茶唄の心得♪ 味は狭山でとどめさす|抹茶入り玉緑茶「あじさやま」
<繁田園のルーツ・狭山について>
狭山丘陵は、東京都と埼玉県の都県境に3,500ha(東京ディズニーリゾート全体で100haなので、実にその35倍!)も広がる、自然豊かな地域です。
映画『となりのトトロ』の舞台になったとも言われており、この一帯は「トトロの森」という愛称も。

所沢市HPより
さて、この地域でのお茶(=狭山茶)づくりがスタートしたのは、1800年代前半。
当店の起源にあたる繁田家もこの地で1812年に茶業を興しました。

「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」
この地域に伝わる有名(?)な茶唄のワンフレーズです
(狭山のお茶屋さんや地元の方しか知らない唄かもしれませんが笑)
ところで、なぜ、このような唄が生まれたのでしょうか。
その理由は、狭山のお茶づくりの歴史にあります。
今では日本三大銘茶と呼ばれる静岡・宇治・狭山。
その歴史を紐解くと、まず静岡茶は、1681年、徳川家へ初めて献上されたとの記録があります。
また、日本茶業の変革ともいえる青製煎茶製法は、1738年に京都・宇治にて発明され、宇治茶は当時、江戸で一大ブームをつくりました。
他方、狭山はそこから一世紀前後も遅れての参入。
当然ですが、先行する有名産地に負けないお茶づくりが必要です。
結果として、狭山地域では、味わいの決め手となる「狭山火入(さやまびいれ)」を開発。
茶葉の一部が焦げることさえ恐れない「狭山火入」は、力強い味わいを生み出すことに成功。そして、狭山茶はその評判を徐々に高め、後発ながらも三大銘茶の仲間入りを果たすことになりました。
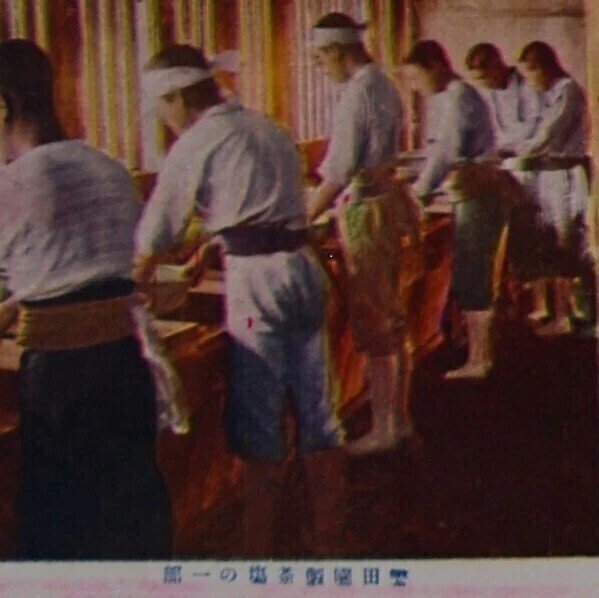
当店の起源の地は狭山ですが、現在取り扱っている原料の大半は鹿児島と静岡の茶葉で、狭山の茶葉は一部のみ。
しかし、「産地ではなく香りと味を追求する」という当店のこだわりは、約200年前、静岡・宇治に追いつけ追い越せと創意工夫した狭山丘陵の生産者たちから引き継がれているのなのかもしれません。
抹茶入り玉緑茶「あじさやま」は、この狭山のDNAとも言える「香りと味わいの追求」によって生み出された商品です。
<作り手について>
「あじさやま」の原料は、玉緑茶と抹茶です。
まず、主原料の玉緑茶。
当店の釜炒り茶はすべて、全国茶品評会(=最高品質の茶葉を各種別ごとに審査し、その日本一を決定する場)の入札販売会にて仕入れています。
これは、大量生産・大量消費のサイクルにはない、日本茶専門店ならではの原料調達方法です。扱い量は限られますが、これにより高品質な希少茶葉を適価にてお客様にお届けすることが可能になっています。
そして、どちらかというと脇役扱いの抹茶。
しかし当店では、抹茶を使用するすべての商品の原料に、京都・宇治にて300年の歴史を誇る丸久小山園の抹茶を使用しています。
理由は単純明快で、「名店だから」「ブラント産地だから」ではなく……味にこだわるには、上質な抹茶が欠かせないからです。


例年、大臣賞(全国1位)を獲得する名店です
京都・宇治での生産現場では、一貫して品質本位のモノづくりがおこなわれます。

味にこだわった先で行き着いた、品評会出品玉緑茶と丸久小山園の抹茶のコラボレーション。
狭山の地にルーツをもつ当店の味自慢「あじさやま」、ぜひ皆様にも一度お試しいただけますと幸いです。
<商品について>
「あじさやま」の最大の特徴。
それは、上品な甘みと旨み、そして焙煎香のバランスです。
玉緑茶に上質な抹茶を贅沢に加えることで、優しい甘みと柔らかな渋み、そして後味には残らないほのかな苦みが、深みのある味わいへとまとめあげます。

という方も多い人気商品です
伝統的な煎茶製法では生み出せない奥深い味わい。
日本茶に飲み慣れたお客様にも、一度お試ししただけますと幸いです。
<お届けのご案内>
こちらのページにて販売しております
<淹れ方&楽しみ方>
〈温かいお茶の淹れ方〉
茶葉の量:5g
湯量:150ml
湯温:85℃
抽出時間:30秒
【湯温の調整方法】
・沸騰したお湯を湯呑みに移して湯量をはかり、急須へ
・氷を1-2個急須に入れ、氷に当てるようにしてお湯を注ぐことで、湯呑みを使わず直接お湯を注ぐことも可能です
【美味しく淹れるポイント】
・湯呑みにお茶を注ぐときは、一気に注ぐのではなく、3回程度に分けて注いでいただくことで、急須の中の茶葉が適度に揺られ、旨味が抽出されます
・最後の一滴は、茶葉の旨味が凝縮された「ゴールデンドロップ」です。急須の中にお茶を残さず、最後の一滴まで湯呑みに注ぎきってください
・2煎目は、お湯を入れたらすぐに抽出してください。時間をおくと苦味を感じる場合がございます。
こちらの記事が役に立ったと感じて頂けた方は「♡マークのスキ」を押していただければ幸いです(スキは非会員でも押すことができます)。
皆様の日常の「一服」のお役に立てるよう、作り手の方の想いやおすすめの淹れ方をお伝えしてまいります。
