
金閣寺を読む 最終章 花子出版
こんにちは。
クリスマスが終わり、年の瀬に向けて足早に時間が駆けています。実家に居れば、餅をついたり、正月の準備をしたり、大掃除をしたり、と齷齪働いていることでしょう。今は、大阪で独り暮らしですので、気儘に筆を握っております。
では、『金閣寺を読む』最終章が始まります。
梗概
溝口は金閣寺を焼くための準備を進めていた。夜、金閣に上がり、板戸の釘を二本抜いておく。老朽化しており、簡単に抜くことができた。数日経ったが、釘が抜かれていることに気が付く人はいなかった。
カルモチンを百錠入りのものを買った。刃渡り四寸ほどの鞘付きの小刀も買った。
金閣寺には戦後、最新式の火災自動警報器が取り付けられていた。
六月二十九日の晩、案内人の老人が警報器が故障を見つけた。しかし、翌朝に修繕を頼むことになり、溝口は又とない機会を逃すこととなる。
夕刻になり修理工がやってきて、故障した警報器を見物したが、匙を投げて再訪を伝え帰っていった。
昭和二十五年七月一日。火災警報器は今日中に直る見込みはない。溝口にとって、決起の日がやってきたのだ。
夜、金閣寺には珍しく来客があった。溝口の他界した父と交友があった、福井県龍法寺の和尚が訪ねてきた。老師が帰宅するまで、和尚は溝口と話がしたい、と催促した。溝口は躊躇う。和尚の澄明な目で自分の企てが見抜かれないかと。
精進の肴で胡座をかいて呑んでいる和尚の前に、溝口は座った。老師がもたぬ素朴さがあり、亡き父の持たぬ力があった。
「私をどう思われますか」
溝口は和尚に聞く。
「ふむ。真面目な善い学生に見えるがのう。裏でどんな道楽をしておるか、儂は知らん。しかし気の毒に、昔とちがって道楽の金もあるまいがのう。お父さんと儂とここの住職とは、若い時分はなかなか悪さをしたものじゃった」
「私は平凡な学生に見えましょうか」
「平凡に見えるのが何よりのことじゃ。平凡でよいのじゃ。そのほうが人に怪しまれんでよいわい」
虚栄心を持たない和尚と、溝口の会話が続く。そして、溝口は言った。
「私を見抜いて下さい。私は、お考えのような人間ではありません。私の本心を見抜いて下さい」
和尚の目が溝口を捉え、沈黙の重みが溝口の頭上に降る。
次の瞬間、和尚は晴朗な笑い声をたてた。
「見抜く必要はない。みんなお前の面上にあらわれておる」
老師は午後九時に帰り、和尚と老師は酒を酌みかわし、夜中の零時半ごろに和尚は寝床につく。老師は風呂に入り、そして二日の午前一時に寝床につく。
寺は静謐になる。
溝口は布団の上に座り、夜が更けるのを待った。そして、思う。
『もうじきだ。もう少しの辛抱だ。私の内界と外界との間のこの錆びついた鍵がみごとにあくのだ。内界と外界は吹く抜けになり、風はそこを自在に吹きかようようになるのだ。釣瓶はかるがると羽搏かんばかりにあがり、すべてが広大な野の姿で私の前にひらけ、密室は滅びるのだ。……それは、もう目の前にある。すれすれのところで、私の手はもう届こうとしてる。……』
一時間も闇の中に坐り、幸福に満たされていた。
溝口は立ち上がった。寺を忍び出た。
溝口の財産は、書籍類から衣服などの細々したものだけで、それらを柳行李一箇と小さな古いトランク一箇に事前に入れておいた。
それらを金閣寺に運び、板戸の釘を一本一本抜く。
彼の動きは労働者のように機械的作業だった。荷物を義満像の前に運ぶ。蚊帳と敷座蒲団を運び、掛蒲団を運び、トランクと柳行李を運び、最後に藁の三束を運ぶ。
準備を終えると、激しい食欲に襲われる。買っていた食べ残しの菓子パンと最中を貪るように喰べる。味はわからない。
溝口は行為のただ一歩手前にいた。最後の別れを告げるつもりで金閣のほうを眺めたのだ。
金閣が夜の闇に包まれ輪郭を失いつつあったが、その美しさは絶える時がなかった。その美はつねにどこかしらで鳴り響いていた。耳鳴りの痼疾を持った人のように、いたるところで私は金閣の美が鳴りひびくのを聴き、それに馴れた。音にたとえるなら、この建築は五世紀半にわたって鳴りつづけて来た小さな金鈴、あるいは小さな琴のようなものであったろう。その音が途絶えたら……
溝口は激甚の疲労に襲われた。
幻の金閣は金閣の上にありありと見え、それは燦めきを納めない。
溝口は呟く。
『私は行為の一歩手前まで準備したんだ。行為そのものは完全に夢みられ、私がその夢を完全に生きた以上、この上行為する必要がるのだろうか。もはやそれは無駄事ではあるまいか。柏木が言ったことはおそらく本当だ。世界を帰るのは行為ではなくて認識だと彼は言った。そしてぎりぎりまで行為を模倣しようとする認識もあるのだ。私の認識はこの種のものだった。そして行為を本当に無効にするのもこの種の認識なのだ。してみると私の永い周到な準備は、ひとえに、行為をしなくてもよいという最後の認識のためではなかったか。見るがいい。今や行為は私にとっては一種の余剰物にすぎぬ。それは人生からはみ出し、私の意志からはみ出し、別の冷たい鉄製の機械のように、私の前に在って始動を待っている。その行為と私とは。まるで縁もゆかりもないかのようだ。ここまでが私であって、それから先は私ではないのだ。……何故私は敢て私でなくなろうとするのか』
溝口は駆け、金閣の北へめぐった。そして湿った燐寸をする。火は藁の堆積の複雑な影をえがき出し、その明るい枯野の色をうかべて、こまやかに四方へ伝わった。つづいて起る煙のなかに火は身を隠した。しかし思わぬ遠くから、蚊帳のみどりをふくらませて焔がのぼった。あたりが俄かに賑やかになったような気がした。
燃える最中、溝口はカルモチンや短刀を忘れていることに気が付く。この火に包まれて究竟頂で死のうという考えが突然生じる。彼は狭い階段を駆け上がった。
煙は溝口の背に迫る。溝口は究竟頂の扉をあけようと叩く。だが、堅固な鍵は開くことがない。
溝口は体をぶつけた。だが、扉は開かなかった。
ある瞬間、拒まれているという確実な意識が溝口に生まれたとき、彼はためらうことなく身を翻して階を駆け降りた。火をくぐりながら。
溝口は駆けた。山道を駆け登り、左大文字山の頂きまでやってきた。
金閣は見えないが、爆竹のような音、又無数の人間の関節が一せいになるような音が聞こえ、天に冲している火が見えた。溝口は膝を組んで永いことそれを眺めた。
そして、彼は遁れた獣のように負った傷口を舐める。ポケットを探ると小刀と手巾に包んだカルモチンの瓶が出てきた。それらを谷底めがけて投げ捨てる。
別のポケットの煙草が手に触れる。煙草を喫んだ。一ト仕事を終えて一服している人がよくそう思うように、生きようと彼は思った。
以上梗概。
以下、私の読書感想。
終わりました。ものすごい高揚感と虚脱感、さらには自縛していた鎖を切った開放感があります。開放感とは、金閣の頂に住む金色の鳳凰が、燃える金閣によって昇天するような心地とでも言い表しましょうか。
とんでもない小説を、三十一歳の三島由紀夫先生は執筆されたんだなあ、と畏敬の念と多少の嫉妬が脳裏を駆けます。
恍惚となる文章があります。抜粋。
火は藁の堆積の複雑な影をえがき出し、その明るい枯野の色をうかべて、こまやかに四方へ伝わった。つづいて起る煙のなかに火は身を隠した。しかし思わぬ遠くから、蚊帳のみどりをふくらませて焔がのぼった。あたりが俄かに賑やかになったような気がした。
このあたりの描写の正鵠を得た表現と、古典的であり新鋭な表現。冗長さはなく、清く正しく美しく。正しく日本文学の美学の真骨頂だと思っております。
昨今、わかりやすい表現がよしとされています。難解ではなく、浅学でも読める。まあ、それらに是非を求めるつもりはありませんが、私はそのような文字を追っても、一切身が引き締まる思いがしないのです。
堕落と頽廃に導く文学よりも、より人間の根源に問いかけるような文学を渇望しているのであります。
『金閣寺』の最終章を読んで、そのように考えた次第であります。
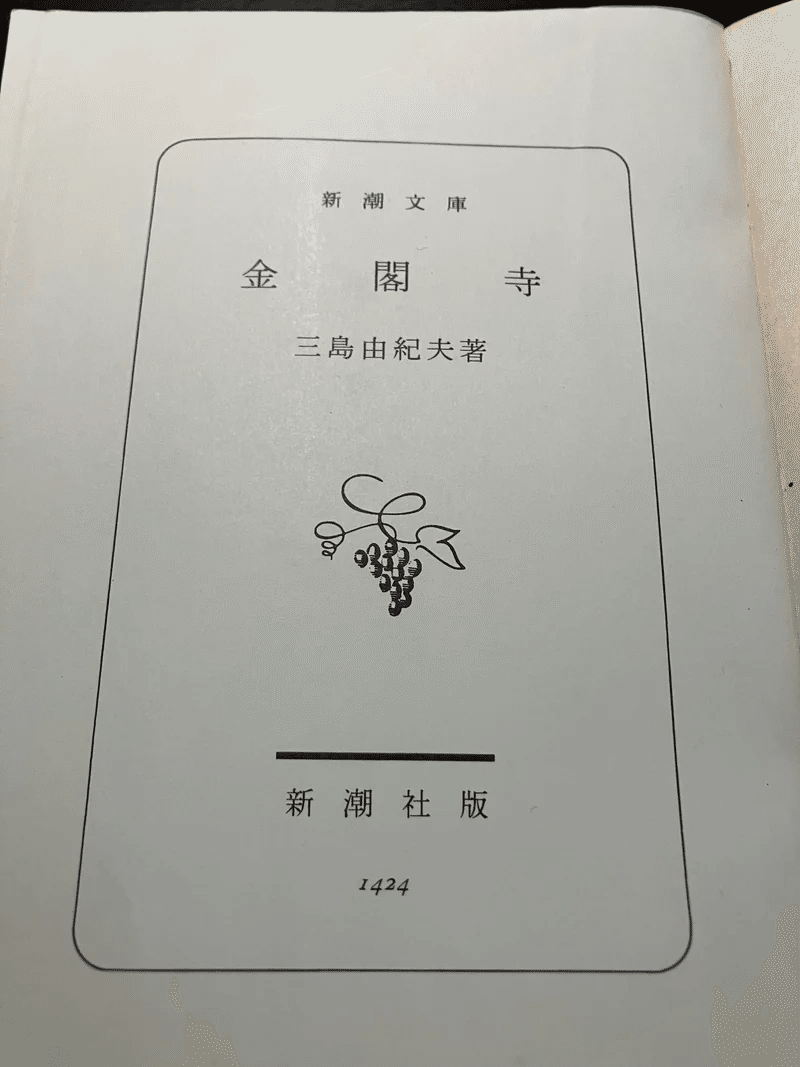
総括の記事を書きますので、またお読み頂ければ幸いです。
花子出版 倉岡 剛
いいなと思ったら応援しよう!

