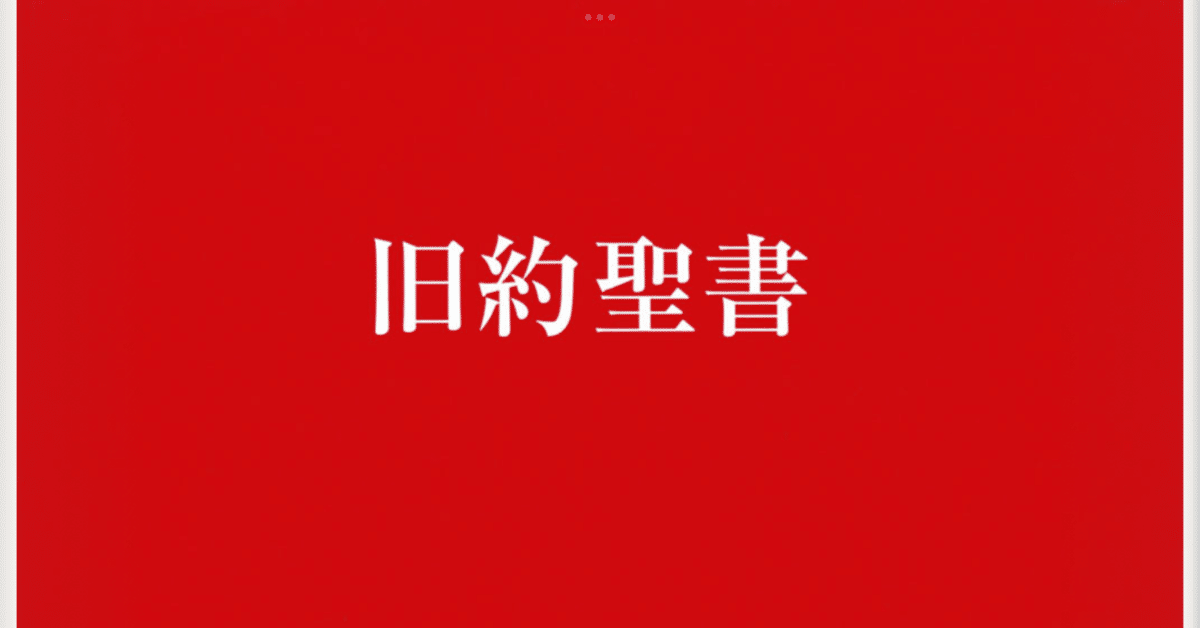
ユダヤの風土:『旧約聖書』中沢洽樹訳 読了
<概要>
全訳ではないが、重要な箇所について旧約聖書を現代人にもわかりやすく解説書付きで意訳に近い形で訳された著作。
<コメント>
旧約聖書を読むにあたって、最初のとっかかりとして本書を選択。旧約聖書自体が目茶苦茶長いので、まずは、おおよそのイメージをとらえるためにはよかったかな、と思います。
いずれにしても旧約聖書を忠実に守ったら現代ユダヤ教徒・キリスト教徒は生きられないでしょうから、当然イスラーム教のコーラン同様、現代宗教指導者等による現代的な解釈が必要だと改めて実感。そして自分たちに都合の良い解釈が生まれるのは宗教の世界の常ですね。
ちなみに旧約聖書の場合は、今受講している東北学院大学の田島卓先生によれば旧約聖書自体が「発展的加筆」と言う、過去に書かれた記述をよりわかりやすく再作成することによって千年かけて作られた経典。したがって「解釈」前提の経典であるとのこと。
『申命記1:5』
「モーセは、ヨルダン川の東側にあるモアブ地方で、この律法の解き明かしに当たった」
→モーセが解釈しているのを「よし」としている
さて、本書は全訳ではないとはいえ内容は多岐に渡り、ざっくり以下のように分類できます。
それでは個別に感想を以下整理。
⒈世界の成り立ち(創世記)
創世記を読むと、人間と動物は連続したものではなく、人間は動物とは違う特別な存在だ、というふうになります。なぜなら人間は神が泥を固めて自分の身を真似て造ったものだから。そして動物を支配するのが人間、という存在。この辺りはだいぶ生物学の知見や東洋的な思想とは違います。
また神が言った。「われらの像に、われらに似せて、ヒトを作ろう。そしてこれに海の魚、空尾の鳥、家畜、すべての野(獣)と、地に這うすべてのものとを従わせよう」
人間含めて生きるものは皆「産めよ。殖やせよ」と神が命じていますので、イスラエルは先進国にも関わらず特殊出生率が「3.0」と突出して高いのも頷けます。
祝福して言った。「産めよ、殖えよ、海水に満ちよ、また鳥は地に殖えよ」夕となり朝となって五日目が終わった。
エヴァ(女性)はアダム(男性)の肋骨から作られ、さらにエヴァがヘビにたぶらかされて善悪を知る木(=禁断の実)を食べて、アダムも勧められて食べてしまう。この結果、人間はエデンの園を追い出されて働かないと生きていけない世界に放り出され、女性は出産で苦しむことになる、という有名なストーリー。
*女性の誘惑→抗いきれない男性→生まれつき人間は罪深い=原罪
心理学的・生物学的に蛇が「人間含む動物一般に恐怖心を与える」という説があり、京大での実験でも「生まれつき人間は蛇が怖い」と言う説もあり、旧約聖書でも蛇を特別扱いしているところをみると、あながち古代人の経験則も『文化がヒトを進化させた』のいうとおり「疎かにはできないな」と思います。
ヤハウェ神が作ったすべての野獣の中で、蛇がいちばん悪賢かった。
また、出産に関して、動物の中で唯一人間だけが出産で苦しむのですが(人間の赤ちゃんは頭が大きいから)、このあたりも旧約聖書の物語は、ちゃんと抑えてあるんですね。神のお言葉(=古代人の知恵?)は深淵です。
そして、一神教にとって「労働は苦しみ」。この辺りの価値観も今に生きる一神教の人たちの価値観に影響しているかもしれません。東アジア人というか日本人の場合は私の印象では「労働は美徳」であって「苦しみ」ではありませんから。
ちなみに現代イスラエル人の祝日は多いし、金曜の夕方から始まる安息日含む土日もちゃんと休むので、イスラエルに住むと休むばっかり、みたいな感覚になるそうです。
⒉ユダヤ人の歴史と神(創世記・出エジプト記・イザヤ書)
⑴ユダヤ人の歴史
アダムに始まって、アブラハムやモーセに至るまで、延々と記されています。
①アダムを始祖としノアに至れば、ノアの方舟よろしくノアの家族以外の人間は全滅。
アダム→セツ→エノス→カイナン→マハラレル→ヤレド→エノク→メトセラ→メレク→ノア
②ノアの方舟で助かったノアの家族の系譜。のバベルの塔を作ったら、神に怒られて言語をバラバラにされてしまう。
ノア→セム→アルパクサデ→シェラ→エベル→ペレグ→レウ→セルグ→ナホル→テラ→アブラム(のちにアブラハムに改名)
③アブラハムは、カナンの地(今のパレスチナあたり)からエジプトへ向かい裕福になってまたパレスチナに戻り、神との契約により、中東からエジプトにかけての始祖となる。のちにヤコブはエジプトに移住し、その息子のヨセフはファラオの元で長官となってエジプトの中枢になる。
アブラハム→イサク→ヤコブ(のちにイスラエルに改名)→ヨセフ
お前の子孫にこの地を与える。エジプトの川からユーフラテスまで。
④ヤコブ以降、イスラエルの民はエジプトにて人口爆増し、ファラオにとって目障りな存在に。そこでファラオは、イスラエルの民にわざと苦役を与えて追い出そうとする。
ヨセフを知らぬ新しい王が、エジプトに現われた。王は国民に言った。
「見よ。イスラエル人は多すぎて、我らの手に負えぬ。早急に意手立てを講じよう。さもないと、彼はますます殖えるばかりだ。そして、ひとたび戦争でも起これば、きっと敵の側についてわれらに刃向かい、この国から脱出するかも知れぬ」
そこで登場したのがファラオの王女に育てられたモーセ。モーセは神の声に従い、イスラエルの民を引き連れてエジプトを脱出。
イスラエル人はラメセスからスコテに向けて出発した。・・・イスラエル人がエジプトに住んでいた期間は、430年であった。
このように、モーセがパレスチナにたどり着くまでの歴史が延々と語り継がれていて、純粋な物語として読んでも面白い箇所。ユダヤと古代エジプトの関係がここまで密接な関係にあるとは、旧約聖書を読むまでは知りませんでした。
⑵神
旧約聖書を読む限り、一神教の神様は、どう考えてもイスラエルの民だけの神。
コーラン日本語訳を読むと、イスラーム教徒にとっては旧約聖書に登場するアブラハムもモーセも預言者のムハンマドと同じ扱い。
アブラハムやモーセを通して発せられた神のお言葉は、旧約聖書の中ではイスラエルの民だけに向けた言葉であっても、ムハンマドからみれば、世界に生きるすべての人間への預言である、というふうになっています(だからアッラーを信じないものは死後全員地獄に落ちる)。
とはいえ、旧約聖書だけ読めば、神はあくまでイスラエルだけの神であって、同時代に生きていたエジプト人の神でもアッシリア人の神でもない。この辺りは明確。
だからイスラエル人にこういうがよい。<われ有り>という神から、このわたしは、おまえたちの所に遣わされたのだ、と。
わたしはおまえの神ヤハウェ。エジプトの地、奴隷の家からおまえを導き出したものである。
後代のエジプト人もほとんどがイスラーム教徒になってしまうので、古代エジプトのホルス神やオシリス神、太陽神ラーなどは過去の遺物になり、イスラエルの神が唯一の神として彼らの信仰の対象になったのは皮肉です(ユダヤ教・キリスト教・イスラーム教の神はみな同じ神なので)。
もしかしたらキリスト教が浸透していく中で、イスラエルの神がローカルな神からグローバルな神に転換したのかもしれません。
ちなみに神自身の性格は、イスラーム教のアッラーとほぼ同じ。全知全能の神であり、すべてを創造する神であり、すべてを司る神。
「われはヤハウェ。万物を造り、ひとり天をひきのべ、みずから地をくりひろげ、易者の徴を乱し、占者を狂わせ、知者をしりぞけ、その知識を嘲る」
「われはヤハウェ。唯一無比。光を造り、闇を創造し、幸を作り、災いを創造する」
すべての行為は、しかり、善であれ悪であれ、いかなる秘密も、神によって裁かれるからである。
⒊各種律法と助言(出エジプト記・伝道の書)
「十戒」が代表的ですが、生きる上での規則については、旧約聖書でも多くのページが割かれています。例えば偶像崇拝禁止については明確に
おまえは偶像を刻んではならぬ。・・・いかなる形像をも。・・・またそれを拝んでも、それらに仕えてももいけない。・・・
と否定しています。翻訳者の解説によれば、偶像崇拝は像を作ることによって「神」が限定されてしまうことになってしまうし、神の被造物である人間が神の像を造ることは神の主権を侵すことになる、とのこと。
⑴禁止
*人殺し、姦淫、盗み、隣人に対する嘘、同胞への金利請求、賄賂・・・
*小山羊をその母の乳でにてはならぬ
→現代ラビ・ユダヤ教のカシュルート「肉と乳製品を一緒に調理しない」の根拠ですね。一方で「豚肉を食べない」などの他のカシュルートは、本書には未記載。調べるとレビ記11にカシュルートの詳細が記されています。
⑵義務
*唯一神のみの信仰、安息日の履行、割礼、孤児や寡婦への施し・・・
中でも男性の「割礼(包茎手術)」は旧約聖書でも重要な神との契約の徴として重要視されているのは意外でした。
「・・・おまえののちの代々の子孫との間に守られるべき契約というのだこれだ。すなわち、おまえたちの男はみな割礼を受けること、その包皮の肉を切って、これをわたしとおまえたちの間の契約の徴とすることだ。・・・わたしの契約は、おまえたちの肉に刻まれて、永遠の契約となるであろう。包皮の肉を切らない無割礼の男子がいたならば、彼はその民の中から絶たれるであろう。それはわたしの契約を破るものだからである」
⑶罰
*生命には生命を、目には目を、歯には歯を、手には手を・・・・
*盗んだものはその二倍の賠償
*男が処女と通じた場合は、その女性との結婚
コーラン同様、旧約聖書も大きなことから細かいことまで、さまざまなルールが規定されていて、この辺りは、旧約聖書がのコーランの手本になっていたのかもしれない。
⑷助言
特に「伝道の書」で、神から人間への助言が散りばめられています。義務としての「・・・しなさい」ではなく、助言としての「・・・するといいですよ」という助言。中身が実に現実的でリアルで面白い。以下主な助言を紹介。
*財産はリスクヘッジのために七つか八つに分けておくこと(伝道の書14)
*生ける犬は死せる獅子に勝る「どんなことがあっても生きよ」(同10)
*何事も中庸であれ「過ぎたるは猶及ばざるが如し」(同8)
*若い者は青春を楽しんで悔いを残すな。したいことはし、見たいものは見よ(同13)
*憂いを取り払って鬱になるな(同13)
*時と偶然が支配する世の中だからこそ、徳福一致はないと思え(同11)
この辺りは神の存在と矛盾するように感じる。コーランの「神の意思は人間には計り知れない」の方が説得力がある。いわゆるインシャーアッラー(神が望むなら)です。
*苦労多い人生だからこそ、(アルコール含む)飲み食いして楽しむべし。(同10)
*何事もベストを尽くせ(同10)
*王(上司)の命令は守ろう。嫌なことがあっても安易に退職するな。王に従っていれば嫌な思いをすることはない(同9)
実に面白い。これが2000年以上前に生まれているのですから。。。
⒋世界説明(伝道の書)
伝道の書は、時代がおおいに下り(BC1000年あたり)、全イスラエルの王となったダビデの息子コーヘレスの言葉が紹介されている箇所。とはいえ、翻訳者によればコーヘレスをダビデの息子にしたのはこの書の内容を権威づけるためのフィクションであろう、とのこと。
「コーヘレス(コヘレト)の言葉」とも訳されていて、コーヘレスの世界説明は生々流転。世界とは生々流転するものであり「すべては空である」となる。つまり古代インド的な思想とよく似ています。
仏教含む古代インド思想では、すべての前提を「輪廻転生」におき、輪廻転生を前提に世界説明し、だから私たち人間は煩悩から抜け出せない、となるのですが、コーヘレスの場合は「生々流転によって人間が煩悩に苛まれる」とまでは言ってません。
どちらかというと、旧約聖書の場合、この世は「空」なのだから、私たちがこの世にいようがいまいが、世界は変わらずに生々流転しており、自分たちを襲う不幸や幸福に右往左往しても意味がない、というような考えのようです。
「空の空である」とコーヘレスが言う。「空の空、いっさいが空である。天が下で人間がいかに労しても、その労苦が、およそ何の益になろう。世は移り、世は来る。しかし地は永遠に変わらない。
以上、旧約聖書の一部を翻訳した本書を読むと、旧約の世界観が若干わかるとともに、世の中は空である、というような東洋的な無常感も記されたりして、一神教のイメージとはだいぶ違うように感じます。今回は、あえて解説本などは読まず、素直に旧約聖書の翻訳本を読んでみました。
今後は、解説本なども読みつつ、さらにユダヤの本質に迫っていこうと思います。
