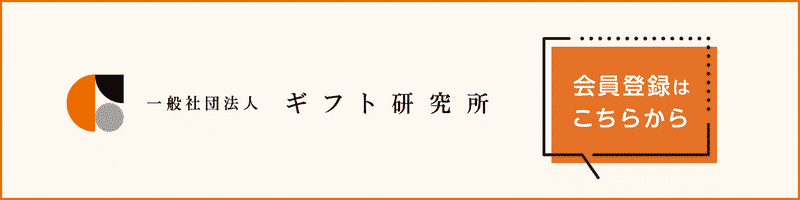【清水由起のデータから読み解くギフト事情 vol.10】誕生から35年超、進化を遂げ続ける「カタログギフト」
ミスマッチを解消する画期的なギフト商品として誕生
カタログギフトが誕生したのは1987年と言われる。贈る人が商品を選ぶのではなく、贈られた人がカタログの中から自分で商品を選ぶという“逆転の発想”から生まれたこのギフトは、贈られた側の好みに合わないといった、贈る側と贈られる側のミスマッチを解消する画期的な商品として広まった。特に、食器類が定番だった結婚式の引出物において、重くてかさばる上に2次会、3次会へと持ち歩く煩わしさを解消するアイテムとして一気に広まり、その後、仏事のお返しなど、フォーマルギフトを中心に利用が拡大していった。
そして、この35年超の間に、時代のニーズやデジタル技術の発展を取り入れながら、カタログギフトは驚くほどに進化を遂げている。

(株)矢野経済研究所調べ
デジタル化で利用シーンが急拡大、もはや特需の様相も
第一の進化は、2000年前後に掲載商品に「食品」が登場したこと。1990年代のカタログ掲載商品は陶器、漆器、繊維製品などの日用雑貨がほとんどであったが、食品が登場したことで中元・歳暮用途としても活用され始め、一躍ギフトアイテムとしての認知が拡がった。贈られた側が選べる商品も、国内外のブランド品から肉、米、海産物、果物など各地の美味しい産直品まで、ありとあらゆるアイテムが揃うようになっている。また、温泉旅行やレストランでの食事、エステといった「コト」を贈る体験ギフトも充実している。10年ほど前からは、カタログ自体に個性を持たせ、和牛だけ、ワイン・日本酒だけ、メイドインジャパンのものだけ、スパ・エステだけを収録したカタログなど、「アイテム特化型カタログ」が増えている。
第二の進化は、WEB化である。従来の“紙”でできたカタログから、カード型カタログギフトへの移行が進んだ。紙のカタログでは誌面に限りがあるが、カード型の場合には、贈られた人がカードに記されている個別のID番号やパスワードを入力した上でWEB上から商品を選択するため、選べる商品の数やバリエーションが格段に増える。また、持ち運びの容易さも利点となり、特にブライダルのシーンで利用が進んだ。そこにはもはやカタログは存在しないため、選べるギフト、チョイス型ギフトと呼ぶほうが相応しくなっている。
第三の進化は、ポイント型の導入である。上記の「第二の進化」によってIDやパスワードで管理するシステムが構築されたことにより、ポイントを贈るというカードタイプのカタログギフトが開発された。ポイントの合算や分割も可能であるため、より高価なアイテムや複数アイテム、マイレージ等にも引換可能になり、贈られた人の自由度は格段に拡がっている。
そして第四の進化は、メールやSNSで贈ることができるカタログギフトの登場である。贈る手段のバリエーションの一つとして開発が進んでいたが、特にコロナ禍においては、非接触ギフトとしての優位性も加わり、消費者の市場認知が進んだ。
こうした目覚ましい進化により、現在では、出産・入学・就職のお祝い、誕生日や長寿のお祝い、企業の永年勤続の記念品や福利厚生、株主優待、ゴルフコンペの賞品、販売促進イベントの景品等、幅広い贈答シーンで利用されるようになっている。
特に昨今は自治体による住民への子育て支援や長寿祝いなども急速に拡がっていることで、カタログギフト業界は特需の様相を呈しているといっても過言ではない。
#大人の学び
#ギフト
#ギフト研究所
#矢野経済研究所
#ソーシャルギフト
~About us~
内田勝規のオンラインサロン
今後の活動予定と9月の振り返り
会員募集中!!
企画型共創コミュニティに参加しませんか?
会員同士一緒になってギフトの価値を創り出していく場です。