
UERUT開始記念イベント「Nature Positiveを森で”実践”するUERUTの取り組み」を開催しました

対面とオンラインのハイブリッド開催でした!
青葉組が新しく立ち上げた新サービス「UERUT」。森づくりの現場とダイレクトにつながる商品やサービスの提供を起点として、それぞれの立場から“植えるとどうなる?”を考え、理想の森づくりを目指していくサービスです。2024年12月4日、UERUTの開始を記念し、MIDORI.so NAGATACHOにて、UERUT FOUNDERローンチイベント「Nature Positiveを森で”実践”するUERUTの取り組み」を開催しました。

平日にも関わらず、当日は約30名が会場に。オンラインも含めると約70名もの方々が参加してくれました。今回は、UERUTの中でも企業向けサービスとなる「UERUT FOUNDER」の説明会を兼ねていたことから、会場にはネイチャーポジティブや生物多様性に配慮した森づくりに関心を寄せる、多種多様な企業の方々が集まっていました。
各企業のストーリーと自然資本の接点を見出すサービス「UERUT」
最初に、青葉組の取締役で、本イベントのモデレーターを務める中間康介から、青葉組の紹介となぜUERUTを始めたのかについて説明がありました。
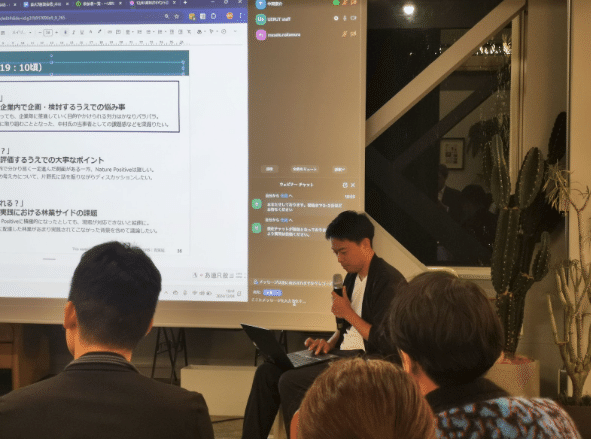
中間 企業と進める森林関連のプロジェクトは、これまでCSRの範疇で行なわれていました。それは、お互いにお互いのニーズがよくわかっていなかったからです。企業は森で何が実現できるかイメージできていなかったし、森づくりをする側も企業が何を求めているかがわかっていませんでした。
もちろんCSRもすごく大事な取り組みです。しかし、それだけだと自然資本に対するインパクトはなかなか大きくなっていきません。そこで僕らは、各企業のストーリーと自然資本の接点を見出すことがとても大切だと考えました。生物多様性に配慮した森づくり(自然資本)が企業価値につながることがわかれば、寄付ではなく投資してもらうことが可能になる。それを実現するサービスが「UERUT FOUNDER」なんです(「UERUT FOUNDER」の詳細はこちら)。
テーマトーク①「実際どうなのよ? ~Nature Positiveを企業内で企画・検討する上での悩み事」

青葉組のビジョンとUERUTの概要を共有したところで、パネルディスカッションに入りました。テーマは「企業価値に繋げる森づくりとは?」。パネリストは、自然エンジニアリング株式会社 取締役/EPCオペレーターの中村真佐人さん、独立研究者/造園ユニットveigの片野晃輔さん、そして株式会社GREEN FORESTERS(青葉組)代表の中井照大郎です。
ネイチャーポジティブを実践する企業担当者、企業にアドバイスしてきた科学者、そして実際に森づくりを手がける林業事業者という三者の視点から、ネイチャーポジティブの現在地を見つめ直す、活発なディスカッションが繰り広げられました。
モデレーターの中間が用意した問いは3つありました。一つはネイチャーポジティブを企業内で企画・検討する上での悩みごとについて。SDGsやカーボンオフセットといった取り組みが当たり前になっている今、次なるアクションとして注目されるのがネイチャーポジティブ(自然再興)の実践です。実際のところ、企業ではこの動きをどのように見ているのでしょうか。企業担当者である中村さんの悩みは、社内のコンセンサスづくりの難しさでした。
中村 企業で取り組むからには、内部でコンセンサスを取らないといけません。そのためには、なぜこれを選んだかというロジックが必要になります。でも、ネイチャーポジティブという概念そのものが新しく、調べれば調べるほど、すごくいろいろなアプローチがあって、どれをやったらいいかが悩ましいんですね。アプローチがありすぎる上にどれもが大事なことばかりで、なぜこれを選んだのかという説明づけが難しい。先行しているカーボンオフセットの取り組みは、すでにいろいろな情報があって教えてくれる人もたくさんいますが、ネイチャーポジティブについては世の中全体でも、我々の組織内でも、リソースが圧倒的に足りていないと感じています。
片野 やはりみなさん、最初はネイチャーポジティブの全体像を知るために専門家に相談しようと考えると思います。でも、ネイチャーポジティブに関しては全体を俯瞰して実際どうなのかを整理する、つまりメタ解析をしている研究者がほとんどいません。今は、そういう人を見つけていく段階です。これまで生態系に関する研究をしていた人たちが、社会要請に合わせてネイチャーポジティブの知見を広げている最中なので、まずはいち早く相談できる人を見つけられるかどうかが大切になってくると思います。
中村 社内で勉強してやろうかという話もあったのですが、それぞれの仕事もある中で、なかなか実現できていません。ただ、自分たちでやるのも一つのソリューションではないかという気はしています。
片野 まさに、TNFDに対応しないと株価に影響が出る大企業などは、今、大学で生態系に関する研究をしていた人などを、専門人材としてどんどん採用しています。忙しい大学の研究者に依頼するよりも、企業内に研究者を抱え、腰を据えて取り組んでもらったほうが成果につながると考えているんですね。今後は企業研究者がますます求められていくのではないかと思います。
テーマトーク②「本当にいい森って? ~Nature Positiveを評価する上での大事なポイント~」

次に、ネイチャーポジティブを評価する上でのポイントについて、研究者である片野さんにアドバイスをいただく形で話が展開していきました。現在、注目を集めるTNFDの現状についても報告がありました。
片野 TNFDレポートは、きちんと出さないと株式の評価を下げますよ、というものです。実は、そこまで強制力をもった枠組みはこれまでありませんでした。そこが一気に注目された要因なんですが、その結果、利益になっているとは言わないまでも、ちゃんとリスクの回避にはつながっているんですね。そこで今は、大企業がお手本として進めているというのが現状です。
中村 TNFDレポートは実際のところ、どのぐらい社会に広まっているのでしょうか。
片野 僕は中小企業からもお試しでやってみたいと相談を受けることがあります。中小企業がそこまでやる見返りがあるかというと、実際の受益まではまだ難しいと思います。見返りがあるとすれば、PRがうまくできるかどうかにかかっている。ただし、事業のスケールが小さいと自然資本との接点もすぐに見つかるので、事業をスケールさせる前から準備しておくのは有効かもしれません。今後の展開次第では、事業が大きくなる前にやっておいてよかったということにもなりえる気がしています。
ネイチャーポジティブやTNFDについては、まだわからないことも多く、企業も試行錯誤中のようです。「環境問題に関する取り組みはまだ70年程度しかやってきていないから、森林とどう付き合っていけばいいかが見えてくるのはこれからです」と片野さん。そのためにも、企業価値と自然資本の紐付けやTNFDの活用はカギになると話していました。
その一方で、企業価値と自然資本の接点は無限に変数があるからこそ、1社ですべてを回収することは不可能に近いとも話します。
片野 それ自体は仕方がないことなので、その企業がもつ既存の良さを活かして、何をやるか絞っていくことが大切です。イマジナリーな議論だけだと、全部やらなければいけないように思ってしまいがちなので、具体的なサイト(用地)を設けてほしいですね。例えば、サイトをもっていない企業が青葉組にお願いして委託事業として森づくりをやってもらう。TNFDレポートは、総体として環境プロジェクトをやっていることを評価する枠組みなので、全部を自社でやらなくてもいいのです。
テーマトーク③「林業業界でどうやれる? ~Nature Positiveの実践における林業サイドの課題~」

さらに中井から、ネイチャーポジティブ実践における林業サイドの課題について説明がありました。補助金をベースに成り立つ林業は、単価が一律で決められているため、売り上げを伸ばすためには作業効率を上げるしか方法がありません。しかしそれでは生物多様性に溢れる森を手間暇かけてつくることはできず、売り上げを伸ばすにも限界が見えています。その結果、給料はなかなか上げられず、将来への不安から辞めていく林業従事者も多いのだそうです。
中井 一例ですが、作業効率重視になってしまうと、生物多様性に関する専門的な知識をもっている社員がいても、その知識が活用される場がないんですね。僕らは、むしろそういう人たちが評価される現場でありたい。ネイチャーポジティブを実践しようとしている企業のみなさんとそんな世界を一緒につくれないだろうかと考えています。
その上で、こうした取り組みを広げていくには「面白く、楽しくやっていく」ことも大切だと中井は言います。これには中村さんも片野さんも大きくうなずいていました。
中井 リスク回避という文脈で生物多様性やネイチャーポジティブに取り組んでも、あまり面白くなっていきません。なにより、やらされてる感があると広まっていかないのではないかと思っています。だからこそ、今日のイベントは「ネイチャーポジティブという大きなうねりを起こしていくぞ」という強い思いをもったイノベーターの集まりという理解でやらせていただいております!
中村 産業は、地域や人と結び付けていかないと面白くなっていかないし、本当の意味で広がっていきません。やはりネイチャーポジティブはお金のためだけにやるのではなく、我々自身が仕事をしていく中で、真剣に取り組むことが大切だと思います。お金は維持していくために必要なだけで、それが目的になったらうまくいかない。だからこそ、いろいろな産業を組み合わせてみんなで進めていきたいとすごく思いました。

片野 楽しくないと続かないというのは、すべてそうだと思います。今回は林業がキーワードですが、そこをひとつの生態系として見ると、林業という利益の取り方があると同時に、まだ可視化されてない森の価値も見えてくる。例えば、これまでの林業であれば下刈りしてしまう5年生の細い紅葉は、庭で使えるので1本2万円で売れたりします。複数の職能の人が同時にお金を稼げるところが、生態系を事業として扱う面白さであり、楽しさだと思います。
中間 まさに森づくりの設計を時間軸で見ていくと、そういうことがよくわかります。5年目は木の実がとれて、10年目は花が咲き、50年後には木材が取れるというふうに、多面的な価値があることが見えてくるんです。そうすると価値が訴求しやすいという話をしたのを思い出しました。
ここにいる人々は、思いを同じくする仲間である。中井の言葉を皮切りに、そんな連帯感が会場を包み込みました。
話が尽きない懇親会

この時点で、すでに時間はだいぶオーバー。いったんパネルディスカッションは終了とし、中間から「UERUT FOUNDER」の具体的な内容について説明がありました。ネイチャーポジティブを実践する上での課題や悩み、押さえるべきポイントを聞いたあとだと「UERUT FOUNDER」がネイチャーポジティブ実践に向けた最初の一歩としていかに入りやすく、あらゆる関係者の受益となりえるかがよくわかりました。
最後に質疑応答の時間も設けられました。次々と手が挙がり、みなさんが青葉組の活動に共感してくれていること、「UERUT FOUNDER」に強い関心をもっていることが伝わってきました。
新しい概念であるネイチャーポジティブをどう実践していくか。そのことを真剣に考え、取り組もうとしている人たちが、この場には集まっていました。その後の懇親会も、会場を利用できるギリギリまで続きました。それだけ多くの人がこのテーマに強い関心をもち、すでに実践しているか、実践しようとしているということなのでしょう。UERUTが、こうしたコミュニティの楽しくも力強いコアとなっていく。そんな手応えと周囲の期待が確かに感じられたイベントでした。
◾️UERUTからお知らせ
(1)UERUT FOUNDERに興味をお持ちの方へ
UERUT FOUNDERにご興味を持ってくださった方は問い合わせページよりご連絡ください。オンラインにてサービスや参加方法についてご紹介をします。
問い合わせ窓口 こちらです!
(2)クラウドファンディングのお知らせ
現在UERUTでは、新潟の冬仕事を作るブランドを立ち上げています。
現在1st目標金額は達成しましたが、ネクストゴール180万円に向けて頑張っています。ぜひ、木工が好きな方、新潟を応援したい方、UERUTに参加したい方は、ページをご確認いただき、応援をよろしくお願いします!

