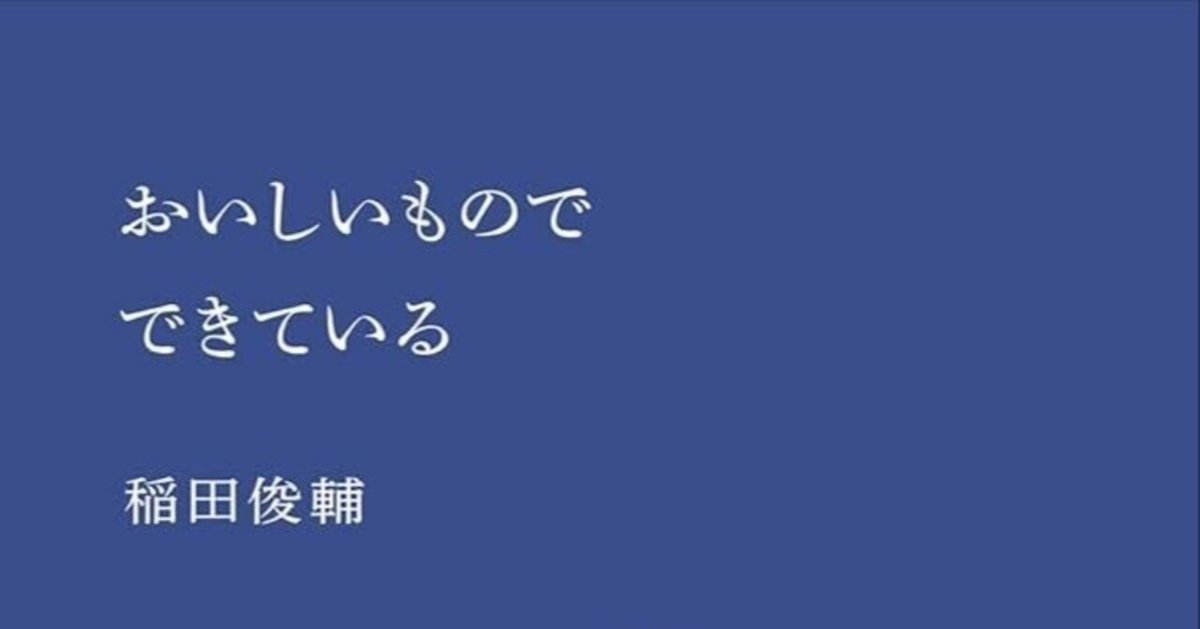
読書メモ・稲田俊輔『おいしいものでできている』(リトルモア、2021年)
平野紗季子さんの『ショートケーキは背中から』(新潮社、2024年)を読んで、というか、平野さんの「味な副音声」というPodcast番組のアーカイブを聴いていて、そういえばと思い出したことがあった。
以前に友人から、自分が読み終わって、しかも面白い本だということで、稲田俊輔さんの『おいしいものでできている』を譲ってくれたことがあった。そのときは料理についてのエッセイにあまり馴染みがなかったので、そのまま本棚におさめたのだが、平野さんのPodcast番組の中で稲田俊輔さんとの対談の回を聴いて、そういえば、と、稲田俊輔さんの本を本棚から取り出した。ようやく、この本を読むタイミングが来たのである。
「食」に関する仕事をされている稲田俊輔さんのエッセイ集。はじめて稲田さんの世界にふれたが、じっくり読んでいくとこれが自分にはなかなか心地よい。著者の「食」のエッセイの特徴は、自身の子どもの頃からの「食」の体験が現在の料理観を形成しているというスタンスで一貫していることである。しかもその体験が、私自身の体験とも妙に重なっているから不思議である。たとえば、「一九六五年のアルデンテ」というエッセイでは、「ミートソーススパゲッティ」についての思い出を語っている。
「僕にとって懐かしいスパゲッティはなんと言っても『ミートソーススパゲッティ』です。最近のイタリアンレストランでは『ボロネーゼ』という名前が冠され、フライパンでチーズとともに麺と褐色のソースがしっかり一体化されたものがすでに主流ですが、ここでいうミートソースはもちろんそれではありません(中略)。
スパゲッティには、麺同士がくっつかないようにという配慮もあって少量のバターがあらかじめ塗されていました。フォークで大きく面を巻き取ると、ミートソースの特徴的な香りを押しのけるように先ずはそのバターの香りがふわりと立ち上がります(後略)」
このあたりの描写は、私の子どもの頃のミートソーススパゲッティについての思い出を喚起するのに十分なものである。共有体験といってもいいかもしれない。
そのあと、伊丹十三さんが1965年に出した『ヨーロッパ退屈日記』に話題が展開していくのだが、この本もむかし読んだぞ。この本もまた、食に関するエッセイが中心だったと記憶する。言ってみれば平野さんや稲田さんのエッセイは、伊丹さんのエッセイの系譜上に位置づけられるのではないか、と勝手な想像が広がる。
「カツレツ贔屓」というエッセイでは、子どもの頃からの夢だった「洋食屋」さんにデビューした思い出が語られる。著者が学生時代を過ごした京都は、実はこの国でも有数の洋食のメッカである。そんな学生街の「ざっかけない洋食屋」を著者は存分に楽しむのである。
私もまた「街の洋食屋さん」には子どもの頃から憧れていた。大人になってから、出張で京都を訪れるたびに、昼食場所として「ざっかけない洋食屋」を探す自分がいる。それはむかしからの憧れに裏打ちされた行動である。
なぜこんなに、著者の思い出が私の思い出と重なるのか。失礼ながら著者の生年を調べてみると、著者は私の2歳ほど下のようだった。つまり同世代である。どうりで共感する思い出ばかりなわけだ。
平野さんのエッセイは「岸本佐知子さん風味」と書いたが、それになぞらえると、稲田さんのエッセイは「酒井順子さん風味」ではないだろうか。もちろんこれは私の「味覚」に過ぎないので、異論は認める。
最近、あまり食欲がなく、食が細くなったなあと実感するようになってきたのだが、この本を読んだら急に空腹感が増してきた。食に関するエッセイを読むと食欲が喚起される。手始めに、この本の中で紹介されている、千葉県のご当地ラーメンである竹岡式ラーメンを食べることにする。
