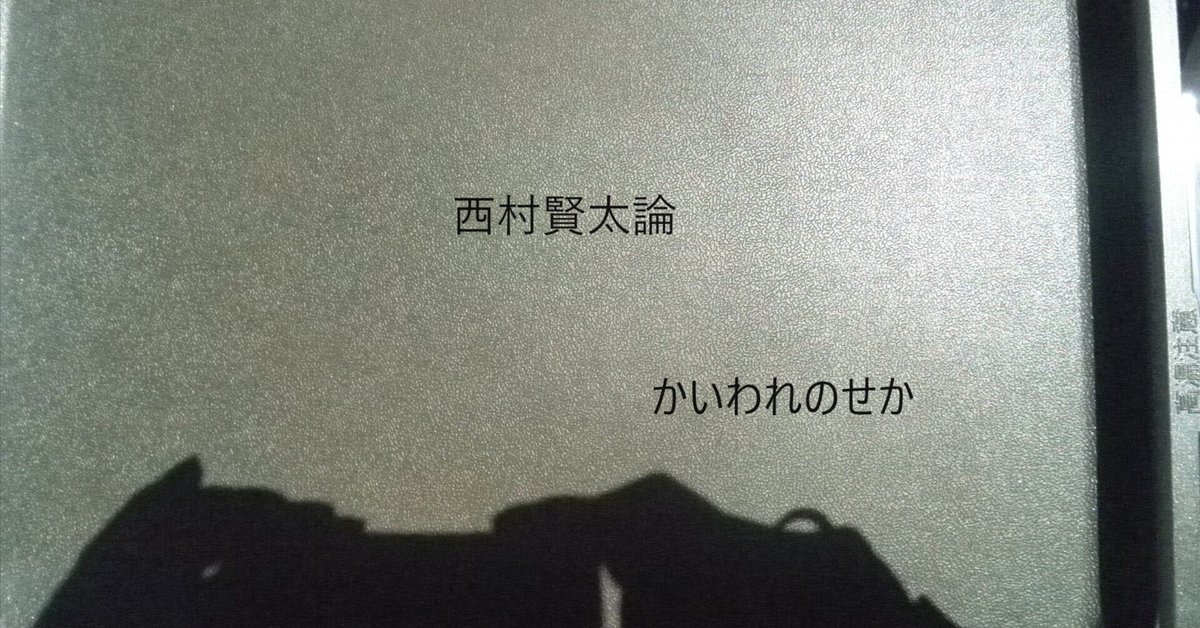
『西村賢太論』―その精緻を極めた文章の中核において―
『西村賢太論』―その精緻を極めた文章の中核において―
『はじめに』
今回、西村賢太論を、発表するに至って、小説家になろうで書き溜めていたものを、随分と使用している。初めに、【序説】として、当時、西村賢太が急死した時の心情を綴った、『追悼、西村賢太』を添えた。
あと、『『芝公園六角堂跡』論・・・西村賢太のユーモアの極み』から、『終わりゆく死への道ー最晩年の西村賢太と明暗ー』、までは、既出の文章である。
今回の書下ろしは、『西村賢太論・・・黒木渚さんも面白がる『小銭をかぞえる』について』、『西村賢太論・・・『雨滴は続く』の真意』、『西村賢太論・・・その異常的記憶力』、『おわりに』、の4点である。長々と論を書いて残して行こうと思って居たが、『雨滴は続く』の文庫本が出たため、今がタイミングかと思われ、noteに、発表することにした。
目次
【序説】
『追悼、西村賢太』
【西村賢太論】
『『芝公園六角堂跡』論・・・西村賢太のユーモアの極み』
『西村賢太・・・試論』
『西村賢太と吉田一郎不可触世界の関連性』
『西村賢太と堕落論』
『西村賢太論…その文体の基軸』
『終わりゆく死への道ー最晩年の西村賢太と明暗ー』
『西村賢太論・・・黒木渚さんも面白がる『小銭をかぞえる』について』
『西村賢太論・・・『雨滴は続く』の真意』
『西村賢太論・・・その異常的記憶力』
『おわりに』
【序説】
『追悼、西村賢太』
㈠
今日、西村賢太の訃報を知った。近年の芥川賞作家の中でも、精緻を極めた文体は、突出していたと思う。西村賢太を、何かの賞の、選考委員に選ばなかったという、現在の日本にも、責任はあるだろう。難解な言葉が、また、消失していくという、危機感を感じるのも、当然である。
㈡
一般に、私小説家と言われても、小説を創造することの困難は、小説家なら、誰しもがあるだろうと思われる。西村賢太に、文章を生み出す苦しみというものが、有ったか無かったかは分からないが、逆に、生みの苦しみがなかったなら、小説家としては、適任であっただろう。
㈢
『小銭をかぞえる』が『文学界』に掲載された時、確かに、西村賢太を知ったきっかけが、有ったと記憶しているが、藤澤清造を知るきっかけになったのも、西村賢太が、芥川賞を取ったからの、出来事だった。非常に感謝の念を持っているし、本物の小説家が、消えたことが、悔やまれてならない。
【西村賢太論】
『『芝公園六角堂跡』論・・・西村賢太のユーモアの極み』
㈠
西村賢太が急死して、しばらくの時が経った。今、自分は、自分が当初から持っていた、西村賢太の小説に、目を通しながら、自分が当初から持っていなかった、西村賢太の単行本や文庫本の、収集に、時を費やしている。非常に、有意義な日々なのである。
㈡
その中でも、自分が持っていなかった、『芝公園六角堂跡』、という文庫本の、表題、『芝公園六角堂跡』を読んで、今更ながら、西村賢太のユーモアの極みに、心酔している状況である。『苦役列車』とは、随分異なる、自意識の真骨頂の様な内容で、述べた様に、ユーモアの極みが、随所に詰まっている。
㈢
西村賢太の師は、藤澤清造だが、自分の師は、と、問われれば、自分は恐らく、埴谷雄高、と答えるだろう。自分の人生を救ってくれた小説家には、畏敬の念を抱くのは、当然である。『芝公園六角堂跡』を、あの世の藤澤清造が読んだら、恐らく、大きく笑って、西村賢太をあの世で、迎え入れているだろう。師弟の間の酒は、美味いだろうなと、空想に浸った、『芝公園六角堂跡』の読後であった。
『西村賢太・・・試論』
㈠
西村賢太が、『苦役列車』で、芥川賞を取った時のころを、今でも鮮明に覚えている。前科があったことは、知っていたし、詰まる所、その様な境遇の人でも、文学で評価されれば、やっていけるということが、証明されたことが、何より嬉しかった。これは、まさに、尊敬していると言うことなのである。
㈡
どの様な生き方をしてきた人間にでも、文学においては、皆、自由で平等だということの、体現者として、多くの人々に、光が当たり、人々を救ったということなのである。それにしても、西村賢太は、その私小説の内容で、判断されがちだが、近年稀に見る、素晴らしい文章の書き手だった。
㈢
文章の脈絡の自然さというものは、我々には遠く及ばない地平で、何と言えば良いのか、、単純だが、文章が上手いのである。間の取り方、会話文の流暢さ、重要な言葉の位置、など、多くの点で、揃っているのである。どれだけ、文学を続けていても、届かない程の、天才の位置に、西村賢太は居たと言える。
㈣
『芝公園六角堂跡』では、自分を、「ゴキブリじみた」と、表現し、自己をおとしめることで、笑いを誘っている。この様に、自己を高貴なものとはせずに、私小説が書けることは、本当はものすごく広い心の持ち主でないと、出来ないことなのである。
㈤
また、藤澤清造への崇拝の念も、しっかりと、読み手に伝わってくる。西村賢太の愛読者ならば、自ずと、藤澤清造への小説への好奇心が、芽生えるだろう。これは、西村賢太の才能なくして、藤澤清造なし、と言った状況にまで至る奇跡である。
㈥
現代の文壇で廃れ掛けていた、私小説を復活させた西村賢太の功績は大きい。自身が、どこまで自分の才能に気付いていたかは、急死した今、定かではないが、自分の才能を自認し、適度に転がす様な形で、もっと長生きして、私小説を書き続けて貰いたかった。今でも、その急死が、悔やまれるのである。
『西村賢太と吉田一郎不可触世界の関連性』
㈠
何から書き始めていけば、適切だろうか。西村賢太がこの世を去って、書物を集める日々だが、近々、数冊、手に入る。貴重な日本文学史の、私小説として、死ぬ間際までの、声、を記録として持っていたい。過ぎ去った過去を追うように、その影を見ている。
㈡
ところで、『暗渠の宿』で、野間文芸新人賞を受賞している、西村賢太だが、私見として、音楽界で、良く似ているな、と思うのが、ZAZEN BOYSの元ベーシスト、吉田一郎(現在ソロで、吉田一郎不可触世界、名で、活動中)である。『暗渠』という曲があるが、聴き心地の良い、名曲である。『暗渠の宿』と『暗渠』、偶然だろうか、と思う訳である。
㈢
無論、偶然であっても良い。吉田一郎不可触世界の曲にも、名曲は多々ある。アルバム、『あぱんだ』も、『えぴせし』も、捨て曲のない、良いアルバムだ。自分はしかし、曲を聴いていると、どうしても、西村賢太を思い出してしまう。是非、西村賢太を読んで、吉田一郎不可触世界を聴いてみて貰いたい。関連性が、内部に表出するはずである。
人間の生活の、泥に似た、人間の体温や汚れが、生き生きと表現された、2人の芸術家が、見えてくるだろう。
『西村賢太と堕落論』
㈠
坂口安吾の『堕落論』は、単に堕落について書いている、ということではなく、第二次世界大戦後の日本の人々が、戦争に負けたから堕落するのではなく、人間だから堕ちるのだ、ということだったと書いていたと、以前どこかで述べたと思う。実に自然な、人間の本質を、言い当てている様に思われる。
㈡
ところで、西村賢太の話になるが、藤澤清造に触れ、堕落を同化して、堕落していた西村賢太も、人間だからどこまでも堕ちることを、表現している。そしてまた、その堕落の最悪度を表現したという意味でも、人間の本質を実態した、まさに、堕落私小説家でもあったと、今になって思うのだ。
㈢
堕落することは、一見良くないことのように思われがちだが、それは一種の人間的成長の様にも受け取れる。西村賢太は、恐らく、堕ちるところまで堕ちた。だからこそ、多くの堕落した人間の共感を得たんだと思う。西村賢太と堕落論、これは、切っても切り離せない、問題ではないだろうか。
『西村賢太論…その文体の基軸』
㈠
西村賢太の書物を、急死してからというもの、ずっと集めていた。無論、その師匠である、藤澤清造のものも、収集してはいたのだ。しかし、藤澤清造の、『根津権現裏』、『藤澤清造短篇集』、『藤澤清造 負の小説集』、どれを読んでも、西村賢太の文体の基軸となっている文体は、見つからなかった。
実に不思議だったのは、通常、歿後であっても、弟子足るものは、師から何かしらの文体の影響を受けるものだ、と思っていたので、拍子抜けしたのである。面白くないということではない、藤澤清造の小説は面白いし、西村賢太が好んだというのも、良くわかるのだ。
㈡
そうして、西村賢太の急死から、続々と特集が組まれ、最後の小説『雨滴は続く』も発売となり、西村賢太の影響は、大きく文壇に攪拌したとは思う。西村賢太の影響によって、藤澤清造が好まれ、藤澤清造の面白さによって、更に、西村賢太の小説が躍動する、この様な状況だった。
丁度、様々に小説や雑誌が発売されるなか、今年の6月13日に、『藤澤清造随筆集』という本が出て、自分もそれを予約していて、13日に届き、目を通したのだが、端的に言って、藤澤清造の『根津権現裏』、『藤澤清造短篇集』、『藤澤清造 負の小説集』、のどこにも見当たらなかった文体が、随所に見られた。
㈢
そうして、そこに、西村賢太の文体の基軸となる文体が、様々な箇所に、見られたのである。つまり、西村賢太の小説の文体の基軸となっていたものは、この、藤澤清造の随筆から学んだものだったのだろう。そういう風に思った。そしてまた、藤澤清造が、随筆において、これ程上手く筆を運べるということも、知ることになった。
藤澤清造の随筆集は、思うところ、『根津権現裏』、『藤澤清造短篇集』、『藤澤清造 負の小説集』の、どれよりも、自分にとっては面白かったし、敢えて言えば、芥川龍之介の、当時の様々な言動も沢山書いてあったので、一挙両得と言ったところだ。西村賢太、その文体の基軸は、藤澤清造の随筆集にあったと、考えて適切だと、今、思っている。
『終わりゆく死への道ー最晩年の西村賢太と明暗ー』
㈠
今回、長らく書いていなかった、西村賢太論を書くにあたって、今年の2月5日に、単行本で刊行された、『蝙蝠か燕か』によって、論を運ぼうと思った。初出は、2021年11月号の、「文學界」である。内容としては、最晩年の西村賢太の、心境小説的、私小説、と言ったところか。
この時まだ、西村賢太は、もうすぐに迫っていた自己の死への道のことなど、考えてもみなかっただろう。小説の内容も、まだまだ、これから、というー意思ー、が読解出来る。そして、この小説が、最晩年の小説だと、規定されることもまた、意識の他であっただろう。
㈡
一つ気になる文章が、『蝙蝠か燕か』には、看守出来る。小説、最後の、文章である。
彼は何がなし、(中略)、蝙蝠か燕かの形影を探した。(中略)あの"没後弟子道"の出発の日に、(中略)、あの日見たところの、群れから取り残された蝙蝠だか燕だかの黒点を頭の中で翻させる。『蝙蝠か燕か』/西村賢太
何か、自己意識を離れたものに、何かを望み託すような、自己忘却の影が、文章からは、見て取れる。
㈢
少し話は変わるが、学生時代、友人が没頭していた、夏目漱石の、『明暗』という小説を思い出した。自分は、しっかりとこの『明暗』を読んでいない。しかしに、タイトルからして、如何にも、自己の人生が明か暗に、分かれる、人生の分岐点を思わせるし、これも、夏目漱石の、最晩年(未完)作である。
人間は、歳を取れば取るほど、狭き道を歩くように、自己は考えている。そんな世界で、あたかも、自己の分岐点が、明暗として現れることが、極自然な様に思われてくるのは、もう、運命に抗えないことを知った時なのである。
㈣
話を元に戻すと、その西村賢太の『蝙蝠か燕か』の最終部分で見た、いや、正確には見ようとした、「蝙蝠だか燕だかの黒点」とは、自身の運命のそのものだったのではないだろうか。それをものの見事に、「翻させる」時、深く刻まれた、西村賢太自身の、一つの宿命を、感ぜずにはいられない。
つまりは、終わりゆく死への道、の一点だったのではないだろうか。自分には、長編で未完の小説、『雨滴は続く』よりも、この、『蝙蝠か燕か』のほうが、よっぽど、西村賢太らしい、最晩年の映像的文章に思われる。
㈤
芥川龍之介賞を取っている、西村賢太であるが、芥川というよりは、何か、志賀直哉の『暗夜行路』を思わせる、自己の暗く細々とした運命への道が、感せずにはいられない。無論、金持ちだった志賀直哉と、この貧乏の底辺に居た西村賢太を、多くの人は、対極に思うだろう。
しかし、金、というよりも、生き様の問題である。時にバイオレンスに満ちる行動暴言は、自分の道を、自分で決めて、全うするという、生き様のことである。誰に何と言われようと、進むべき道を、進めばこその、行動暴言である。
㈥
そもそもが、バイオレンスだの、行動暴言など、倫理に即して行わなければ良いものを、わざわざする、というのは、自分の気持ちに正直にならざるを得ない、という、倫理崩壊に即しているからだ。勿論、悪である。恐らく、己が己を欺くことへの嫌悪が、そうさせるのだろう。
『終わりゆく死への道ー最晩年の西村賢太と明暗ー』と題した、この文章だが、結句、最晩年の西村賢太は、明暗の暗のほうを、選んだと思って居る。しかし、西村賢太は、恐らく、敗者ではなく、勝者であろう。西村賢太の没後、文壇を、未だに、西村賢太は支配している。天国で、恐らく、明と、笑っているに違いない。
『西村賢太論・・・黒木渚さんも面白がる『小銭をかぞえる』について』
㈠
2008年、西村賢太は、『小銭をかぞえる』という小説で、第138回芥川賞候補になった。その頃から、評価は高かったと言える。勿論、それ以前に、『暗渠の宿』で第29回野間文芸新人賞受賞しているのも、見逃せない事実ではある。
そして後の、2011年に、『苦役列車』で、第144回芥川賞受賞することとなる。芥川賞の『苦役列車』は、受賞作だけあって、非常に面白いが、『小銭をかぞえる』の、候補の時点で、既に、芥川賞当確だったと自分は思って居る。
㈡
先日、youtubeの、黒木渚さんのラジオ番組、黒木渚の棘(毎週火曜日、21時から)で、黒木渚さんの、西村賢太の『小銭をかぞえる』が面白い、という発言があった。実際、タイトルも内容も、自分も読んだが、相当面白い。社会の底辺に生きる、最高の作品である。
つまり、面白いのだが、その文章に使われている言葉は、非常に難しい言葉が多いのも、西村賢太の特徴である。『苦役列車』で、初めて自分は西村賢太の小説を読んだが、芥川賞を受賞するだけの、知的な文章には圧倒された。そのあと、『小銭をかぞえる』や、『暗渠の宿』を読むこととなる。
㈢
そして、今、手元には、数えれば相当に多々あるという言葉が適切だろう、西村賢太の小説が、段ボールの中に丁寧に収納されている。勿論、借金をするまでに、生活がヤバくなったら、売ることになるだろうが、まず現在の状況を鑑みると、死ぬまで、保持して置けそうだ。
黒木渚さんが、『小銭をかぞえる』の、特にどの箇所を、特別に面白がったかは定かではないが、こうやって、黒木渚さんの発言に、西村賢太の名前が出ること自体、西村賢太の死後評価は高いと思って自然だろう。54歳で亡くなったが、西村賢太には、もっと長生きして、良作を書いて貰いたかった。
『西村賢太論・・・『雨滴は続く』の真意』
㈠
西村賢太の、文庫本最新作、『雨滴は続く』が発売となっている。単行本では既に出版されているが、自分は単行本を購入はしたが、ほとんど目を通していなかった。だから、『雨滴は続く』をしっかりと読むのは、今回が初めてなのである。
㈡
「最後、最長にして最高の遺作長編1000枚」、この様に帯には書かれている。重要な文庫本のため、2冊買っておいた。そして現在、読み始めているのだが、やはり面白い。自分の価値を自分で下げるという、滑稽なる笑い、西村賢太は、その笑いと、そうすることで、読者を獲得する術を、心得ているかに見える。
㈢
特別原稿を入れると、555ページ、現在、132ページまで、時間の合間を作って、読み終えたところだ。長編となると、自分は良く、投げ出してしまうことが多いが、『雨滴は続く』はとても面白いので、読み進めるのが容易い。
㈣
この面白いという言葉だが、西村賢太に言う場合、ストーリーが面白い、言葉遣いが面白い、世界観が面白い、などなど、様々に面白いと言う、複合的な面白さである。こんなに面白い小説が、未完であることが、悔しいくらいである。
㈤
そんな面白さの中で、119ページに、見過ごせない文章があった。
「いいものは必ず、真の鑑賞眼を備えた読み手によって細々ながらも読み継がれると云うのは、今更彼ごときが言うまでもないことだが、(以下略)」
という、正に名文である。実に正しいし、そうあって貰いたい、日本の文壇にも、と同調した。
㈥
『雨滴は続く』を完読していないので、まだ何とも言えないのだが、『雨滴は続く』の一つの真意であることは、確かだと思われる。これから読み進める楽しみと共に、明らかに西村賢太は、超常識的である節を、この名文に見たところだ。
『西村賢太論・・・その異常的記憶力』
㈠
西村賢太の死後、過去の西村賢太の単行本、文庫本、また、掲載雑誌などを、事細かに調べ、収集しまくった過去がある。今でも、それらを大切に保存しているし、未読の本もあるが、熟読した本もあり、或る種の家宝的位置にまで来ている。
㈡
とは言え、一読者の自分としても、それらの本が、藤澤清造との関連の中で描かれており、その勢いで、藤澤清造の本も、それなりに集めたし、読んだものだ。ただ、圧倒的に、西村賢太の本を、乱読した過去ではある。
㈢
ところで、現在、文庫本で販売されている、『雨滴は続く』を読んでいて、何やら、重要な、非常に重要なことに気が付いた。ほぼ私小説だ、と仮定しての話だが、西村賢太の記憶力についてである。小説に出て来る人物との会話や、動態した場所、また、自己歴史において、その記憶力は、異常である。
㈣
こんな台詞や会話の言葉一字一句を、ーそれも、不快だったことなどに対する、恨みの感情までもー、逃さずに覚えていて、それを文章化しているのである。こんなことは、並大抵の人間が出来る技ではないと思われる。
㈤
つまり、西村賢太の本の構造は、記憶力によって、成立しているのだと、思わずにはいられない。自己を中卒だと卑下している個所も多々あるが、記憶力だけで言ったら、正直、ハーバードでも行けるんじゃないかと、素直に思わされる小説群である。
㈥
『西村賢太論・・・その異常的記憶力』、と題したが、自分にとって、今更気付いた感が、自分の判断力の愚かさを思うが、単純に、西村賢太は面白いし、云いたかったのは、その、異常的記憶力の発見についてなのであった。
『おわりに』
一先ず、纏まった形で、『西村賢太論』が出せたことを、心中、嬉しく思って居る。自分は、西村賢太が芥川賞を取った時を、リアルタイムで観て居た。すごい作家が現れたと同時に、これは馬鹿にしている訳ではなく、本当にすごいという意味で、中卒の芥川賞作家というのが、心底嬉しかったのである。文學において、学歴など関係ないということ、どんな人でも希望を持って小説を書くことが出来ること、そのことを体現した人だった。私小説内で使用される言葉も、辞書が必要になる様な、難しい言葉が適切に、しかもユニークに描写されていることが、『西村賢太論』―その精緻を極めた文章の中核において―、という題名にした理由である。
昔書いたのだが、現在の本物の小説家は、川上未映子さん、故西村賢太さん、市川沙央さん、だとしたのも、西村賢太論を書く理由である。『雨滴は続く』に会った、文章をもう一度引用して置きたい。
「いいものは必ず、真の鑑賞眼を備えた読み手によって細々ながらも読み継がれると云うのは、今更彼ごときが言うまでもないことだが、(以下略)」/『雨滴は続く』
西村賢太の小説は、まさにこの文章に当て嵌まると思う訳である。本人はこの文章を書く時に、自分の小説もその範疇だという自負はあっただろうか。今でも、そのことが、自分を悩ませる。自己評価というものが、どういうものだったかを、生前、是非、語って貰いたかった。
『おわりに』、として、ここで筆を置くが、西村賢太さんが、天国で、幸せで有ることを、願うばかりである。
