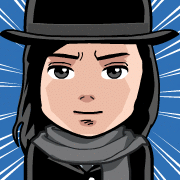中原中也の埋もれた名作詩を読み直す。その42/大島行葵丸にて

1935年4月に
中原中也は
文学雑誌「紀元」の同人であったよしみで
伊豆・大島への
1泊旅行に招待されます。
約4か月間
故郷山口で暮らし
東京の生活に戻って
まもなくのことでした。
「紀元」は、
大岡昇平が
「紀元」には坂口安吾も加わっていたが、坂口自身はすでに「竹藪の家」「黒谷村」などで新進作家としての位置を確立している。むしろその友人や後輩の集団なので、中原としてはやや身を落した感じである。小説家志願の集りで、詩人は異例なのだが、安原喜弘、富永次郎など、昔の「白痴群」同人を誘い、編集会議などによく出席していたようである。「その一週間」「亡弟」など小説風の断片は「紀元」のために書かれたのかも知れない。(中原中也全集解説)
――と記す同人誌のことです。
中原中也は
坂口安吾に誘われて
昭和8年(1933年)5月から「紀元」に参加し
この頃が中原の経歴のどん底(同上解説)とも大岡が記す
ピンチの時代に
発表の場の一つにしていました。
その「紀元」主催の
大島1泊旅行に招待され
珍しいことに
詩人が船に乗ったシーンが
歌われることになりました。
■
大島行葵丸にて
――夜十時の出帆
夜の海より僕(ぼか)唾(つば)吐いた
ポイ と音(おと)して唾とんでった
瞬間(しばし)浪間に唾白かったが
じきに忽(たちま)ち見えなくなった
観音岬に燈台はひかり
ぐるりぐるりと射光(ひかり)は廻(まわ)った
僕はゆるりと星空見上げた
急に吾子(こども)が思い出された
さだめし無事には暮らしちゃいようが
凡(およ)そ理性の判ずる限りで
無事でいるとは思ったけれど
それでいてさえ気になった
(一九三五・四・二四)
■
東京の竹芝桟橋あたりから出発したのでしょうか。
夜10時に出帆した
東海汽船の船の甲板から
暗闇の海へ
つばを吐くとポイっと音がして
少しの間、つばは波間に漂い
白いかたまりを見せていたけど
すぐに消えてなくなって
観音崎灯台の明かりが
ぐるぐる回っているのが見え
夜空は満面の星だった
ゆっくりと星空を見ていると
急に赤ん坊のことが思い出され
無事に暮らしているだろうかと
目一杯理性的に考えて
無事で暮らしているだろうと思ったのだけれど
それにしても気になって仕方なかったという
内容の詩です。
吾子(こども)は
前年10月18日に誕生した
長男文也のこと。
□
昭和10年(1935年)の年譜に
「3月、長門峡に行く。帰りの汽車で吐血。」とあり、
この詩を作った頃にも
詩人の体調は
芳しいものではなかったことが推測されます。