
『大鞠家殺人事件』(芦辺 拓)はいかに生まれたのか【著者×担当編集者】アフタートーク 第5回
対談=芦辺 拓(作家)× 古市怜子(東京創元社)
聞き手・構成=円堂都司昭

※対談はソーシャルディスタンスを守り、マスクをつけて行いました。
やがて大阪大空襲に見舞われる激動の時代を背景に、船場の商家の惨劇を描いた芦辺拓『大鞠家殺人事件』は、第75回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門と第22回本格ミステリ大賞小説部門を受賞した。傑作は、いかに生まれたのか。長きにわたりタッグを組んできた二人に話を聞いた。また、著者を光文社で担当してきた鈴木一人も参加した。
「これは本格ミステリになります」
――古市さんは、いつから芦辺さんを担当しているんですか。
古市怜子 私が東京創元社へ入社した二〇〇四年からなので、十八年間になります。
芦辺 拓 僕が、大阪から東京へ移る直前でした。それ以来、ずっと担当してもらっています。書籍では『少年は探偵を夢見る 森江春策クロニクル』(二〇〇六年。文庫化で『名探偵・森江春策』に改題)が最初。デビュー十五周年で三十冊目の本だったんですが、刊行時期のことで怒ってしまって、古市さんを泣かせてしまった。
古市 一からの本作りはその時がほぼ初めてで、ご迷惑をかけてしまいました。それ以前に、アンソロジー『あなたが名探偵』(二〇〇五年)に収録された「読者よ欺かれておくれ」という犯人当てを担当して、原書房さんから出た『真説ルパン対ホームズ 名探偵博覧会』(二〇〇〇年)の文庫化(改題で『真説ルパン対ホームズ 名探偵博覧会I』二〇〇五年)もやらせていただきました。
――その後、芦辺さんが東京創元社から刊行したのは、『綺想宮殺人事件』(二〇一〇年)、『スチームオペラ 蒸気都市探偵譚』(二〇一二年)、『ダブル・ミステリ 月琴亭の殺人/ノンシリアル・キラー』(二〇一六年)……。
芦辺 無茶な話ばかり持っていって、古市さんにどう納得してもらったのか謎ですが(笑)、どれもすんなり決まった記憶があります。
古市 例えば、スチームパンク×本格ミステリの『スチームオペラ』は、SFを出していない版元なら「マーケット的にうちにあわない」と判断されたかもしれません。でも、当社のSF読者はミステリにも乗り入れる形で読んでいる方が多いし、なによりも物語のネタが面白かった。女性を主人公に書くという芦辺さんにはあまりなかった試みでしたが、『彼女らは雪の迷宮に』(二〇〇八年。祥伝社)で女性を書く芦辺さんの筆が乗っているなと思ったので、女の子を語り手にしませんか、とお話ししたことを覚えています。
芦辺 光文社の鈴木さんには「芦辺さんに女は書けない。ダメだわ」と言われたけど(笑)。
鈴木一人 芦辺さんには女性を書いてもらおうと思っていないので(笑)。
古市 真っ向からの対決(笑)。
芦辺 僕にはずるい計算があって、書きたいものがいっぱいあっても普通なら許してもらえないところを、「これは本格ミステリになります」と言って許してもらう(笑)。
古市 全く疑いもしない(笑)。そこは本格ミステリになると信頼しているからです。
――二人の打ちあわせの基本パターンみたいなことはあるんですか。
古市 たいていお仕事をしている時に「こんなのが書きたい」と話をうかがうので、次はそれでとなることが多いです。今の作品から次の作品へと絶え間なく話している感じ。
芦辺 古市さんも鈴木さんも原書房の石毛力哉さんもそうだけど、すぐに話が通じてポンポンとアイデアを投げてくれる。たまに違う版元の編集者と仕事して、しかもミステリ畑じゃなかったりすると、いかに不自由か(笑)。「少年少女の主人公は売れないです」、「この時代が舞台だとダメ」とかいわれ、自分が普段甘やかされていると知るわけです。
鈴木 いいように言ってくれていますけど、僕らだってダメ出ししていますよ(笑)。
古市 私はけっこうなんでも、はい、はいと言っているかもしれない(笑)。はっきりダメと言ったのは伝奇チャンバラくらいですね。
芦辺 今、某社で書いています。伝奇チャンバラ的世界観を応用した本格ミステリだったら鈴木さんか古市さんとやるんですが。

スタンドアローンな作品として
――『大鞠家殺人事件』の構想はどこから。
古市 たしか、芦辺さんからお母様のご両親が飲食店を経営されていた話をうかがって、『けったいな人びと』(一九七三年放送のNHKドラマ)みたいなものを書きたいという話につながった。
芦辺 僕はモダニズムの東京・大阪が好きで書いてきましたけど、物語的原点としては花登筺的な暗く因習に満ちた大阪の商家とかコメディの大阪、上方落語の大阪もある。でも、そちらは書いてこなかったし、他の大阪在住ミステリ作家もあまり書いていない。その種のものを書きたかったのと、ちゃんとしたお屋敷ミステリをやろうというのがありました。横溝正史なら『三つ首塔』とか、村のなかで展開する『八つ墓村』にしても物語がダイナミックに動く。ページターナー的でその場所が変化していくミステリをやりたいというのは、鈴木さんと組んだ『千一夜の館の殺人』(二〇〇六年)で一度実現しましたが、もっとじっくりお屋敷ものをやるとして自分が書けるのは大阪の商家かなと思いました。
これも鈴木さん担当で「小説宝石」(二〇〇九年十二月号)に書いた「雨の午後の殺人喜劇」に『大鞠家殺人事件』の大鞠美禰子は既に登場していた。短編集『少女探偵は帝都を駆ける』(二〇〇九年)の表題作に出てくる中久世美禰子が大鞠家に嫁いで大鞠美禰子となったのだから、十数年前からいるキャラクター。それで『大鞠家殺人事件』のタイトルは早い段階から決まっていましたが、当初は戦後の設定で考えていました。横溝の『犬神家の一族』や『悪魔が来りて笛を吹く』のようにいろいろシステムが崩壊する戦後の時期に格式を保とうとするなかで起こる殺人事件を想定していたんです。没落した家に畑違いの軍人の家から美禰子が嫁いでくる。そんな、大阪の料亭から伊豆・熱川の旅館へ嫁にくる花登筺『細うで繁盛記』的な設定を考えていました。ところが調べてみると、船場の伝統的な商家で戦後に焼け残ったところはほとんどない。また、商家のシステム自体が戦前にすでに崩壊していた。それで時代を移しました。
古市 最初は戦後という組み立てでお話をうかがっていたので、谷崎潤一郎『細雪』と近くて読者もイメージしやすいと思ったんですが、戦前・戦中を挟むなら戦争、大空襲が入ってくる。それなら、歴史を描くという意味がより伝わりやすいだろうし、時代設定の変更に積極的に賛成した記憶があります。
――『大鞠家殺人事件』の「あとがき――あるいは好事家のためのノート」にも書かれていますが、古市さんからは、スタンドアローンな作品として森江春策はじめ既存キャラクターを一切出さず、他のシリーズとも接続させないという提案をされたとか。
古市 はい。現実の歴史と結びついた芦辺作品という点では、『時の誘拐』(一九九六年)などの「時」シリーズがありますけど、他のシリーズと接続しているとイメージを引きずってしまう。せっかく船場というある種の異空間を作ってもらうのだから、読者に没入してもらうためにスタンドアローンでとお願いしました。
――芦辺さんの名探偵・森江春策は、様々な形でいろんな世界に現れる、ある意味で神出鬼没の存在ですが、今回は封印したわけですね。
芦辺 森江春策が最終的に聞き役になる構想もあったんですが。スタンドアローンの提案をされた時、はい、はいと聞いておいて、結局、過去のキャストを数人出しました(笑)。『細うで繁盛記』でも主人公が熱川の温泉でいびられ苦労すると大阪から応援が駆けつけた。それと同じようなことです。うちの細君には『大鞠家殺人事件』の嫁いびりは「手ぬるい。全然いじめられてない」と言われましたが(笑)。まあ、こういう人だとよくわかっている芦辺劇団・殺人新喜劇のキャラクターは使いやすいということもあり、応援がきたのはご勘弁願いたい。ただ、船場という僕にとっては未知の世界で、大鞠家の周辺に医者の浪渕先生や車夫の源さんなどが出てきて新しい人間関係を作っていく過程は楽しかったですね。
古市 提案のポイントは、謎解き役が「いつもの人」になるのを避けていただきたいということでした。先の読めなさみたいなものが、御存じの名探偵がいる安心感で損なわれる部分がある。その意味で終盤になって探偵が現れることは気にしませんと申し上げました。
芦辺 ただし、登場人物表には名前がない。後半に出てきて、僕にとってはお馴染みさんだけど、多くの読者には初対面のように感じられる人。
古市 外部の目がなければ解けない謎ですし、一種の安楽椅子探偵だからこそ犯人を名指しできる。外部からきたことを強調してもらったので、そこは平仄があうと思います。
芦辺 空襲ですべてがなくなり現場検証もできない焼野原で推理するのが、一つのテーマです。建物も人もなくなったなかでなにが起きたかを想像する、いわば究極の形。つまり、それは探偵小説を外部から読む読者の立場かもしれないと思いながら書きました。
――『大鞠家殺人事件』は「ミステリーズ!」二〇二〇年八月号からの連載途中で同誌が休刊(二〇二一年二月号)。それから後半が書下ろされ、昨年十月に書籍が刊行されました。時代考証も必要な内容でしたし、いろいろ苦労があったのでは。
古市 連載初回は、芦辺さんは大変だったはず。どんな土地か説明が必要ですし、船場言葉もある。人の呼び方に特徴があって「イトさん」「ごりょんさん」「あにぼん」とか。
芦辺 船場の商家ものをやると言いながら、自分がなにも知らないことに締切りが近づいて気づいたんです。まず、重要なのは、大鞠家が何の商売をしているか。ありがちな糸問屋や布問屋よりも個性が欲しかったから困ってしまった。あとがきにも書きましたが、僕が大阪時代からお世話になっている建築史家の橋爪紳也先生に相談したら、メールで空襲地図から当時の婿入りのやり方とか大量に資料を送ってくださった。
ミステリ的に面白いのは薬屋だけど、「明智小五郎対金田一耕助」(二〇〇二年)で使っていた。それで、僕が大好きな宮武外骨の明治時代の『滑稽新聞』を復刻版で読んでいたら、目立つのが化粧品のパロディ広告。実際あった「人造美人水」のパロディで、かけるほど不細工になる「人造醜婦水」とか。橋爪先生とそれはいいねとなって、当時の地図から「化粧品販売なら南久宝寺町です」と教えられ、地域の回想録を読むとB29墜落の話が出てきた。小説を書きつつ探っていくと、面白い話が出てくる。鮎川哲也先生が『黒いトランク』執筆時の体験談に「のめり込んで仕事をしていると材料や情報が向こうから飛び込んでくる」とあって、僕も毎回体験しますが、今回はそれが非常に大きかったです。

――連載を始めてから書くのに詰まることは。
芦辺 もう、えらいことになりました。昔の探偵小説のような四百枚程度の短いものにしようと話していたのに、第二回になっても殺人が起きない。大阪の人々が、結婚式見物の噂話とか喋り出して止まらない。第二回の終わりにやっと殺人事件の電話がかかってくる。
――なかなか事件が起きない原稿を読んで古市さんは、どう思いましたか。
古市 事件が起きなくても船場の人々の群像劇が無類に面白かったですね。殺人が起きたら人間関係に変化があるし、謎が出てくれば引きになりますけど、その前からもう、ここの人たちってこんな人生を背負っているんだとか、細かく書かれた船場の風俗とかが面白かった。
芦辺 最近のミステリは、読者が退屈するのを恐れてすぐに事件を起こす傾向がある。今回はあえてそうしなかったことを褒めてくださる方が多くて、評価につながったのは面白かったです。事件の前にまずこの世界を書いておきたいというのが大きかったんです。
連載では、実は第三回の第三章に出てくる殺人事件のトリックを予定から変更しました。もっとすごいのは、書いた原稿を古市さんに送った後、うちの細君に読ませたら「蝋人形が出てこないけど、忘れたの?」と言うので、忘れたっ!(笑)と、あわててこのくだりを挿入してくださいと追加の文章を送る極悪非道なことをやりました。
古市 いえいえ、気づいていただいてよかったです。
芦辺 あそこで蝋人形を出さなかったら、つじつまがあわない。
古市 長年の勘はすごいですね。
芦辺 でも、僕は、事前に人物の出し入れとか細かく克明に作っている人を見ると、どうしてできるんだろうと思ってしまう。僕はだいたい次のシーンがどうなるか、映像的にどうつながるかをその場で考えて書いているんです。そういうやり方でなんとか七十冊ほど作ってきた(笑)。次にその偶然の奇跡が起きるかどうかは定かでない。
――書いている途中でトリックを決めるんですか。
芦辺 トリックのストックが一応はあって、順次、これをというところもあります。ただ、今回は最初に考えたトリックがつまらなくて悩んだわけです。
――古市さんは、書きあがる前に芦辺さんから作品の全体像を聞いていますよね。
古市 芦辺さんと十八年間、お仕事をさせていただくなかで、以前はサプライズ感を出したいと肝心なところは伏せていらしたこともありましたけど、最近は大まかに犯人は誰か、大きいトリックはここになると事前にうかがっています。
芦辺 前は編集者に心を開かなかったんだけど(笑)。
古市 (笑)。
芦辺 とにかく驚いてほしかったので書下ろしの場合でも原稿を区切って送っていました。怖かったんですよ。今でもそうだけど区切って送る時は引きのところで終わらせる。編集者が続きを読みたくなるとかサプライズがあるように。それが長年の間に、ネタバレをしても面白さや演出についてお互いに共有できるのではないかと信頼関係ができていった。
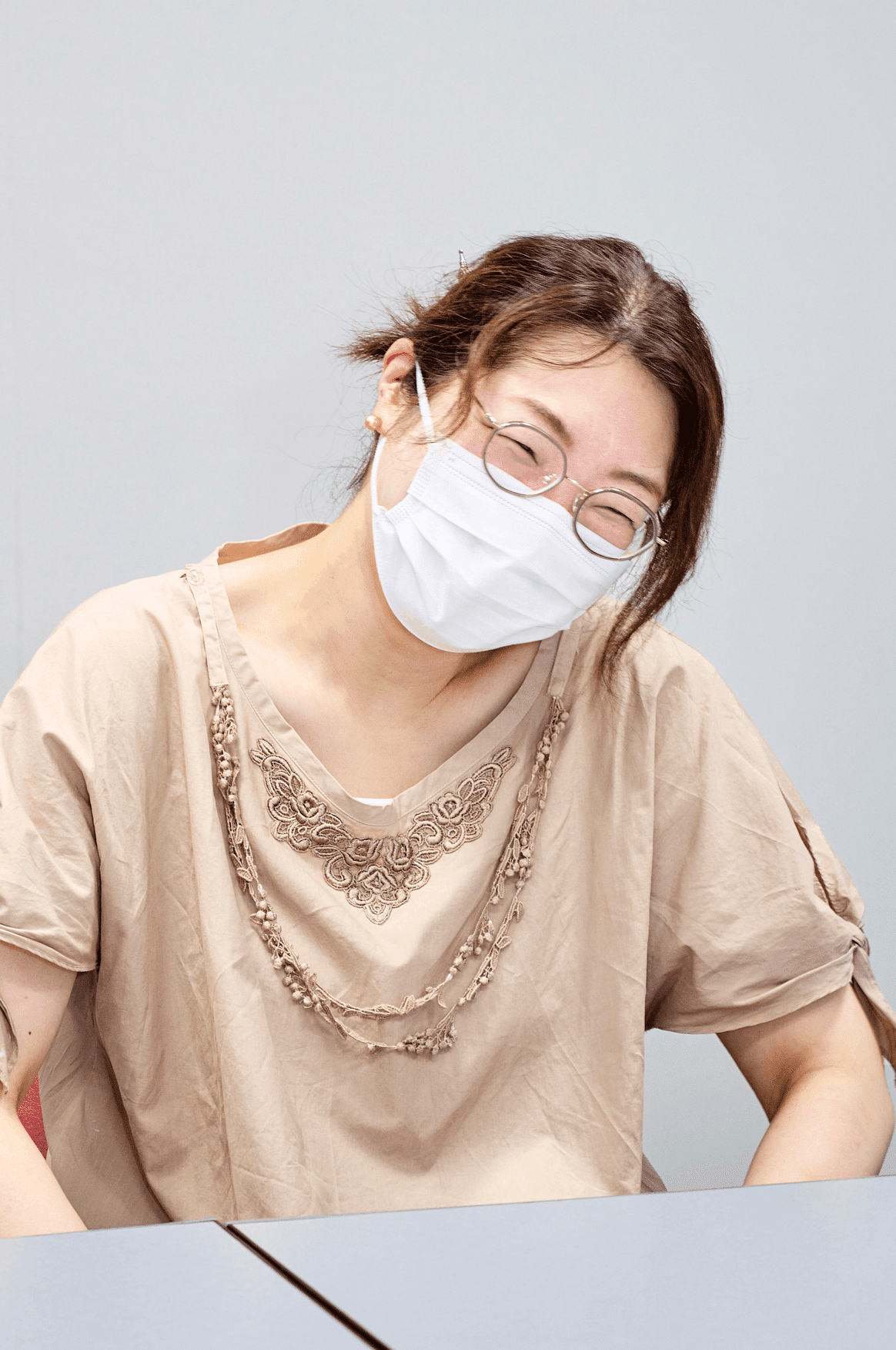
物語としての小説を書けた喜び
――先ほど、奥様(ピアニストの風呂本佳苗氏)に原稿を読んでもらった話が出てきましたが、毎回そうしているんですか。
芦辺 だいたい「貸しなさい」と言って持っていきます(笑)。最初に、漫画家の唐沢なをきさんが夫人とブレインストーミングしておられる例を出して協力させたんです。「みんな、してはるんや」と騙した。でも、細君がどなたか作家の奥様に「お話とか一緒に考えるんですか」と聞いたら「とんでもない! そんなことしたら怒られます」と言われ、普通ではないことに気づいてしまった(笑)。
古市 奥さんに原稿のダメ出しをされたらもう……。
芦辺 「ここが足りない」と容赦ないですからね。編集者と一緒に物語を作ってきたけど、ミステリを書いているとこういう人物を描く、こういう一コマを描くとか、どんどん物語を展開していく楽しさを忘れがちになるんです。だから、必然性がどう、整合性がどうではなく、もっとお話作りを楽しもうよという姿勢を教えてくれる人が横にいて、楽しい話になっているかを見てもらう感じです。僕は西條八十『あらしの白ばと』復刊の編者をしましたが、彼女はこの作品が昭和二〇年代に雑誌「女学生の友」に連載されて以来、殴った人間と介抱する人間が次の回に間違って入れ替わっていたのを見つけた鋭い人なので。
――橋爪紳也さんとの交流は、芦辺さんが大阪にいた頃からですよね。
芦辺 大阪の旧いことを調べるといつも橋爪さんの著作にいきつく。それで、ある人に紹介されてお会いしたんです。僕が東京に移ってからも大阪に関する面白い話を教えてもらい、設定にいき詰まった時は話を聞いてみようとなります。橋爪さんは大阪中心部で育ち、家は職人を多く使って商売をしていましたから、今回にぴったりな知恵袋だったわけです。
古市 芦辺さんご自身が紙資料にすごく当たられる方で、編集者の生半可な知識では手の出しようがありません。
芦辺 本を処分して図書館ですませる作家や評論家が多くなりましたが、コロナ禍で図書館も一時休館になり、やはり資料は自分の手元になければと思い知りました。また、気軽にネットで売り買いできないくらいに古書が値上がりして、僕もある時期から本をかき集めるようになりました。
古市 こちらが調べてわかることの数十倍の情報を持っていらっしゃる。
芦辺 そうでもないですよ、今回も校閲や古市さんから膨大なダメ出しの資料がきた(笑)。大阪大空襲の編隊の編成が、資料の書き写し間違いで混乱していたのをチェックされたり。吉村昭は『桜田門外ノ変』を書いた時、雪がいつから降り出したかにこだわったらしい。それは大事なことです。雪がどう降ったかが井伊大老暗殺事件に絡んでいるのは間違いないし、その時の天気や雪の降りぐあいを決めるのも作家の仕事。自分の演出に一番インパクトを与えるようにするんです。それは、資料調べと作家であることのどちらを選ぶかでもある。
――書籍化作業はスムースに進みましたか。
古市 「ミステリーズ!」休刊後、後半を書き下ろしていただいたわけですが、年末の各種ミステリ・ランキング投票に間にあわせるなら九月末までに刊行しなければいけない。
芦辺 前年の『鶴屋南北の殺人』(二〇二〇年。原書房)が入稿から二ヵ月で本になったから僕は甘く考えていました。でも、古市さんは「二ヵ月で本を作ることはしない」と。
古市 じっくり作っていきたかったし、お互いに考える時間があった方がいいものになる。日本推理作家協会賞と本格ミステリ大賞の対象期間は十二月までなのでそれに向けて頑張ることになりました。
芦辺 本が出る前、自分で勝手に『大鞠家殺人事件』の架空ポスターを作ったりしました。
鈴木 小説は、当初の予定よりかなり長くなりましたよね。たぶん、七百枚近くある。
古市 最初は、サクッと読める昔ながらの堅牢な探偵小説というイメージで四百枚と聞いていましたが……。実際、書いていただいてわかりましたが、最後に空襲で焼けてあの世界が崩れていく。その時のため、あれだけ華やかな世界を書きこむことに最初の二回を丸々使ったことが活きている。小説としてすばらしい効果でした。だから削れないし、描写のために費やさなければいけない枚数だったので、覚悟を決めました。芦辺さんの読者は、二段組だろうが分厚かろうがついてきてくれると、ある程度の確証もあったので。
鈴木 僕は二段組回避のために文字を細かくして一行あたりの文字数を多くするとか調整します。やはり慎重になってしまう。
古市 私の場合、小林泰三さんの『アリス殺し』を担当して、思った以上に若い人には二段組への忌避感がなかったという経験があったので。
――『大鞠家殺人事件』は、日本推理作家協会賞と本格ミステリ大賞を受賞しました。
芦辺 推協賞の結果は事務局から電話がくるはずだったんですが、古市さんたちと待ち会をしていると、未知の番号からかかってきて「京極です。決まりました」と言われて。
古市 京極夏彦代表理事自らがかけてこられて、初回投票から評価が高かったと教えていただいて、あれは感動的な瞬間でしたね。
芦辺 本ミス大賞の方は候補にすらならない時期がずいぶん続いて、完成まで十年かかった『鶴屋南北の殺人』も候補にならなかったことが僕には重くのしかかり、「じゃあ、どうしたらいいのか」と七転八倒していました。
古市 レベルが高いものを書き続けてもなかなか賞に届かないのを、運と言ってしまうのは残酷すぎると思っていました。本を出すことは華があるように見えますが、根底にあるのは地道な作業の連続なだけに賞という形で顕彰され注目されるのは本当にいいことですね。
芦辺 これでもう、僕のぼやきの言葉を聞かずにすむ(笑)。
古市 いやいや、絶対にぼやくでしょう(笑)。
芦辺 『鶴屋南北の殺人』で時空間のシャッフルと技巧の極限をやった後、小説の本道というか物語としての小説を『大鞠家殺人事件』で書けた喜びは大きかった。山田正紀さんが『ミステリ・オペラ』で言っていた探偵小説でしか書けない真実、そのような手応えを感じたのは確かです。でも、書きつくした感じではなく、まだまだ書きたいものはあります。
古市 「紙魚の手帖」十月号から「明治殺人法廷」の連載が始まります。自由民権運動の下支えになった新聞記者、弁護士などがインテリではなく、当時の感覚ではならず者だったという。
芦辺 明治二十年の保安条例で危険思想を持った連中が東京から追放され、大阪に大量に流れてくる。そこを舞台にして書きます。間違いなくスタンドアローンな内容です。
古市 今からワクワクしています。
《ジャーロ No.84 2022 SEPTEMBER 掲載》
■ ■ ■
▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
いいなと思ったら応援しよう!

