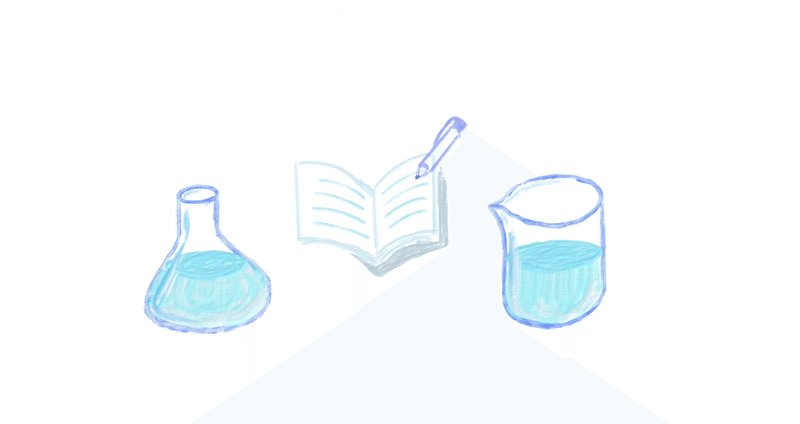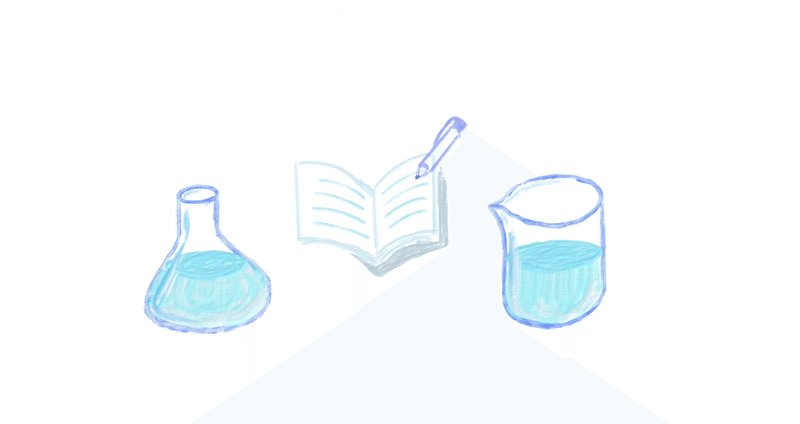ガラス器具(化学研究用)
化学研究において、ガラス器具は実験の精度を左右する重要なツールです。
(更新11/17, 13:13 有料部分に写真を一枚追加しました)
研究に使われるガラス器具の多くは、ホウケイ酸ガラス(通常のガラスよりホウ酸の含有率が高い)で作られており、様々な化学薬品や高温に対して高い耐性を持ちます。
そして欠かせないのが透明性です。反応の様子を確認できるため、実験の過程を細かく観察できます。
また、不活性であることも重要です。容器が化学反応に影響を及ぼすと実験は台無しです。化学反応