
エンタメ異人伝 VOL.16 原田勝弘
(※こちらの記事シリーズ「エンタメ異人伝」は2018年にソニーミュージックエンタテインメントの「エンタメステーション」にて公開された記事を再掲しています)
原田勝弘 株式会社バンダイナムコエンターテインメント
グローバル事業推進室 グローバルマーケティング部 ゼネラルマネージャー/チーフプロデューサー/ゲームディレクター(当時)
(※メガネ姿で現れた原田氏。クリップオン型のサングラスを装着し、いつもの姿になられたところでインタビュー開始となった)

原田さん、もうちょっとワルい感じで…
黒川――やはりパブリックの場ではサングラス姿でないとマズいんですか?
原田 別にダメってことはないんですけど、ウチの大下(聡)社長が僕を見るたびに「お前、サングラスしないのか」って言うんですよ。いや、本気でおっしゃっているわけではないと思うんですけど(笑)。僕、昔はサングラスしてなかったんですよ。
――そうでしたよね。
原田 海外出張に行ったとき、たまにしてたぐらいです。西海岸とかホントに眩しいんで。でも、カプコンさんとコラボすることになったときに、カプコンの方々が「原田さん、もうちょっとワルい感じで」って言ってきて。『鉄拳』はワルな人しか出てこないので、そのイメージに合わせてみたいなことが企画段階の覚書の中に書いてあったんですね。原田氏は小野(義徳)(注1)さんと出るときにはサングラスをする的な……。
注1:『ストリートファイターV アーケードエディション』のエグゼクティブ・プロデューサーを務めるなど、『ストリートファイター』シリーズをはじめとする、カプコンのさまざまなタイトルを手がけてきたクリエイター。
――なるほど(笑)。
格闘ゲームコミュニティ出身で、プレイヤーからゲーム開発者になった…?

原田 それで、やり始めたんですけど、そうしたら取材の人とかがサングラスをしていないと話し始めないようになっちゃって。「アレ(サングラス)は?」みたいな空気になって、サングラス装着待ち…になったりとか。以来、ファンと写真を撮るときも何をやるときも、リクエストが入るようになったので必ずサングラスをしないとってなっちゃったんですよ。
――そういうわけだったんですね。原田さんはあまりプライベートなことを、お話になっていないと思うんですけど、僕なりに事前にいろいろ調べたんですよ。いわゆる『コスプレ』でゲームキャラなどのスタイルをして、ゲームセンターでイベントを積極的に行われていたとか。
原田 僕は多くの人から「格闘ゲームコミュニティ出身で、プレイヤーからゲーム開発者になった」って思われているんですけど、実際にはそのイメージを利用していたというか、当時からお客さんに溶け込んでいただけで、実はイベントを開催していた当時かられっきとしたナムコの社員だったんです。でも、いろんなゲームのイベントをやっていたので、傍目にはバイトなのか店員なのかお客さん代表なのかが分からなくて、そういうゲームコミュニティの人がナムコに行って、いろんなゲームを作っているんだ、あの人はゲームセンター出身だ、みたいに見えてしまったんです。これは最近バラしてますけどね。ごめんなさい、実はあの時から社員でしたって、ハハハハ。
――それはもう言っても大丈夫なんですか?
原田 大丈夫です。「なんだよ~」みたいにいわれることはありますが(笑)。でも常にユーザー目線で居たかったし、いまもそこは忘れないようにしていますから。
僕のプロフィールはあちこち間違っていますよ

――ちなみに、生年月日はいつになるんですか?
原田 生年月日はね、敢えて伏せてるんです。
――そうだったんですか。それはなぜ?
原田 最初はいろんなところでクイズとかにするんで、伏せとこうってなったんです。そうしたら、世の中に出ている僕のプロフィールがけっこうブレちゃって。今、いっぱい情報がいろんなメディアに載ってますけど、ホントにブレてるというか、あちこち間違ってますよ。それが面白いから、みんな言わないでおこうって。

――なるほど~。では、大まかに教えてもらってもいいですか。
原田 四捨五入したら50歳になりますね。
――そうなんですか。実はずっと年齢がどのくらいなのか分からなかったんですよ。原田さんは若くも見えるし、僕と一緒ぐらいってことはないけど、もっと上にも見えるし。
原田 よくそう言われます。上にも見えるし、下にも見えるって。そういえば『DEAD OR ALIVE』を作られていた板垣(伴信)さん(注2)は出身大学が一緒で、同じ時期に在学しているってファンの間で言われたんですけど、あの人は年齢的に僕よりけっこう上のはずなんですよ。板垣さんも僕も浪人はしていないし。だから、学年的にはかぶってない、僕が入ったときにはあの人はもう卒業してたはずだって当初言い張っていたんですけど、衝撃の事実が判明して。あの人は大学に7年間行ってたって本人から聞かされたんですよ。あの方は麻雀がかなり強いんですが、大学時代に麻雀ばっかりやって留年していたらしいんです。なので、実は僕がキャンパスに行ってた時期とかぶってたんです。
注2:テクモ(現コーエーテクモゲームス)時代に人気3D格闘ゲーム『DEAD OR ALIVE』を生み出したクリエイター。現在はヴァルハラゲームスタジオ最高顧問、株式会社ソフトギアのメタル顧問を務める。(注※当時)
――板垣さんからしたら、オマエいたじゃねえかみたいな(笑)。
原田 そうなんです。だから、同時期に同じ大学に一緒に通ってた後輩だったって言われたら、確かにプロフィール上はそうなるんですね。でも在学中会った記憶はないですけど。
宮崎駿さんの『風の谷のナウシカ』には、どハマりしましたね。
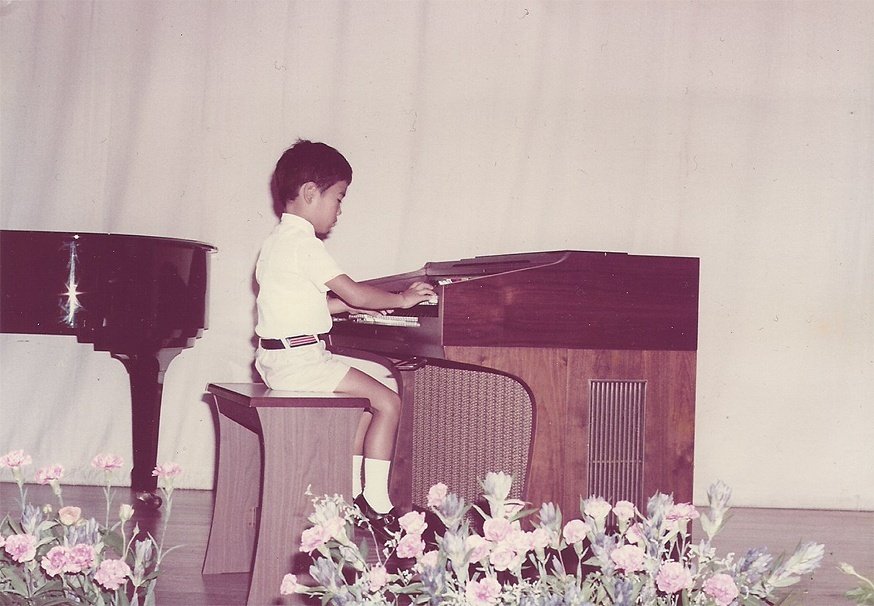
――70年代生まれということですが、子供の頃に影響されたものはありますか。
原田 あります。父親の姉が喫茶店をやっていたんですが、そこに『ブロックくずし』と『インベーダーゲーム』が入ってきたんですよ。インベーダーブームのちょうど直前ですね。あのブームってちょっとずつきたじゃないですか。ちょうど人気になり始めた頃に、あれに衝撃を受けて。まず、音ですよね。「ドゥッ、ドゥッ、ドゥッ」っていう『インベーダー』のあの重低音。モニターの画面にも見たことのない色の付いたセロファンかなんかが貼られていて。
――そうでした、そうでした。
原田 あと、当時のそういうお店って暗~いじゃないですか。大人の空間っていうか、みんなタバコもガンガン吸っていて。そういうのを子供ながら見てて、多分ゲームそのものというより全体の雰囲気も含めてなんでしょうけども、いっぺんにやられてしまったんです。だけど、親はやっぱり……当時のインベーダーハウスだとか喫茶店は大人が集まる場所でしたし、心配だったようです。 僕があまりに引き込まれているっていうのが分かったんでしょうね。すごく引きはがそうとされました。でもね、人間ってやるなって言われたら……。
――余計にやりたくなりますよね。
原田 そうなんです。そういう体験も込みで、すごく自分の中に刻まれましたね。影響を受けたものはもうひとつあって、僕には姉がふたりいたんですが、どちらも割とマンガやアニメが好きで、絵とかも描ける多才な人だったんです。その姉たちの影響でアニメ、マンガに早くから触れる機会が多かったんですね。手塚治虫さんのアニメとか、松本零士さんのマンガやアニメとか。
これはあまり他のインタビューで言ったことないんですけど、なかでも宮崎駿さんの『風の谷のナウシカ』には、どハマりしましたね。もちろん、アニメ版も好きですが、マンガ版は特に。あれは、すごい大好きだったです。もうちょっと大人になると、鈴木裕さん系のゲーム(注3)に没頭するようになるんですけど、小さい頃はさっき言ったような『インベーダー』とか、マンガだと白土三平の『サスケ』や『カムイ伝』なんかも好きでしたね。
注3:少年時代の原田氏は80年代に鈴木裕氏率いるセガのAM2研が作り出した体感ゲームのトリコになっていたという。この点に関しては後段のVRに関するくだりの部分で詳述している。
さらに『ゴルゴ13』どハマリ、生き方まで影響を受けました
――けっこう大人びていたんですね。
原田 はい、その頃から『ゴルゴ13』(注4)も大好きでした。でも、親からは(マンガを)禁じられてたんですよ。僕は長男で、しかも3人目の末っ子だったから、多分姉と違う教育をしたかったんでしょうね。とにかくマンガもアニメもゲームもバカになるからダメだと。
注4:国籍、経歴、本名すべてが謎に包まれた超A級のスナイパー、ゴルゴ13の活躍を描いた、さいとう・たかをによるアクション劇画。1968年に連載が開始された長期連載作で、現在も小学館の『ビッグコミック』にて連載中。
――(笑)。
原田 親はそこまで厳しくしたつもりはないそうですけど、全部シャットアウトされてた記憶があります。で、そうなると何が起きるかというと、意地でもゲームをしたい、マンガを読みたいとなるわけです。とはいっても、自分の手許にはなんにもないですから、そうなるとやることはもうふたつですよね。ゲームは親の目を盗んでゲームセンターに行くしかない。
――そうですね、はい。
原田 じゃあマンガはどうするかというと、姉がいるときにこっそり見せてもらうか、もしくは親戚の家に行ったときに、その親戚のお兄ちゃんの棚にあるものを見る。でも、親戚のおじさん、お兄さんは年上ですから持ってる本が全然違っていて、ちょっとアダルトな感じのヤツがあるんですよ、『実験人形ダミー・オスカー』(注5)とか・・・。
注5:普段は気弱だが、ショックを受けると自信満々のマッチョな男・オスカーに変貌する主人公が活躍する、原作・小池一夫、作画・叶精作のセクシーコミック。掲載誌が男性誌の「GORO」だったこともあってきわどい描写が多い。
――ありましたねえ~、分かりますよ。
原田 そういうのしか読めなかったんですけど、その中でも一番これはと思ったのが『ゴルゴ13』で、もう一個が『マカロニほうれん荘』(注6)。あのふたつには、どハマりしました。『ゴルゴ13』はそのときから現在の最新巻までずっと読み続けています。
注6:70年代に絶大な人気を誇った鴨川つばめの不条理ギャグマンガ。同時期に連載されていた『がきデカ』とともに、のちのギャグマンガに多大な影響を与えた。
――へえ~、すごいですねえ。
原田 小学生には難しかったですけどね。でも、『ゴルゴ13』はすごかったですよ。中学・高校・大学の授業で、もしくは自分自身で世の中のニュースを学んでいくじゃないですか。ところが、僕はそうした歴史上のいろんな事件を、なぜかすでに知っていたんですよ。で、なぜだろうと思ったら全部『ゴルゴ』で読んでいたんです。
『ゴルゴ』の世界って面白くて、ゴルゴ13の存在だけがフィクションで、他はだいたい史実や現実の世界に基づいていたりするんです。だから、「そういうことだったんだ」って授業とかでいろいろ追体験できたんです。そういう構図もあったので、余計どハマりしました。あのマンガにはいろんな意味で、生き方も含めてだいぶ影響を受けましたね。
40センチぐらい掘ると縄文時代と弥生時代の土器が出る奈良県

――ちなみに、ご出身は秘密ですか?
原田 いや、それは大丈夫です。生まれは大阪の豊中市で、3歳までいたんですけど、4歳になる手前ぐらいで奈良県に移りました。
――大阪や奈良という土地が、ご自身の人生観に与えた影響などはありますか?
原田 大阪は4歳ぐらいまでしかいなかったので、あまり記憶にないですね。せいぜい伊丹空港(大阪国際空港)から飛んでく飛行機がうるさかったくらいでしょうか。やたら低いところを飛行機が飛ぶときがあって、けっこううるさかったんですよ。だから、奈良に来たとき、空を見上げると飛行機がはるか上を飛んでて、やたら静かなところに来たなって思ったことは覚えています。大阪で印象に残っているのはそれぐらいですね。でも、奈良に住んでいたことは思い返すと、いろんな影響が自分の中でありましたね。
――たとえばどんなことでしょう。
原田 奈良県ってけっこう尋常じゃない県なんです。あそこって日本発祥の地と呼ばれているような場所じゃないですか。で、地殻変動とかがそんなに起きてない場所でもあるんですよ。だから、40センチぐらい掘ると縄文時代と弥生時代の土器が、ほぼ同じ場所から出てきたりするんです。
――そういうものなんですか。
原田 簡単に出てくるんです。小学校の文集に「趣味、土器集め」とか、みんな書いちゃうぐらい。近所のお兄ちゃんが小さな鏡を掘り当てて、それを調べたところ教科書の鏡の伝来の記述が〇〇年さかのぼっちゃった、みたいなことも。
――歴史が変わるぐらいの発見だったと。
原田 はい。教科書が改訂になったとき、「あの発見をしたのは奈良のあそこのナントカお兄ちゃんらしいよ」「マジか!」みたいなことが起きるところなんです。土偶や埴輪も普通はバラッバラの破片で出てくるんですけど、ほぼほぼ原形留めたものがボンって出てくる例もあって。
――ホントに? すごいところですね。
原田 ガードレールをひとつ付けるので、工事のために掘っただけで馬の頭の骨と刀みたいなのが大量に出てきたりしたこともあった。だから、大型スーパーとかが6月にオープンしますってなっても、みんな無理だなって絶対思うわけですよ。
――何か出てくるから。
原田 はい。基礎工事をしたら古墳が出てきた。で、調査のために掘ったら、その古墳の下から、さらに古い年代の古墳が出てきたとか。だから、奈良県って駐車場が全部屋上にあったりするんですね。掘ったら大変なことになるから。
――掘るとまた工期が伸びると。
原田 奈良って木簡(注7)なんかもよく出てくるんですよ。なんで木簡がそのまま残ってるかというと、泥と水が混じって密封状態で埋まっているから腐らないんですって。でも、水が抜けて、そこに空気が入ったりすると腐っちゃうんで、ヘタに掘れないっていうのもあるらしいんですよ。
注7:短冊状の木の板に墨で文字が書かれたもの。日本では飛鳥時代や奈良時代に記録用として使用されていたことから古代史研究のための貴重な史料となっている。
――それは知りませんでした。
原田 だから、藤ノ木古墳(注8)が出て世の中大騒ぎになったところが、僕らが学校に行く途中の道だったりとか、マラソン大会のスタートが法隆寺だったとか、ご神体が山だったりとか。東大寺の奈良の大仏を見に行くのも大好きで、仏像とかああいう日本の精神性というかメンタリティみたいなものに対する理解が深まるんです。奈良にいると、そうしたことに気づくことが多くて、そこはちょっと面白かったですね。
注8:奈良県斑鳩町で発見された古墳。国宝指定の埋葬品がいくつも出土したことから大きな注目を集めた。

年上の人とのネットワークでロケーションテストを知る日常
――面白い場所なんですね。ただ、これは僕の勝手なイメージですが、奈良にいてエンターテインメントに触れる機会がちょっと少なかったということはないですか。
原田 少なかったですね。それに、東京や大阪より入って来るのもちょっと遅いんです。
――そうだと思います。ゲームだと高校生ぐらいで体感ゲームの時代という感じですか?
原田 いや、体感ゲームは中学のときから本格的に。
――それは『アウトラン』(注9)とかの頃ですか。
注9:セガのAM2研が1986年に開発した体感ドライブゲーム。深紅のボディの可動筐体やヨーロッパを彷彿とさせる魅力あふれるコース、軽快なサウンドなどが注目を集めた。
原田 そうですね。で、大阪は比較的近いんですけど、子供だから融通きかないんです。学校区から出ちゃいけないとか、いろいろあるじゃないですか。だから、ゲームセンターが併設してる大きな本屋とか、ボーリング場にあるゲームセンターとかに、そういうゲームが1台入ると奈良県中の人が集まってくるんです。それで、新しい筐体の周りをみんなで囲む、もしくは100円を握りしめてロケーションテストに並ぶっていうことを、ずうっとしてましたね。
――でも、そうした情報をどこで手に入れていたんですか。当時はネットもないし。
原田 ないですね。だから、そういうネットワークが形成されるわけですよ。そのときやっぱり大人ってすごいなと思ったんですけど、年上はいろんな情報を持っているわけです。学年が1個上がっただけで、だいぶ違うんですよ。なので、年上と知り合いになるしかない。
僕は一番上の姉が6つ、2番めの姉が3つ上で、けっこう離れているので年上の人と話すのは苦にならなかったんです。なので、いろんな学年が上の人たちから情報をもらって、「原田君、店長から聞いたけれども、明後日『スペースハリアー』(注10)が入るらしいよ」、「アレか~、オレは写真でしか見たことねえ、朝から行くぞ!」みたいな。
注10:1985年にセガのAM2研が開発した3Dテイストのアーケード向けシューティングゲーム。戦士ハリアーを操り、次々に現れる敵を撃ち倒していくスピーディな展開や自機にあわせて可動する大型筐体などが大きな話題となり、絶大な人気を誇った。
――『インベーダー』と『スペースハリアー』の間って、時代的にけっこう空きますよね。その間もゲームはされていたんですか?
原田 やってましたよ、ずうっと。ゲームセンターでシューティングゲームとか、ありとあらゆるものをガリガリと。あの当時のゲームセンターって確かに不良もいて、絡まれたり脅されたりしたこともありましたけど、そんなのはごく一部分で、95パーセントはまともな人。ホントにいいオッサンから子供までいて、みんなで情報交換しながらゲームを遊べるコミュニティだったんです。
――ですよね、分かります。
ゲームをやってるときの背徳感がもうヤバかったんです
原田 だけど、親とかPTAは理解してくれなくて。自分の学校区でやってると、すぐにバレるから校区外に行くじゃないですか。でも、多分その学区のPTAと連携していて連絡がいくんでしょうね。すぐに先生とPTAが来て、しょっぴかれるというか連れていかれ。翌日にヤンキーみたいなヤツから僕みたいにただただゲームがやりたいヤツまで、全員同列に並ばされて、全校生徒の前で「僕はゲームセンターに行きました、すみません」って謝罪させられる。そういう時代だったです。
――ええ~? そんなことさせられるんですか。
原田 はい、親も激怒ですよね。「何を考えてるんだ」って感じで。
――やっぱりそうはなってほしくなかったわけですよね、親御さんとしては。
原田 いっぱい習い事をやったし、塾とかにも行ってましたからね。でも、習い事に行く合間を利用してゲームセンターに行ってたし、部活が早めに終わったときにも、まだ部活があるフリをして立ち寄ったりとか、そういうことばっかりやってました。だからでしょうね。僕の中でゲームをやるのは面白いことであると同時に、とっても後ろめたいことでした。やっぱり教育って恐ろしいですよ。今になって考えればゲームをやる事なんて悪い事じゃない。だけど、当時はもうゲームをやってるときの背徳感がもうヤバかったんです。
親には100円、50円を入れても返ってくるものがないじゃないかって言われてましたね。リターンがない、まだガチャガチャの方がいいって。大人になれば体験にお金を払うっていうというのは、なんら不思議なことではないと分かりますけど、子供の頃はそんな理屈はないので、そういう風に言われると、確かにボクは何にお金を払っているんだろうってなるんです。バカだから真に受けちゃうんです。けど、面白い。ということは、僕はひょっとして中毒なのかな、…ぐらいに思って、ドッキドキしながらやるわけですよ。で、PTAの人が後ろに立ってたときのドッキリ具合ったら、ありゃしない。
野球、テニス、ヨット、美術、文武両道の教育方針のなかで
――厳しい時代ですね~。
原田 だから、PTAのおじさん、おばさんのいい人・悪い人の区別は見つかったときの、このワンゲームを待ってくれるか、途中で中断させて補導するかの差でしかなかったですもんね。今から思うと「ゲームやって何が悪いんだ」ですけど(笑)。
――そうですよね。朝礼でお詫びなんてありえないですよね。
原田 ありえないですよ。でもそういう時代でした。なんでゲームやって怒られなきゃいけないんだと思いますよ。むしろゲームから学んだことも多かったと言いたいです。
――そのあと大学に入られるわけですが、なぜ東京の大学を選ばれたんですか?

原田 僕は親からスポーツをやれと言われてたんです。なんで、小学生のときから野球やらテニスやらいろいろやっていて、15歳からヨットを始めたんです。
――ヨットですか。すごい家庭ですね。
原田 不思議な家庭なんですけど、とにかく文武両道が方針で。でも、僕はオタク要素が非常にあったんで、ちっちゃい頃からデッサンをしたり、イラストやマンガを描いたりしていたんです。なので、東京かどうかはともかく本当は芸大に行きたくてしようがなかった。
――そちらの方面が志望だったんですか。
原田 はい、中学校のときも関西で行ける範囲の美術系のある学校を受験して受かってました。ただ、親は受験して自分の実力を試すのはいいけど、そのあとはいわゆる公立の普通科の高校に行きなさいと。どういう意味で言ったのかはあんまり詳しく覚えてないですけど、とにかく、絵の道に進むのはやめてほしかったんでしょうね。
幼稚園から高校卒業するまで無遅刻無欠席無早退
――まあ、それはね……厳しい世界ですから。
原田 だいぶ言われました、画家になってもなかなか食っていくのは大変だぞと。 僕は画家の本を大量に買ってもらっていたんです。その画家の描いた絵だけでなく生い立ちとかが書かかれているんですけど、親からお前その本をちゃんと読んでるか?いまでこそ著名な画家でも、現役時は売れなかったりする世界だぞ、一握りの人間だけがやっていける世界だぞ、というような話をされて。
それで、高校のときはあきらめたんです。で、そのときに、お父さんとかお母さんとかPTAとか、いわゆる「親世代の大人たちに、どうしたら認められるのか?」というのを、自分なりに凄く考えたんです。それで、恐らく学校の成績もスポーツもよければ、つまり文武両道でどちらも指折りの成績なら殆どの大人はきっと認めてくれるだろうと考えた。だから、僕は高校のときはもう勉強と部活ばっかりやってました。部活の帰りにこっそりゲームセンターに行くのはやめませんでしたけどね。
――ああ~。
原田 なので、勉強はそこそこちゃんとしてました。部活に関しても僕は高校のときからヨット部で国体とかに出ています。奈良県って海がないじゃないですか。だから、平日は田んぼの溜池で基本動作の練習とかするんです。直径150mほどで超狭いんで、実戦練習にならないんですけどね。ヨットのルールブックや気象学の本を読んで勉強もして。ヨットは揚力で走るんで航空幾何学の勉強も本を読んでしてました。で、土日だけ芦屋のヨットハーバーに行って、実際に海で練習すると。

そうやって僕はまず高校時代に国体で8位入賞して表彰台に乗ったんですよ。海なし県でも、ここまでできるってことを証明した上に、僕は学校の授業もしっかり受けてました。なにせ幼稚園から高校卒業するまで無遅刻無欠席無早退という真面目さでしたから。。あと学校成績の評定平均値っていうのがけっこう高かったんですね、そのおかげでいろんな大学に自己推薦できました。まさに親に言われたとおりの文武両道ですよ。これなら認められるだろうと。お父さん、お母さん、僕はここまでやりました。なので、芸術大学に行きたいですと。そういうつもりだった。
「絵を描けたらあらゆるものになれる、つながってる」と信じていた

――すごいですね。
原田 芸大に行くための予備校にも部活をしながらこっそり1年間ですけど通ってました。試験用のデッサンやデザイン画を規定時間で描くとか、そういう試験対策までやって、万全の準備をしたんです、で、親もいくつか芸大を受けるところまでは認めてくれたんです。受験料まで払って受験票まで手元に来ていました。でも、いざ受けるとなると、やっぱり同じことを言われるわけですよ。お前、芸大行ってどうすんだ、将来は何者になるつもりなんだと。いや、俺は絵が描きたい、絵で食っていきたいって言うと、お前そんなヤツ何人いると思ってんだって。これは参ったな、高校受験時代と結局同じことが起きてる、やっぱりループしてるぞと。
そのときはまだゲームっていうところには直結はしてなかったんですけど、当時は「絵を描けたらあらゆるものになれる、つながってる」って僕は信じてたんですね。マンガ、アニメ、ゲームという僕の好きなオタクの世界に行けるだろうと。でも、親は今うまくいってんだから、芸大ではなくいわゆる普通の大学に行きなさいと。当時は中央大学の法学部だとか早稲田大学だとか、そういうところも受けて、受かったらそっちに行けって言われたんです。
――そういう経緯だったんですか。
原田 で、それはそれで簡単には受かるまいと思ってなかったんですけど、数校受けて全部合格しちゃったんですね 。
親との賭けに負けたような状態…とは?
――それは素晴らしいですね。
原田 そうなんですけど、ある意味、親との賭けに負けたような状態になったんです。なので、もう1回思い直したんです。よし、大学卒業までは親の、そして世間の大人達の期待に応えようと。なぜならば学費を出してもらうわけですから。
当時高校3年生。よく考えたら、確かに僕は自分で稼いでないなと。だったら、もう4年間は親の期待に応えるか、もしくは自身で稼いで生活も学費も自己完結するしかないけど、当時の自分にできることなんて知れていた事もあって、考えを巡らせて。いわゆる世の大人から評価されやすいというか、親が期待する大学にせっかく受かったんだし、とも思って早稲田に行ったんです。で、留年もしませんでしたし、サークルではなくいわゆる体育会部活のヨットも続けて。そこで4年生の時は主将もやりました。僕、早稲田大学ヨット部の63代目主将なんです。早稲田のヨット部って野球部の次に伝統のある部活で、旧日本海軍系のOBとか先輩がいっぱいいるんです。まあ厳しいところでした。

――すごい部なんですね。
原田 はい、そこで主将をやって全日本4位。かつ、ちゃんと留年もせず、しっかり単位も余分に取って。で、卒業となると就職活動をするじゃないですか。やっぱり当時の体育会って就職にすごく強いんですよ。とにかく大企業には強かった。当時は既にバブルははじけていて、いわゆる就職氷河期元年ではあったんですけど、それでも強かった。そこで、また登場するのがお父さん、お母さんです。ウチの父親はいわゆる消防の偉い人だったんですね。
――地元の名士ですね。
原田 はい。軍隊で言えば大佐クラスみたいな地位に就いてて。とても社会の役に立っているって言ったらなんですけど、みんなに尊敬されていたし、確かに僕自身が父親を尊敬していました。そんな親ですから、自分の息子が早稲田に行って卒業するとなると、どこに行くんだ、OBからの伝手もあるだろう、お父さんもいろんなところ紹介できるから、ちょっと話を聞かないかって。

すべてをシャットアウトしてゲーム業界に行くという決意
――当然、そうなるでしょうね。
原田 でも、僕はそれを全部シャットアウトして。ヨット部のOBの世話にはならない、お父さんのネットワークもいらない、自らゲーム業界に行くと。
――おお。でも、オタク業界はいろいろありますけど、なぜゲームだったんですか。
原田 僕が18歳で大学に入ったとき最初に何をやったかというとですね、自分のバイトで稼いだお金でテーブル筐体を買ったんです。それぐらいゲームが好きだった。
――テーブル筐体ですか!
原田 あれは僕のひそかな決意のあらわれだったと思うんです。大学入って東京に来たんですけど、もう当時のゲームセンターの店舗数がすごくって。なんだ、これはと。秋葉原に行ったら『ダブルドラゴン』(注11)の基板が5000円とかで売ってるんですよ。「え、どういうこと? これ、家でできるじゃん」と。
注11:主人公の格闘家を操作して敵と戦いながら進んでいく、1987年にテクノスジャパンが開発した格闘アクションゲーム。ファミコンやゲームボーイ向けの移植版も発売された。
――そう思いますよね(笑)。
原田 中古テーブル筐体が1万5千円、『ダブルドラゴン』の中古基板が5千円で計2万円。これだけ出せば家でやり放題だ、なんてこったって思って。それでもうおかしくてなってしまって、『ファンタジーゾーン』(注12)とか、いろんな基板を買ってきて家でやってたんです。しかも、親の監視がなくて解放されてるじゃないですか。もちろん、部活で忙しかったんですけど、もうゲームをやってる時間が楽しすぎて、これはもうたまらないと。なんとかこれで食えないかなと思ったんです。ただ、そのときは作る側じゃなくて、やる側でって思ってました。
注12:1986年に開発されたセガのアーケード向け横スクロールシューティング。パステル調のメルヘンチックな画像や、敵を倒して集めたコインを使ってパワーアップしていくシステムなどが話題を呼んだ。
――あ、プレイヤー側で。
原田 はい。当然その当時ですからただのプレイヤーでは食えるわけはないけど、きっとなにかしらの方法があるだろうと思ったんです。
親はもう大激怒というか大疑問というか
――高橋名人みたいな?
原田 もちろん、高橋名人にも憧れました。名人もよく考えたられっきとした会社員なんですよね。だから、たとえばゲームを売る人とかだったら、できるんじゃないかみたいなことを考えて。とにかく決心はしていたので、就職活動が始まったときに「オレはゲーム業界行くから」って言ったんですよ。したら、親はもう大激怒というか大疑問というか。
――許さないってなるでしょうね。
原田 もう、本当になんのために……お前いくらかかったか知っとるのかと。当時からよく週刊誌のネタとかになっていて、今でもたまに話題にになっていますが、地方から早稲田にやって学費に下宿代に仕送りにと全部払うと4年間で1千万円ぐらい簡単にかかるんです。しかも、僕はヨット部のお金も出してもらっていて。
――そうか、じゃあもっとかかりますね。
原田 はい。だから、僕は親から1千万円以上出してもらってて。もちろん、うちの親はそれを投資だとか一言も言いませんし、プレッシャーも何もかけませんでしたが。ただ、お前いろんなチャンスがあるんだぞと。しかも、当時ゲーム業界って、まだ一部上場しているところがあんまりなかったんです。
――でしょうね。
本命はセガだったが、一番最初に受けるのが偶然ナムコになった

原田 で、どこに行くんだって言われて僕はいくつか……実は当初の本命はセガだったんですけどね。僕は最初営業で受けたんです。ナムコもセガも全部営業で受けようと思っていて、スクウェア、カプコン、SNKやタイトーもそうです。ばーっと全部応募して資料を取り寄せて日程を組んで、一番最初がナムコだったんですね。本当はセガが最初だったんですけど間違って理系のセミナー&試験に行っちゃったんです。そうしたら営業は日程と試験内容が違うよって言われて、スケジュールを組みなおし。それで一番最初に受けるのが偶然ナムコになったんです。
――あ、そうだったんですか、なるほど。
原田 で、ナムコやセガを受けるって言ったら、当時うちの親はその……ナムコを知らなかったんです。それでカーっとなったのもあるんですね。僕の世代から言わせると、ナムコを知らないってどういうことだと。カーッとなって。
――そこですか(笑)。
原田 だって、いくらなんでもそれはないだろって。『パックマン』ぐらい知ってるだろと。
――知らないんじゃないかなあ~。
原田 とにかく、親からすると全然聞いたことのないところに行くっていうのが、抵抗があったみたいで。でも、いや冗談じゃないと。お父さんとお母さんには申し訳ない。今までお金をかけてもらって、そこはもう本当に感謝してるし、お父さんとお母さんは大好きだし、家庭にも一切不満はない。けれども、どうしてもこれだけは自分で選ばないと、オレ絶対一生後悔して、一生ゲーム業界に行きたかった、行きたかった、と言い続けるし、なんでもかんでも他人のせいする人間になっちゃうからと。だからせっかく親にも世にも恵まれている今だから、どうしても自分で選びたい。もっと言えば、もう俺は本当にゲームがしたくてしたくてしょうがないんだと。そうしたら親は商社に行ってゲームを扱えばと言ってきたんですけど、いやそれじゃあダメだと。僕は仕事で堂々とゲームを遊んでも怒られない場所に行きたいって言ったんですよ。今思えばまさに子供の言い分みたいですけど、この世にゲームを遊んで怒られない場所があるならそこに辿り着きたいという想いがあまりに強かった。
最初に内定をくれたことに恩義を感じてナムコに決めたんです

――はあ~。
原田 それで、最初にナムコに内定もらって。他も合格頂いたり二次面接に進ませて頂いてたんですが、最初に内定をくれたことに恩義を感じてナムコに決めたんです。で、当時のナムコって新入社員は開発も営業も就職時の職種は関係なく全員ゲームセンターに配属されるんですよ。、で、社員はそのゲームセンターでタダでゲームをやるのはご法度、いわゆるタダゲー禁止だったんですね。
――社員なのに(笑)。
原田 まあ、タダゲー禁止は分かります。でも、閉店後とか開店前とかにお金を払ってやる、いわゆる夜ゲーと呼ばれる行為もダメって言われたんです。
――それもダメなんですか。それじゃあゲームやれませんね。
原田 はい。それにもう驚いて。なんじゃそらと。「堂々とゲームをやってても怒られない場所に行きたい」って啖呵を切っておいて、ゲームやってたら怒られるとこに来ちゃったよみたいな(笑)
――ハハハハハ。
原田 だから、灰皿拭きながら、最新のゲームを客がやってるのを見るっていう。それって余計地獄じゃないですか。

ゲームをしたいがために考えた結果だったが…
――ですよねえ(笑)。
原田 遊びたいけど遊んじゃダメ。だったら視界にないほうがまだマシじゃないですか。なんじゃこらと思いながら、それでも頑張ってたんですけど、そうしたら親が僕の働きぶりが見たいっていうんで、配属先を調べて来ちゃったわけです。で、ちょっとそこで親がショック受けちゃったんですよ。
そのときの僕はネジ回しでなんかクリクリやったり、灰皿磨いたりしてたので、そこだけを見られちゃって、灰皿磨くために就職したのかって言われて。いや違う、あれはエンターテインメントのもてなしの基本なんだ、サービス業なんだからという話を一生懸命したんですけど、そこだけ見ちゃうと分かんないですよね。加えて、「好きなゲームもやれてないんじゃないか?」って言われて、確かにそうだなと僕も少し落ち込んでしまって……当時の僕のモチベーションはそれだけ、ゲームがしたい、それだけだったですからね。社会貢献とか暖かい家庭を築くとか、当時の僕にはそんな崇高な思いはないですから。
――ただただゲームがしたいと。
原田 そうです。だから、僕は頭の中で「ゲームがしたい」「ゲームをするために、この会社に入った」「ゲームで食べていくにはどうすればいいんだ」「日中にゲームをする方法は?」ってずうっと。あのときはホントにそのことだけ考えて、脳みそをフル回転させてたんです。
それで、すごくいいことを思いついたんです。当時はまだコスプレってキーワードもほとんどなかった時代ですけど、たとえば店員がゲームのキャラクターの格好をしたり、ピエロみたいなちょっと面白い服装をしたりして、ゲーマーを集めてイベント……つまりゲーム大会をやる。とりあえずカプコンさんとかSNKさんの格ゲー大会なんかを主宰すれば、僕も参加できるんじゃないか、一緒に楽しめるんじゃないかって。
――確かにできますよね(笑)。
原田 もう一個考えたのは、なんのゲームがどれぐらい上手いですって書いたバッジを店員たちが付けるっていうものです。僕はシューティングゲームが得意です、レースゲームが得意ですっていうバッジを付けて、その店員に勝ったらワンクレジットサービスするとか。あと、僕がそのゲームのことを教えます、初心者の方はなんでも聞いてくださいと。あと一人でゲーセン来たお客さんの為のライバルプレイヤー役をやりますよ、というサービスを始めて。そうすると、ゲームを教えるって名目で、勤務中に堂々と、しかもすごい遊べるんですよ。まさにちょっとしたプロゲーマーの誕生じゃないですか。これに関しては「オレ、勤務中に遊ぶ天才だな」と思いましたね。
――ハッハハハハハハ、そうか、そうですね。よく考えましたね、それ。
売り上げが記録過ぎて中村雅哉さんから社長賞をもらえることになった件
原田 もちろん、当時若かった僕は店の売上のこととかシリアスに考えてなくて、単なる自己実現のモチベーションしかありませんでした。でも、そのモチベーションでやったところ、当時働いてたお店が……東京事業所っていわれる管轄のお店だったんですけど、4カ月連続で歴代の売上をどんどん更新したんです。その店舗系列の全盛期の売上を超えちゃったんですよ。
――そこを超えちゃったんですか。
原田 そうなんです。これは生々しい話ですけど、ゲームセンターの入っているビルって、いろんな契約形態があって、この売上までの家賃は一定額だけど、それを超えたら歩合が発生しますというのがあるわけです。だいたい歩合なんて発生しないぐらいの額で設定しているんですけど、店長からその売上を超えて歩合が発生するから、今週はイベントをやめてくれとか、月末はやめてくれとか言われて。イベントを抑制しなきゃいけないぐらいお客さんが集まるようになったんです。
――そんなに、うわ~。
原田 すごく大盛況になったんです。で、当時の僕はまだ入社半年ぐらいだったんですけど、今は亡き中村雅哉さん(注14)から年末に社長賞をもらえることになったんです。中村さんのすごいところはボーナスの明細表の中にメッセージを……もちろん全社員宛に向けた共通のコピーされたメッセージですけど、必ず入れてたんです。皆さんこの夏はどうでしたかとか、新入社員も入ってきてどうのこうのとか。でも、そこに誰かの特定社員の固有名詞が載ったことはなかった。なぜなら社員全員に出す手紙だから。
注14:バンダイナムコエンターテインメントの前身であるナムコの創業者。1955年にナムコの原点である「中村製作所」を設立。1977年にナムコに社名を変更し、『ギャラクシアン』『パックマン』『ゼビウス』など数多くの名作を世に送り出した。2017年1月22日死去。
――そうでしょうね。
原田 でも、その年に出した手紙の中には「新入社員の原田勝弘君のように自己実現することで夢を叶えて~」みたいなことが書いてあったんですよ。それで、多くのナムコの先輩社員方から「原田、お前の名前が載ってる」「オレは入社10年以上経つけど、こんなの見たことねえ」「お前、これすげえことなんだぞ」って言われて。入社してまだ半年ぐらいで、そんなことになっちゃったんで「マジで?あの中村雅哉さんに褒められてんの?!」って思いました。
――すごいじゃないですか。
原田 そうするとですね。親には「オレ、社長賞もらえるらしい」「ボーナスの明細にこんなこと書いてるらしいよ」「お客さんも幸せ、オレも幸せ、会社も幸せ。全員幸せにしているんだよ」とか言って。全部計算してやったんだと、それだけ俺はゲームをよく分かってるんだと……もちろん、まったく計算なんかじゃないですよ。だって、自分がゲームをやりたかっただけですもん。ただ、ゲームをしたいという欲求で知恵を絞ったらこんな副作用が、という感じで。
開発部門だったら、もっとゲーム遊び放題だ!

――そうかもしれないですけど、結果すごいことになったわけですよね。
原田 それで社長(中村雅哉)に直接お話しできるチャンスを頂いたんです。入社してまだ半年ぐらい、1年目の10月頃だったですかね。そのときに「原田お前、せっかくのチャンスだから社長に言いたいことはないか」って当時の部長に言われて、「僕は色々新しい部門でも頑張りたいので、開発とかそういうのをやりたいです」と。僕はゲームセンターでイベントをやって、このゲームはもっとこうだったらとか、お客さんからいろんな意見をもらってたんです。なので、この経験を活かしてって……まだ半年しかやってないんですけど。今思えば、もっと営業を何年もやってからそんな偉そうな言えよと自分に対して思うんですけどね。まあ、とにかく当時はそんなふうにもっともらしいことを言ったんですけど、実は僕の中での一番のモチベーションは「開発部門だったら、もっとゲーム遊び放題だ!」だったんです。
――まあ、遊べますよね(笑)。
原田 開発にいくと、当然自社の開発中のタイトルとか、他社の面白そうなゲーム基板や体感ゲームとか大量にあるわけですから。当時、ゲームセンターはまだまだ勢いがありましたからね。で、研究だとかいって朝から1日中会社でゲームをやって、夕方にあーだこーだと会議をして帰る。そんな仕事があるかって。それは仕事じゃない、遊びだと。そう思いつつも、まさにそれが俺のやりたかった仕事だと思いました。
――ハハハハハ。
原田 ただ、当時は部門間異動ってほぼなかったんですね。ましてや営業から開発ってのはほぼ無かった。しかも、僕は当時は専門知識がないわけですから。せいぜい絵が描けるくらいですが、そんな入社試験も受けてないし。
――営業で入ったんですもんね。
原田 はい。だから、部門間異動なんか本来ならできないんですけど、当時の僕はすでに社内で有名になってたんですね。新入社員でえらい集客してる、すげえヤツがいると。で、週刊ポストとか、そういういろんな雑誌が取材に来られて、大活躍してるゲームセンターのコスプレ店員みたいな感じで載ったんですよ。しかも、社長賞をもらって社内でも名前が出て、ホープみたいになってたんで、営業部長が異動させまいと止めるわけですよ。
――それは、そうでしょう。
開発に行けないんだったら会社辞めて、来年(入社試験を)受け直します

原田 わざわざレストランに呼ばれて、メシを食いながらすごいこと言われたんですよ。今はもうないですけど「プラボ鶴見」っていう店があったんですよね。ここはナムコの営業の憧れの店舗で、なんと月商1億ぐらいあったんです。一番のモンスター店で、そこを任されるってすごいことなんですけど、その「プラボ鶴見」に次のお前の舞台を用意していると。営業の人が聞いたら「それはすごいオファーだぞ!」なんですけど、僕は「いや、開発に行けないんだったら1回会社辞めて、来年(入社試験を)受け直します」と。当時の「プラボ鶴見」は売り上げも凄いけど当然仕事も厳しくて、ゲームなんて絶対遊べないと思ったんですね。だから真っ向から断りました。判断基準もゲームが遊べるかどうか、そこでしたね。
――すごいな~。
原田 心の中では、会社を受けなおしてそれで落ちたらどうしようとも思ってたんですけどね。でも、僕はそれぐらいゲームがやりたかった。とにかくゲームを遊びたくてしょうがなかったです。そうしたら、社長からちょっと言ってもらったのもあったと思うし、いろんなところから手が回ったんでしょう。今のバンダイナムコグループの会長である石川が。
――石川祝男さん(注15)ですね。
注15:現バンダイナムコホールディングス会長。ハンマーでワ二を殴っていく『ワニワニパニック』などの開発を手がけたことで知られる。(※当時)
原田 はい、当時はまだ部長ぐらいだったんですかね。あの方と今のバンダイナムコスタジオの中谷(始)社長(注16)。このふたりが面談してくださって、「キミが原田クンか、それでどうしたいの?なにがしたいの?」と。
それで、「なんでもしたいです」って言ったら、当時ナムコって企画職が自由度が高くて、企画に来ればなんでもできるよと。シナリオを書いてもいいし、絵を描いてもいいし、プログラムを習ってもいいしスクリプトを書いても良い。だから、企画に来なって言われて。僕は絵を描いてたので、アーティストの課長からも誘われたりしたんですけど、なんでもできる、学べるんだったら自由度高い企画に行きまーすみたいな。
注16:バンダイナムコスタジオ代表取締役社長。旧ナムコから発売されたシューティングゲーム「ギャラガ・リーグ」のひとつである『ギャプラス』などを手がけたことで知られる。(※当時)
「……え、原田ってオタク?」みたいな。
――それで開発の方に。すごいストーリーですね。
原田 だから、しっかり考えて行ったわけではないんです。今のプロゲーマーではないですけど、いかにゲームを遊んで給料をもらうかっていうことに賭けてましたね。これは僕の中での確信ですけど、いわゆる反動ですよ。子供の頃に一番やりたいことを抑圧すると、どっかで帳尻合わせの反発が来るんだなって。僕は反抗期もなかったし、いわゆるヤンキーにもなったことはない。学生時代に暴れてたみたいな武勇伝もホントなくて、大人から見ると文武両道の望まれるべき学生でした。大学でもずっと学ランを着て登校してましたし
――学ランですか。
原田 はい。学ラン着て、髪の毛も短いし。で、部活で腕立て、腹筋、ランニングの日々だったので真っ黒だったし、当然今よりシュッとしてました。それで、インカレだの六大学戦だの早慶戦だのって海でヨットレーサーやってるけど、家に帰るとゲームのポスターだとか、かわいいキャラクターポスターが貼ってあったりとか。他人には見せられないギャップですよ。だから、僕の部屋に遊びに来たヤツらはびっくりしてましたよね。「……え、原田ってオタク?」みたいな。
――アハハハハ、やっぱりそう見られちゃうんですね。
原田 「テーブル筐体あるよ」「なんじゃ原田、お前ヨットセーラーじゃないの?」とか。今でこそオタクは市民権得てますけど、当時は表に見せないってのがけっこう普通でしたから。

――ヨットセーラー(ヨットの乗員)なのに、凄いギャップ、みたいな。
原田 そうそう。授業もマジメに出て、普段学ランで、毎日腕立てしてるから腕も太くて。真っ黒に焼けてて、髪も短髪で。
――今もすごいガッチリされてますよね。
原田 当時はもっとでした。そうやって普段から「フンッ、フンッ」って筋トレやって、上半身裸でタオルかけてるようなヤツが、家ではケント紙にかわいい女の子の絵をいっぱい描いているわけですよ。で、そういうのを見ると、みんな「え、これ原田が描いたの?うわぁキメー」「キモチワルイ~」ってなるわけですよ。周囲がギャップに耐えれなかったんですね。

みんなが普段見てる腕立て伏せをしている俺は本当の俺じゃない…
――そうかあ……。
原田 でもまあ自分の中ではみんなが普段見てる腕立て伏せしてる俺は本当の俺じゃなくて、魂はゲームとかそっちにしか向いてなかったんで。だから、違うんだ、違うんだって心の中で思ってました。で、なんでそうなったのかっていうと、やっぱり子供の頃に抑圧されたからです。だから、ゲームがやりたい、ゲームがやりたいになっちゃったんですよ。
――ゲーム・オリエンテッドな感じですか。
原田 はい。だから、僕はちょっと他のゲーム開発系の人と違うかもしれないなと。もちろん、いわゆるクリエイターと呼ばれる人たちのゲーム開発にまつわる話、スピリットないしその苦労や思うところってのは100%共感できます。でも、一方で僕は自分自身がプレイヤーでいたいというか、常に遊びたい側でもあるっていう。そういう意味で、割と趣向が近しいなと思ったのは日野(晃博)さん。
注18:レベルファイブの代表取締役社長。『妖怪ウォッチ』『イナヅマイレブン』『レイトン教授』シリーズなど、数々の人気作・話題作を生み出したことで名高い。
――レベルファイブの、はい。
原田 日野さんとはいろいろ話す機会が多くて、ちょっとやるゲームのタイプは僕とは違うのかもしれないですけど、あの人もとにかくゲームを遊びたいっていうのがすごいんですよ。で、僕も研究とかそういうのは置いておいて、自分の趣味でゲームをもっと遊びたい。だから、いまだにゲーム環境だけは家でも譲れないというか、PCゲームの環境だけは常に最新の状態にしています。この部分だけは失いたくないなって思ってるんですよ。環境揃えるあたりは日野さんも凄くて。
バレないように会社に置いているもの、家に置いたら大変なもの
――じゃあ、今でも最新のゲームとか関心のあるものは常に遊んでいると。
原田 最新に限らず昔のゲームであったも買い直したりします。実はいまだにそのJAMMA(アミューズメント機器の規格の名称)の基板などを嫁に内緒で。
――買ってるんですか(笑)。
原田 はい、バレないように会社に置いてるんですけどね。4:3の昔のモニターとか、今のうちに買っとかないと将来無くなっちゃうかもしれないし。16:9のモニターで4:3の画面って割と当時の比率をしっかり再現できなかったりする場合もあるんですよ。画面の余白や画面枠の形も資格情報に影響与えてしまうし。だから、そういうレトロな機械も今のうちに買っとこうってなるんですけど、そんなの家に置いたら大変です。世代ギャップがある嫁からすると、4:3モニターとかブラウン管なんて「これって、何?」じゃないですか。ただでさえ大学時代に買った筐体がまだ置いてあるぐらいですから。
――なんのため、みたいな感じはあるでしょうね。
原田 テーブル物置みたいになっちゃってるんで、「これ捨てられないの?」って半年に1回ぐらい聞かれてますね。でも、「いや、頼む。俺が18歳のときに初めてバイトで買ったヤツだから、これだけはちょっと」って言って。もちろん、最新のゲームもやりたいですけど、やっぱりいまだに昔の古いアーケードゲームを遊びたくて。だから、会社にも基板をけっこう置いてるんですよ。俺は大人になったら、うまい棒を100本買うんだ、そしてまとめて食ってやるんだ、みたいな子供の頃の夢ををゲームで実践しちゃってる状態です。子供の頃になけなしの50円玉、100円玉で遊んで、PTAに捕まってた反動がこんな形で。
――でも、そういう気持ち、すごい分かりますよ。ちょっとおうかがいしたいんですが、今はお父様とお母様はどう思われているんですか?
原田 いまは管理職だからね、みたいな感じで認めてくれてはいますね。そもそも、開発に移った頃には「地道に開発職を勉強してる」と伝えていたので、その頃にはかなり安心していたようですけどね。ただ、今度はそこで何を作ってるか、気になるわけじゃないですか。その頃は『鉄拳』以外にも『ソウルエッジ』(注19)がちょうど立ち上がったぐらいで、僕は『ソウルエッジ』もデバッグだとか意見言ったりとかちょっと手伝ってたんです。で、これらのゲームって、結局のところ表現としては殴ったり斬ったりじゃないですか。
注19:伝説の剣・ソウルエッジをめぐってキャラクターたちが死闘を繰り広げる1996年発売のナムコの3D武器格闘アクション。『ソウルキャリバー』シリーズは本作の続編となっている。

『プロップサイクル』ってあるでしょ。ああいいうゲームを作ってる
――そうですね。
原田 暴力ゲームですよね。多分これをやってるって言ったら、親はまた心配すると思ったんですよ。先にも話した通り、僕は反抗期もなかったしヤンキーになったことも無かったし、格闘技は2つほど習っていましたが暴力とは無縁でした。ただ、当時からケント紙に「ワイングラスに大量の眼球が入ってる」みたいな絵を2週間かけてひたすら緻密に描きこんだりとか、やたらホラー映画ばっかり見ていたので、色々心配されてたんですよね(笑)。いや、僕はまったく正気で自分なりのアイデアを絵で表現したり、ホラー映画は単純にエンターテインメントとして好きなだったんですけど、親としては僕の内面に何かバイオレンス的なものが内包されているんじゃないかと心配していたみたいなんですよ。
で、当時のナムコの『プロップサイクル』(注20)ってゲームがあったんですよ。あの自転車をこぐヤツ。あれは同期がデザイナーのひとりで、僕にはなんの関係もなかったんですけど、けっこうイメージが良さそうだと思って。「ゲームセンターに『プロップサイクル』ってあるでしょ。ああいいうゲームを作ってる」って親にはウソを言ってました。で、しばらくしてまた何作ってんのって聞かれたときに、ちょうど僕の2個下の後輩やプログラマのチームが『太鼓の達人』(注21)を作ったんです。それで、あれが日本でヒットし始めたんですね。しかも、親御さんとかにもウケたんですよ。
注20:1996年にナムコが開発した体感ゲーム。自転車型の筐体にまたがり、ペダルをこいで人力飛行機・ラペロプターを飛ばすというもので、バンダイナムコが運営するVR ZONEの『ハネチャリ』は本作のアイディアがベースとなっている。
注21:2本のバチを持って、リズムに合わせて太鼓を叩いていく音楽ゲーム。2001年に稼働開始となった1作目が大ヒット。以降、さまざまなバージョンアップを繰り返し、家庭用ゲーム機やスマホ向けにも発売されるなど現在も高い人気を誇っている。
――家族でも楽しめますもんね。
原田 これも自分は関係ないんですけど、同じ部署で部下や先輩が作ってるわけだから内容も詳しかったんですよ。なので、親から今何をやってんだ?って聞かれたときに『太鼓の達人』ってまたウソ言ってました。

久夛良木さんのおかげで親からの信頼を勝ち得る
――でも、喜ばれたんじゃないですか?
原田 そりゃ心配はしないですよね。世の親御さんにはイメージ良いですから。とにかく、暴力ゲームを作ってるとは、ずっと言ってなかったんですよ。
――でも、やっぱりどこかで言ったんですよね。
原田 それはもうしょうがないから言いました。けど、その頃にはもうゲームはゲームセンターじゃなくて、プレイステーションのイメージに取って代わられちゃってて。久夛良木(健)さん(注22)が活躍してた頃で、もうグループを牽引する勢いだったじゃないですか。あれでイメージが良くなったんですよね。当時、久夛良木さんはナムコとすごく仲が良くて。
注22:プレイステーション事業を立ち上げた功労者。2004年にタイム誌が選ぶ「世界で最も影響ある100人」のひとりに選ばれるなど、当時の久夛良木氏は世界の注目を集めていた。
――そうでしたね。
原田 はい、僕もすごく仲良くさせてもらったんですけど、あの久夛良木さんと知り合いだと。あの頃の久夛良木さんってタイム誌とかニューズウィーク誌とかに取り上げられてましたよね。世界で影響力のある100人とかの、上位に入ったりしていたじゃないですか。
――入ってました。
原田 そんな久夛良木さんと仲良くやらせて頂いている、そのおかげもあって、あの久夛良木さんとやってるんだよ~って言っときゃ、親はいいわけですよ。親戚も「勝弘君、プレステでなんかやってんだ」って。「うん、プレステでいろいろ。ポリゴンやってるよ、ポリゴン」みたいな(笑)。

役職、その影響力と発言力、そしてそのジレンマ
――よかったですね。原田さんは営業を起点として。すべてを手に入れたじゃないですか。今はどうですか、ご自身として。
原田 僕は建前が嫌いなんで本音で言いますけど、やっぱり仕事の「楽しさ」っていろいろあると思うんです。「ゲームを作りたい」にもいろんな意味があって、最近だといきなりプロデューサーとして「作る」とか「開発」っていう新しい世代も増えていますけど、本来的かつ根本的には「ゲームを作る、開発する」っていうのは、「開発者」としてゲームを作り上げる事で生むというのが原点。で、これはゲーム開発者としての現場経験がある人には共感を得る部分ですが、この「開発」って仕事は現場でコードやスクリプトをガリガリ書いたり仕様書をどんどん詰めていったりとか、絵を描いたりデザイン会議したりとか、いわゆる「クリエイター」と呼ばれる職種に近ければ近いほど楽しかったりするんですよね。でもですね、会社的に、つまり事業的な自由を手に入れようと……つまり自分がやりたいゲームを作ろうと思ったら、ちゃんと社内での影響力や発言力を持って、責任も持って、予算も持ってるほうがいい。極端な話、管理職になったほうが、権限や予算を含めた自由がきくわけですよ。
――そうでしょうね。
原田 これは俺がやるプロジェクトなんだと、ここに俺は50億使うんだと。そんな感じで、ようは会社の役職的に偉くなったほうが当然いろいろやりやすい。でも、ここにジレンマがあるんです。確かに偉くなったら、いろんな権限がもらえる。だから、頑張って偉くなろうと思って、入社して20数年頑張ってきたんですね。僕は当時最年少とか言われたんですけど、課長になったのが31、2歳だったかな。部長になったのも10年以上前ですからとにかく管理職になったのはけっこう早かったんです。そうやって割とちゃんと権限をもらえて、確かに権限は多くなったんですけど、そうすると当然いわゆる「開発現場」からは離されていくんです。
――よく分かります。
原田 いわゆる作ることから離れてプロデュース、マーケティング、そして組織全体のマネジメント主体になっていくんです。これ、当初は自分の中ですごいギャップがあって。じゃあ、マネジメントしたくないのかっていうと、そこはしっかりしないといけないという使命感もある。社会の一員として下を育てる、みんなで会社を存続させていくっていう責任がある。で、その外側では何に繋がっていくかというとゲームファンです。このファンが望んだものを世の中に出すため、出し続ける為には、やっぱりゲームを作るところ、出すところが潰れちゃうと意味ないんですよ。だからマネジメントってのは凄く重要な仕事なんです。
その一方で、いわゆる「ゲームを生み出す、作り出す、作り上げる」という現場仕事からはどんどん遠ざかっちゃう。手に入れる権限と、手から離れていく「ゲーム開発」という仕事のギャップに悩んだ時期もありました。ゲームデザインを詳細まで組み上げていく楽しさを手放さないと、ゲームタイトルそのものをどう将来に導いていくかの決定権限を持てない。この相反関係は一体なんなんだろうな、僕はかつで自分が望んだ仕事に今就けているんだろうか?という悩みです。
いわゆる「ゲーム開発・製作ではなく、ゲーム制作ないし事業としてのゲーム作り」を最初から志している人にとって「プロデューサー」というのは、目指すべきゴールのひとつでしょう。だけどゲームというものがそもそも「現場開発」発進で生まれていた時代に開発職をやっていた人間からすると、それはいわゆる80~90年代のハリウッド映画界でいうところの「プロデューサー」に近いイメージ、つまりビジネス面をやりくりする人であって、映画監督でもカメラマンでも作曲家でも俳優でも無い。つまり、「ものを作る」という意味合いにおいて、ディレクターとプロデューサーには明確な線引きがあるわけです。もっと言うと「このゲームを開発しました、産みました」って言えるのはプログラマにしろビジュアルデザイナーにしろ企画にしろデバッガーにしろ、どんなに上の役職でもディレクターまでが限界で、それ以上の役職や事業側としてのプロデューサーになっちゃうと「プロデュースしました、手掛けました」としか言えないし実感できない。プロデューサーは作品に自分の言葉やメッセージが入ってるとは言えるかもしれないけれど、作品に「自分のDNAレベルまで組み込まれている」と実感できるのは、ディレクターまでが限界なんじゃないか、そんな感覚というか見え方が、ゲームプロデューサ職がまだ確立されていなかった時代からゲーム開発をやってた世代にはあると思うんですよ。
――なるほど。
原田 ただ、先に言ったように、事業側つまりプロデュース側や管理職には、権限と会社の存続をかけた重責があるので、先にも述べた通り、やはりとても重要なんです。
これは声を大にして言いたいですけど、例えばですが格闘ゲームで言えば90年代のブームのあと、いろんな格闘ゲームが消えましたよね。なんであのゲームの続編出ないんだろうとか、なんであのゲームはなくなったんだろうとか、格闘ゲームに限らずですけど、みんないろんなところで言ってるじゃないですか。たとえば会社自体がなくなったケースもあれば、そのタイトルの収益が成り立たないから続かなくなったものもあればと、いろんな事情でなくなってる。でも、ちゃんと儲かってたらやるわけですから。無くなっちゃったら、ただただファンが悲しむだけです。ということは、そのゲームタイトルを生み出す会社の存続責任が僕らにはあるってすごく思ってて。
――はい。
原田 それは例えば『鉄拳』も同じで、そこをうまくやっていくには、やっぱりマネジメントをやんなきゃいけない。ファンを失望させちゃいけないだけでなく、自分自身も悲しいから。というのがあるので、マネジメント頑張りましょう、みんなを引っ張っていきましょうと。未来はこうだよっていうビジョンを示しながら、やっていくうちにディレクター、プロデューサー、チーフ・プロデューサーときて部長だ、ワールドワイドのマーケティング部長だと。どんどん「開発職」というこの業界でいう本当の意味での「現場」から離れていっちゃった。

ワールドワイドのマーケティングの部長としてやっていってくれ
――すごいですよね。でも、なぜ海外まで担当するようになったんですか。
原田 以前のバンダイナムコは海外比率が低かったんですね。どうやったら世界市場で売れるかってことが課題になっていました。その一方で僕は逆に20代の頃から、既に海外に売るためのいろんな情報をソニーからもらったり、世界中に出張して学んでいたので、、時代の変遷含めてマーケット情報や海外パブリッシャーの戦略ややり方を知ってたんです。今ではE3にもコミコンにも、果てはEVOなんかのイベントでもバンダイナムコの経営陣含めて皆さんこぞって行きますけど、ああいうショーの出張でさえ、初期の頃からずっと行ってたのは僕ぐらいで、場合によっては僕一人、みたいなのが普通でした。そうなると、今になって「原田、海外詳しいな」となるわけですよ。、そこで「ワールドワイドのマーケティングの部長としてやっていってくれ」って何年か前に言われて。
――それは、そうなりますよね。
原田 それで、海外のバンダイナムコグループの海外とやり取りして、自社のあらゆるタイトル、特に海外比率の高いタイトルなんかは『ダークソウル』(注23)とかも含めて、どういう風にマーケティングして、売っていくかっていうことを自社の海外グループと一緒にやるわけです。時代の流れもあって、バンダイナムコの家庭用の海外比率もしっかり上がって、うまくいってるんですけど、そうなると実はさらに離れていってますよね、開発職、つまり作るってことから。
注23:『ダークソウル』シリーズの国内の発売元はフロム・ソフトウェアだが、タイトルへの出資はバンダイナムコエンターテインメントによるもので権利も同社に帰属しており、海外パブリッシングはバンダイナムコエンターテインメント自身が行っている。
――それは自分が本来目指したものではないと。
原田 目指したものだったのかどうか、配属当初は悩んだ時期もありました。昔の自分であれば、ただひたすらに研究と称して他社のゲームをやりこんだり、GDCなんかで他社さんの業界仲間と技術談義してるのが性に合ってるわけですから。
――そうですね。会社を越えた情報交換もありますよね。
原田 僕らの世代は他社さんであっても業界仲間同士仲がいいので、最新のサンプルソフトをみんなで送り合ったりしますよね。この間も辻本良三さん(注24)が『モンスターハンター:ワールド』を送ってきてくださったんですね。これが昔だったら遊びながら「ここのフィールドのこの描画、うまいことやってんな~」とか言って周囲からは「お、原田さん、研究してるのかな?」みたいな。
注24:カプコンの超人気タイトル『モンスターハンター』シリーズの開発を手がけるクリエイターで、プロデューサーとしてシリーズのタイトル全般を統括している。
――仕事という名目で遊ぶと(笑)。
原田 でも、今のワールドワイドマーケティングの部長である僕がですよ。『モンハン:ワールド』をやって「描画が云々」とか言ってたら、それはよく考えたらただ遊んでるだけですよね。それより『モンハン:ワールド』のマーケティングがどうなってるか、どういう売り方をしてるのか、何がユーザーに響いていたのか分析しろと。まあ、それを知るために遊んでいるんですって言えればいいですけど延々と遊んでいたら「実は遊んでんじゃね?」って絶対部下からも上からもバレますよね。そうなるとですね、もう会社じゃ絶対遊べない。むしろパワーポイントやエクセル表と、がっつりにらめっこして仕事の戦略をどう実行するかを考えるしかないじゃないですか(笑)。基本自社の家庭用タイトルの全てに対してマーケ責任があるわけですから、単純に時間も無くなりますし。
――ああ、そうかあ。
いつまでも自分の人生の主人公は自分じゃないんだ

原田 だいぶ長くなりましたけど、傍から見れば僕なんかは楽しくやってるほうに見えると思いますが、責任と権限を頂くたびに、先に話した本当の意味でのゲーム開発、という現場との距離が離れていく事に色々思う事はあります。ただ、ある意味、ただゲームがやりたいという想いを抱いてた子供だった自分が、ようやく大人になってきているのかなっていうのも一方ではあります。こういうとバカみたいですが(笑)。なにせこの業界に身を置いて以来、全てにおいて自身のゲーム中心生活を優先してきたので、家庭を持ったのも40歳ですからね。
――ちょっと遅めですね。
原田 つまり、僕は人に比べて一人暮らしが長いほうだったわけです。18で上京して40までの22年間ですからね。そんな僕が、家庭を持って「あ、これか」って思ったのは、ゲームをやりたくてもやっぱり子供との時間のほうが優先になりますよね。昔はゲームで徹夜とかゲーム仲間との付き合い優先で週末過ごすとかでしたが、当然そういうのはできなくなってくる。こうして仕事だけでなく家庭における責任もいっぱい発生するじゃないですか。
――それは当然あるでしょうね。
原田 そうやって、なんというかこれまで自分だけの時間だったものが減ってゆく。でも、それは子供への愛情だとか、当然お金もそうだし、いろんなところで次の世代にいろんなことを託していくっていうターンに入ったってことじゃないですか。人生の主役が子供に移っていったよ、いつまでも自分の人生の主人公は自分じゃないんだよっていう。
会社も同じで、次の世代に今のバンダイナムコにあるIPっていわれるものとか、ゲームっていわれるものを渡していかなきゃいけない、途絶えないようにしていかなきゃいけないんですね。そういう責任を負っているんだと。当然それは分かっているし実感する。ただ面白い事に、心のの半分はやっぱり小学校6年生ぐらいのときのままで、日々どうやったらゲームができるか?こういう仕事のやり方すればもっと面白いんじゃないか、いうのがすぐ浮かんできちゃう(笑)。
どう見てもちょっとおかしいコクピットのようなデスク周り
――ハハハハ、ああ~なるほど。
原田 今の僕のフロアは基本的には管理職系とかマネジメントやプロデューサーが集まっている場所なんですよ。つまり、ディレクターやプログラマやアーティストが肩を並べて座っているわけじゃない。つまり開発現場というわけじゃない。。
だから、わりとシンプルなデスク構成の人が多いです。下手したらノートPCとモニターだけって人もいるぐらい。多い人でせいぜいモニターを2個並べるくらいなんですけど、僕だけ16:10モニター2台並べて、加えて4:3のモニターがあったりアーケードゲーム機とかいろんなゲーミングデバイスに囲まれてるわけです。デスクの周りも一時コクピットみたいになってて、どう見てもちょっとおかしいんですよ。

――そんなことになってるんですか。
原田 はい。アーケードのスティックとかもいっぱいあって。それで、ちょっとした休み時間に。ほんの5分、10分ってレベルですけどゲームやるんですね。でも、その5分、10分でも神妙な顔をしてやらざるをえないんですよ(笑)。だって、フロアでは僕みたいにガチャガチャとかバチバチアーケードコントローラーを叩いてる人は殆どいない。キーボードとマウスのクリック音しかしない中で、僕だけカチャカチャカチャカチャって、『1942』だとか『バトルガレッガ』(注25)で連射してたり、『源平闘魔伝』とか遊んでたり、いやそれはどう見ても研究じゃないだろうと。
注25:1996年にゲームセンターで人気を博した縦スクロールシューティング。2016年にPS4向けに復刻版『バトルガレッガ Rev.2016』が発売され、往年のシューティングファンを喜ばせた。
――ハッハハハハハ(爆笑)。
原田 だけど、やりたいから神妙な顔して、「なんかこのゲーム、今度アーカイブになるらしいんだよ」「海外でも注目されてるらしいんで、オリジナルの基板でやってるんだよ」とか言いながらやるわけです。昔考えた「ゲームをやって食っていく」っていう、原点を取り戻すにはどうすればいいのかなと思ってね(笑)。だから、プロゲーマーの人とか、すごくうらやましいですよね。そういう意味でいうと今はeスポーツもありますし。
――でも、そこには戻れないですよね。
原田 多分、戻れないですね。いろんな責任が発生してしまっていますから。でも、みんなどうやって、そこの心身のバランスを取ってるのかなっていうのは興味がありますけどね。僕も『鉄拳』とか『サマーレッスン』で、チーフ・プロデューサーとかクリエイティブプロデューサーみたいな肩書がついてたりしてますけど、じゃあ昔みたいに現場に座って一緒にスクリプトを書いたり、絵を描いたり、いわゆるゲームに自分のDNAが入っていくような、あの身が焦げるような開発現場仕事をしているのか、というと今となってはそういう立場ではないわけで。
やっぱり、世界のゲーム業界の売り方、作られ方、競合会社が持ってるビジョンみたいなのが、どうマネジメントされてるのかってことを業界の繋がりで知ったり、調べたり、戦略をどう自分の組織に落とし込むか、業界未来予測と自社のゲームIPの向かう方向を考えたりとかが中心ですよね

VRは現代における体感ゲームじゃないか
――悩みは尽きませんね。あと、ふたつ聞かせてください。原田さんは他のインタビューで、VRは現代における体感ゲームじゃないかというお話をされていましたが、やはり原田さんの中でずっと興味の対象であったということですか?
原田 そうです。正確にはそれがいわゆる「ヘッドマウント」ってデバイスの形を指していたわけではないにしろ、やっぱり「バーチャルリアリティー」っていうキーワードは自分にとって昔から大きい存在でした。いろんなインタビューで言ってると思いますけど、やっぱり原体験は間違いなく鈴木裕さんが作られた体感ゲーム。あのインパクトがヤバくって。あの稼働筐体……『ハングオン』(注28)もすごいと思ったんですけど、アレは(筐体を)自分で動かすじゃないですか。でも、そのうちに『アウトラン』と、あと『スペースハリアー』が出てきて。
注28:バイク型の筐体に乗り、マシンを左右に傾けながらコーナーを攻めていくバイクレースゲーム。1985年に開発された記念すべきセガの体感ゲーム第1作で、バイクの形をしたインパクト抜群の筐体は大きな反響を呼んだ。
――『スペースハリアー』はやっぱり大きかったですか。
原田 すごくなかったですか? 僕は子供心にこれはシートベルトがいるなって思ったぐらいの揺れとゲームとのシンクロ度合いで。
――すごかったですよね。今思うとホントすごいゲームだなと思いますよね。
原田 『パワードリフト』(注29)とか『アフターバーナー』(注30)とかもたまらなかったですね。『トップガン』(注31)を観たあとに、『アフターバーナー』を遊んじゃうと、もうね。今見ると、そりゃグラフィックは今には遠く及びませんけど、当時の僕たちにはあの絵と音楽のカッコよさと、あの煙のアレと……よく考えたら、なんで戦闘機が正面同士で戦うんだってなるんですけどね(笑)。そういうリアリティ以上の臨場感があった。
注29:立体的なコースをバギーで駆け抜けていくスピード感抜群のレースゲーム。セガのAM2研が開発した体感ゲームのひとつで、1988年より稼働開始となった。
注30:戦闘機を操作して迫りくる敵機を撃ち落としていく、1987年開発のセガの体感3Dシューティングゲーム。レバーの操作に合わせて激しく動くコックピット型の筐体は大きな話題となった。
注31:トム・クルーズ演じるアメリカ海軍パイロットの活躍を描いた1986年公開のアクション映画。欧米はもちろん日本でも記録的大ヒットとなり、主題歌や挿入歌も人気となるなど一大ブームを巻き起こした。2019年に続編の公開が予定されている。
――そうそうそう(笑)。
原田 とにかくなんか「くるもの」があったんですね。だから、僕の頭の中には、あの頃に体験したゲームがずっと残ってて、いつか超リアルな映像でできる日がくるんだろうってのが漠然とあったんですよ。だから、GDCとかで発表されるテクノロジーとしてのバーチャルリアリティーとか、ガジェットなんかも随分前から追っかけてたんですね。
――ええ。
原田 90年代の「AKIBA PC Hotline!」の記事とか読んでると、海外のヘンテコな時代先取り過ぎるガジェットがいっぱいあったじゃないですか。で、なんじゃこらと思ってたものが2年後ぐらいにわりと一般化されつつあったりとか。そういうところに、なんか最近VRがちょっと出てきたっぽいぞと。
ちょうど360度モニターとかIMAXだとか、ああいうのが来はじめた頃で、これゲームになったら面白いんじゃないかと思ってたときに、いわゆるオキュラスのヘッドマウントが出てきたんですね。これをやろうとしてるヤツがいるのが分かって、俺らもやるぞってなったんですよ。
――なるほど~。
原田 最初は飛行機とか車とかに乗るみたいなのを考えました。でも、それは他の人もやりそうだったんで、ちょっと違う方にいこうと。そのときちょうど『鉄拳』のキャラクターをどうやって好きになってもらおうかっていうのが懸案になってたんです。そういう議論がプロジェクトの中でまったく別スレッドとしてあったんで、ここにバーチャルリアリティーをぶつければと。
――そういうことだったんですね、面白いですね。
原田 それで、人間生理的なものをともにすると仲良くなるっていいますよね。一緒に飲みに行くとか、食事するとかはその典型でね。宮崎駿先生の作品も必ず子供とかヒロインとか、いい人がゴハンを食べるシーンがあるじゃないですか。でも、悪者はせいぜい赤いワインぐらいしか飲まないですよね。多くの映画やアニメでも基本的に、冷徹な悪役なんかには、人間らしくおいしそうに頬張っている姿は描写しない。
逆に、おいしそうに頬張ってる姿を見せたキャラは、読者もしくは見ている人に親近感を抱かせたいのかなっていう。そういうテクニックとして使ってますよね。これはファンの間では知られたエピソードですけど、僕は当初VRを使った『鉄拳』で、それをやろうとして失敗したわけです(注32)。その当時はバーチャルリアリティーっていうものを、頭で理解しているつもりでいて、心で理解していなかったんですね。
注32:『鉄拳』のVR対応における失敗について、原田氏は2016年に開催された3D合同シンポジウム「VRとAIが拓く新たな3Dの世界へ」での講演や2014年に行われた「黒川塾21」など、さまざまな場面で言及している。

格闘ゲームのプレイヤーはアスリートに近い
――なるほど。もうひとつ、eスポーツに関して聞かせてください。『鉄拳』はまさに日本から発信できるeスポーツを代表するコンテンツですけど、eスポーツについて何かお考えみたいなものはありますか。
原田 鉄拳はこれまでも多くの実際の格闘家の方を使ってアニメーションキャプチャー、いわゆるモーションキャプチャーをしてきました。格闘家の方ってやっぱり格闘ゲーム好きも多くいらっしゃって、『鉄拳』とかもけっこう遊んでたりするんです。で、その格闘家の方たちがよく言われるんですが、相手の動きを見て、それに反応して、次はこうくるんだよな、ああくるんだよなと自分の攻め方を組み立てて、フィジカルで感じて、脳みそに思い描きながら、攻防の成功と失敗のフィードバックを基に自分の手先足先に自分の動きを伝えていく、また戦術を練り直す、っていうプロセス自体はホントの格闘と格闘ゲームは非常に似ていると。
――ほう~。
原田 それは確かにそうなのかなと僕も思って。もちろん、優秀なプレイヤーが優秀な格闘家になるわけではまったくないですよ。ただ、頭の中で起きてる事や仕組みとしてはすごく似てる、同じようなプロセスを経てるっていうのが面白いと。だから、本当の格闘とは全然ベースもやってることも違いますけど、それでもああいう競い合うようなゲームはスポーツにある意味近い、近しい能力が必要とされるってところでは合致してる気がするんですよ。
――なるほど。
原田 特に格闘ゲームのプレイヤーはアスリートに近くて、いくつか要素があるんですが、まず複雑な操作を行う指先の器用さ、これは脳から伝えて動かすっていうフィジカルな部分ですよね。もちろん、反射神経とかもフィジカルな部分で、、次にそこに全体の戦略があって、次にその場判断の戦術、というものがあって。あと経験ですよね。勝った負けたを繰り返すことによるノウハウなどの蓄積。で、ゲーム自体の知識も常に最新にする必要があって、そこに知力、加えてメンタル面が必要になってくる。格闘ゲームは運の要素よりは、実力勝負の側面が強くて、加えて大抵1対1の競技なので負けは全部自分で受け止めなきゃいけない。そうしたときの悔しさとか、心が折れないかっていうところも含めて全部自分にかぶさってくる。これは完全にアスリートじゃないですか。
――うん、そうですね。
原田 そういうところでいうと、僕はけっこうしっくりくる。けれども、一方ではですよ。ゴルフとかサッカーとかテニスとかって、50年前からルールはほとんど変わってないですよね。じゃあゲームはっていうと『鉄拳7』でも『6』でもいいですけど、もっとさかのぼって20年前ぐらいだったらちょうど『鉄拳3』あたりですか? この『鉄拳3』を20年遊ぶかっていうと、もうほとんど遊ばれてないし、遊ぶにしても「やっぱこのグラフィックじゃな」とか「この技の数じゃ物足りないな」となる。だから、新しくしていかなきゃいけないじゃないですか。この関係は他の競技にはない。
――普遍性みたいなものの問題ですか。
原田 はい。競技の構造として、求められる普遍性みたいなところは作る側に託されてるし、極端なことを言うと新作が出るかっていうのも別に約束されていない。でも、競技自体が消えるスポーツってなかなかないですね。そういう意味では現行のスポーツって言葉のもつイメージで括って考えるのはよくないかもしれないし。
基本的なエコシステムが回ってない限りはeスポーツってないんだろうと思う
――確かに。
原田 だから、多分eスポーツというくくりだけではダメなんだろうなと僕は思うんですよね。やっぱり、根本的にエンターテインメントとしての、ゲームとしての面白さと、ファンコミュニティがちゃんとあって、競技としてだけじゃなく、友達と遊んでもそれなりに面白いっていう。この基礎エンジンというか、基本的なエコシステムが回ってない限りはeスポーツってないんだろうと思っています。
――その通りですね。よく分かります。
原田 だから、たまにeスポーツのためだけのゲームを作ろうなんて企画を聞くんですけど、仮に面白いのが作れても、じゃあそのゲームは20年、30年、ずっと競技されているかというと、最初の人数規模を保って遊ばれ続けてるなんてことはないですよ、多分。
――それは僕もそう思います。
原田 ギリで5年、10年は遊べるかもしれないです。でも、じゃあ30年後もしくは半世紀後も遊んでるというのはかなり考えにくい。当然、バージョンアップしなきゃいけないですが、それがされる保証はないですよね。一方で頑張れば半世紀続くかもしれない、みたいなゲームタイトルとかIP自体はあるといえばある。やっぱりゲームとして愛され続けるってキーワードがとても重要で、これはスポーツとは少し違う構図だから、僕はeSportsの為だけに特化したゲームを作るってのはすごく難しいし、そこはちょっと違うんじゃない?と個人的には思っています。

なんで俺が子供の頃にこの時代が来なかったんだ!
――ええ……そうですね。
原田 一方でプレイヤーコミュニティはある意味、すごく幸せな状況が生まれようとしてます。今まではゲームでお金をもらえるのは、作っている人か売ってる人だったじゃないですか。でも、今では海外でもYouTubeやTwitchで実況してるだけで、しっかり稼いでたりしますよね。プレイヤーとして、ものすごい寄付をもらったり、もしくは広告をもらったりする。あれは立派なプロプレイヤーじゃないですか。あと実況だけやっている人もいますよね。
――います、ストリーマーですね。
原田 『鉄拳』とかでも、そんなに強くなくて大会でも上位にはこないけど、すごいゲームには詳しくて、実況としていろんなイベントに呼ばれて、ギャラをもらっている人がいるわけです。海外にそういうストリーマーがどんどん登場しているんですよ。人によってはただプレイしているだけなのに同時視聴で何千人も視聴者が集まるという。もう人気ゲーマーですよ。
――今はそういう方、けっこういますよね。
原田 そういう方にはスポンサーがつく場合もあるし、ストリーミングプラットフォームからの広告収入とか含めて、毎月ちゃんと稼いでいる。それだけで食べてるんです。これはすごいなと思って。ゲームのことを語れるだけでも、お金になって、それを撮影したり配信したりすることで人を巻き込める。そういうゲームとして収益の間口が増えてるっていう、この流れ自体は止めたくないじゃないですか。ゲーム経済の回り方が外側に波及し始めたわけですから。そこはなんとかしたいという気持ちもあるんですよ。で、eスポーツとこうした現状の両輪をどうすればいいのか、そこにいま頭を悩ませています。
――やはり難しいんでしょうね。
原田 はい。eSportsはいまでこそ話題になっていろんな方が動いてくれますが、僕みたいに昔から大会だとかイベントを仕掛けてきた側からすると、これまでも多くの困難があって、簡単に拡大できるものでないこともよくわかってます。でも、こうしたeSportsをとりまく環境に対して満額回答を持ってると思い込んでるひとから「どうしたらいいですか?、原田さん」って言われるんですけど、そんなこと今になってポロっと満額回答が分かれば世話ねえよと。
――オレでも分かんねえよ…と。
原田 もちろん、さっきも言った、作る人と売り手以外がゲームに携わることで食っていける新しい世界。この新しいエコシステムから生まれたゲーマーのコミュニティの人たちを何とかしてあげたいという想いは強いです。Twitchなんかでね、ホントに美味しそうにコーラを飲みながらね、楽しそうにゲームやってる人がいるんですよ。そうすると5ドル、5ドル、5ドルって。寄付が来たり、サブスクライバーとかスポンサーとかになってもらってるわけですよ。おお、これは夢の時代がきたじゃん、僕もこっち行きたかったって。
――ホントですよね。
原田 ゲームをやってるだけでメシを食ってるヤツがホントに現れた。良い時代になったよな。僕なんか小学生のときゲームをやってPTAに捕まって、全校生徒の前で謝らせられたんですよ? それが今はカメラの前でゲームをやってるだけでお金が飛んでくるんです。
この変わりようですよ。
――すごい時代になりましたよね。
原田 なんで俺が子供の頃にこの時代が来なかったんだ!っていつも思いますよ。
――ハハハハハ。でも、すごくよく分かります。
原田 ゲーム業界に新しい時代がきたんですよね。この時代を生きる人たちのために、やっぱり元となるコンテンツが必要になるわけですよ。それはeスポーツというキーワードだけでグルグル回るかっていうと、そうじゃないと。やっぱり本来のエンターテインメントとしての、ゲームとしての面白さがなきゃいけない。ここを全部繋ぐにはどうすればいいんだって、課題がどんどん増えてるわけですよね。それで、悩む側に回ってるっていう。だから、ただ悩まずゲームを遊ぶ側のヤツらが超うらやましい(笑)。すみません、最終的にゲームがやりたいだけどのオッサンの話になっちゃいましたね。
何度も言いますが反動ですよ

――いや、いや。熱い気持ちはすごい伝わってきましたよ。いろいろな方にお話をうかがってきましたけど、ゲームに対する思いは特に強いかなって感じがします。
原田 他のクリエイターの方とは、多分強さの意味がちょっと違うと思うんですけど。
――そうかもしれないですけど、やっぱりゲームに対する情熱というか熱量はすごい高いと思いますよ。
原田 何度も言いますが反動ですよ。だから、僕は3歳の娘がゲームをやっていても絶対止めません。ただし、『途中で投げない、くじけない、クリアできるまで頑張る』と言いづづけてます。
――3歳でですか(笑)。
原田 子供なので難しいとすぐあきらめちゃいそうになる。新しいゲームもどんどん遊びなさい、だけどまずこれをクリアしようよ、頑張ろうよって。そうすると、3歳の子にとってはだんだん修行みたいになってくるらしく「パパ、ゲーム止めて良い?」って。すごいんですよ、ゲームをやめたいって言うんです。「ゲームやめたい」って僕の子供時代じゃ聞いたことが無いキーワードだからびっくりしちゃって(笑)
――かわいいなあ~。
原田 それで「もう難しい?」って聞いたら「難しい」だけじゃなくてと。もう「クッパが怖くてしょうがない」とか言い出すんです。「クッパ、ムリ~」と。じゃあ、最後クッパだけはお父さんがやっつけてあげるから見てなさいって。そうやると、ゲームに対する接し方も変わってきて、あと「パパ凄い」ってなるんですね(笑)
――ほお~。
原田 だから、「頑張ってるね」「どうしたらもっとスコアが伸びると思う?」とか言ってると、ゲームとしっかり向き合えるようになってくる。すると、キリの良いところで本人的に納得してやめるので、親が心配になるような感じでずーっと執着しないんですよ。
ゲームはさせたくないって親御さんも多いと思いますが、ゲームはやっぱり良いですよ。多くの研究でもゲームの良い側面がどんどん語られるようになってきてますが、何よりも子供が興味を持ったら是非やれるところまでやってみたら、と言ってやって欲しいですね。
そうすれば、少なくとも反動で僕みたに40歳過ぎてもゲームやりたいゲームやりたい、みたいな大人にはならないかも(笑)
――なるほど。いや、いいお話でした。どうもありがとうございました。

取材構成 黒川文雄 @取材2018年
@エンタメステーション
撮影 / 北岡一浩 取材協力 / 仁志睦
御高覧ありがとうございます。励みになります。このnoteの記事は2017-18年にエンタメステーションに掲載した記事が廃刊につき閲覧ができなくなったものをを復刊させているものです。更新は黒川の手が空いているときに行っているため不定期更新ですが、これからもよろしくお願いします。
以下のテキストは有料ですが、このエンタメ考古学や黒川塾などの活動を応援していただけるかたのみ課金のうえ閲覧いただければ幸いです。基本的に書いてある事はお礼の言葉です。ありがとうございました。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
