
Slackの「👀」を超えよ!AIと共に変化するチームづくり
AI時代は、頼もしく不安だ。
新しい年が始まり、心機一転「今年こそは」と意気込んでいる人も多いはず。でも、組織の中では意外と早い段階で「なんだか去年と変わらないな」って思ってしまう瞬間が訪れていませんか?
たとえば、「新しい目標を掲げたのに、結局いつもの根回しや忖度ばかり」「チームの連携を強化したいのに、空気を読むばかりで本音が出てこない」「Slackでチーム全体に呼びかけたけれど"👀”の絵文字カウンターが10個を超えただけで返信がない…」といった悩み。
その中でもAIのニュースは日々更新されていき、最新情報をキャッチしながらも現場で消化しきれていないことに不安を覚え、悶々とすることもあると思います。

このリアクションはよく使う
実際、私の元にも相談が来ます
リブランディングやインナーブランディングの支援をしていると、「社内の人間関係が原因でプロジェクトが思うように進まない」という声をよく耳にします。目標や計画は立派でも、結局その「人間関係のモヤモヤ」がボトルネックになってしまうんですよね。
これは、裏を返せば「ちゃんと話せていないこと」が根本原因のことが多いんです。「伝えているつもり」「わかっているはず」そんな思い込みがコミュニケーションの壁を作ってしまっているケースがとても多いのです。
…さあ、ここで、心のなかで一緒にさけびましょう。
せーの!

それが相手にも自分にも起きています
…そんなこと、わかってるよ!!!!!
そうですよね。もちろんそんなこと「👀」の時点でとっくに気がついているはずです。少なからずマネジメントに関わる方々でしたら、年末年始の合間に多くの積読本や記事を読みあさっていると思います。(それにしても👀←この顔文字が本当に苦手…こんな表情したことありますか?笑)
実際、私もその問題について頭を悩ませているひとりでもあります。
これまでもスタートアップ、プライム企業、売上100億円を超える中小企業・団体とプロジェクトを組んだ数でいえば数百単位となりますが「ちゃんと本音で話してくれているか」「どうしたら無駄なことを考えず、目標に向かって積極的に・主体的に動いてくれるか」をしょっちゅう考えたりします。
さて、この問題をどこから着手したらよいのだろうか、そんなことを考えていた矢先、ご一緒していた企業のブランド戦略担当の方から新年のご挨拶が届きました。そこにはひとつのPDFが添付されていました。
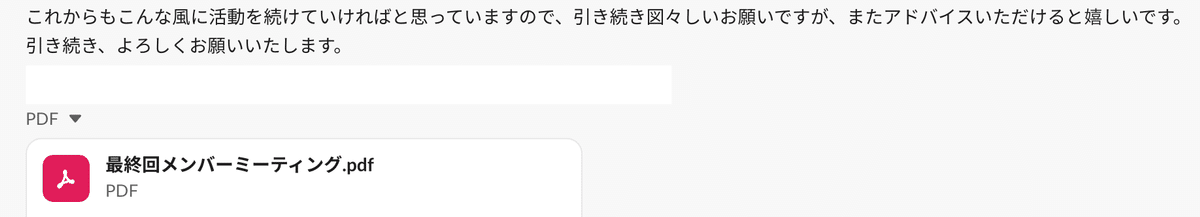
結論、開いた5分後に泣いてました。
あまり涙腺は弱くない方の私が、新年早々に泣きました。
そこには、2年間に渡り繰り広げられていた社内プロジェクトの最終ミーティングの様子がレポートにまとめられていたのです。
2年間、自分の通常業務と並行してブランディング戦略のほかさまざまな広報活動に携わり、紆余曲折や葛藤を乗り越えてブランド浸透に奔走したことももちろん感動なのですが、最後のこの一文に泣かされてしまいました。
このプロジェクトチームは一旦解散となりますが、このモチベーションを次の施策に繋げたい。という話しもメンバー内から挙がっています。この会社を想う気持ちはひとつ。より良い会社づくりのため部署間を超えた連携をこれからも続けていきたいと考えています。
よくある社内の忖度や不透明性。同じ会社でも業務内容が見えず、コミュニケーションが取れない。そのようなことはどの会社でも起こり得るのですが、まさにその壁を第一段階、第二段階と乗り越えていることを背中で見せてくれました。
社員の生の声は、何よりも大切なエネルギーの源です。かくいう私も早速、ファイル名の冒頭に【宝物】とつけてレポートを保存しました。ありがとうございます。
共通言語で語ろう、そして増やそう
会社の規模が大きく、もともとお互いのコミュニケーションもないといった組織が、同じメンバーで同じ会社、同じ組織でありつつも、最終的には組織文化醸成ができ、部署を超えた連携が始まって、その点が段々と面に広がっていったのはなぜか。
俯瞰してみると、
そこには「共通言語」が生まれ、増えたことにほかならないです。
私たち人間の社会生活においてコミュニケーションは必須です。共通言語を持つことは、互いの信頼関係が生まれて、安全性が担保されていきます。
共通言語があると、共通認識がうまれます。その状態を維持していけば、安心感を覚える「環境」ができます。
安心できる環境があると、適応力に差がでます。
以下はリクルートマネジメントソリューションズが発表したデータです。
“個人の心理的安全性から適応感へのパスについては、高群で.30、低群で.50となる。つまり、職場の心理的安全性の水準が低いと、心理的安全性を感じていない個人の適応感の低下の影響が大きくなるということだ”と発表されています。

共通言語をきっかけに環境ができ、同じ組織・会社でも発揮できる能力に変化が出る。それが特に適応力になれば、この差が、特にこれからのAI時代で「これって何のため?」と疑問や不安が自然となくなり、「そのツールをどんな目的で使い、どう価値を生み出すか」という視点に変わります。この違いが、今後のAI時代における競争力の差を生むのではないかと考えています。
なにより、わたしたちの身の丈に合う言葉のやりとりは、感性を育てます。その感性が、何よりもその人、組織の財産になるはずです。
この時代にさらに増やすべきなのは対話
AIが多くの業務を代替する時代になっても、人間同士の「対話」や「共感」は機械には代替できない価値です。イーロン・マスク氏がテスラの社員をリモートワークから現場に復帰させたのも、対話を増やし、セレンディピィティを生み出すことを大切にしたからだと予想されます。
個人的にはハイブリッドな働き方を推奨していますが、互いの共通言語を持ち、対話を進め、理解し合える組織は、変化に強く持続的な成長が可能になるとインナーブランドの視点でも見込んでいます。
「👀」の反応はさておいて、ぜひ、有志たちを集め、「WHY」と言う視点をもって、共通言語を起点に対話を進めてみてください。否定しないルールを共有した上で、対話を楽しんでもらいたいと思います。最初は手軽な話題で良いと思います。まずは対話になれる環境を作ってみてください。
新年のスタートは、組織を変える絶好のチャンスです。情報の共有だけでなく、対話を通じて共通言語を増やしていきましょう。
それが、AI時代を生き抜く組織の強みとなってあなたのチームを次のステージへと導く鍵になるはずです。
今年のチームは、きっとここから変わるはず。
共通言語の一例:
1. 昨年この会社で取り組んだなかで一番思い出深い成功体験
2. その理由
3. 今年やりたい取り組み、その理由 など
未来をつくる共通言語が欲しいと言う方は、ぜひこちらもお読みください▼
質問受付開始!
