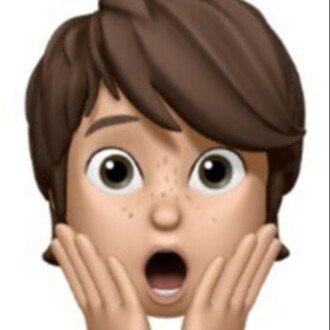【IB子育て・日々悶々】そもそも学校ってなんだろ〜
久々に、教育について色々考える機会があって書いてみることにした。
この秋、初めて熊本の地を踏んだ。子どもたちの秋休みを利用して、どうしても来たいと思っていた熊本に子どもたちを引き連れてやってきたわけだ。
1番の理由は
Streer Sports Studio 熊本(通称:SSS熊本)と、その運営をやっている1人のWing Kumamotoの小笠原くんに会いに行くため。
予想通り、子どもたちは「今すぐこれを東京にも欲しい」と言うほど、施設のコンセプトに共感していた。
ちなみに、「アーバンスポーツ」への関心は、文科省の肝入りで、ある意味がっつりと全国津々浦々、向上させられているようだ。
→これも小笠原くんたちに聞くまで知らなかった事実!
こんなに補助金も出ているらしい。
こんなのを読むと
ツーリズムに関する設問では、競技会・大会出場のための旅行経験は、イベントや競技会・大会などへの出場のために、宿泊を伴う旅行経験者が55.3%を占めている。行ってみたい施設の有無では、「全国の施設にぜひ行ってみたい」が83.5%、「まあまあ行ってみたい」を加えると98.2%となっている
まぁ、確かに私でさえ東京から熊本まで来ちゃったので。十分「スポーツツーリズム」に乗っかっちゃってるようなもの。
さてその一方で、子どもたちが抱える社会課題の一つである「不登校」の問題は、熊本でも、東京でも変わらないようだ。
ちょうど、小笠原くんたちと話していても、周囲に学校行けなくなっちゃった子たちがいて、でもそんな子たちでも、スポーツ施設を通じてちゃんと家族以外の大人や子どもと付き合えている子もいる、というような話しを耳にした。
今日やまださんのnoteを読んでいて、改めて学校に行かれない子の理由の大多数が
「無気力・不安」
となっていて、無気力っていう言葉に、集団生活を送ることの窮屈さに耐えるために、無気力でいることが唯一の方法かもなぁと思ったりしてしまった。
今から振り返ると、小学校2年の頃、年間の欠席日数が30日に上った私ですが、母曰く本当に熱出してたと言っていましたが、弟が体調崩して休むと一緒に休んでいた私で、いい感じにズル休みをしていたようだ。
ただ母がゆる〜く受け止めてくれたおかげで、私はその後中学くらいからは、皆勤連発するくらい学校生活に馴染んでいった。
もちろんこういうゆるい生活が許されたのも専業主婦をしていた母が家に居てくれたおかげではあるのだが、それ以上に学校に行きたくない私の気持ちをちゃんと受け止めてくれたことも大きかったのかなと思う。
一方で、我が家の子どもたちは学校は楽しく通う場所であって、行きたくない気分になったりしていないのは、やはり学校の先生や同級生はじめ、集団生活なんだけれども、ある意味それぞれの個性を受け止めてくれる場が用意されているからなのかもしれない。
そういえば、今年読んだ孫泰蔵さんの著書「冒険の書 AI時代のアンラーニング」に、学校教育の発展に関する件が書いてあったけれど、「産業革命」のために、大勢の働き手に同じ行動をしてもらいたいことが理由だったと聞く。
こんな論文「イギリス産業革命期の児童の雇用と教育」(永田正臣著)も発見。
やっぱり、今の形は社会の様子と合ってないようなぁ。。。と思う今日この頃。
いいなと思ったら応援しよう!