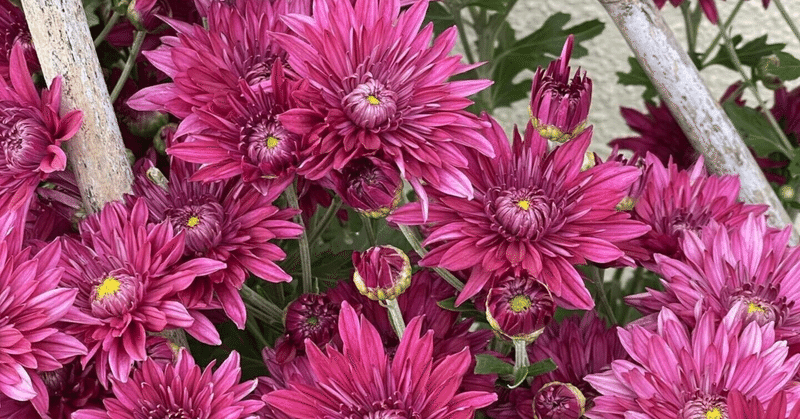不定期にnoteに掲載している「これだけは覚えておきたい日常生活でよく使う『ことわざ』『言い伝え』『故事成語』」をマガジンにまとめて販売することにいたしました。ことわざに興味をお…
¥1,000
- 運営しているクリエイター
#教訓

日常生活でよく使う「これだけは覚えておきたい『ことわざ』『言い伝え』『故事成語』」(第19回)- - -「一難去ってまた一難」
Ⅰ「一難去ってまた一難」ということわざの成立過程・意味・用法について 「一難去ってまた一難」は、日本のことわざであり、困難や苦難が絶えず訪れるという意味を表しています。このことわざの成立過程は具体的には明らかではありませんが、多くのことわざと同様に歴史や人々の生活経験から生まれたと考えられています。 意味としては、一つの困難や問題が解決されても、次に新たな難題が現れるという現実を指しています。生活においては絶え間ない試練や困難が待ち受けていることを示唆しており、人々に忍
¥100