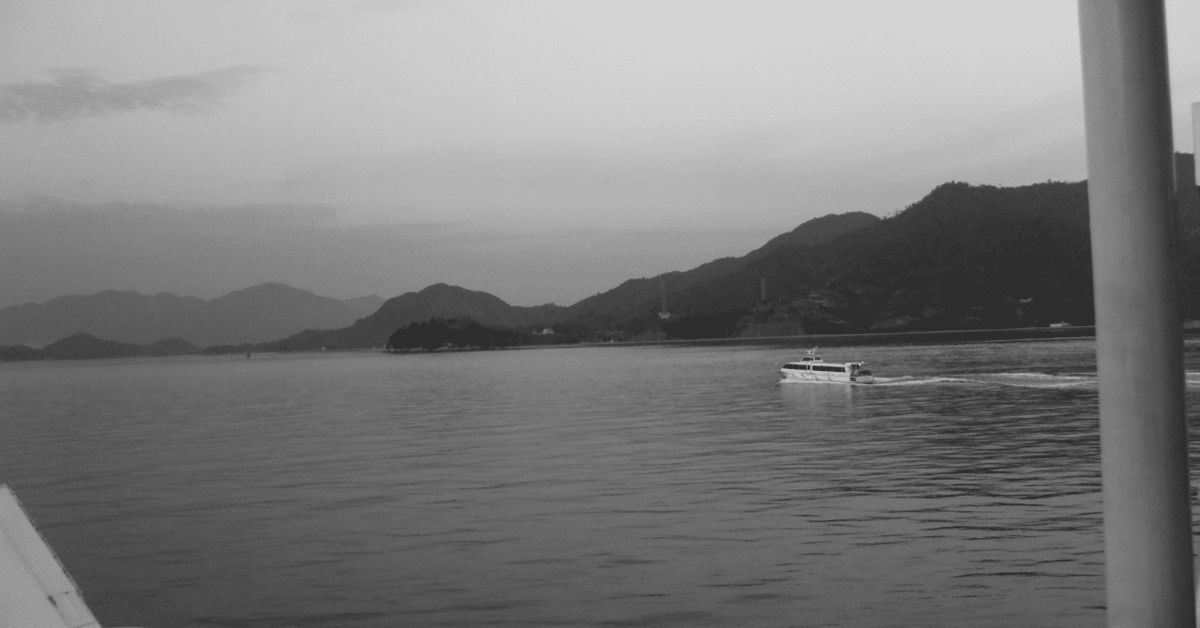
「歴史を逆なでに読む」 カルロ・ギンズブルグ
上村忠男 訳 みすず書房
「逆なで」とはベンヤミンの歴史テーゼ(ちくま文庫だとコレクション1収録)に現れる言葉。ここでは異端尋問官とか裁判官とかもろもろの書類(現時点では残存する史料)の作成者の意図に逆らってそれらを読むということ。そこに関してデリダの「テクストの外部は存在しない」というテーゼに反論しているが、「外部は存在しない」というのと「テクストの内部に外部が巣食っている」というのは関心のあり方の違いだけではないのか。
歴史を逆なでに読むー日本語版論集への序言
1
第1章 証拠と可能性
第2章 展示と引用ー歴史の真実性
第3章 証拠をチェックするー裁判官と歴史家
第4章 一人だけの証人ーユダヤ人大量虐殺と現実規則
2
第5章 人類学者としての異端裁判官
第6章 モンテーニュ、人食い人種、洞窟
第7章 エクゾティズムを超えてーピカソとヴァールブルク
結びに代えてー自伝的回顧
1部が歴史学方法論、2部が他者理解論という構成。第4章が歴史と物語の境界を曖昧にする物語論では、ナチスのユダヤ人大量虐殺は存在しなかったとする歴史修正主義を論駁できない、という論考。1部と2部を橋渡しする第5章は異端尋問官の記録を読むことによって、異端尋問官とは違った視点に立つことは可能か、という論考。それを受けて第6、7章は「歴史を逆なでに読む」実践編、といったところ。
(第2、5章は読書メモがなかった・・・)
二人とも、伝統を、それを生産した者の意図とそれを利用してきた者の意図に逆らって利用した。ある意味では、二人とも、伝統を逆なでに読んだのであった。
(p15)
第1章 「証拠と可能性」
第1章は「帰ってきたマルタン・ゲール」(中世のマルタン・ゲール事件を題材にした映画作成のための歴史考証をもとにした本)をとば口に、歴史と物語(小説)その他の差異をみようとするもの。デフォーやフィールディングの時代には「これは歴史なのですよ」と註釈を入れたのに対し、バルザックやマンゾーニの頃になると「(今までの)歴史叙述では看過されてきた日常の細部を照らし出す歴史叙述それが小説なのだ」という考えが出てくる。
知りうることの範囲をこえて推測をたくましくできるというのは、人間の高貴さと強力さの一部です。歴史はありそうなことがらに頼るとき、まさしく、人間のそのような性向を助長ないし鼓舞すること以外のなにごとをもおこなってはいないのです。歴史は、そのときにはしばらくのあいだ、物語ることをやめます。その場合には、物語はよい道具とはならないからです。そして物語の代わりに、帰納という道具を使います。
(p44)
彼(アルセニオ・フルゴーニ、イタリアの中世史家)は、その『十二世紀の資料におけるアルナルド・ダ・ブレッシャ』のなかで、「文献学的=結合的方法」、すなわち、過去のもろもろの証言に欠落した部分があっても、それらは神の摂理の働きでなんとか埋め合わせがつくものだ、という研究者たちのあいだに広く浸透している素朴な思い込みと、熾烈な論戦をまじえている。
(p46)
史料の欠落部分を物語的想像力で埋め合わせて復元しようとする、伝統的物語論の態度をここでは批判している。ではどのような方法が他にあるのか。それがこの後の章で展開されるのだろうか。
(2017 02/19)
歴史家と裁判は似ている、というか交差している。証拠を必要としていること、弁論が重要であることなど。
第3章 「証拠をチェックするー裁判官と歴史家」
架空の伝記と「真正なる記録」とを混ぜ合わせることによって、歴史家たちは三重の障害ー対象(農夫、魔女)が普通一般に受け入れられている基準からすれば取るに足りない存在である、証言がわずかしか残っていない、ふさわしい文体モデルが存在しない、というーをひと飛びで乗り越えることができたのである。
(p88)
19世紀から徐々に出てきた庶民の歴史記述(ミシュレ「魔女」など)。これと20世紀のものとの違いは、20世紀のは一人の人物の歴史をできるだけ復元しようとしていたのに対し、その前の世紀のものは古代から今までの農夫とか魔女とかの記録を通史的に眺め、それを架空の人物に投影している、というところ。
第4章 「一人だけの証人ーユダヤ人大量虐殺と現実規則」
すべての証言はただ自分自身を証言しているにすぎない。自身の生まれた契機、自身の起源、それのめざす目的を証言しているにすぎず、それ以外のなにものをも証言してはいない。
(p125)
未来派の絵画のような断片化されているこの短編自体も気になるが、このセッラの言葉を受け入れた上で、さらにそれを「逆なで」に読むことが要求されるのか。その読み方は続く第2部で…
(2017 03/08)
第6章「モンテーニュ、人食い人種、洞窟」
モンテーニュの「エセー」の「人食い人種」の記述が「多民族理解」の先駆けとなった、という近年の通説に対し、別の読みもあるのでは、とするギンズブルグ。次はモンテーニュ自身が「エセー」を例えた文章。
グロテスク、すなわち、その多様さと法外さが唯一の魅力である空想的な絵画
(p154)
この後で出てくるのだが、ガリレオがタッソの『解放されたエルサレム』に挿入した紙に書いたという、タッソとアリオストとの比較がある。ガリレオによれば、タッソの叙述は「油彩画というより寄木細工または象眼細工に」似ている。継ぎ目を目立たなくするほど細工するのは難しく、どうしても輪郭がくっきりし過ぎて味わいがない。それに対してアリオストは「柔らかくて、丸味があり、力強くて、浮き出しに富む」油彩画に喩えられている(p173)
ガリレオが書いているところによれば、彼は、アリオストの『狂乱のオルランド』を読んでいたときには、自分が最も著名な大家たちの作になる数多くの古代の彫像で飾られた王室の柱廊にいるような気分になった。これにたいして、タッソの『解放されたエルサレム』のほうは「めずらしいものを趣味にしている名もない人物の熱中ぶり」にたとえるのが最もふさわしいというのである。
(p175)
モンテーニュの場合は先のp154の文で見られたように、どこかタッソ寄りのグロテスクさを愉しんでいる。いろいろな文書が均衡美もなく雑然と並ぶ「エセー」はつぎはぎだらけのマニエリスムというわけだ。
モンテーニュが驚くほど容易に新世界の原住民たちを彼ら自身のあるがままの姿に即して理解することができたという事実にしても、これ自体は、さらに広く、風変わりなもの、遠く離れたところにあるもの、異国的なもの、新しくて珍しいもの、自然を模倣した芸術作品(プラトリーノの洞窟のような)、そして彼の目にはとりわけ自然に近いところで生活しているようにみえた住民たちに強く魅せられていたことの一部分をなすことがらであったのだ。
(p176)
そしてこういう世界観、審美観というのは、一人モンテーニュだけでなく、この時代多くの人々に共有されていたものであったという。
さて、この論文の最後には、ブラジルからの原住民がフランス国王に面会した時の彼らの驚きを「エセー」からギンズブルグは引用している。
あなたがたのなかには、あらゆる種類の利便に満ちあふれた連中がいる一方で、その「半身」たちは、それらの連中の門口で乞食をし、飢えと貧乏で骨と皮になっているのが見てとられるが、どうしてこの生活に困っている「半身」たちがこのような不正を耐え忍んでいられるのか、どうして相手方の喉元につかみかかったり、家に火をかけたりしないのか、不思議におもう
(p184)
(2018 11/05)
第7章ピカソの「アヴィニョンの娘たち」
細かいところはちょっとわからなかったが、自分的には、こに絵が物語的要素の地中海性と、非物語的要素の北欧性を合わせもった絵だ、という指摘が面白かった。後者はピカソも大いに参照したル・ナン兄弟の構図。
ル・ナン兄弟によって『鍛冶屋』のなかで描かれている人物たちは、まるで突然の訪問者に驚いたかのように、絵の外を見ている、とサント=ブーヴはかつて書いた。ジャック・テュイリエは、この指摘を受け継いで、ル・ナン兄弟の絵においては、しばしば、人物たちの一点に停止した視線が「絵をそれを見ている者へと開け放つ」と強調している。
(p194)
この構図が「アヴィニョンの娘たち」にも共通し、しかも予備段階ではあった(物語的要素を感じさせる)画面左右の男の人物を削った、という。
それからアフリカ芸術と西洋古典的人物構成比とをこれまた共存させている、という話に移る。相対する要素だと思われるこの二つは、実は世界的にみると共通して「古典的」なものである、とピカソは捉えたのではないだろうか、と。
アビ・ヴァールブルク(19、20世紀のドイツの美術史家)は、 プエブロ族の儀礼等を見て、ゲーテ「ファウスト」の言葉を借り(「まるで古い本でもめくっているようだな/アテネとオライビ、親類だらけとはね」(オライビは現地の村)p225))、ピカソと同じ着想を語っているとギンズブルグは指摘。
(2018 12/24)
「結びに代えてー自伝的回顧」
これは『夜の歴史-サバトを解読する』(邦訳題は『闇の歴史-サバトの解読』竹山博英訳 せりか書房)の成立までを回想的に述べたもの(日本での講演)。
ベナンダンテと呼ばれていた民間儀礼?で、夜の平原で魔法使いと戦う、というものが16世紀頃にあったという。ギンズブルグが丁寧に裁判記録(当然異端審問側の記録)を読んでいくと、どうやら審問側も知らない文化の一端で、ルーツは中央アジアのシャーマニズムにあり、ハンガリーとフィンランドを結ぶ付近に分布している、とギンズブルグは考えた。それを審問側はサバトと読み替えていて、ギンズブルグは最初は「これは異端ではなく階級闘争の一つの現れなのではないか」と思って研究していた。それには左派の政治家のロシア系の父の影響もあったという。
特殊例をみつけて「面白いものがみつかった」とほくそ笑むアノマリー(変則)と、一つの規則に還元しようとするアナロジー(類似)の学者の記述。ギンズブルグは自身をやや前者側と認識しているが、仮想の対話相手としているレヴィ=ストロースはやや後者なのだろう。
ベナンダンテの詳細は「闇の歴史」を読むこととして、ここでは最後に一文を引いておく。
わたしたちがすでに知っていること、もろもろの経験を詰め込んだわたしたちの手荷物の一部分となっていることのみが、たえまなく降り注いでくる混乱した偶発的な情報の山のなかから新しいものを分離し、新しいものとして認識することを可能にしてくれるのです。
(p242)
(2021 12/31)
