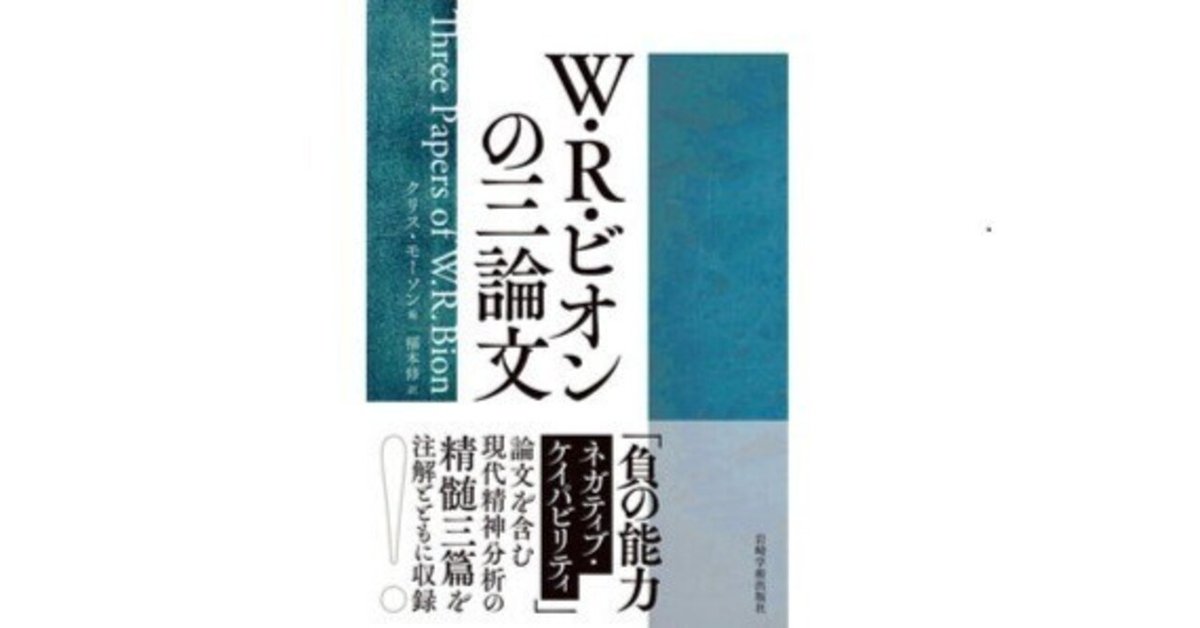
『W・R・ビオンの三論文』
後期ビオンの始まり?
本書は、“Three Papers of W.R. Bion” Edited by Chris Mawson, Routledge, 2018.の全訳である。タイトル通りビオンの三つの講演記録を収録し、それぞれに編者のクリス・モーソン(1953-2020)がかなり長めの、これまで知られていなかった重要な資料も交えて解説を付けている。
ウェブ上の「内容説明」では、あとがきあるいは解題の代わりに書いた補遺のうち、負の能力(ネガティブ・ケイパビリティ)に関する部分が、引用されている(http://www.iwasaki-ap.co.jp/book/b635696.html)。詳細は実際に手に取ってご覧いただければと思うが、その概念は、まだ提示されたところである。より詳しくは、『注意と解釈』(1970)と合わせて検討される必要があるだろう。
さて、『精神分析の要素』(1963)までのビオンは、解釈の対象を三つの次元、(1)感覚の領域、(2)神話の領域、(3)情念の領域に跨るものとしていた。そして解釈の生まれる場面を主に、患者の投影を受け止めて理解すること、「包容することcontain」、母親の「夢想」に類比していたのではないだろうか。そこでただ排泄の受け皿とならず、情動的・言語的理解にまで至ることを含めると、それはカップルとしての心が意味を生み出すという、一種のポジティブ・ケイパビリティである。
その局面で彼がネガティブ・ケイパビリティ、心という容器を空にすることを強調するようになったのは、Kへの関心からOへの関心への移行に一致している。しかしもっと臨床に関連して言うと、「夢想」つまりは普通の発達の範囲で理解しようとしていると、理解が限定されると感じるようになったのではないだろうか。『ブラジル講義』の例を見てみよう。
『ブラジル講義』からの例1
「頂点を変更すると、患者は曲を書いたり演奏したりしようとすることに耐えらないほど、或る音符を他のものと識別する能力を有しているのかもしれず、私たちには彼が音楽家として能力不足に見えるかもしれません。しかし、彼が音楽家であることや音楽を聴くことさえできない理由は、彼が大変鋭敏な音楽家だからです。
頂点をまた変更すると、患者が諸々の色(物理学者ならば視覚要素と呼ぶ、光の波長の諸変化の中の差異)を、見えないからではなくて分析者が見られるよりも遥かに多く見えるので、諸々の差異に耐えられないほど識別できるとしましょう。私たちは、こうした頂点を増やすことができます。その人が、特別な才能を有していないためにできないように見える領域には、何の制限もありえません。「ああ、彼は幻覚を見ています」とか「彼女はひどく不穏な状態です」と言うことは、巨視的な視点からは本当かもしれませんが、被分析者ができることを私たちが見たり聞いたり直観できたりするとしたら、本当ではないでしょう。精神分析者たちは、諸々の差異や被分析者の諸困難に、それらが何であるかを認識するのに十分なほど長く、耐えることができなければなりません。精神分析者たちが被分析者の言うことを解釈できるべきならば、自分たちが解釈を知っているという結論に飛びつかずに被分析者の言明に耐える、優れた能力を有していなければなりません。これはキーツが、シェイクスピアは〈負の能力〉に耐えることができたに違いない、と言ったときに意味していたと私が考えるものです。」(『W・R・ビオン全集』第7巻p.48)(『ブラジル講義』「一九七三年 サンパウロ6」)
無能力に見えるものは、実は過剰能力の故であるという、常識の逆転がある。ここでの「頂点vertex」は、普通の言い回しでは「観点」で通じるところである。しかしその表現は視覚に結び付いており、いわば〈理解〉――〈記憶〉と〈欲望〉の現在形である――の過多なので、五感のどれと特定しない形により抽象している。こうした拡張自体、一種のネガティブ・ケイパビリティによるとも言える。同じく『ブラジル講義』から、もう一例見よう。
『ブラジル講義』からの例2
「私は、もしも私がこの患者を聞くなら、もしも私が患者の言おうとすることを聞くと覚悟するならば、もしも患者が私のところに来るならば私が自分に見えるものを見ると覚悟するならば、患者は私が普通の言葉を使っても私が彼に言うことを理解できないかもしれませんが、私が逃げ出しておらず、彼を精神病院に閉じ込めておらず、明日彼に会う手配ができているという事実の意味を、理解することできるかもしれないと信じています。そのどれも言語的に表されてはいませんが、それでも、これまで分析者が部屋にとどまり、おそらく明日も部屋にいるだろうという事実自体が、分析者が理解せず患者が理解していないけれども、2人がともにはっきりさせなければならないであろう言語を構成することがありえます。それが正しいのならば、今日のセッション、明日のセッション、そしてまだ行なわれていない他のあらゆるセッションが、患者に影響を与えるかもしれません。もし分析者が耳を傾け、目を開き、耳を開き、感覚を開き、直観を開く覚悟をしているならば、成長すると思われる被分析者に影響を与えます。セッションは患者の心に、身体的な経験の事柄であれば『良い食べ物』と言えるものを提供します。
分析者はまた、無知――自分自身の――と、自分が神秘、半分の真実[原書p.48–〈負の能力〉]の場にいることに耐えられなければなりません。このことは、心にとってそれが成長できるような経験をすることを、可能にするように思われます。もしも赤ん坊に、その子が死ぬほど苦しんでいたり狂っていたり愚かだったりするのを怖がることに耐えられる母親がいるならば、その赤ん坊はそのような母親がいることで、気分が改善するようです。もしも母親が耐えられなければ、赤ん坊も耐えられず、結果として赤ん坊は、心が成長できないと思われます。もしも赤ん坊が成長していくならば、それは特異な仕方でそうしなければなりません。そのことは翻って、それを一定の形に成長させる効果があります。後に誰かが、「精神病的」とか「統合失調症的」とか「境界例」と言うでしょう――それはまるで診断のように聞こえます。」(『W・R・ビオン全集』第7巻p.125)
この例では、〈負の能力〉に関連した「半分の真実」への言及があるのみだが、注はビオン存命中で、著者に確認済みと思われる。ビオンは、患者に予断を持たずに待つ姿勢を示す精神分析の設定が、ネガティブ・ケイパビリティを発揮しうることを語っている。結局、それは容器の性質だからである。続いて母親への言及がある。母親が赤ん坊の情動の乱流に耐えることは、夢想の一部である。そこで不安や不快に反応してすぐに行動に移さないのが、ネガティブ・ケイパビリティであろう。ただ、母親のすることは受容に限らない(積極的な受容であっても)。赤ん坊にあれやこれやと持ち掛けて、自然と交流の世界に引き入れている。治療では通常、関連性がありうるものでもそうした持ち込みは行なわずに受身性を保つことになっている。
だが「夢想」はアメリカに渡って、オグデンのように治療者が自分の経験からの連想を述べるものに変わっていったようである。それは概念受容の問題なのだろうか、それともビオン自身の変化によるものなのだろうか。むしろ、ビオンが指しているネガティブ・ケイパビリティは、その手前のことだろう。それは多様性を可能にする条件でもある。
