なぜか買ってしまうカラクリを考える「グリーンDAKARA編」vol.3
なぜあの商品はヒットしたのか?
ブランドマーケティングの世界ほど「勝てば官軍」な世界はあまり無いのですが、ヒットした理由、ロングセラーになっている理由、ヒットするまでの失敗の歴史を、大学生が分かるようにひも解いていきます。
これまでVol.1とVol.2で以下について書いてきました。
Vol.1:グリーンDAKARAの成功には、しくじりに学んだ歴史があった…?!(https://note.mu/fujimarketing_12/n/nf4458aa9468d)
Vol.2:グリーンDAKARA商品化にあたっての競合商品との差別化、
プロモーションにおけるターゲット層の選択と集中(https://note.mu/fujimarketing_12/n/n2fd6683951fa)
そして今回は最終回。
発売から時が経ち、現在に至るお話し。これはブランドマーケティングの宿命とも言うべき、商品のLCM(ライフサイクルマネジメント)についてです。
※ライフサイクルマネジメントとは?
あらゆる商品は導入期、成長期、成熟期、停滞期、衰退期、と言われる5段階のステージを踏みます。ただし、売れない製品は各ステージで淘汰されるため、衰退期まで進む商品は稀であるとも言えます。ステージの変遷時間は商品により異なるため、適切な定量データをもとに判断する必要があります。詳しくはマーケティングの教科書でも読んでください。
・ライバルの攻勢にも負けず、盤石な体制となったグリーンDAKARAに待ち受ける次なる試練
2012年の発売時に数々の仕掛けにより、スマッシュヒットとなった「グリーンDAKARA」は、2013年には「グリーンDAKARAやさしい麦茶」を発売し、ブランド体制としても盤石のものとなりました。
しかし、日本は資本主義経済。ライバルメーカーは黙っていません。
日常水分補給飲料としての立場を作られたCoca-Cola社は翌年、アクエリアスブランドとして「アクエリアス海と太陽の恵み」を発売。

写真引用:Coca-Cola社ホームページ(https://www.cocacola.co.jp/press-center/press-release/news-20140608)
天然素材、緑色イメージ、水分補給飲料、という全てを被せてくる手法の商品を発売。(同社の十八番手法ですね)
しかし、ファーストペンギン商品であるグリーンDAKARAはこの商品の影響は受けず、安定的な売上成長をマーク。
そのためCoca-Cola社は翌年の2015年にも「Toreta!とれた!」を発売して再挑戦。

染谷将太君を起用したCMを実施しますが、やはりグリーンDAKARAにはかないませんでした。
これでもう日常水分補給飲料市場は安泰、グリーンDAKARAの完全勝利と思いきや、、
2015年は同サントリー社より「南アルプスの天然水ヨーグリーナ」が新発売。あまりの美味しさに発売直後に品切れになるという一大ブームを巻き起こします。
実はさかのぼる事、2011年頃から各社のミネラルウォーターブランドのいろはすや南アルプスの天然水からの、フレーバードウォーターもブームとなっていました。
フルーツの味がするミネラルウォーター市場は、オフィスワーカーが飲む、という点ではグリーンDAKARAとカニバリゼーションを起こしていました。
それがヨーグリーナのブームでフレーバードウォーターブームが再到来。
製品訴求ポイントは異なりますが、日常生活の中で喉が渇いた時に飲む、というシーンでは一致。グリーンDAKARAも発売から3年が経過していることもあり、ライフサイクルマネジメントでは一気に停滞期に入りました。
そこで、翌2016年にグリーンDAKARAを前年リニューアル!!
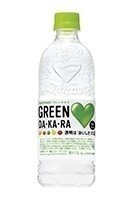
写真引用:サントリー社ホームページhttps://www.suntory.co.jp/softdrink/news/pr/article/SBF0401.html
・商品リニューアルで大きく変えた戦略転換
様々な工夫の末、ヒット商品として世の中に受け入れられていたグリーンDAKARAの風味・見た目を一新するという、攻めの一手に出ます。
正直、このリニューアルを見た時には僕も驚きました。「ええええ、透明にしちゃうの!?もはや日常スポドリじゃないじゃん…!?」というフツーの感想です。当時、ネット上にも「これは改悪。前に戻してほしい」という反応が多く上がりました。
メインの訴求ポイントは変えていませんが、透明飲料となり、味もより薄めに変更。配合されている素材数は減りました。
この方針変更における背景として以下を推察します。
・発売当時にライバル視していたスポドリ市場は、年々縮小傾向となっている。アクエリアスブランドも売上の下落が続き、ポカリスエットも同様。
一方、伸び盛りなのはヨーグリーナやいろはす桃などのフレーバードウォーター市場。コンビニ棚を見てもフレーバードウォーターのフェース数の方が多い現状です。
うまみのある市場が自社・他社商品の移り変わりに伴い変化したため、白濁の見た目(=スポドリ要素)に固執する必要がなくなり、
逆に、見た目が透明な方がクリーンなイメージでグリーンDAKARAの天然イメージに合っている、という結論に至ったのではないでしょうか。(定性調査やFGIを重ねた結果と推察します)
ともあれ、2016年のリニューアル発売後も無事にコンビニ棚に並んでいる事から、大幅な売上ダウンにもならず、リニューアル成功という結果に落ち着きました。
ビバレッジ飲料ブランドのライフサイクルマネジメントの観点からすると、今年の2018年夏には次なるリニューアルが入るものと予測されます。
現在の商品ポジショニングからから類推すると、ブランドエクステンション商品の発売が来るのではないでしょうか。
以上、なぜあの商品はヒットしたのかを考えるグリーンDAKARA編でした。
・今後書いてみたい事
うまくいかなかったブランディング事例
マーケティングという名の異なる仕事の種類解説
次に伸びる産業、会社
マーケティング用語について考えてみる(KPIとKGIの使い方・考え方)
マーケティング分析&研究 藤本たぬき
