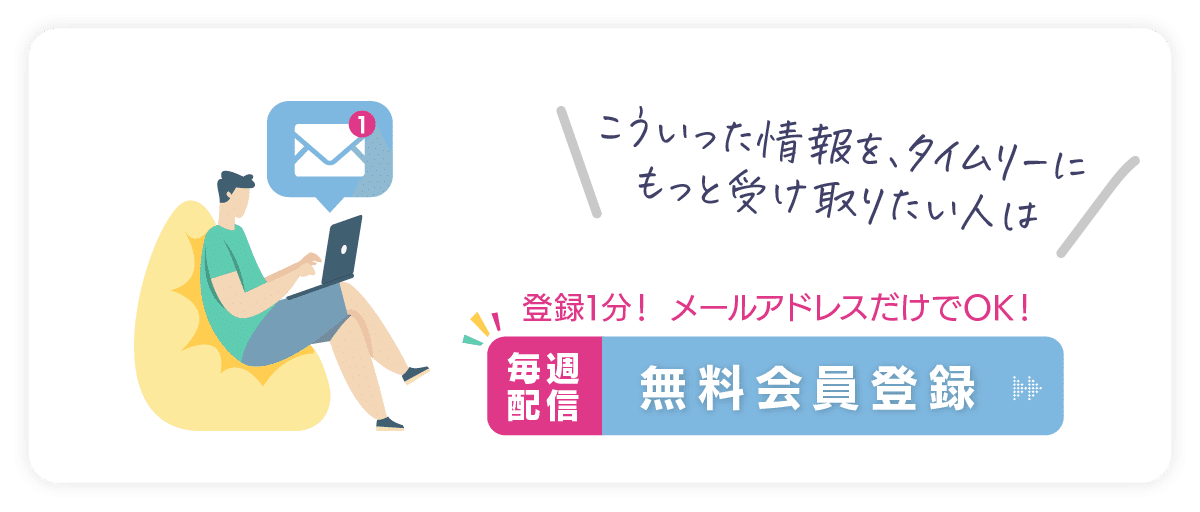年末年始に読みたい、「人生の選択」や「生き方」を考える3冊
年末年始は、日々の忙しさから少し離れ、自分自身と向き合う絶好の時間。2024年の自分を振り返り、2025年を迎える準備として、人生やキャリアを深く考えるための本を読んでみるのはいかがでしょうか。
今回ご紹介するのは、それぞれ異なる視点から「人生の選択」や「生き方」を問いかける3冊です。
これらの本を通じて、自分自身の「次の一歩」を考えてみませんか。
1冊目:大切なものを”大切にする”ための本
1冊目は、『イノベーション・オブ・ライフ:ハーバード・ビジネススクールを巣立つ君たちへ』(翔泳社)です。
著者はクレイトン・クリステンセン。アメリカ合衆国の実業家であり経営学者でもあります。彼自身初の著作となる『イノベーションのジレンマ』で、「破壊的イノベーション理論』を確立。企業におけるイノベーションの研究における第一人者と言われています。その後、イノベーションに特化した経営コンサルティング会社「イノサイト」を共同で設立し、ハーバード・ビジネス・スクール の教授も務めました。
「イノベーション・オブ・ライフ」は著者自らの経験と深い洞察をもとにして、人生という「事業」を成功させるための指針を示した一冊です。
この本の特徴は、複雑なビジネス理論を、私たちの日常に起こる出来事や悩み、そして人生の選択に結びつけているところです。
経営学の理論をもとに、キャリアの選択、人間関係、子育てなど、誰もが直面する問題に対して、新たな視点と解決策を提供します。ビジネス世界での成功を目指すだけでなく、豊かで意味のある人生を築くための道標になりそうです。
ここから、フリーランスに特に役立つと思われる内容を抜粋して紹介します。
衛生要因・動機付け要因という考え方です。
「衛生要因」とは少しでも欠けると不満を生み出すものを指します。代表的なものは、「地位・報酬・作業条件」などです。
一方、「動機付け要因」とは仕事への愛情を生み出すものを指します。代表的なものは、「やりがいのある仕事・責任・自己成長」などです。
ここで重要なのは「衛生要因」が満たされると不満の解消になるけれど、充足感や満足感は得られない、ということです。つまり、たとえ報酬が上がっても、それだけでは仕事を愛するようにはならないということです。
この考えをもとに、本ではこのように記されています。
知らず知らずのうちに不幸なキャリアや不幸な人生にとらわれるのは、自分を真に動機付けるものを根本的に誤解しているせいである。
不幸なキャリアや不幸な人生にとらわれず、幸せなキャリアや幸せな人生を送るには、「動機付け要因」を理解していることが重要なのです。
キャリアの舵とりを、地位や報酬に委ねない
「動機付け要因」を理解するためには、以下のような問いを自分にぶつけてみると良いそうです。
・この仕事は自分にとって意味があるだろうか
・成長する機会を与えてくれるだろうか
・何か新しいことを学べるだろうか
・だれかに評価され何かを成し遂げる機会を与えてくれるだろうか
・責任を任されるだろうか
ビジネスの社会では、衛生要因である「地位・報酬・作業条件」で自分の成功を測りがちです。でも、本には次のように書いてあります。
動機付け要因は職業や時間を経てもあまり変わらないため、これを絶対的な指標としてキャリアの舵とりをしていけばいい。
衛生要因は大切ですが、そればかりに偏りすぎず、やりがいや自己成長につながる仕事、つまり動機付け要因で仕事を選ぶことが大切であることを覚えておきたいと思いました。
資本をお金ではなく、時間に置き換える
次は、良い資本(金)と悪い資本(金)の理論です。
「良い資本(金)」とは、長期的な視点に立って使われ、持続可能な成長をもたらす資本のことです。一方、「悪い資本(金)」とは、短期的な利益や即時の成果を求め、結果として組や個人の長期的な成長を妨げる資本のこと。
早く大きく成長することを求める資本(悪い資本)はほぼ例外なく企業を崖に突っ込ませる。
本では、資本を「お金」ではなく「時間」と置き換えて考えることが示され、人生における時間の使い方の大切さを諭してくれます。
若きエリートたちが陥りがちな間違いは、人生への投資の順番を好きに変えられると思いこむことだ。
たとえば、「もう少し子供が大きくなったら家庭に力を入れよう」と考える人もいるかもしれません。でも、子供、家族、友人との関係構築は時間がかかります。
すぐに見返りが得られるものに自分の資源(時間)を投資して、時間のかかることを後回しにしてしまう…。このように、優先順位を間違えてしまうと真に豊かな人生は手に入らないと言います。
大切な人たちとの関係に実りをもたらすにはそれが必要になるずっと前から投資をするしか方法はないのだ。
フリーランスは仕事を抱えすぎて、1人ブラック企業のようになることもあります。一時的な繁忙期があったとしても、人生の優先順位を間違えずに、幸せな人生のために時間を使っていきたいものです。
これ以外にも「ミルクシェイク理論」「能力の理論」「アウトソースのリスク」など、ビジネス理論を用いながら人生における大切なことを教えてくれています。
この本が示してくれる数々の「知恵」は、充実したキャリアと人生を築く手助けになってくれそうです。
2冊目:100年人生を充実して生きるための本
2冊目は、『ハーフタイム:成功から意義へ人生をシフトする』(東洋経済新報社)です。
著者はボブ・ビュフォード。地元CATVを全国規模に成長させたCEOとして有名です。「リーダーシップ・ネットワーク」「ピーター・F・ドラッカーNPO財団」「ドラッカー・インスティテュート」といった非営利組織の設立にも関与し、経営やリーダーシップに関する教育と支援を積極的に行ってきた一人です。
この本には、人生の中年期における自己再評価の仕方と新たな目標設定の立て方がまとめられています。
人生を2つのフェーズに分け、前半戦は成功を目指し野心を持って仕事に打ち込む時期とし、後半戦はこれまでの経験や知識を活かして、社会に貢献しより大きな価値を生み出す時期としています。
ハーフタイムに突入するのは40代が多いそうですが、50代でも60代でも遅すぎるということはないそうです。
前半戦から後半戦へシフトする期間を、タイトルにもなっている「ハーフタイム」と位置づけており、このシフトする期間がとても重要だと書いてあります。
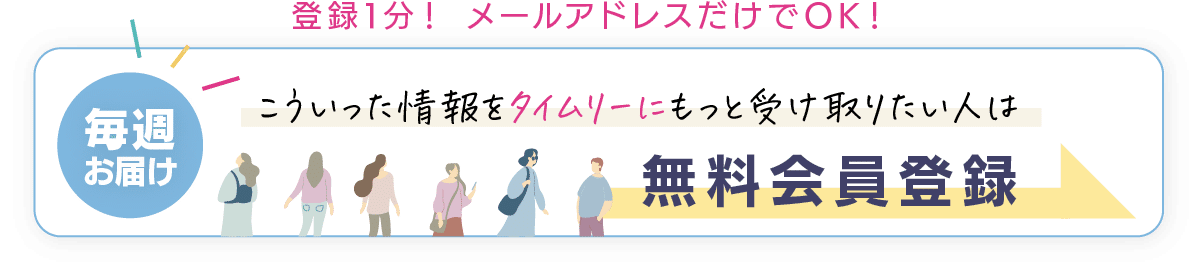
内省し、人生後半の目標を設定する
過去の経験を振り返り、そこから学び、未来に向けて新たな目標を設定する期間。このハーフタイムの過ごし方で後半戦の質が決まるそうです。
成功を追求する前半戦から意義を求める後半戦への移行期となるハーフタイムでは、以下のようなことをすると良いそうです。
自己再評価: 自分自身を見つめ直し、これまでの成功や達成を再評価する。そして次のステップとして何を目指すべきかを明確にする。
新たな目標設定: 自分が本当に情熱を持っていることや、他者にどのように貢献したいかを考え新しい目標を設定する。
内省の促進: 自己理解を深める。自分の価値観や人生の意義について改めて考える。
他者との関係構築:どのような人間関係を築きたいか、自分が影響を受けた人々について考える。
本には、自己の再評価をして、新たな目標設定を促すための具体的な質問が書いてありました。一部を記しておきます。
・私は今大切な何かをみすみす逃しているのではないか
・私は何に精魂を傾けているか
・自分は何者なのか
・自分は何を大切にしているか
・10年後の自分は何をしていたいか。20年後はどうか
フリーランスのキャリアはライフスタイルや価値観と密接に結びついていることが多いもの。とはいえ、じっくりこの質問を自分に投げかける時間を取れない人は少なくないでしょう。だからこそ、時間がある年末年始にこそ、「働く理由」や「生活で大切にしたいこと」を考えてみてもいいかもしれません。
3冊目:ストレス社会で心穏やかに生きられるための本
3冊目は、『社会という戦場では意識低い系が生き残る』(朝日新聞出版)です。
著者はぱやぱやくん。元幹部自衛官としての経歴を持つエッセイストです。防衛大学校を卒業し、陸上自衛隊に勤務。SNSでの活動を通じて人気を博し、Xでは約30万人のフォロワーを持つインフルエンサーです。「ぱやぱやくん」という名前は、自衛隊時代に教官から「お前らはいつもぱやぱやして!」と叱咤激励されたことに由来しています。
表紙の絵や"意識低い系"というタイトルから、ほわっとしたゆるやかな内容なのかと思われそうですが、内容はいたって真面目。「賢く生き抜く術」が書いてありました。
面白いのは、元自衛官らしく現代社会を「戦場」と表現しているところ。確かに、過剰な競争や自己啓発、成功への強迫観念に苛まれる現代人にとって、社会は「戦場」かもしれません。
だからこそ、この本で紹介されている「意識低い系の生存戦略」は、知っておいて損はないはずです。
フリーランスに役立ちそうな「生存戦略」をいくつか紹介します。
生存戦略:人間関係の防空識別圏の設定
防空識別圏とは、国防において領空への侵入を防ぐための警戒領域のことを指します。著者は人間関係においても「領空」と「防空識別圏」という考え方を取り入れることを勧めています。
本当に傷つく可能性のある領域(=領空)まで他人を入れる前に、その人が「敵」か「味方」なのかを見極める期間を作ってみましょう。
残念ながら他人を利用しよう、騙そうと考える人は一定数存在しています。だからと言って「他人を見たら泥棒と思え」では、せっかくの良い出会いを逃すことにもなりかねません。
本には「早い段階で白黒つけるのはやめておきましょう」と書いてあります。そのための「防空識別圏」です。
フリーランスという働き方は、クライアントや取引先、仲間などとの人間関係が多様です。この「防空識別圏」の考え方を取り入れることで自分を守りつつよい人間関係を築いていけるのではないでしょうか、
生存戦略:攻撃されないためにあえて面倒な奴になる
攻撃的な人はどこにでもいます。攻撃的な人をなるべく無効化するための「自衛」の技が紹介してありました。そもそもなぜ人を攻撃するのか。その理由は、「自信がない」か「余裕がない」から、と著者は言います。
攻撃する人はいつでもどこでも自分よりも下の立場の人をつくることで安心感を得ているそうです。
こういう人に対して絶対やってはいけないことがしょんぼりすること、自信をなくすこと。逆に最大の対処法は「面倒くさい人になること」。たとえば、発言の根拠を求めることが有効だそうです。
そのほか、あえて「ヨイショする」こともお勧めしています。
「面倒くさい奴」になるか「ヨイショして自尊心を上げてあげる存在」になるか、状況によって変えても良いかもしれません。
自然体でいられるのが一番ですが、そうも言っていられないこともあります。自分を守るためのテクニック(本には『毒』と表現してあります)をしっかり持っておくことは大切です。
生存戦略:他人を救出できるのは屈強な人だけ
陸上自衛隊には「衛生科」という負傷した隊員を助ける職種があり、一般隊員以上に屈強な人が多いそうです。
もし、誰か1人を助ける役目を任された衛生科の隊員が途中で倒れたら負傷者は2名になってしまいます。だから、彼らを助ける人たちは、屈強でなければならないそうです。
同じことが我々にも言えるのだそうです。
あなた自身が無理をして自分も倒れてしまうのは、優しさではありません。
自分も大変な状況なのにほかの人の仕事を引き受けて自分がパンクしては元も子もありません。ではどうしたら良いのでしょう。
誰かを助けたいと思ったら、
①自分の状況確認をする。
②無理だと判断したら、「助けられる状況にある人」をサポートする。
「助けられる状況にある人」は自分の代わりに困っている人を助けることが出来る状況にある人を指します。その人をサポートすることで遠隔的ではありますが助けたい人を助けられるのです。
自己犠牲は優しさでも思いやりでもないのかもしれません。人に優しくするように自分にも優しくしたいものです。
本を読むと、この本に書いてある「意識低い系」が怠け者のことではないとわかります。
・自分のペースで物事を進める
・自分を大切にする
・無駄に競わない
・自分基準を持つ
・心身の健康を大切にする
こういう人たちのことを著者は「意識低い系」と位置付けています。これらは働き方、仕事内容、スケジュール、健康維持などすべてを自己完結しなくてはならないフリーランスにとって非常に重要なことではないでしょうか。
フリーランスが無理をせず、自分らしいペースで、楽しく働いていけるための道筋を示してくれる1冊です。
年末年始のひととき、これら3冊を通じて自分自身と向き合い、未来への道筋を描いてみてはいかがでしょうか。
人生やキャリアに新たな視点を与えてくれるこれらの本が、次の一歩を踏み出す力になるはずです。
平井圭子
富山県出身。青山学院大学経営学部経営学科卒。
プロフェッショナルファームで10年以上人事業務に従事。妊娠・出産を経て人事系フリーランス&キャリアカウンセラーとして独立。現在はベンチャー企業の人事業務支援、大手法人のダイバーシティ&インクルージョン推進支援、大学・高校での相談業務に携わる。
仕事の目標は仕事が楽しいと思える人を増やすこと。
プライベートでやりたいことは全国の素敵な本屋さん巡りをすること。