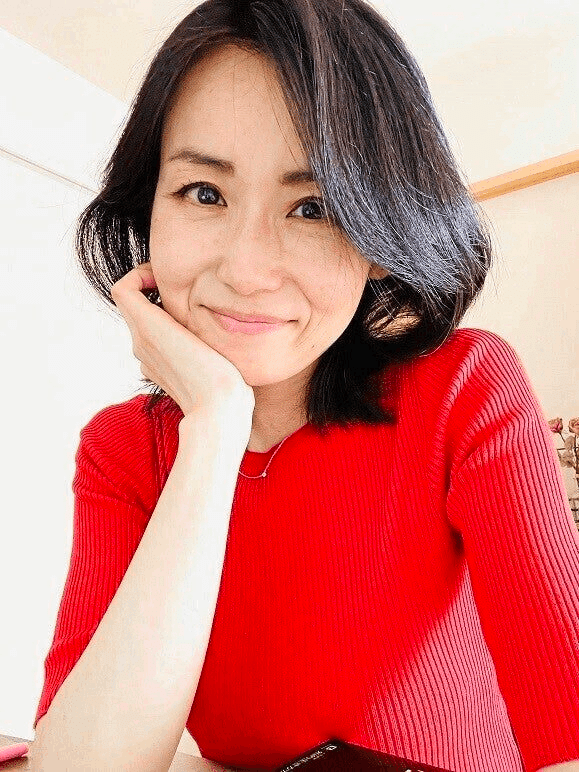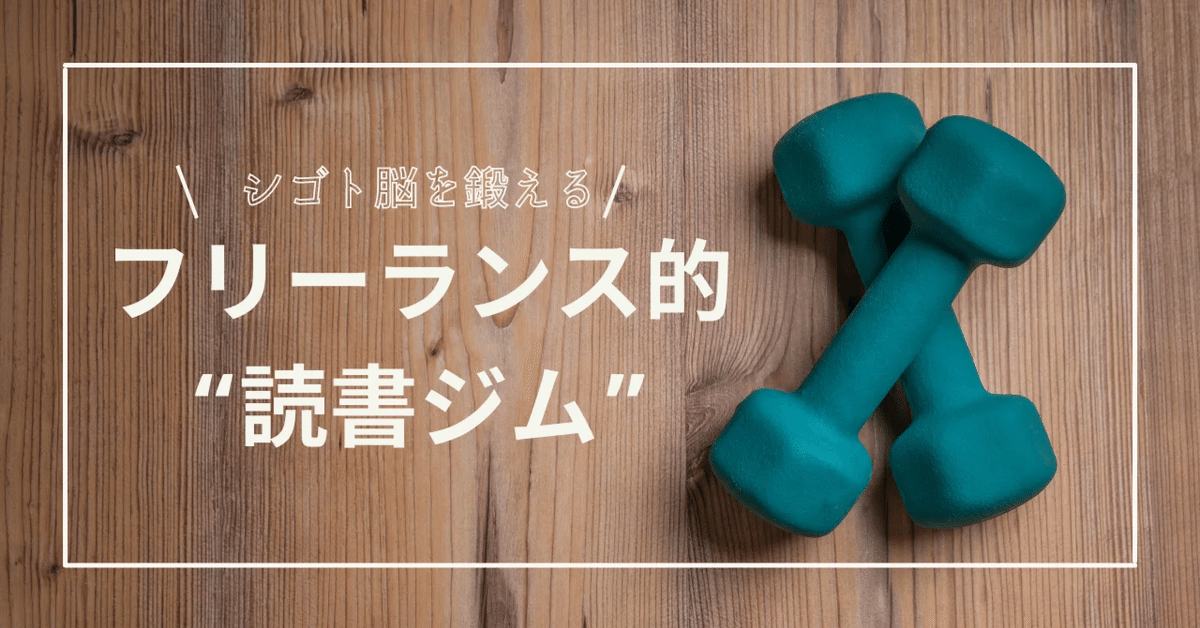
「これからの自分のあり方」を考える。年末年始に読みたい3冊
本は多くのことを教えてくれます。
本の中には大勢の先生がいます。
本は人生を豊かにしてくれます。
今年もたくさんの本と出会うことができました。
新しい年を迎えるにあたり、フリーランスが「これからの自分のあり方」を考えるきっかけを与えてくれた本を3冊紹介します。
【1冊目】令和版、コミュニケーションの本質論
1冊目は『わかりあえないことから コミニュケーション能力とは何か』(講談社現代新書)です。
これからの我々に必要な「コミュニケーション能力」とはどんな能力なのかということを教えてくれる本でした。
著者は平田オリザさんです。平田オリザさんは、日本の現代演劇界で大変注目されている劇作家・演出家です。
大学在学中に劇団「青年団」を旗揚げし、卒業後は「こまばアゴラ劇場」の経営者へ。日本各地の学校で対話劇を実践するなど、演劇の手法を取り入れた教育プログラムの開発に力を注いできた方です。
最近では、2021年に兵庫県豊岡市に開校した、演劇と観光を学べる日本初の国公立大学「芸術文化観光専門職大学」の初代学長に就任し、話題を集めています。
さて、コミュニケーション能力が重要であることは、学校、企業、家庭、地域社会、至るところで叫ばれています。きっと「はじめまして」の人と仕事をする機会が多いフリーランスの皆さんもその必要性を実感されているのではないでしょうか。
とはいえ、「コミュニケーション能力とは、どんな能力なのか」と問われたら、フリーランスである私自身、うまく答えられる自信がありません。
そんな問いを解決してくれるのが、この本です。
世に溢れている「コミニュケーション能力をつけるハウツー本」とは一線を画している点、また、コミュニケーション教育に直接携わっている平田さんの経験から語られる考察が魅力です。
コミュニケーション能力のダブルバインド
本では、日本社会の現状が次のように表現されていました。
日本社会全体がコミュニケーション能力に関する「ダブルバインド」が原因で内向きになり、引きこもっている
ダブルバインドとは二重拘束という意味です。つまり、コミュニケーションの文脈でいえば、2つのコミュニケーション能力が日本社会全体を拘束している、という意味になります。
1つ目のコミュニケーション能力とは、「異文化理解能力」です。
「異文化理解能力」とは「異なる文化、異なる価値観を持った人に対してきちんと自分の主張を伝えることができる能力」や「文化的な背景の違う人の意見もその背景を理解し時間をかけて説得・納得し、妥協点を見出すことが出来る能力」のことを指します。
この能力は、OECD(経済協力開発機構)も重視しています。
2つ目のコミュニケーション能力は「(日本の)従来型コミュニケーション能力」です。たとえば、「上司の意図を察して機敏に行動する」、「会議の空気を読んで反対意見を言わない」などの能力のことを指します。
この2つのコミュニケーション能力が二重拘束されている(=ダブルバインドされている)状況は、「会議では自由に発言してください」と言われたので、反対の意見を言ったら「あの人は空気が読めない」と言われてしまった、ということです。
学校や会社などで、遭遇したことは誰もがあるのではないでしょうか。
人はこのようなダブルバインドな環境に置かれると「自分が自分ではない感覚」「乖離感」を感じるようになるそうです。これが日本で引きこもりやニートが増えている要因のひとつではないかと書いてありました。
必要なのは、「説明しあう文化」を受け入れること
これまでの日本社会は、等質な価値観を持った者同士の集合体を基本として構成されてきました。「わかりあう文化」「察しあう文化」です。
一方、ヨーロッパは陸続きなため、自分とは違う文化や価値観を持つ人と共生する必要があります。自分とは「違う人」と共生するには、自分が何をどう考えるかを伝える必要があります。本にはヨーロッパ社会のことを「説明しあう文化」と書いてありました。
もちろん、日本社会とヨーロッパ社会は文化の土台から大きく異なっています。ですが、今後、我々は今以上に国際社会で生きることになります。つまり「説明しあう文化」に慣れていく必要があるのです。
察しあう・わかりあう日本文化に対する誇りを失わないままに、他者に対して言葉で説明する能力を身につける必要がある。
上記のように、これからの我々にとって大切なことは「コミュニケーションのダブルバインドをなくす」ことではなく、日本社会の「分かり合う文化」「察しあう文化」を生かしたままヨーロッパ社会の「説明する文化」を受け入れていくことなのです。
今後、求められるのは「対話の基礎体力」
では、どうすれば「説明する文化」「他者に対して言葉で説明する能力」を身につけることができるのでしょうか。
そのヒントとなるのが、「対話」と「会話」についての考察です。
会話=価値観や生活習慣なども近い親しいもの同士のおしゃべり。
対話=あまり親しくない人同士の価値観や情報の交換。あるいは親しい人同士でも価値観が異なるときに起こるその擦り合わせなど。
平田さんによると、日本には「対話」という概念があまりないそうです。
なぜなら日本は等質な価値観を持った者同士の集まりだったから。分かりあい、察しあうことが重要視されてきたからです。
つまり、対話する必要性がなかったのです。しかし、国際社会で生きるこれからの日本人には「対話力」が不可欠です。
本には「対話の基礎体力」という言葉が出てきます。
異なる価値観と出くわしたとき、物おじせず、卑屈にも尊大にもならず、粘り強く共有できる部分を見つけ出していくこと
この「物おじもせず、卑屈にも尊大にならない」という態度に新鮮さを感じます。
そして、次のように続きます。
単に対話を教え込むのではなく、対話を繰り返すことで出会える喜びも伝えていかなくてはならない。
対話は繰り返すことが重要で、他者との間に喜びを生み出すものだと言うのです。
この対話力、果たして、国際社会で生きる人だけが必要なのでしょうか。
今、日本人の価値観も多様化し、多様な生き方や暮らし方が認められるようになってきました。だからこそ、「察する、分かりあう」という従来型のコミュニケーション能力だけでは、日本人同士でもうまくいかなくなっていくでしょう。
2つのコミュニケーション能力を使いこなすことでより豊かな人間関係が築けるのではないでしょうか。
【2冊目】大切なものを大切にできる、シンプルな時間術
年末年始こそ読みたい本の2冊目は『WHITE SPACE ホワイトスペース 仕事も人生もうまくいく空白時間術』(東洋経済新聞社)です。
ホワイトスペース(空白、余白)がなぜ大切なのか、どうすればホワイトスペースを創り出すことができるのか、ということを教えてくれる本でした。
著者はジュリエット・ファント。ビジネス研修のコンサルティング会社、ジュリエット・ファント・グループの創業者でCEO。フォーチュン500企業のアドバイザーを務めるほか、『フォーブス』『ファスト・カンパニー』をはじめ多くのメディアに登場しています。
現代に生きる我々は、かつてないほど時間に追われています。そのため、一日の生産性をあげるには隙間時間を創らないほうがよいと考えがちですし、それが、今までの時間術のノウハウ本の主流でした。
しかし、著者は本当に効率的で創造的な仕事をするためには何もしない時間、つまり「空白(ホワイトスぺース)」が必要だと書いてありました。
ホワイトスペースを取ると思考や内省や休息や創造のための時間を生み出せる。
タスクがびっしり詰まっていると、立ち止まって考えることもできず、身も心も消耗し、疲弊していくと言うのです。
火起こしと同じです。火をおこすときには空気の通り道である空間(スペース)が必要です。我々もいい仕事をするには空間、余白、スペースが欠かせないのだそうです。
では、どうやったらホワイトスペースを創り出すことができるのか。
本にはホワイトスペースを奪う「正体」と「封じ込める方法」が書かれていました。
4つの時間泥棒を意識する
我々から時間を奪っていくのは、4つの「時間泥棒」だと言います。
【1】意欲
【2】優秀さ
【3】情報
【4】活発さ
なぜ「時間泥棒なのか?」。その理由は、以下の「やりすぎ」につながるからです。
【1】意欲 → 頑張りすぎ
【2】優秀さ → 完璧主義
【3】情報 → 情報過多
【4】活発さ → やりすぎ
この4つは「ヘドニック・トレッドミル」(快楽のランニングマシン)という心理的概念に沿って働いているそうです。
新たな状態に慣れてすぐに物足りなさを覚えだす「快楽順応」とも言うそうです。ゴールについたと思うたびにゴールラインが動いていくイメージです。
「もっと成し遂げたい」「もっと秀でたい」「もっと知りたい」「もっとやりたい」。この「もっともっともっと」の気持ちです。
でも、そのマインドでいたら、いつまでたってもゴールには到達しません。時間がいくらあっても足りないのです。
そんな「もっともっと」と考えてしまう人たちに向けて、「もっと」を封じ込めるためのシンプルな問いが書いてありました。
【1】意欲 → 手放せるものはある?
【2】優秀さ → 十分とはどの程度?
【3】情報 → 本当に知るべきことは何?
【4】活発さ → 本当に注目すべきことは何?
この問いに答えを出していくと、TO DOリストの断捨離ができ、ホワイトスペースを創り出すことができるのだそうです。
ホワイトスペースとワークライフバランス
ホワイトスペースはワークとライフのバランスを取るためにも欠かすことのできないものです。
本には大きな反響を呼んだ「死ぬ瞬間の5つの後悔」が書いてありました。
【後悔1】 自分に正直な人生を生きればよかった
【後悔2】 働きすぎなければよかった
【後悔3】 思い切って自分の気持ちを伝えればよかった
【後悔4】 友人と連絡を取り続ければよかった
【後悔5】 幸せをあきらめなければよかった
個人の生活にホワイトスペースをもっと組み込めば、家族や友人、恋人との生き生きした時間はもっと増やせる。
上記の通り、本で書かれているように、ホワイトスペースを大切にすることは自分の人生を大切にすることと同義なのです。
ホワイトスペースは我々がよりよく生きるために欠かせないもの。
だからこそ、ホワイトスペースを取り入れて、大切なものを大切にできる人生を送りたいものです。
【3冊目】キャリアが「RPG化」する時代の新キャリア論
さて、いよいよ最後、3冊目の紹介です。
選んだのは、『29歳の教科書』(プレジデント社)。
Web3、DAO(分散型自律組織)時代におけるキャリア論と言える一冊で。「これからの時代、どうキャリアを形成していけばよいか、どんな力をつけておけばよいのか」のヒントを教えてくれる本でした。
著者は越川慎司さん。外通信会社に勤務後、ITベンチャーの起業を経て、2005年に米マイクロソフトに入社。日本マイクロソフト業務執行役員としてOfficeビジネスの責任者等を務めた後、2017年に株式会社クロスリバーを設立されています。
自社にて、選択式週休3日・完全リモートワーク・複業(専業禁止)を導入し、新たな働き方を実践しながら800社以上に「稼ぎ方改革(More with Less=より短時間で、より大きな成果を)」の実現を支援しています。
『AI分析でわかったトップ5%社員の習慣』『AI分析でわかったトップリーダーの習慣』『ずるい資料作成術』『超会議術』『巻込力』など多数の本を執筆されています。
この本のタイトルは『29歳の教科書』ですが、29歳でなくとも、ヒントになることがたくさん書いてありました。
キャリアがRPG化していく
第1章に、「これからのキャリアはRPG化する」と書いてあります。RPGとはロールプレイングゲームのことです。
本では、PRGゲームは、以下のように進むと説明されています。
個人で戦い十分にレベルアップしたら今度は仲間を増やしてパーティー(チーム)を作っていく。そして、より遠くへ冒険の旅にでる。
我々のキャリアもこのようになっていくと書いてあります。
外部環境と自分の能力、そしてちょっとだけ将来を見据えて行動を変えていきながらレベルアップし、より強いモンスターと戦い、活躍のフィールドを拡げていく。それをオープンワールド化する世界で行っていく。
現在、社会課題が複雑化し、一個人や1つの会社だけでその課題を解決することが難しくなっています。
だからこそ、まさにアベンジャーズのようなプロジェクト型のチームが必要だと、本には書いてあります。
これからは必要な能力を持った人たちがプロジェクト型で結集し1つのチームで取り組んでいくという形が主流になる。
面白いのは、チームを作る際、「社内のみ、正社員のみ、都心部のみなど、従来「壁」と思われていたものは打破される」と書いてあること。
フリーランスや複業・兼業人材の増加も然り、もうすでにこの動きは起こり始めているのではないでしょうか。
「なりたい姿」をイメージして、行動を変えていく
本では、こういう時代に「どんな考え方を持ち、行動すべきか」が次のように書かれています。
こういう時代には自分自身で考えて「なりたい姿」をイメージし行動実験(行動変容)をしていかなければならない。
社内のみ、正社員のみ、都心部のみなどの壁がなくなり、自由度が増した分、一人一人が自分で「なりたい姿」に向けて、行動を起こしていかないといけないということ。それが、新たな時代のキャリア論なのです。
磨きたいのは、7つの力
では、そんな自律型キャリアを築くために、どのような力を身につけておけばよいのでしょうか。本には7つの力が紹介されています。
【1】探求力・・・課題と必要なスキルを自分で探す力
【2】学習継続力・・・(一生学び続ける覚悟)
【3】復元力(レジリエンス)・・・ダンジョン(洞窟)から抜け出る力
【4】初動力・・・決めたらすぐに行動に移す力
【5】巻込力・・・パーティーを組む力
【6】集中維持力・・・ゾーンに突入する力
【7】洞察力・・・WHY思考で根本解決する力
すぐにすべての力を得ることはできないかもしれませんが、日々の経験の中で足りない力を意識的に磨いていき、これからの激動の時代を生き抜いていきたいものです。
プロフェッショナル・フリーランスが拡大する
フリーランス当事者として、勇気づけられたのは、エピローグに「プロフェッショナル・フリーランスが拡大する」と書いてあったことです。
著者は、フリーランスの拡大は「完全能力主義を助長することになる」とも書いていました。
つまり、正社員であっても、フリーランスであっても能力主義に突入するということ。
一見、厳しい時代と言えるかもしれませんが、逆にフリーランスにはチャンスの時代とも言えます。時代に対する感度を上げ、専門性を磨き、これからの時代を楽しんでいきたいものです。
この3冊が「これからどう働いていきたいか」の問いをくれた
この3冊の本は、これからの時代に「自分がどう働いていきたいか」を考える機会を与えてくれました。
私が3冊を通して、出した結論は以下です。
ワークとライフをうまくバランスし、周りの人たちとしっかり対話しながら関係を深め、時代に対する感度を上げ、学び続けながら自分の専門性を高めていく。
こんな風に自分をデザインできたら、わくわくする未来が待っている気がします!
平井圭子
富山県出身。青山学院大学経営学部経営学科卒。
プロフェッショナルファームで10年以上人事業務に従事。妊娠・出産を経て人事系フリーランス&キャリアカウンセラーとして独立。現在はベンチャー企業の人事業務支援、大手法人のダイバーシティ&インクルージョン推進支援、大学・高校での相談業務に携わる。
仕事の目標は仕事が楽しいと思える人を増やすこと。
プライベートでやりたいことは全国の素敵な本屋さん巡りをすること。